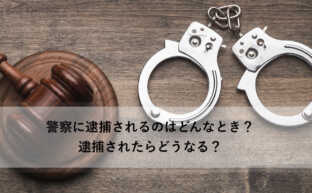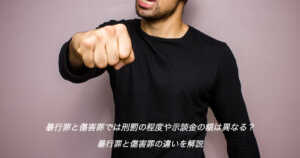
一般に、人に暴力をふるってしまった場合、「暴行罪」や「傷害罪」という罪に問われるかもしれないと思われるでしょう。
暴行罪や傷害罪は、一見すると同じような行為に対する罪に見えますが、罪が成立するための要件はそれぞれ異なります。
また、どちらの罪に問われるかで科される刑罰の程度や支払う示談金の額も変わってきます。そのため、暴行罪と傷害罪の違いについて知っておきたいという方もいるでしょう。
ここでは、
- 暴行罪と傷害罪の違い
について詳しく解説していきます。ご参考になれば幸いです。
暴行罪 逮捕については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、暴行罪と傷害罪の決定的な違いは法定刑

暴行罪と傷害罪は似たような罪だと思われがちですが、法定刑に大きな違いがあります。
それぞれ法定刑がどのようなものなのかを見てみましょう。
(1)暴行罪の法定刑
暴行罪の法定刑ついては、刑法第208条に定められています。
その内容は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
つまり、暴行罪の場合、最も重い法定刑は2年の懲役刑ということになります。
(2)傷害罪の刑罰
傷害罪の法定刑については、刑法第204条に定められています。
その内容は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
傷害罪の場合、最も重い法定刑は15年の懲役刑になるため、暴行罪における2年の懲役刑と比較すると非常に重い刑が法定されているといえます。
2、暴行罪と傷害罪の成立要件の違い

暴行罪と傷害罪では法定刑の内容も異なりますが、各罪が成立するための要件にも違いがあります。
それでは、どのような状況となった場合に暴行罪や傷害罪が成立するのでしょうか?
それぞれの成立要件を具体例と一緒に見ていきましょう。
(1)暴行罪の成立要件
暴行罪が成立するための要件としては、刑法第208条に「暴行を加えたものが人を傷害にするに至らなかったとき」と定められています。
つまり、「暴行」を加えられた相手が「傷害」を負っていなければ暴行罪が成立します。
この場合の「暴行」とは、人に対する物理力の行使をいいます。殴る・蹴る・押す・胸ぐらを掴むなど、人の身体を直接攻撃するような行為は、もちろん物理力の行使として「暴行」にあたります。
もっとも、行使する物理力が必ずしも人の身体に接触する必要はありません。
たとえば、人に直接当てるのではなくて人の近くに当てて驚かすつもりで物を投げつける場合、狭い室内で人を脅かすために凶器を振り回す場合、高速道路上で嫌がらせのために並進中の自動車に幅寄せをするようないわゆるあおり運転をする場合なども、暴行罪でいうところの物理力の行使であるとされ、「暴行」にあたります。
(2)傷害罪の成立要件
傷害罪が成立する要件としては、刑法第204条に「人の身体を傷害した」と定められています。
つまり、傷害罪とは、行為の結果として、人が「傷害」を負った場合に成立します。
したがって、暴行罪でいうところの「暴行」によって、人が傷害を負ったという場合には、傷害罪にあたり得るということになります。
そこで、「傷害」を負うとは、どのような場合をいうのでしょうか。
「傷害」とは、人の生理的機能を侵害するものをいい、人の生活機能の毀損すなわち健康状態の不良な変更を惹起することをいいます。
暴行罪にいうところの「暴行」として、人を殴る・蹴るなどした場合に、たとえば、その人があざを作ったり、骨折をしたりすると、人の健康状態を不良に変更して人の生理的機能を侵害したものとして、「傷害」を負わせたということになります。
また、「傷害」を発生させる原因としては、上記のような、暴行罪でいうところの「暴行」すなわち物理力の行使に限りません。
たとえば、嫌がらせ電話をすることによって相手に不安感を与えて精神衰弱症にする場合や、騒音をだすことによって相手に精神的ストレスを与えて睡眠障害等にさせる場合など、人の精神面に支障をきたした場合にも、人の健康状態を不良に変更したものとして、「傷害」を負わせたということになります。
さらに、たとえば、自身の性病を秘して性交等を行ったことで、相手に性病などの病原菌を感染させたという場合、病毒を感染させて健康状態を不良に変更したものとして「傷害」を負わせたことになり、傷害罪が成立しうるのです。
このように、「傷害」とは、出血を伴う傷や骨折など一見してわかる外見的なものだけではありません。
上記のとおり、人の精神的な不良や病原菌の感染などについても「傷害」と考えるため、めまいや失神、病気の感染、急性中毒、PTSD(心的外傷後ストレス障害)なども「傷害」にあたることがあります。
3、暴行罪と傷害罪の過失犯の違い

暴行罪や傷害罪が成立するための要件として、客観的な行為に関する部分は今までに述べたとおりです。
それに加えて、暴行罪や傷害罪が成立するには、主観的な要件として、「故意」に犯罪行為を行ったということが必要になります。
「故意」とは、犯罪事実の認識・認容と定義されるのが一般的です。わかりやすく言い換えると、犯罪を構成する自らの行為を認識し、それをよしとする(認容する)ことを指します。
一方で、「故意」はないものの、不注意で他人に危害を与えてしまうような場合もあります。この場合は「過失」があるものとして扱われることになりますが、暴行罪と傷害罪では、「故意」の有無や「過失」の存在に関する扱いにも違いがあります。
(1)暴行罪に過失犯はない
ある客観的な行為が暴行罪に該当する場合でも、主観的な要件の部分が「過失」である場合、過失による暴行に対する罪は法定されていないので、過失暴行という意味での罪は成立しません。したがって、過失による暴行により相手が「傷害」を負わなければ、少なくとも、人に対する暴行という点については、犯罪として扱われないということになります。
たとえば、マンション2階のベランダから空き缶をうっかり不注意で下に落としてしまい、下の道を通行していた人に当たってしまった場合、当該行為は「過失」による「暴行」となり、その人が「傷害」を負わない限り、暴行罪にはなりません。
しかしながら、マンションの下の道を歩いている人をめがけて、その人に当てるつもりで空き缶をマンションのベランダから下に投げたのであれば、「暴行」の「故意」があるといえるので、その人が「傷害」を負わない場合でも、暴行罪が成立することになります。
もっとも、「未必の故意」が認められる場合にも、暴行罪が成立する可能性はあります。
未必の故意とは、犯罪行為による結果の発生は確実ではないものの「結果が発生しても構わない」と認容している状態を指します。
たとえば、下の道を通行する人がいればその人にあたってしまうかもしれないがそれでも構わないと思って、マンション2階のベランダから空き缶を投げた場合、「未必の故意」があったといえ、暴行罪が成立しうることになります。
(2)傷害罪には過失犯がある
上記のとおり、過失による暴行に対する罪は存在しませんが、傷害罪の場合では、過失により人を傷害した場合の罪として「過失傷害罪」が存在します。
したがって、過失で他人に「暴行」を加えてしまった場合でも、相手が「傷害」を負ったのであれば過失傷害罪に問われることになります。
例えば、不注意でマンション5階のベランダから物を落としてしまい、歩いている人に当たって「傷害」を負わせた場合には、過失傷害罪が成立することになります。
過失傷害罪の法定刑は、「30万円以下の罰金又は科料」と刑法第209条に定められています。
過失による傷害行為ということで、故意による傷害行為の場合と比べると法定刑は軽いといえます。
4、暴行罪と傷害罪の示談金相場の違い

暴行罪や傷害罪に該当する行為は、「他人の法律上保護された利益を侵害した」ものとして、民法上の不法行為に該当しうるところ、その場合、行為者には当該行為による損害を賠償する責任が発生することが民法709条に規定されています。
そのため、暴行罪や傷害罪が成立する場合には、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができるといえます。
そこで、加害者としては、被害者に対して、犯罪行為についての謝罪や上記民事上の責任も含めた賠償金の支払いなどを行い、犯罪行為について被害者から許しを得るといった、いわゆる示談を行うことが考えられます。
もともと暴行罪や傷害罪を規定することで保護すべきとした利益とは、人の生命・身体の安全です。したがって、自身の行為を謝罪して被害者に損害賠償金を支払い、示談をすることで、被害者から許しをもらうことができれば、刑罰を与えることで人の生命・身体の安全を保護する必要性が少なくなるといえ、科される刑罰が軽くなる可能性がでてきます。
さらに、暴行罪や傷害罪で起訴がされる前に示談が成立すれば、自身の謝罪・損害賠償・被害者からの許しなどの要素を考慮したうえで、不起訴処分となる可能性も高まります。
そのため、示談とは非常に重要なものになります。
犯罪行為の態様や交渉の経緯、傷害の程度等によって、示談金額は大きく変わりうるところではありますが、まずは、暴行罪と傷害罪の、それぞれの示談金の相場についてみていきましょう。
(1)暴行罪の示談金相場
暴行罪における示談金の相場は、10万円~30万円と言われています。
示談金の金額が法律で明確に定められているわけではありません。法定されている罰金刑の上限が30万円なので、その金額前後の支払いで示談されることが一般的とされています。
しかし、示談はあくまでも被害者の合意を得て行われるものなので、被害者が高額な示談金を求めるようなケースもあります。
また、暴行行為の内容がたまたま「傷害」を負わなかっただけであるような悪質なものであった場合や、被害者が未成年者であった場合など、行為時の具体的事情によって、示談金は高額になることもあります。
(2)傷害罪の示談金相場
傷害罪の示談金の相場額は数十万円と言われていますが、傷害の程度によっては100万円を超えるような場合もあります。
傷害罪では、被害者が傷害を負っているため、治療費や通院にかかる交通費などの諸費用、休業損害などさまざまな損害が発生します。
傷害の程度が大きくなれば、治療期間も長くなり、治療費も高額になるため、示談金は高額になります。
また、重大な後遺障害が残るような場合であれば、後遺障害に対する慰謝料などの損害も加算されるため、示談金も数百万円といった非常に高額な金額となる可能性もあります。
5、暴行罪と傷害罪の違いのまとめ

暴行罪と傷害罪はさまざまな違いがあります。
ここまで紹介した暴行罪と傷害罪の違いを図にまとめたものを見てみましょう。
| 暴行罪 | 傷害罪 |
刑罰 | 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
成立要件 | 「暴行」を行ったが、その結果、相手は「傷害」を負っていない | 「暴行」その他の行為を行った結果、相手が「傷害」を負った |
過失による行為 | 法定される罪なし | 法定される罪あり(過失傷害罪) |
示談金の相場 | 数万円~30万円程度 | 数十万円だが、傷害の程度によって数百万円を超えることもある |
まとめた図を見て分かるように、暴行罪と傷害罪では暴行等による傷害の有無が重要なポイントとなりますが、法定刑の幅も大きく異なりますし、示談金の相場も大きな違いがあります。
6、喧嘩の際に成立しうるその他の犯罪

喧嘩になって相手に何らかの「暴行」を加えた場合、成立しうる罪は暴行罪や傷害罪だけではありません。
その他の罪についても知っておきましょう。
(1)器物損壊罪
喧嘩をした際に、「他人の物」を壊した場合には「器物損壊罪」が成立する可能性があります。
「他人の物」とは、喧嘩相手の所有する物だけではなく、たとえばお店の備品や公共物なども含まれます。
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」と刑法第261条に定められています。
もっとも、器物損壊罪は、未遂罪や過失による罪は存在しません。
(2)脅迫罪
喧嘩をした際、相手に脅迫行為を行えば、「脅迫罪」に問われる可能性があります。
「脅迫」とは、人あるいはその親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の根族)の生命や身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨の告知をすることをいいます。
したがって、「お前の家族を痛い目に遭わせてやる」といった内容を告げたとすれば、脅迫罪になり得ます。
脅迫方法としては口頭だけではなく、文書やネット上のブログ、SNSなども含みますし、実際に脅迫した相手が畏怖する必要もありません。
脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と刑法第222条に定められています。
(3)傷害致死罪
喧嘩で「暴行」を行い、その「暴行」が原因で相手が死亡してしまった場合には「傷害致死罪」が成立します。
もっとも、主観的な要件の部分において、「暴行」時に人を殺害する意思(殺意)があった場合には殺人罪が成立する可能性があります。したがって、傷害致死罪は、あくまでも傷害あるいは暴行の故意で相手を「暴行」したものの、結果的に相手を死亡させてしまった場合に適用されます。
傷害致死罪の法定刑は、「3年以上の有期懲役」と刑法第205条に定められています。なお、有期懲役の上限は、「20年である」と刑法第12条第1項に定められています。つまり、裁判で有罪判決が下された場合には、原則として最低3年は有期懲役になり、最長では20年の有期懲役になり得るということになります。
(4)公務執行妨害罪
たとえば、喧嘩の通報を受けて駆け付けた警察官に対して、「暴行又は脅迫」を行った場合には、「公務執行妨害罪」が成立する可能性があります。
公務執行妨害罪は、公務員の職務に対する妨害に科される罪です。
したがって、当該公務員に対して直接に暴行・脅迫を加えることだけでなく、たとえば警察官の押収した証拠をその場で破壊する場合など、職務に対する間接的な行為によって公務員の職務を妨害した場合も、同罪の成立要件は満たされることになります。
なお、同罪が成立するには、実際に職務が妨害されたことは必要ではありません。したがって、職務を妨害しても結局は警察官に逮捕された場合なども、同罪が成立しうることになります。
公務執行妨害罪の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と刑法第95条に定められています。
7、暴行罪や傷害罪で不当に重い刑罰を科されないようにするには弁護士に相談!

暴行罪や傷害罪には、これまで述べたように、客観的・主観的な成立要件や示談において様々な違いがあります。
暴行罪や傷害罪にあたる罪として容疑をかけられた場合、不当な重い刑罰が科されるのを避けるためにも直ちに弁護士に相談することをおすすめします。
暴行罪や傷害罪などの被害者がいる犯罪では、被害者がまだ警察に被害届を出していない段階で、被害者と話し合いをして示談をすることで、逮捕を回避できるケースも多いです。
もっとも、当事者同士で話し合うことは感情的になってしまいトラブルが大きくなるおそれがあるため、避けるべきだといえます。
とはいえ、不当な重い刑罰が科されるのを避けるためには、被害者への初動アプローチが非常に重要となってくるので、専門家である弁護士のサポートを受けながら問題の解決を目指すべきです。
刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談すれば、今の時点で何をすべきかを知ることができます。
まとめ
日常生活の中で、ちょっとしたきっかけでトラブルになってしまうことは誰にでもあり得ます。
しかし、暴力をふるってしまえば暴行罪や傷害罪に問われてしまいますし、暴力でなくても傷害罪が成立する可能性のある行為はたくさんあります。
被害者が警察に被害届を出せば刑事事件として捜査されることになり、その結果逮捕されてしまうおそれや、最終的に刑罰が科されてしまうおそれもあります。
そのため、暴行罪や傷害罪が成立しうるようなトラブルになってしまった場合には、直ちに弁護士に相談するようにしましょう。
刑事事件に詳しい弁護士に相談すれば、逮捕の回避や不起訴処分を目指してサポートしてもらうことができます。