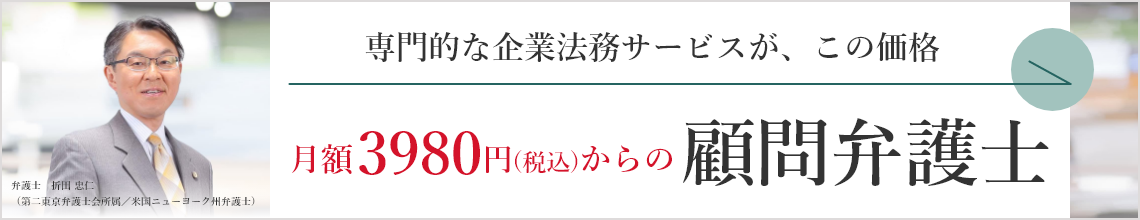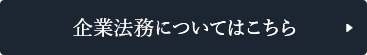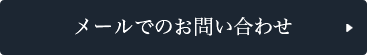企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
民事再生とは?会社を再建するための申請方法や備えたい10の知識
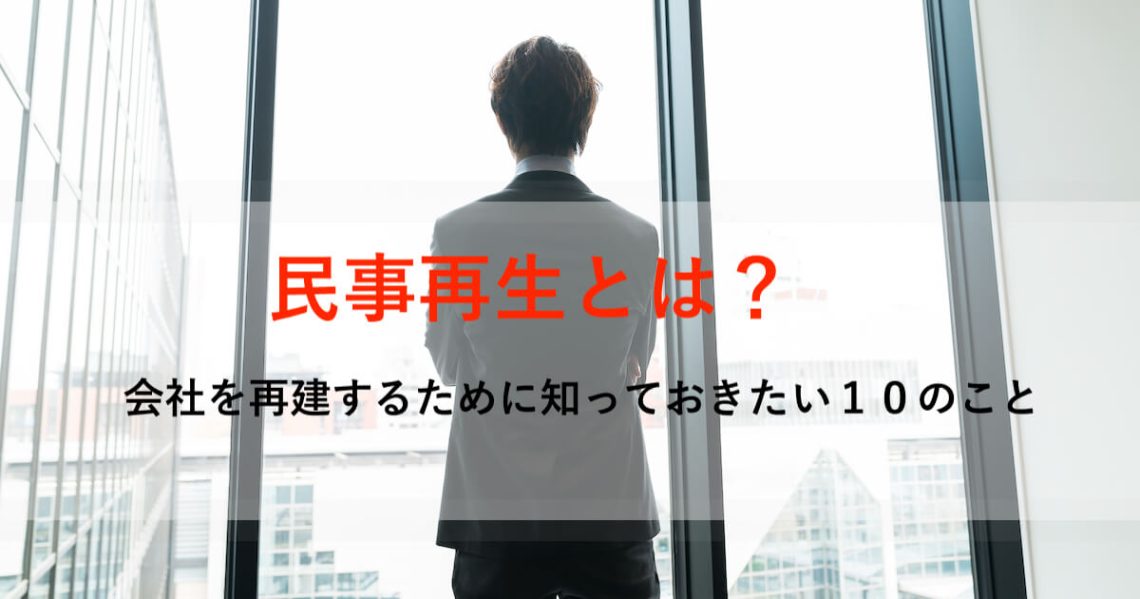
民事再生とは、会社再建型の倒産手続の代表的なものです。
借金や経営難でお困りでも、せっかく作って営んできた会社を閉めるのは避けたいという方も多いと思います。
特に、多くの従業員を抱えている方は、社員の生活を考えて会社を破産させるのは最後の手段としたいという方もいるかもしれません。
そのような場合に、会社の経営を継続しながら事業の再生を図ることが可能な手続きが「民事再生」です。
今回は、
- 会社の民事再生とは
- 民事再生の利用条件
- 民事再生のメリット・デメリット
- 民事再生の申請方法
などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
その他にも、民事再生をすると社員はどうなるのか、民事再生と会社更生はどのように違うのか、民事再生の成功率はどれくらいかなど、気になる点もご紹介します。
この記事が、会社の経営難に悩みつつ打開策をお考えの方の手助けとなれば幸いです。
法人の債務整理に関してはこちらの記事をご覧ください。
[nlink url=”https://best-legal.jp/company-reconstruction-22753/”]
1、会社の民事再生とは

民事再生とは、経済的に困窮した債務者が、債権者の多数の同意を得て、かつ、再生計画について裁判所の認可を受けること等によって負債を圧縮し、債務者の事業や経済生活の再生を図る手続きのことです(民事再生法第1条)。
(1)民事再生は再建型の倒産手続き
負債を抱えて経営が困難となった会社の負債を整理する手続き(倒産手続き)には、大きく分けて「清算型」と「再建型」の2種類があります。
清算型は会社を消滅させる手続きであり、「破産」がこれに当たります。
[nlink url=”https://best-legal.jp/corporate-bankruptcy-procedure-29108″]
再建型は会社を蘇らせるための手続きであり、民事再生の他に「会社更生」という手続きもあります。
(2)民事再生と会社更生の違い
会社更生は株式会社のみを対象としており、主として大規模な株式会社の再建手続に用いられます。
裁判所の厳格な監督の下、選定されたスポンサーの支援を得て、会社を経営しつつ、債務を弁済し、再建を図ります。すべての利害関係人を手続に取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更までを含めて、抜本的再建を目指すものです。
ただし、一般の債権者のみでなく、担保権者や株主の権利まで大幅に制限され、手続が複雑で、再建まで時間がかかる(最長15年)、費用負担が大きい、などの問題があります。
また、倒産時の経営者は、原則として、引き続き経営に関与することができません(最近は様々な要件緩和が行われています)。
[nlink url=”https://best-legal.jp/corporate-reorganization-law-6852″]
このようなことから、再建型手続として、もっと使いやすく、幅広く用いられる制度が望まれていました。
そこで、中小企業などでも利用しやすい再建型法的手続として、2000年4月から始まった制度が民事再生です。
対象は株式会社のみでなく、特殊法人、個人等、幅広く認められます。
債務者が主体となり、再生を目指すもので、会社更生法に比べて、手続が簡易です。
また、多様なメニューが用意されてきており、大きな事件から、小さな事件まで柔軟に対応ができます。
手続が開始された後も、原則として事業は継続し、債務者を監督する監督委員が選任されますが、経営者は交代しません(この点が、会社更生法との大きな違いです)。
ただし、例外的に管財人が選任された場合には、経営者は、自ら事業を継続することはできなくなります。
このほか、民事再生手続では、債務者自ら債権者への説明会を開くほか、財産状況や再建の見込み等の情報を積極的に提供するなど、債権者にとって、手続が公正で透明なものとなっている点等の特徴があります。
債権者の多数決で手続を進めることができ、手続期間も原則3年であり、早期の再建を図ることができます。
(3)民事再生には個人向けの手続きもある
民事再生は、本来的には法人を想定して創設された制度です。
しかし、個人事業主や給与所得者等の個人でも破産を回避して経済生活を再生できるように、民事再生法に個人の債務者に関する特則が設けられ、2001年4月から施行されました。
この特則は、「個人再生」と呼ばれており、個人の債務者にとって非常にメリットの大きな債務整理の方法となっています。
[nlink url=”https://best-legal.jp/individual-renaturation-6409″]
(4)会社の民事再生の成功率は低い?
実際に民事再生を利用して見事に再建を果たした会社がどのくらいあるのかは、気になるところでしょう。
この点、東京商工リサーチの調査によれば、2000年4月1日から2016年3月31日までに負債1,000万円以上を抱えて民事再生を申し立てた事例について、その後の進捗が確認できた法人のうち、生存企業は29.1%に過ぎないとされています。
引用元:東京商工リサーチ|「民事再生法」適用企業の追跡調査 (2000年度-2015年度)
この数字を高いと見るか低いと見るかですが、一概に「低い」ということはできません。なぜなら、会社の再建は本来的に非常に難しいものだからです。
個人の場合は、借金苦から救済しなければ生命に関わるおそれもあるので、債務整理の成功率は非常に高くなっています。
それに対して、会社は「経営に行き詰まったのなら一度潰して、また設立すればいい」という考え方もあるため、必ずしも成功するものとはいえないのです。
その中で、3割近くの会社が民事再生に成功しているということは、考えようによっては高い数字と見ることもできます。
いずれにせよ、民事再生法によって、一定の要件を満たせば会社の再建が可能となるスキームが用意されているのですから、会社の再建を目指す方は諦めず、十分に準備を整えた上で民事再生に取り組むとよいでしょう。
2、民事再生の4つのパターン

会社の民事再生における再建方法にはいくつかのメニューがあり、主に以下の4つのパターンに分けられます。
(1)自力再建型
自社の事業による収益から再生債務を返済し、自力で再建を図るパターンです。
最も本来的なパターンともいえますが、安定して収益を上げていることが条件となるため、どんな会社でもこのパターンを採ることができるわけではありません。
(2)清算型
自社の事業を受け皿となる会社へ営業譲渡して、旧会社は清算し、受け皿会社において事業の再建を図るパターンです。営業譲渡によって得られた対価は、再生債務の返済に充てられます。
会社の民事再生によって生存する企業の割合が29.1%しかないのは、この清算型のパターンが採られるケースが多いことも影響しています。
ただ、営業譲渡した側の会社もすべてが消滅するわけではなく、一部の事業を残して独自に再建を図る会社もあります。
(3)スポンサー型
自社を再建するためのスポンサーとなってくれる企業を見つけて、その企業から資金援助や出資を受けるなどして再生債務を返済し、再建を図るパターンです。
いったん経営に行き詰まった会社が自力で再建するのは難しいことが多いため、民事再生で会社の再建を成功させるには、スポンサー企業を確保できるかどうかにかかっているといってもよいかもしれません。
スポンサー企業を確保するには、何らかの面で他社から見た魅力が必要ですので、自社の強みを把握して、今後の展開を魅力的にアピールすることが重要となります。
(4)プレパッケージ型
最近注目されているパターンとして、「プレパッケージ型」というものもあります。
プレパッケージ型もスポンサー型の一種ですが、通常のスポンサー型と異なる点は、民事再生の申し立て前にスポンサー企業を確保しておき、申し立てと同時にそれを公表することです。
初めからスポンサー企業がついていることで、民事再生の申し立てによる会社の信用やイメージの低下を食い止めることができ、早期に会社の再建を図りやすくなります。
また、自車の従業員や取引先の動揺を抑えることができるというメリットもあります。
3、会社の民事再生を成功させるための条件

会社の民事再生で、再生計画案が認可されるための法律上の条件は、債権者総数の過半数、かつ、債権総額の2分の1以上の債権を有する債権者の同意を得ることです。
この条件を満たして会社の再建を成功させるためには、次の5点がポイントとなります。
(1)会社が収益を上げる見込みがあること
まず第一の条件は、会社が今後、収益を上げていく見込みがあることです。
この見込みがなければスポンサーも見つかりにくいので、自力型にせよスポンサー型・プレパッケージ型にせよ、民事再生を成功させるのは難しくなります。
今後の収益を改善するには、これまで採算が取れていなかった部門を整理し、収益性の高い部門を会社の中核として据えることが基本となります。
新たな事業を計画するのもよいですが、スポンサーや債権者から見ると「先行が不透明」という印象を受けてしまいがちです。
したがって、これまで収益を上げてきた部門を強化する方が望ましいといえます。
併せて、コストを削減することも重要です。不要な設備を手放したり、業務フローの見直しなどが必要となります。
リストラによる人件費の削減を検討しなければならないこともあります。
売上げとコストの両面を見直して、スポンサーや債権者から見て「儲かりそうだ」と思われるような経営戦略を策定することがポイントです。
(2)スポンサーを確保する
自力型で会社の再建を見込めるほどに収益性を改善できればよいですが、多くの場合はスポンサーによる支援が必要となります。
なぜなら、民事再生を申し立てると金融機関からの融資を受けることができなくなり、資金繰りが難しくなるからです。
取引をするにも信用取引は利用できず、もっぱら現金決済を行う必要があります。
企業活動において「融資なし、現金決済のみ」で収益を上げていくことは現実的には難しいので、資金援助をしてくれるスポンサーの存在は重要です。
また、スポンサーがいることで自社の企業イメージや信用の低下を食い止めることができ、収益の維持・増加も期待できるようになります。
民事再生を申し立てた後ではスポンサーが見つかるかどうかは分からないので、事前にスポンサーを確保する「プレパッケージ型」が望ましいといえます。
(3)一定の費用を準備できること
民事再生では、裁判所に支払う予納金、監督委員に払う報酬、申立てを依頼する弁護士に支払う費用などが必要です。
今後一定期間の運転資金も確保しておく必要があるので、それなりの金額を準備しておかなければなりません。
スポンサーから支援を受けることも含めて、早めに準備を進めるべきです。
(4)未払いの優先債権が少ないこと
優先債権とは、税金、給料や退職金の支払いなど、一般の借金より先に支払わなければならない類のお金をいいます。
これらのお金が多いと、一般の借金の返済に回す資金がなかなか確保できないため、民事再生の再生計画案を実行することが困難になります。
現在、優先債権の未払いがある場合は、早めに少しでも減らしておくことです。
(5)銀行などの強い反対がないこと
先ほどもご説明したように、会社の民事再生では債権者総数の過半数、かつ、債権総額の2分の1以上の債権を有する債権者の同意が得られなければ再生計画案が否決され、手続きに失敗してしまいます。
もし、大口の債権者が民事再生に反対すれば、民事再生を成功させることはできないのです。
銀行からの融資が債権総額の2分の1以上を占めているようなケースでは、その銀行の理解を得ることが不可欠となります。
大口債権者に対しては特に、今後の収益をどのように改善するのかを説得的に伝えて、会社再建への協力を得ることが重要です。
4、会社の民事再生で得られるメリット

会社の民事再生を利用した場合、破産や会社更生とは異なり、以下のメリットが得られます。
(1)会社経営を継続できる
民事再生では、借金などの債務を減らしてもらったり、原則として最長10年の返済の猶予を受けることができるので、会社をたたむことなく事業を継続することができます。
(2)経営権を手放さずに会社を再建できる
民事再生を利用する経営者は、原則として会社の財産を管理する権利、経営権を手放すことなく手続きを進めることができます。
会社更生の場合は経営陣が退任する必要があるので、この点は民事再生の大きなメリットといえるでしょう。
(3)資金繰りに必要なお金を残すことができる
民事再生の申立てをして銀行などの金融機関に通知すると、それ以降は再生債務者の銀行残高で金融機関は相殺することができません。
そのため、民事再生通知後の入金は、会社の資金繰りに生かすことができます。
(4)不渡りなどを回避できる
通常、民事再生の申立と同時に弁済禁止の保全処分の申立を行いますが、これにより手形の不渡りを出して取引停止になるといった事態を避けることができます。
5、会社の民事再生で注意すべきデメリット
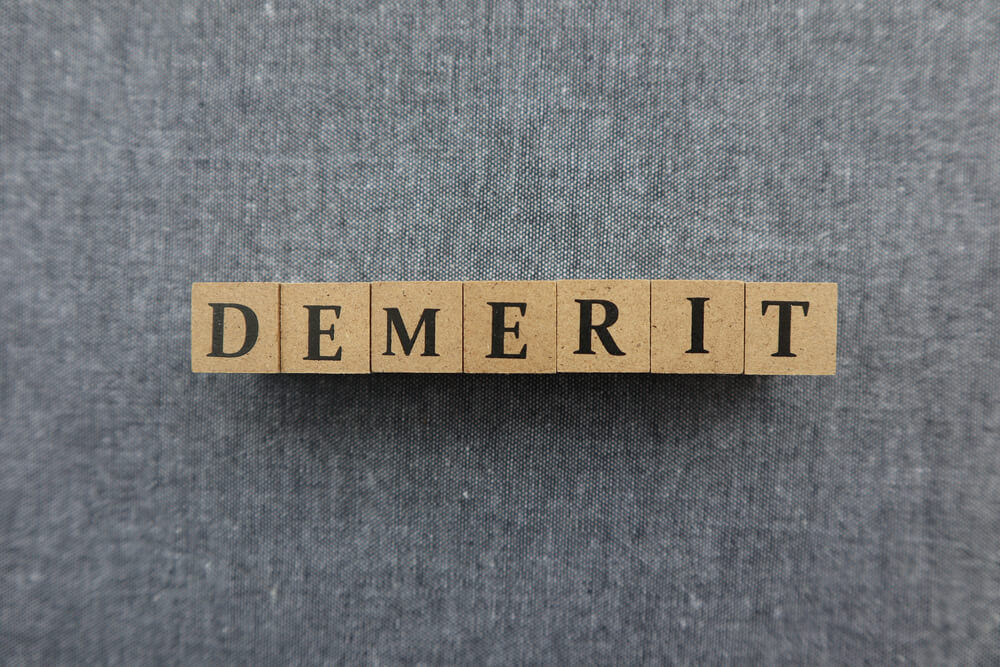
一方で、民事再生には以下のデメリットもあるので注意しましょう。
(1)担保に入れたものを失うおそれがある
民事再生では、原則として担保権が実行されることを止められません。
突然土地の抵当権が実行されたなどという事態を防ぐためには、担保権者と弁済協定を締結しておく必要があります。
(2)債務免除に税金がかかる
再生計画によって債務の免除がされると、免除額が課税の対象となります(債務免除益課税)。
債務免除益課税が課されると、再生計画が認可されても税金が支払いきれないという事態になりかねないので、税務署と分割払いの交渉をするなどの対処が必要になります。
(3)代表者の債務は免除されない
会社の民事再生は、あくまでも会社の債務を整理する手続きです。
会社の債務を代表者が連帯保証している場合は、会社の民事再生に成功しても代表者の連帯保証には影響がありません。
したがって、代表者も別途、個人再生などの債務整理を検討する必要があることが多いです。
(4)信用不安のリスクがある
民事再生の申立てを行うと、再建型の手続きとは言っても倒産のうわさが立つ可能性が高く、信用不安を招いて売上げの減少などが生じるおそれがあります。
このデメリットを最小限に食い止めるには、事前にスポンサーを確保することです。
[nlink url=”https://best-legal.jp/civil-rehabilitation-disadvantages-21997″]
6、民事再生による従業員への影響は?

会社が民事再生をすると、従業員はどうなるのでしょうか?従業員の生活を守るために民事再生を選択する経営者の方は気になるところでしょう。
(1)再建型のパターンの場合
自力再建型・スポンサー型・プレパッケージ型によって会社を再建させる場合、基本的には民事再生を行っても従業員に影響はありません。
ただし、収益性の改善(コスト削減)のためにリストラ解雇を検討しなければならない場合はあります。
解雇が必要な場合は、適切な手続きを踏んで行うようにしましょう。
なお、従業員への給料や退職金は、一般の債務よりも優先して支払う必要があります。
会社都合での解雇となりますので、再就職をあっせんするなどして誠実に対応するようにしましょう。
(2)清算型のパターンの場合
清算型の民事再生で会社を消滅させる場合は、それに伴って従業員も全員解雇となります。
この場合も上記と同様に、適切な手続きで解雇すること、給料や退職金は優先的に支払うこと、従業員に対して誠実に対応することが大切です。
7、会社の民事再生の申請手続きの流れは?

会社の民事再生手続きは、裁判所が関与する上、多くの債権者とのやり取りが必要になるので、少々複雑です。
具体的には、次の10の段階を踏んで行います。
(1)民事再生手続の申立て
民事再生手続は、裁判所に対して申立書類を提出して申立てを行うことでスタートします。
通常は、申立てと一緒に「弁済禁止の保全処分」の申立ても行い、当日中に認められます。
弁済禁止の保全処分とは、民事再生を申し立てた再生債務者に対して民事再生申立ての前日までに発生した借金等の返済を禁止して、債務者の財産が減ることを防ぐためのものです。
(2)監督委員の選任
会社の民事再生の場合、会社の財産を管理する権利は会社に残りますが、完全に自由にさせたのでは民事再生手続きの意味がありません。
そこで、民事再生手続きを監督させるための監督委員が、裁判所によって選任されます。
監督委員とは、民事再生手続きの全般にわたって債務者の行為を監督する人のことです。
債務者は、裁判所が指定した行為については監督委員の同意を得ることが必要になります。
(3)再生手続き開始決定
申立から2週間を目安に、裁判所による再生手続開始決定が行われます。
再生計画案が認められる可能性がない時は、裁判所が申立てを棄却することもあります。
(4)再生債権の提出
再生手続開始決定後、裁判所が定めた期限までに、会社にお金を貸していたり、売掛金がある債権者は、債権届を提出して再生手続に参加する意思を示します。
(5)財産状況の報告
再生計画案を作成するにあたって、再生債務者は再生手続開始決定時の会社の財産目録や貸借対照表などを提出し、財産状況の報告を行います。
(6)負債総額の確定・債権認否書の提出
債権者から提出された再生債権の届出について、再生債務者は認めるかどうかを決定し、その結果を認否書に記して提出します。
これによって、民事再生の対象になる負債を確定させます。
(7)再生計画案の作成
再生計画案とは、債務をどうやって返済していくかを決めて記したものです。
裁判所が定めた期日までに、再生債務者は再生計画案を作って提出します。期日に間に合わない場合は、再生手続きが認められず廃止されることもあるので注意が必要です。
(8)再生計画案の決議
債務者が提出した再生計画案は、債権者集会で決議にかけられます。
可決される条件は、先ほどもご説明しましたが、次の2つです。
- 債権者集会に出席した議決権者の過半数の賛成
- 議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の賛成
(9)再生計画の認可
再生計画案が可決されると、裁判所で再生計画の認可が行われます。
これによって、再生計画が法的効力を持つことになります。
(10)再生計画の遂行
再生計画が認可されると、再生債務者はこの計画に従って返済していくことになります。
再生計画は認可されてから3年間は、監督委員が、再生債務者が再生計画通りに返済を履行しているかどうかの監督を行います。
[nlink url=”https://best-legal.jp/civil-mat-playback-procedure-6858″]
まとめ
民事再生は、中小企業でも再建型の倒産手続を利用できるようにと創設された制度なので、大企業向けの会社更生よりも簡易的で柔軟な手続きとなっています。
とはいえ、その手続は一般の方が簡単に実行できるものとはいいがたく、法律の専門家である弁護士の力を借りなければ難しいものです。
そもそも民事再生で再建が可能かどうかを判断するにも、専門的な知識が要求されます。
会社に支払不能・支払停止・債務超過の可能性があり、再建か清算かの選択が迫られる事態が生じているならば、できるだけ早く弁護士に相談し、対応を考えていきましょう。
[nlink url=””]https://best-legal.jp/company-reconstruction-22753/
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事
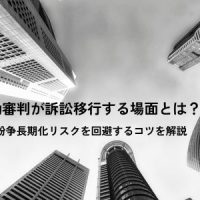
労働審判が訴訟移行する場面とは?紛争長期化リスクを回避するコツを解説
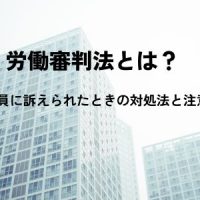
労働審判法とは?会社が従業員に訴えられたときの対処法と注意点を解説
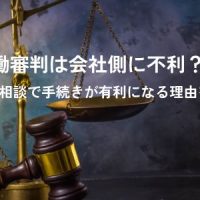
労働審判は会社側に不利?弁護士への相談で手続きが有利になる理由を解説