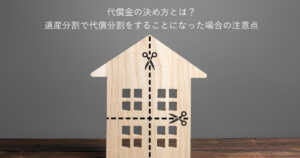
遺産が現金や預貯金だけであれば各相続人の相続分に応じて分割すればよいので、相続は比較的簡単に終わります。
しかし、遺産に不動産が含まれる場合には、不動産は現金や預貯金のように物理的に分割することができませんので、相続手続きは難しくなります。
遺産に不動産があり、現金や預貯金がほとんどないという時にはさらに難しくなります。
このような場合に、「代償分割」という遺産分割方法がとられることがあります。
代償分割とは、不動産を相続人の一部が現物で取得し、現物を取得した相続人が、その他の相続人に対して、代償金を支払うという遺産分割方法です。
代償分割では、対象となる不動産をどのように評価するかによって、代償金の金額が変わってきます。
代償金額は、まずは相続人同士の話し合いによって決めることになりますが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判によって決めることになります。
今回は、
- 不動産の代償分割における代償金の決め方
- 代償分割を行う際の遺産分割協議書の書き方
- 代償金を払えないと言われたときの交渉方法
- 代償金と税金との関係
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
この記事が、代償分割における代償金の決め方でお悩みの方々のご参考になれば幸いです。
なお、代償分割について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。。
目次
1、不動産の代償分割における代償金の決め方

遺産である不動産を代償分割することになった場合には、代償金をどのように決めたらよいのでしょうか。
以下では、代償分割における代償金の決め方について説明します。
(1)不動産の代償分割は「評価額」による
代償分割とは、先に述べたとおり、遺産分割において、一部の相続人に不動産等の現物を取得させる一方で、その相続人が他の相続人に対し債務(代償金の支払い)を負担するという分割方法です。
簡単にいえば、相続人の一人が遺産の現物をもらう代わりに、他の相続人に対して、その対価を支払うという方法です。
代償分割は、相続財産のほとんどが不動産である場合のように物理的に分割することが難しい遺産が含まれている場合に用いられる分割方法です。
代償分割を選択した場合には、遺産を現実に取得しない相続人は、遺産を取得した相続人から代償金をもらうことになりますので、その代償金をいくらにするかがポイントとなります。
そして、代償金を決めるには、その前提として、対象となる遺産を適切に評価することが重要です。
(2)不動産の評価方法は複数ある
不動産を対象として代償分割を行う場合には、対象となる不動産の評価をどのように行うかが問題となります。
不動産には、以下のように、①公示価格、②固定資産税評価額、③相続税評価額(路線価)といったさまざまな評価方法があります。
どの評価方法を採用するかによって評価額は異なりますので、その結果として最終的に取得することができる代償金の額は、大きく異なってきます。
できる限り多くの代償金をもらいたいと考える場合には、より高額に評価することができる評価方法を採用することが必要になります。
①公示価格
公示価格とは、国土交通省の土地鑑定委員会が特定の標準地について毎年1月1日を基準日として公示する価格のことをいいます。
2人の不動産鑑定士が鑑定評価を行い、その結果を土地鑑定委員会が審査・調整して、最終的な正常価格として公示しています。
公示価格は、一般の土地取引に指標を提供するとともに、公共事業の用に供する土地の取得価格の算定、相続税評価および固定資産税評価の基準にすることを目的にしています。
②固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、地方税法349条による土地家屋課税台帳などに登録された基準年度の価格または比準価格のことをいいます。固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、訴額算定などの基準にされています。
また、固定資産税評価額は、固定資産評価基準により不動産ごとに決められており、土地の固定資産税評価額は、公示価格の70%を目安に設定されています。
固定資産税評価額の評価替えは、3年に1度しか行われないため、土地の価格に変動を生じる要因が生じたとしても、その要因が評価額に反映されるまでにはタイムラグがあり、公示価格や路線価格、実勢価格との差が生じやすい面があります。
③相続税評価額(路線価)
相続税評価額(路線価)とは、財産評価基本通達により、相続税、贈与税などの算出の基準として、毎年1月1日時点の価格が対象土地の地目ごとに路線価方式、倍率方式のいずれかによって算定され、毎年夏ごろに国税庁や各税務署で公表されている価格のことをいいます。
路線価は、毎年評価替えされているので地価変動をより詳細に反映しているといえます。
財産評価基本通達は、相続税・贈与税などを賦課するための財産評価の方法に関する全国共通の画一的な基準であり、課税上の公平感を保つという点で優れています。
また、路線価は、各種不動産評価額の上限価格と下限価格の間にあることが多いため、当事者の納得を得やすく、特に相続税申告案件では、路線価を基準として評価合意を得ることが多いです。
(3)代償分割における評価方法は当事者の合意によって決める
不動産の評価方法は、上記のように大きく分けて3つの方法が存在します。
どの評価方法を採用するかによって不動産の評価額ひいては代償金の額が大きく変わりますので、代償金をもらう予定の相続人としては、どの評価方法を採用するかが重要です。
代償分割に限らず、遺産分割協議における評価方法は、上記の評価方法による評価額を基準に、場合によってはその額を調整するなどして、評価額をどうするかについて当事者間で協議することになります。
後述するとおり、税金面で気を付けなければならない点はありますが、当事者間で合意ができれば、不動産の評価額をどのようにするかは当事者の自由です。
そのため、上記の評価額以外の評価額を不動産の評価額とすることも可能です。
当事者間で合意が形成できない場合には、調停を申し立てて裁判所で話合いをしたり、それでも合意できない場合には審判に進めることになりますが、そこで裁判所が指定した不動産鑑定士による鑑定を行うことになります。
鑑定にあたっては、当事者が高額な鑑定費用を負担しなければなりませんので、調停では、費用負担を避けるためにお互いが主張する中間の金額で合意するなどの方法がとられることもあります。
2、代償分割を行う際の遺産分割協議書の書き方

代償分割をすることになった場合には、そのことを遺産分割協議書に明確に記載する必要があります。
代償分割をするということを明記しなければ、相続人から支払われた代償金は、相続とは無関係な贈与であるとして贈与税が課税されるリスクがありますので注意が必要です。
代償分割の遺産分割協議書の雛形は、以下からダウンロードしてご利用いただけます。
3、代償金を払えない!そう言われたときの交渉方法

代償分割を前提に進めていたところ、代償金を支払う予定の相続人から「代償金を払えない」と言われた場合には、どうすればよいのでしょうか。その場合の交渉方法のいくつかを以下でご紹介します。
(1)分割払いを認める
不動産の評価額によっては、不動産を取得する相続人が支払う代償金の金額が高額になることがあります。
当初想定していたよりも高額な代償金となった場合には、代償金の支払いを予定していた相続人としてもすぐに対応できないかもしれません。
そのような場合には、代償金を一括払いではなく、分割払いでもよいと伝えてみるのもよいでしょう。
分割払いにすることによって、代償金を支払う相続人としても資金調達に余裕ができ、代償金の支払いが可能になることがあります。
ただし、分割払いにすることによって将来支払いが滞るリスクがありますので、分割払いにする場合には、そのリスクを軽減するために、遺産分割協議書を公正証書にするとよいでしょう。
公正証書にして、強制執行認諾文言をつけることによって、将来支払いが滞ったとしても、裁判手続きを経ることなく強制執行の手続きを行うことが可能になります。
(2)共有分割、換価分割を提案する
そもそも遺産である不動産を取得する相続人に代償金を支払う余裕がないという場合には、代償分割の方法をとることはできません。
そのような場合には、共有分割や換価分割の方法を提案するとよいでしょう。
ただし、共有分割は、不動産を共有状態にする遺産分割方法ですので、将来共有者間で不動産の利用や処分をめぐって争いが生じるおそれがあります。
そのため、代償分割が困難な場合には、まずは換価分割(当該不動産を売却して得た代金を分割する方法)を提案し、それでも合意できない場合の最終的な分割方法として共有分割を提案するとよいでしょう。
(3)他の相続財産のうち、自分に価値の大きなものを求める
被相続人に複数の不動産がある場合や、不動産以外にも相続財産がある場合には、代償分割ではなく現物分割(相続財産をそのまま現物で相続する方法)を行うことも検討するとよいでしょう。
代償金の金額に相当する相続財産があるのであれば、それをもらうことによって代償金の支払いに代えることができます。
4、多すぎる代償金は贈与税の対象に

代償分割によって代償金を受け取ることになった場合には、贈与税との関係で注意が必要な点があります。
以下では、代償金と贈与税の関係について説明します。
(1)原則として代償金の支払いには贈与税は課税されない
代償分割による方法で相続人から代償金を受領した場合には、相続税の課税対象になることはあっても、原則として贈与税が課税されることはありません。
なぜなら、外見上は、一方の相続人から他方の相続人への財産の移転ですが、実際には、遺産分割として行われているためです。
(2)例外的に代償金に贈与税が課税されるケースとは?
代償金の額が、代償金を支払う相続人が取得した遺産の適正な評価額に照らして大きすぎる場合には、代償金に贈与税が課税される可能性があります。
また、被相続人の死亡によって相続人に支払われた生命保険金で代償金を支払った場合には、贈与税が課税されるリスクがあるため注意が必要です。
たとえば、被相続人が亡くなり、長男と次男の二人が相続人であったとします。被相続人の遺産としては、不動産が3000万円あるのみですが、長男は死亡保険金5000万円を受領していました。
不動産は、次男が取得し、長男が次男に対し代償金として1000万円を支払った場合にはどうなるのでしょうか。
この事例では、死亡保険金も遺産に含めて代償金の金額を算定していますが、そもそも、死亡保険金は、受取人固有の財産であり、被相続人の相続財産には含まれません。
そのため、長男が次男に支払った1000万円については、代償金とは評価されず、長男から次男に贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されることになります。
5、不動産を代償分割する場合の不動産取得税の支払い方

相続人が相続財産に含まれる不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う場合には、代償金として、現金を支払うことが大半です。
代償金を現金で支払う場合には、相続税以外には特に税金が課税されることはありません。
ただし、代償金の支払いは、現金だけでなく、代償金を支払う相続人が所有する不動産を渡す方法も可能です。
ただし、この方法を採った場合には、代償金として不動産を受け取る側に不動産取得税が課税されることになりますので注意が必要です。
不動産取得税は、課税標準額×税率によって計算することになります。
税率は、土地の場合は3%、建物の場合には、住宅が3%、非住宅が4%です。
そのため、代償金として不動産を受け取った相続人は、取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を管轄する都道府県の税事務所に申告しなければなりません。
まとめ
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割といった方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
代償分割は、遺産の大半が物理的に分割が困難なものであるとか、遺産が不動産だけであるといった場合に有効な手段ですが、代償金の取り決めをしっかりとしておかなければ、思いもよらない不利益を被る可能性があります。
代償金の決め方で不利にならないようにするためにも、代償分割をすることになった場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。





