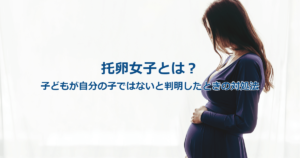
托卵女子とは、夫以外の男性との子を産み、その子を夫の子であると偽り、夫に育てさせる女性のことを指します。
多くの父親は、子どもが本当に自分の子であるか疑念を抱いたことがあるかもしれません。しかし、ほとんどの父親は、その疑念を払拭し、子どもを自分のものとして愛情を注いできたことでしょう。
ところが、托卵女子の策略により、夫が他人の子を育てさせられる実例も存在します。
法的には、子どもが実際には他人の子であっても、親子関係は法的に認められており、養育責任を負うことになります。これを知った父親は、ショックや怒りを感じることでしょうし、納得がいかないのも理解できます。
本記事では、以下の点に焦点を当てて解説します。
・托卵女子の実態とは?
・托卵女子の子どもに対する養育責任と法的規定
・養育費(監護費用)の支払いを拒否するための方法
目次
1、托卵女子とは?

そもそも「托卵」とは、カッコウなどの鳥類が他の鳥の巣に卵を産みつけ、その鳥に孵化したひな鳥を育てさせることをいいます。この動物の習性になぞらえて、他の男性との子どもを産んで夫に育てさせる女性のことを俗に「托卵女子」といいます。
結婚前に愛していた男性との子を身ごもり、それを隠したまま結婚するケースもあれば、結婚後に浮気した相手との子を身ごもり、夫との子であると偽って出産するケースもあります。中には、女性自身も夫との子であるのか他の男性との子であるのかが分からず、堕胎する決心ができないまま出産してしまうケースもあるでしょう。
しかし、一般的に托卵女子というと、より悪意の強いケースのことを指すことが多いです。
例えば、「貧しくてもイケメン」のような男性の子を身ごもり、子供の実の父であるその男性とは一緒にならずに、容姿が悪くてもお金持ちな相手と結婚し、夫との子であると偽って育てさせ、潤沢な養育費を得るというようなケースの女性が典型的な「托卵女子」であるといえます。
2、托卵女子の夫は自分の子ではなくても養育義務を負う?

托卵女子に騙された夫にとっては残念なことですが、自分の子として出生届を提出した以上は原則として養育義務を負わなければなりません。
実際には自分の子ではなくても、婚姻中に妻が妊娠した場合や、婚姻の成立の日から200日以上が経過した後、または離婚後300日以内に妻が出産した子どもは、夫の子であると推定され、法律上の親子関係が生じます(民法第772条)。このことを「嫡出推定」といいます。
法律上の親子であれば、当然に養育義務を負うことになります(民法第820条)。そうだとすると、自分の子ではないと気付いた後、法律上の親子関係を解消して養育義務を免れることができるかどうかが問題となります。
3、托卵女子の夫が養育費(監護費用)の支払いを拒否する方法は?

托卵女子の夫が子どもへの養育費(監護費用)の支払いを拒否するには以下の方法がありますが、必ずしも容易なことではありません。
なお、「養育費」と「監護費用」はどちらも子どもを育てるために必要な費用のことで、同じ意味に捉えて差し支えありません。法律上は「監護費用」と呼ばれますが、日常では「養育費」と呼ばれることが多いです。
(1)嫡出否認の訴え(1年以内)
自分の子ではないことが判明した場合、夫は「嫡出否認の訴え」を起こすことができます(民法第774条)。
「嫡出否認」とは、嫡出推定を覆すことであり、これが認められると嫡出推定が及ぶケースでも法律上の親子関係が否定されます。
手続きとしては、まず家庭裁判所に「嫡出否認調停」を申し立てます。この調停で当事者が「夫の子ではない」という合意をした場合、DNA鑑定などによってその合意が正当であると認められれば、その合意に従った審判がなされます。それにより、夫と子どもは親子ではなくなります。
合意ができない場合、夫はさらに家庭裁判所に「嫡出否認訴訟」提起します。この訴訟で夫が勝訴すれば判決で嫡出が否認され、夫と子どもとの親子関係が否定されます。
ただし、嫡出否認の訴えは夫が子の出生を知ったときから1年以内に行わなければなりません(同法第777条)。自分の子ではないことを知らなかったとしても、1年が経過してしまうと嫡出推定を覆すことはできなくなります。
(2)親子関係不存在確認の訴え(利用条件あり)
夫が子の出生を知ったときから1年が経過してしまった場合でも、「親子関係不存在確認の訴え」を起こせる可能性があります。
手続きとしては、嫡出否認の訴えの場合と同様、まず家庭裁判所に「親子関係不存在確認調停」を申立て、調停で当事者の合意が得られない場合はさらに家庭裁判所に「親子関係不存在確認訴訟」を提起します。
調停で合意が得られるか、訴訟で夫が勝訴した場合は夫と子どもとの親子関係が否定されます。
ただし、親子関係不存在確認の訴えを起こせるのは、妻の妊娠時に夫婦が別居していたり、既に夫婦関係が破綻していたりして、夫婦が性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるような場合に限られることに注意が必要です。
例えDNA鑑定で夫と子どもとの親子関係が否定されていたとしても、上記のような事情がない限り、基本的に親子関係不存在確認の訴えによって父子関係の存否を争うことはできないとした最高裁の判例があります(最高裁平成26年7月17日判決)。
子どもが社会的に安定して生活していくためには、嫡出推定によって法律上の父子関係を確定させ、家庭の平和を維持することが重要です。そのため、民法の規定は法律上の父子関係と生物学上の父子関係とが一致しない場合が生じることも許容していると最高裁判例で述べられているのです。
そうすると、妻の妊娠時に夫婦が同居していたケースでは、調停で妻が夫の子ではないことに同意しない限り、親子関係の不存在を認めてもらうことは難しいということになります。
(3)実の父親に子どもを認知してもらう
(2)のケースで、実の父親に認知してもらうことができれば、そちらで法律上の親子関係が生じますので、夫と子どもとの親子関係は否定することも可能となります。したがって、実の父親が判明している場合には、その人に認知してもらうように求めることが考えられます。
任意に認知してもらえない場合は、「認知の訴え」を起こすことが可能です。
認知の訴えを起こせるのは、子どもまたはその直系卑属、および法定代理人に限られますが、夫も現時点では子どもの法定代理人ですので、認知の訴えを起こせます。
手続きとしては、やはり家庭裁判所へ「認知調停」を申立て、調停で合意ができない場合は改めて家庭裁判所で「認知訴訟」を提起します。
調停で合意が得られるか、訴訟で夫が勝訴した場合は認知の効力が生じますので、夫と子どもとの親子関係が否定されます。
(4)妻に対して権利の濫用を主張する
親子関係を否定できないとしても、事情によっては妻からの養育費の請求が「権利の濫用」に当たることを主張し、支払いを拒否できる可能性があります。
養育費の分担に関する事案における最高裁判例で、
- 夫がこれまでに子どもの養育監護のための費用を十分に分担してきたこと
- 夫の子ではないことを妻が知っていたにもかかわらず、夫に告げなかったために夫は親子関係を否定する法的手段を失ったこと
- 離婚に伴い妻は相当多額の財産分与を受けること
といった事情を総合的に考慮し、妻からの養育費の請求を権利濫用に当たるとして認めなかったものがあります(最高裁平成23年3月18日判決)。
ただし、DNA鑑定で夫と子どもとの親子関係が否定されるだけでは、妻からの請求が権利濫用に当たるわけではないことに注意が必要です。
夫がこれまでに十分な養育費を負担していなかったり、離婚後に妻だけで子どもを養育することが経済的に厳しかったりする場合には、妻からの養育費の請求が認められる可能性が高いです。
4、托卵女子と離婚はできる?

事情にもよりますが、夫が妻から「あなたの子よ」と騙されて他人との子どもを育てされられていた場合は、妻と離婚できる可能性があります。
(1)托卵は不法行為に当たる可能性がある
子どもが生まれた時点で他人の子であるということが分かっていれば、通常、その子を自分の子として育てたいと思う男性はいません。
それにもかかわらず妻が夫を騙して自分の子であると信じ込ませ、育てさせる行為は民法上の不法行為に当たります。
ただし、妻が妊娠初期の時点で夫との子か他の男性との子か分からないと正直に告げ、夫が「どっちであっても自分が育てる」と言ったような場合は、不法行為が成立しない可能性が高いです。この場合は妻が騙したわけではありませんし、夫も自分の意思で判断しているからです。
(2)不法行為が成立すれば離婚が可能
通常、自分を騙して他人との子を自分に育てさせるような妻と夫婦関係を続けることは難しいといえるでしょう。
この場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という法定離婚事由(民法第770条1項5号)が認められる可能性が高いです。
法定離婚事由があれば、妻が離婚を拒否したとしても裁判をすれば強制的に離婚できます。
また、結婚後に浮気をして他の男性との子を出産した妻に対しては、「不貞」(同条1号)を主張して離婚できる可能性もあります。
(3)慰謝料を請求できることもある
何年も自分の子だと思って育ててきたのに、実は妻に騙されていて他人の子であることが判明したときの、夫のショックや怒り、失望などの精神的苦痛には計り知れないものがあります。
托卵が不法行為に該当する場合は、夫は妻に対して慰謝料を請求することもできます。ただし、慰謝料の金額は様々な事情によって異なります。
前記「1」でご紹介した例のように、妻が意図的に夫を騙したケースでは高額の慰謝料が認められやすいでしょう。
一方で、妻自身も夫の子か他の男性との子かが分からず、夫も出産直後の時点で血液型などによって自分の子ではないと知る機会があったにもかかわらず、自分の子であると思い込んでいたような場合には、慰謝料は低額となる可能性があります。
5、妻の托卵が疑わしいときの対処法

子どもを育てていく中で、「どうも自分に似ていないような気がする」「本当に自分の子なのか?」と疑心暗鬼になっている男性もいらっしゃることでしょう。
妻の托卵が疑わしいときは、以下のように対処することをおすすめします。
(1)DNA鑑定をする
一人で悩むくらいなら、DNA鑑定を依頼して事実を確かめた方がよいでしょう。自分の子であることが科学的に証明された場合は、迷いを断ち切って子どもを育てていけるはずです。他人の子であることが判明してはじめて、今後どうすべきかを検討することになります。
(2)親子関係をどうするか決断する
親子関係を否定するための法的手段は、前記「3」の(1)~(3)でご紹介したように3種類あります。
ただ、法的手段をとる前に、ご自身がどうしたいのかをじっくりと考えてから決断した方がよいでしょう。
実の親子ではなくても、何年も我が子だと思って育ててきた場合には親子の情や絆のようなものも生じているでしょうし、そんな子どもとの関係を簡単に絶とうとは思えないこともあると思います。自分なりに納得した上で、あえて自分の子として育てていきたい場合は、その方向で決断するのもよいでしょう。
納得できない場合は、親子関係を否定するための法的手段を検討することになります。子の出生を知ってから1年が経っていない場合は、早急に嫡出否認調停を申し立てるようにしましょう。1年以上が経過してしまうと、親子関係を否定することは非常に難しくなることが多いからです。
(3)養育義務の問題はできる限り話し合いで決着をつける
親子関係を否定できない場合、前記「3」(4)でご説明したように妻からの請求に対して「権利の濫用」を主張できるケースもありますが、基本的には法的に養育費の支払いを拒否することは難しくなります。
ですので、できる限り妻との話し合いで決着を付けることが得策です。当事者が合意すれば、夫が養育費を負担しないと取り決めることもできます。子どもは妻が責任を持って育てていくという内容で合意できるよう、粘り強く交渉しましょう。
いったん養育費の支払いを取り決めると、基本的に子どもが成人するまで支払い続けなければなりませんので、場合によっては離婚時の慰謝料や財産分与で多少の譲歩をしてでも、養育費の支払いを拒否した方が得策となる可能性が高いです。
(4)法律上の親子関係が残る場合は親族間の扶養義務があることに注意
法律上の親子関係を否定できなかった場合、子どもに対しては一生涯、親族間の扶養義務を負わなければならないことに注意が必要です(民法第877条1項)。妻からの養育費の請求は拒否できても、子ども自身から生活費や学費の支援を求められた場合には拒めないのです。
とはいえ、妻との話し合いで「子どもは妻が責任を持って育てる」と取り決めておけば、少なくとも子どもがある程度の年齢に達するまでは事実上、養育費の負担を拒否できる可能性が高くなります。その意味でも、養育費の問題について妻との話し合いで決着を付けることは非常に重要です。
6、妻の托卵が判明したときは弁護士に相談を

妻の托卵が判明したとき、夫が「他人の子を育てる義務はない」「悪いのは妻と相手の男性だ」と考えるのも当然のことです。
しかし、これまでに解説してきたとおり、夫が子の出生を知ってから1年が経過してしまうと、夫と子どもの法的に親子関係を否定して養育費の負担を拒否することは難しいケースが多いのが実情です。妻が誠意を持って対応すればよいですが、そんな妻ばかりではないでしょう。
困ったときは、弁護士に相談することをおすすめします。
そもそも民法が制定された明治時代にはDNA鑑定などの科学技術が発達していなかったことから、法律が現在の時代にマッチしていないという問題があります。
前記「3」(2)でご紹介した最高裁の判例(最高裁平成26年7月17日判決)では、現代においてもDNA鑑定の結果よりも民法の規定を優先すべきであるという判断が下されました。しかし、この判決を下した裁判官5人のうち裁判長を含む2人は反対意見を述べています。賛成した裁判官3人の中でも2人は、立法上の問題を示唆する補足意見を述べています。
このように、裁判官も嫡出推定に関する民法の規定については問題意識を持っていますので、事案の内容によっては最高裁判例とは異なる判決が得られる可能性があります。
ただ、そのためには裁判で具体的な事実を立証することに加えて、極めて高度な法律論を展開しなければなりません。弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。それが難しいと思われるケースでも、弁護士に依頼すれば妻との交渉を代行してくれます。弁護士の専門的な法律の知識と豊富な経験に基づく交渉力によって、妥当な解決が期待できます。
托卵女子に関するQ&A
Q1.托卵女子とは?
「托卵」とは、カッコウなどの鳥類が他の鳥の巣に卵を産みつけ、その鳥に孵化したひな鳥を育てさせることをいいます。この動物の習性になぞらえて、他の男性との子どもを産んで夫に育てさせる女性のことを俗に「托卵女子」といいます。
Q2.托卵女子の夫は自分の子ではなくても養育義務を負う?
托卵女子に騙された夫にとっては残念なことですが、自分の子として出生届を提出した以上は原則として養育義務を負わなければなりません。
Q3.托卵女子と離婚はできる?
- 托卵は不法行為に当たる可能性がある
- 不法行為が成立すれば離婚が可能
- 慰謝料を請求できることもある
まとめ
今まで育ててきた子どもが自分の子ではなかったとしても、子ども自身に罪はありません。そのため、民法の規定や裁判例の多くは子どもの利益の保護を第一に考えた立場をとっています。とはいえ、妻に騙されて他人の子を育てさせられてきた夫の立場としては、納得できるものではないでしょう。
妻の托卵が発覚した場合には、ご自身が今後どうしたいのかをよく考えて決断した上で、その方向で妻との交渉や法的手段をとることが重要となります。
親子関係を否定して養育費の支払いを拒否したい場合は、難しい法律問題に直面することが多いので、弁護士にも相談した上でじっくりと検討することをおすすめします。弁護士の力を借りて、納得のいく解決を図りましょう。














