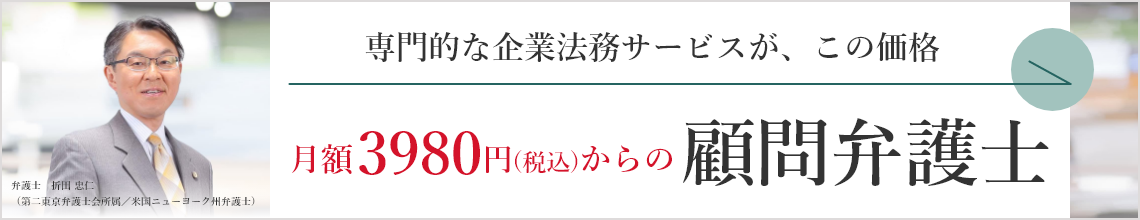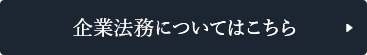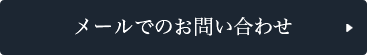企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
ファクタリングとは|売掛債権を前倒しで現金化可能

新型コロナウイルスの影響等により、資金繰りが厳しくなっている中小企業経営者の方も多いかと思います。会社の運転資金や生活費に充てるため、少しでも早く現金が欲しい場合に利用できるのが「ファクタリング」というサービスです。
この記事では、ファクタリングとは何なのか、どのような場合に利用されているのか等について解説します。
本記事がお役に立てば幸いです。
1、ファクタリングとは?
まずは、ファクタリングとはそもそも何なのかという点について、基本的な事項を解説します。
(1)売掛債権を早期に現金化できる
ファクタリングとは、弁済期が未だ到来していない売掛債権につき、ファクタリング業者に対して売却することで、前倒しで早期に現金化できるサービスをいいます。
企業が取引先に対して商品やサービスを提供した際、その購入費用は月末や翌月末等にまとめて支払うとされることが多くなっています。
つまり、企業は原則として、商品やサービスを提供したことの対価をすぐに受け取ることができません。
しかし、たとえば資金繰りがひっ迫しているような状況では、売掛金の入金を少しでも早めたいというニーズが発生します。
このような場合に利用されるのが、ファクタリングということになります。
(2)保証型と買取型について
なお、ファクタリングには、「保証型」と「買取型」の2種類があります。
「保証型」のファクタリングは、売掛債権の未回収リスクを回避することを目的とし、売掛金が回収できなくなった場合に、ファクタリング会社が保証金を支払ってくれるというものです。
これに対して「買取型」のファクタリングは、資金調達を目的とする、利用者とファクタリング業者の間の債権譲渡取引をいいます。
一般的に「ファクタリング」という場合、買取型による資金調達を想定していることが通常です。
そのため、この記事では「買取型」のファクタリングについて解説します(単に「ファクタリング」と言った場合には、「買取型」のファクタリングを指すものとします。)。
2、ファクタリングを利用する目的とは?

中小企業がファクタリングを利用する目的には、いくつかのパターンがありますので、その内容について解説します。
(1)キャッシュフローを改善する
業種によっては、売掛金の支払いサイクルが非常に長い場合があります。
この場合、企業によっては、売掛金が入ってこない間の運転資金を借り入れによりカバーせざるを得ない等、キャッシュフローが悪化してしまいます。
そこで、キャッシュフローを改善するために、定期的にファクタリングを利用して、手元のキャッシュの充実を図るということがしばしば行われています。
(2)急にまとまった資金が必要になった
緊急事態対応等を原因として、急にまとまったキャッシュが必要となった場合にも、一時しのぎの手段として、ファクタリングが利用される場合があります。
ファクタリングを利用すると、すぐに現金が得られる反面、将来受け取ることができる売掛金の金額よりも少ない金額しか得ることができません。
しかし、目の前の急場をしのぐことが優先と判断される場合には、ファクタリングの利用もひとつの手段になるでしょう。
(3)売掛先の倒産リスクを軽減する
ファクタリングにより早期に売掛債権を売却してしまえば、その時点で、売掛先が倒産して売掛金を回収できなくなるリスクから解放されます。
あまりにたくさんの売掛債権を抱えていると、急に取引先が倒産してしまった場合のダメージが極めて大きくなってしまいます。
ファクタリングを利用することにより、このような売掛先の倒産リスクを軽減することができます。
3、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングについて

ファクタリングの方法には、大きく分けて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。
両者の大きな違いは、売掛債権の債務者である取引先に知らせずにファクタリングを行うか(2社間)、それとも取引先も巻き込んでファクタリングを行うか(3社間)という点にあります。
2社間ファクタリング、3社間ファクタリングのそれぞれの仕組みとメリット・デメリットについて見ていきましょう。
(1)2社間ファクタリングの仕組み
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング業者のみの間でファクタリング契約を締結し、取引先に知らせることなく、ファクタリング取引を完結する方法です。
2社間ファクタリングにおける取引の流れは、以下のとおりです。
<2社間ファクタリングの流れ>
①利用者とファクタリング業者の間でファクタリング契約を締結する。
②ファクタリング契約に従い、利用者はファクタリング業者に対して、売掛債権を売却する。ファクタリング業者は利用者に対して、債権譲渡代金を支払う。
③売掛債権の弁済期までに、利用者がファクタリング業者に代わって取引先から売掛金を受領する(取引先は何も知らず、取引の契約に従って、利用者に対して支払いを行う。)。
④利用者がファクタリング業者に対して、取引先から受領した売掛金の全額を支払う。
(2)3社間ファクタリングの仕組み
一方、3社間ファクタリングは、利用者・ファクタリング業者・取引先の3社間でファクタリング契約を締結して行われます。
3社間ファクタリングにおける取引の流れは、以下のとおりです。
<3社間ファクタリングの流れ>
①利用者・ファクタリング業者・取引先の3社間でファクタリング契約を締結する。
②ファクタリング契約に従い、利用者はファクタリング業者に対して、売掛債権を売却する。ファクタリング業者は利用者に対して、債権譲渡代金を支払う。
③売掛債権の弁済期までに、取引先はファクタリング業者に対して、直接売掛金を支払う。
(3)どちらを利用すべき?
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングを比較した場合に、どちらの方法を利用すべきかについて、ケースごとに解説します。
①2社間ファクタリングを利用した方が良い場合
- 取引先にファクタリング利用を秘密にしたい場合
取引先にファクタリング利用の事実が知られた場合、資金繰りの悪化を疑われてしまい、会社に対する信頼が損なわれるのではないかという懸念があります。
取引先にファクタリング利用を秘密にしておきたいという場合には、2社間ファクタリングによる必要があります。
- 取引先を交えた交渉の手間を省きたい場合
取引先を巻き込んでファクタリング契約を締結する3社間ファクタリングの場合、取引先も契約当事者になるため、契約交渉や契約締結のための手続、確認等を取引先も交えて行う必要があります。
特に、取引先が規模の大きい企業である場合には、意思決定のスピードがスローになりがちであり、契約交渉に手間と時間が大きくかかってしまうこともしばしばです。
このような契約交渉の手間と時間を省きたい場合には、2社間ファクタリングを選択する方がベターでしょう。
②3社間ファクタリングを利用した方が良い場合
- 手数料を抑えたい場合
3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングと比べて、手数料の金額が低くなる傾向にあります。
2社間ファクタリングの場合、取引先から利用者に対して、売掛金がいったん支払われます。
つまり、ファクタリング業者の側から見れば、その段階で、利用者に売掛金を使い込まれてしまったり、利用者が倒産してしまったりするリスクが存在します。
このリスクを考慮して、2社間ファクタリングでは、手数料が高めに設定されています。
一方、3社間ファクタリングの場合は、取引先からファクタリング業者に対して、売掛金が直接支払われるため、上記のようなリスクがありません。
そのため、2社間ファクタリングの場合と比較して、手数料は低く抑えられています。
以上から、手数料の金額を抑えたい場合には、3社間ファクタリングを利用することをおすすめします。
- 大手のファクタリング業者を利用したい場合
世間には、ファクタリングを装った違法業者も存在しているため、利用するのであれば、大手で信用のあるファクタリング業者にしたいという方も多いでしょう。
しかし、大手のファクタリング業者では、2社間ファクタリングのサービスを提供していない場合がほとんどです。
そのため、大手のファクタリング業者を利用する場合には、必然的に3社間ファクタリングを行うことが前提になります。
4、ファクタリングの業種別利用例

ファクタリングは、さまざまな業種の企業において、利用されています。
以下では、業種別に見たファクタリングの利用例について紹介します。
(1)建設業
建設業では、ゼネコン・下請け・孫請け等、複数階層にわたって契約が行われているため、支払いサイクルが長くなりがちです。
しかし、人件費等の固定費は毎月発生するため、ファクタリングにより支払いサイクルの短縮化が図られています。
(2)運送業
運送業では、車両の購入や突然の事故・故障等により、突発的にキャッシュが必要となる事態が発生することがあります。
キャッシュを借り入れで賄うことも考えられますが、新規車両購入時のリース・ローン等の審査への影響等を考慮し、ファクタリングが利用される場合があります。
(3)インターネット通販業
インターネット通販業では、主にクレジットカード決済が用いられるため、売り上げが実際に入金されるのは、販売からある程度時間が経ってからになります。
特に、サービスの立ち上げ当初は、キャンペーン等による持ち出しも発生し、資金繰りが非常に厳しくなるケースが多いといえます。
そのため、サービスが軌道に乗るまでの間、ファクタリングを利用して、キャッシュ不足を防ぐことが試みられています。
5、ファクタリング利用時の注意点は?

ファクタリングは、資金繰りに難を抱える企業にとって便利なサービスですが、一方で、利用時に注意しなければならない点も存在します。
(1)通常の融資よりも手数料が高い
ファクタリングは、将来受け取れる売掛金を今受け取るという意味で、「売掛金の前借り」であるといえます。
つまり、ファクタリングの機能は、実質的に融資と同じですが、ファクタリングの方が、通常の融資よりも手数料率が高くなる傾向にあります。
そのため、ファクタリングを繰り返し利用していると、かえって資金繰りが悪化してしまう可能性があるので、注意しましょう。
(2)ファクタリングを装う闇金業者が存在する
ファクタリングは、あくまでも貸付ではなく、債権譲渡取引であるという整理の下、貸金業法の規制対象外となっています。
しかし、ファクタリング業者の中には、売掛債権が決済されないときは、利用者に買い戻させる特約を付す等して、自ら未回収リスクを取ることなく、ファクタリングを行っているケースも存在します。
このような場合には、債権譲渡ではなく、担保貸付とみなされ、貸金業法等の規制対象となります。
具体的には、ファクタリング業者に、貸金業者としての登録が必要となるほか、出資法上の上限利息の規制に服することになります。
これらの規制を遵守せず、ファクタリングに仮装して、違法な条件での貸付を行っている闇金業者には、十分に注意しましょう。
(3)ファクタリング契約を締結する際のポイントは?
上記を踏まえて、利用者がファクタリング契約を締結する際に、契約上注意しなければならないポイントについて解説します。
①契約書に債権の「売買契約」であることが明記されている
あくまでも債権譲渡契約であり、貸付には該当しないといえることを確認する必要があります。
そのため、契約書において債権譲渡契約(債権の「売買契約」)であることが明記されていることを確認しましょう。
②売掛債権の買戻し義務または償還義務が定められていない
すでに解説した通り、売掛債権が回収不能になった際、利用者に買戻し義務や償還義務が定められている場合には、売掛債権に関するリスクが移転していないとみなされます。
この場合、貸金業法の規制対象となり、現状では、ほとんどのケースが違法と判断されると考えられます。
そのため、利用者に売掛債権の買戻し義務または償還義務が定められていないことを必ず確認しましょう。
③債権の買取代金が債権額から著しく乖離していないこと
比較的短期間に回収できる売掛債権について、高額な手数料を課すようなファクタリングは、貸金業法等との関係での適法性の問題を横に置いても、利用者にメリットがあるとはいえません。
ファクタリングを実際に利用する前に、手数料の金額や料率については、十分に確認しましょう。
まとめ
中小企業にとって、ファクタリングは資金繰りの急場をしのぐための有効な手段になり得ます。
しかし、世間には悪徳ファクタリング業者が存在することも事実で、業者選びや契約内容の精査を慎重に行う必要があります。
ファクタリングの利用を検討する中小企業経営者の方は、悪徳ファクタリング業者に引っかからないよう、実際のご利用前に、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事
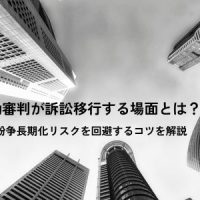
労働審判が訴訟移行する場面とは?紛争長期化リスクを回避するコツを解説
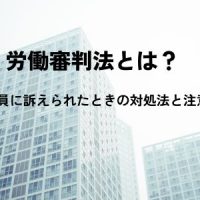
労働審判法とは?会社が従業員に訴えられたときの対処法と注意点を解説
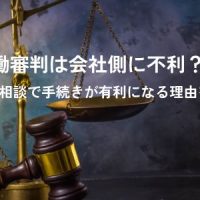
労働審判は会社側に不利?弁護士への相談で手続きが有利になる理由を解説