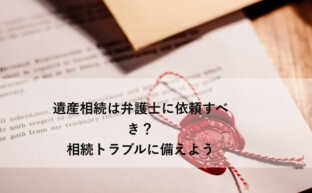親が多額の借金を残して亡くなったときは、相続放棄をすることで負債の相続を免れることができますが、自分が相続放棄をしたために我が子が代わりに祖父母の借金を相続してしまうのではないかと気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続放棄をすることによって代襲相続が発生するかどうかは、事前に知っておく必要があります。
また、相続放棄も代襲相続も、本来の相続が行われる場合とは異なる流れで故人の財産や負債が承継されるため、注意しなければ相続人間で思わぬトラブルが発生するおそれがあります。
そこで今回は、
- 相続放棄をすると代襲相続が生じるのか
- 相続放棄をすることで他の相続人にどのようなリスクがあるのか
- 他の相続人とトラブルになった場合はどうすればいいのか
といった問題について解説していきます。
相続放棄を考えているけれど代襲相続が気になるという方のご参考になれば幸いです。
相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、相続放棄による代襲相続を知る前に〜①そもそも代襲相続が起こるケース

代襲相続とは、本来なら相続人となるはずの人が一定の事由により相続できない場合に、その人の子が代わって相続人となる制度のことです。
自分で手続きを行う相続放棄と異なり、代襲相続は自分の意思とは関係なく起こります。
そのため、ときには予期せぬ相続関係が発生してしまうこともあります。
そこで、まずは代襲相続がどのようなケースで起こるのかをご説明します。
(1)相続人が死亡している
代襲相続がどのような場合に起こるかについては、民法第887条2項で3つのケースが定められています。
第八百八十七条二項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
引用元:民法
まず1つめのケースでは、被相続人の子が相続開始前に既に死亡している場合です。
この場合は、その人の子(被相続人の孫)が代襲相続によって相続人となります。
孫も既に死亡している場合は、孫の子(被相続人の曾孫)が相続人となります。
このように代襲相続人が既に死亡している場合にさらに発生する代襲相続のことを「再代襲相続」といいます。
なお、被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合は、甥や姪が代襲相続によって相続人となるケースもあります(民法第889条2項)。
甥や姪が代襲相続する場合はさまざまなトラブルが発生しがちなので、後ほど3(3)で詳しくご説明します。
(2)相続人が相続欠格により相続できない
代襲相続が発生する2つめのケースは、相続人が相続欠格に該当する場合です。
相続欠格とは、法定相続人に該当するものの被相続人の財産を相続によって取得するのが相当でないと認められる「欠格事由」がある場合に相続権が認めらないことをいいます。
欠格事由は民法第891条で次の5つが定められています。
- 故意に被相続人や他の相続人を死亡させたか、死亡させようとしたことで刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたことを知っているのに告訴や告発をしなかった場合(ただし、本人が子供であったり認知症などのために是非弁別能力を欠くときや、殺害者が本人の配偶者や親、子、祖父母、孫など直系血族であった場合は除く)
- 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作成したり撤回や取り消し、変更することを妨げた場合
- 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言の作成や撤回、取り消し、変更をさせた場合
- 遺言書を偽造や変造、破棄、隠匿した場合
以上のいずれかに該当する違法または不当な行為で相続関係に影響を及ぼした人は、相続人となることができません。
しかし、その人の子については、独自に相続欠格に該当しない限り相続権を剥奪される理由はありません。
したがって、相続人が相続欠格により相続できない場合は、その人の子が代襲相続して相続人となります。
(3)相続人が相続廃除され相続できない
代襲相続が発生する3つめのケースは、相続人が相続廃除された場合です。
相続廃除とは、遺留分がある推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えるなど著しい非行があったときに、被相続人がその推定相続人の相続権を失わせるために家庭裁判所で行う手続きのことをいいます(民法第892条)。
被相続人は自分で直接家庭裁判所に廃除を請求することもできますし、遺言で廃除の意思表示をすることもできます。
遺言で排除の意思表示をしたときは、被相続人が亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求することになります(民法第893条)。
なお、推定相続人とは、被相続人が亡くなったら相続人となる立場にある人のことをいいます。
遺留分がある推定相続人とは、要するに被相続人の配偶者と子(子がいない場合は両親や祖父母)のことです。
推定相続人に著しい非行があることを理由に被相続人が廃除したとしても、その推定相続人の子については独自に著しい非行が認められない限り、相続権を剥奪される理由はありません。
したがって、相続人が相続廃除されたことによって相続できない場合も、その子が代襲相続して相続人となります。
(4)養子の代襲相続
代襲相続できるのは被相続人の直系卑属、つまり孫や曾孫などです。
それでは、「被相続人の養子の子」や「被相続人の子の養子」は代襲相続できないのでしょうか。
養親と養子はもともと他人でも、養子縁組をした日から法律上の血族関係が発生します。
そのため、養子にも実子と同じ相続権が認められます。
そこで、養子と代襲相続の関係についてですが、養子縁組の後に生まれた養子の子は養親(被相続人)の直系卑属に該当するので、代襲相続します。
一方、養子縁組の前に生まれていた養子の子は養親(被相続人)の直系卑属とは認められず、代襲相続はできません。
被相続人の子の養子は、被相続人が亡くなるよりも前に養親と養子縁組をしているはずなので、代襲相続します。
2、相続人が相続放棄した場合は代襲相続されるのか

どのようなケースで代襲相続が発生するかについては、前記1で民法の規定を参照しつつご説明しましたが、そこでは「相続放棄」のケースは出てきませんでした。
では、相続人が相続放棄した場合は代襲相続されるのでしょうか、されないのでしょうか。
まずは、相続放棄とは何かについて簡単に確認しておきましょう。
(1)相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の全ての財産に関する相続権を放棄することをいいます。
相続放棄には、プラスの財産を取得できなくなるというデメリットもありますが、借金などマイナスの財産も引き継がなくなるというメリットがあります。
相続放棄をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きを行います。
併せて、戸籍謄本や遺産目録などの必要書類も提出します。
相続放棄の手続きには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないという期限がある(民法第915条1項)ので、注意が必要です。
(2)相続放棄をしたら代襲相続されるのか
では、相続放棄をしたら代襲相続されるのかについて結論を言いますと、代襲相続されません。
相続放棄をした人は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。
そのため、その子や孫などの直系卑属が代襲すべき相続権がそもそもありません。
相続欠格や相続廃除の場合は該当する個人の相続権が剥奪されるだけなので代襲相続しますが、相続放棄の場合は初めから相続権がなかったことになるので代襲相続しないのです。
したがって、祖父が多額の負債を残して亡くなり、その子が相続放棄をした場合孫が代襲相続することはありません。
この場合、孫は相続放棄などの手続きは何もしなくても祖父の負債を相続することはないので、心配いりません。
ただ、逆に、祖父に借金がなく、多くの資産を残して亡くなった場合、子が何らかの事情で相続放棄をすると、孫は自分の親に代わって祖父の資産を代襲相続したいと思ってもできないことになります。
(3)ただし甥や姪は可能性あり
相続放棄をすると代襲相続は発生しないという結論だけを覚えてしまうと、思わぬトラブルが発生するケースもあります。
なぜなら、代襲相続は被相続人の直系卑属だけではなく、兄弟姉妹から甥や姪にも起こる可能性があるからです。
具体的にご説明しましょう。
①子の相続放棄により甥や姪が代襲相続するケース
被相続人に子がおらず、両親や祖父母も既に亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となりますが、この場合にも代襲相続が起こります(民法第889>条2項)。
兄弟姉妹も既に亡くなっている場合で、その子(甥や姪)がいるときは、甥や姪が代襲相続します。
このとき、被相続人の財産の収支がプラスであれば問題になることはないでしょうが、多額の借金があれば、甥や姪が被相続人の借金を相続することになってしまいます。
上記は、被相続人に子がいない場合ですが、子が相続放棄した場合にも、子がいなかったと同じことになるため、兄弟姉妹への相続や甥・姪への代襲相続が起こる場合があります。
例えば、被相続人Aさんに一人息子のBさんがいるものの、配偶者はなく、両親も祖父母も既に亡くなっているとします。
その他の親族としては、既に亡くなっている兄の一人息子(被相続人の甥)であるCさんがいるとしましょう。
このケースでAさんが亡くなったとき、Bさんが相続放棄をすると、Cさんが自分の親(被相続人の兄)を代襲して相続することになります。
②相続放棄によるトラブルを回避するために
上記のケースで、Cさんとしては、Aさんの一人息子であるBさんが相続すると考えるはずなので、まさか自分がAさんを相続するとは考えもしないのが普通でしょう。
日頃から親密に交流していた場合はまだしも、疎遠になっていた場合はなおさらです。
Bさんが相続放棄をしたことは、裁判所からCさんへ通知されるわけではありません。
BさんからCさんへ伝えなければ、Cさんにとっては知るよしもないことです。
それにもかかわらず、Bさんが相続放棄をしてCさんに伝えずにいると、Cさんは何も知らない間にAさんの借金を相続してしまうことになります。
そんなCさんから苦情を言われた場合、Bさんとしては「あなたが相続人だから仕方がない」と告げて相手にしないことも法律上は可能です。
しかし、それでは円満な親族関係は望むべくもないでしょう。
親族間のトラブルを回避するためには、自分が相続放棄をすることで影響を受ける親族がいないかを確認し、いる場合は相続放棄することを連絡しておきましょう。
連絡さえしておけば、Cさんも期限内に相続放棄をするなどの対策が可能になります。
3、親の相続を放棄した者は祖父母の代襲相続をするか

相続放棄と代襲相続の関係で、もう一つ注意すべきことがあります。
相続放棄をすると、自分の子や孫は代襲相続しないことはおわかりいただけたと思います。
今度は、自分の親が亡くなったときに相続放棄をした後に、祖父母が亡くなった時、自分が親に代わって祖父母を代襲相続できるかという問題を考えてみましょう。
結論から言いますと、この場合は代襲相続できます。
その理由は、民法の規定を見れば明らかです。
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:民法
つまり、親の相続を放棄した場合、初めから相続人とならなかったこととみなされるのは親の相続についてだけです。
祖父母の相続については、相続権を失っていません。
したがって、親に借金があるために相続放棄をしたものの、その後に亡くなった祖父母にプラスの資産がある場合は、代襲相続によって資産を引き継ぐことができます。
祖父母にも借金があった場合は、改めて相続放棄をしなければその借金を引き継いでしまうので、注意が必要です。
4、相続放棄、代襲相続でわからないことがあれば弁護士へ相談を

相続放棄をすれば、自分は被相続人の借金から免れることができても、思わぬところで親族に影響が出る場合もあります。
かといって、相続放棄には3ヶ月という申述期限があるので、いつまでも悩んでいるわけにもいきません。
相続放棄の手続きは難しいものではありませんが、必要書類の収集に手間と時間がかかる場合が多いので、早期に準備を始める必要があります。
相続放棄と代襲相続の関係については、この記事をよくお読みになってご自分のケースに当てはめていただければ、きっとご理解いただけるはずです。
とはいえ、複雑でわかりにくいケースが少なくないのも事実です。わからないことがあれば、悩んで時間を無駄にすることがないよう、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
まとめ
「相続放棄をすると子が代襲相続するのか?」という疑問に対する回答は「相続放棄した人の子は代襲相続しない」ということになります。
しかし、相続放棄をしたことによって他の親族に影響が及び、トラブルが発生するリスクがあります。
トラブルを避けるためには、相続放棄と代襲相続の関係を正しく判断し理解して行動しなければなりません。
複雑な法律関係についてお悩みの場合は、お気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。