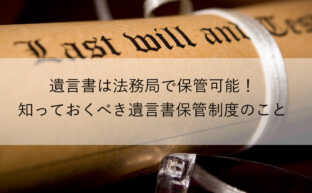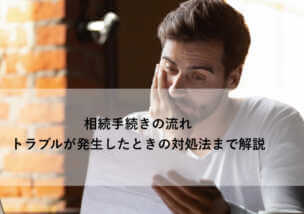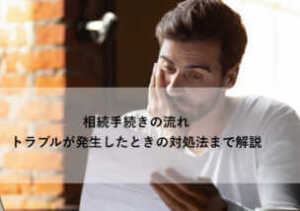
相続手続きの流れとは、どのようなものなのでしょうか。
身内の方が亡くなった場合に相続の手続きが必要になるということは、多くの方がご存知のことと思います。
実際に相続が開始すると、おそらく想像している以上に、何をいつまでにしなければならないという細かいルールがたくさんあります。
相続人全員が協力して手続きを進めることができれば問題は少ないですが、相続トラブルが発生して思うように手続きを進めることができないこともよくあります。
そこで今回は、
- 相続手続きの流れとは
- 相続手続きでトラブルが発生したときの対処法
- 相続手続きを相談できる窓口
などを中心に、相続の手続きや流れについて詳しく解説していきます。
現在、相続手続きで何からのトラブルに直面してお困りの方にも、今後の相続手続きに不安のある方にも、この記事がご参考になれば幸いです。
相続に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1、相続手続き全体の流れを時系列で確認

相続手続きには、何をいつまでにしなければならないという決まりがたくさんあります。
そのため、身内の方が亡くなったら、必要な手続きについて漏れがないようにひとつひとつ進めていくことが大切です。
そこでまずは、身内の方が亡くなった後にやるべきことを時系列で確認しておきましょう。
以下の一覧表について、基本的には上から順にひとつひとつご覧いただきたいのですが、ケースによっては必要がない手続きも含まれているはずです。
ご自身のケースで必要な手続きはどれかという点にも着目しながら、ご確認ください。
| 相続に関する手続き | 期限 |
1 | 死亡届・死亡診断書の提出 | 死亡を知ったときから7日以内 |
死体埋葬火葬許可証の交付申請 | ||
2
| 親族等への連絡 |
適宜(通常は死亡当日~数日以内)
|
葬儀 | ||
3 | 年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出 | ・国民年金は死亡日から14日以内 ・厚生年金は死亡日から10日以内 |
4 | 未支給年金の請求 | 受給権者の最後の年金支払日の翌月初日から5年以内 |
5 | 国民健康保険証の返却 |
死亡日から14日以内
|
介護保険資格喪失届の提出 | ||
世帯主の変更届 | ||
6
| 遺言書の有無の確認 |
できる限りすみやかに
|
遺言書の検認 | ||
相続人の調査 | ||
相続財産の調査 | ||
遺産分割協議 | ||
遺産分割協議書の作成 | ||
7 | 相続登記 | なるべく早く |
8 | 相続放棄の申述 | 自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内 |
限定承認の申述 | ||
9 | 故人の所得税の準確定申告 | 死亡日の翌日から4ヶ月以内 |
10 | 相続税の申告・納付 | 死亡日の翌日から10ヶ月以内 |
11 |
遺留分侵害額請求権の行使
| 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、それらの事実を知らない場合は相続開始から10年以内 |
12 | 高額療養費の還付請求 | 還付の対象となる支払い月の翌月1日から2年以内 |
13 | 国民年金の死亡一時金の請求 葬祭費・埋葬費の請求 | 死亡日の翌日から2年以内 |
14 | 遺族年金等の請求 | 死亡日の翌日から5年以内 |
15 | 生命保険金の請求 | なるべく早く |
遺産分割そのものには特に期限はなく、身内の方が亡くなってから長期間が過ぎてしまった後でも、遺産分割協議をすることはできます。
しかし、上記の表のうち、明確に期限が決められているものについては、期限が経過してしまうと手続きができなくなったり、ペナルティを課されたりすることがあるのでご注意ください。
2、一般的な相続手続きの流れ
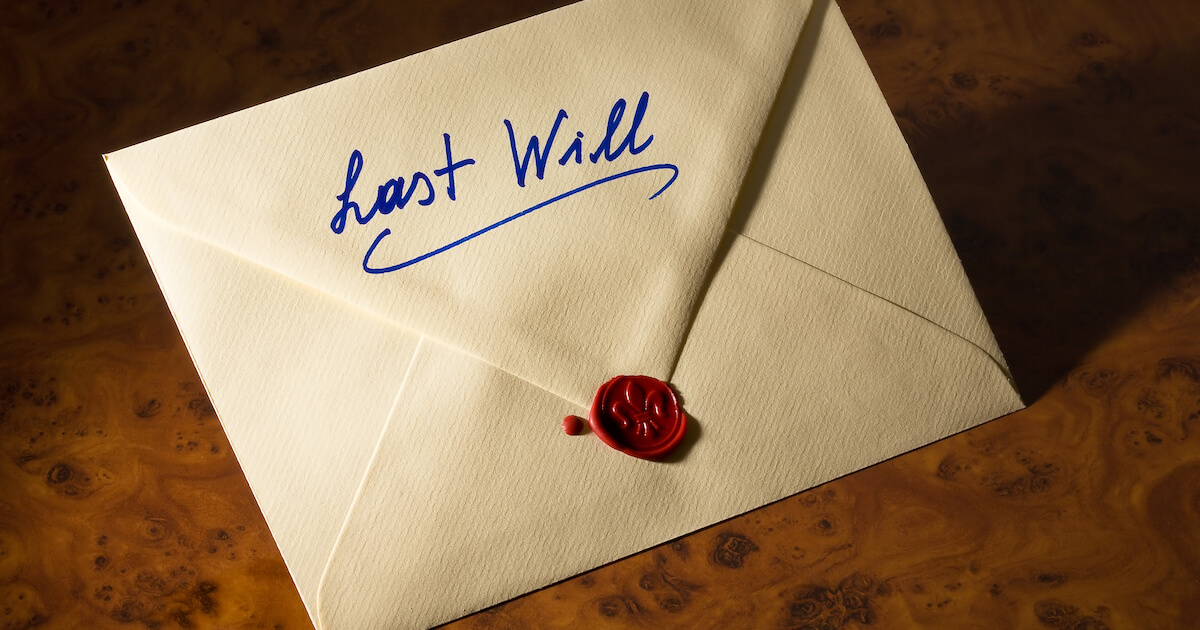
それでは、相続手続きの流れを具体的にみていきましょう。
ここでは、相続人間に特にトラブルがなく、円満に相続財産を分割できる一般的なケースを想定してご説明します。
なお、以下の順番はおおよそのものですので、可能なものから順に、また、いくつかの手続きを並行して進めていきましょう。
(1)遺言書の有無の確認
身内の方(被相続人)が亡くなったら、まずは遺言書がないか確認しましょう。
自筆証書遺言または秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所へ検認を申し立てなければなりません。
ただし、自筆証書遺言については法務局で保管されていた場合には検認は不要です。
なお、公正証書遺言の場合も、検認は不要です。
遺言書で遺産分割の方法が指定されている場合は、基本的には指定されたとおりに遺産分割を行います。
ただし、相続人全員が同意した場合は、別の方法で遺産分割を行うことも可能です。
(2)相続人の調査
まず、法律上相続人となる者を調査し確定します。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して行います。
相続人の調査を怠り、遺産分割協議が終わった後に相続人が現れると、すでに行った遺産分割協議が無効となるなど、思わぬ紛争に発展することがありますので、注意が必要です。相続税の計算にも大きな影響を与えますので、相続が開始したら、まずは相続人の調査・確定をしましょう。
なお、胎児は相続については、既に生まれたものとみなされるので、相続人に含まれます。
(3)相続財産の調査
相続財産となるものを調査し、その価値を算出していきます。
不動産の価値は、厳密には不動産鑑定士による鑑定によりますが、相続人間で固定資産評価や路線価、不動産会社の査定などを基準に算定するという合意を行うこともあります。
(4)遺産分割協議
遺言書がない場合には通常、相続人間でどのように相続財産を分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行います。
実際に会って話し合うことでももちろん良いですし、電話や手紙、メールなどを用いて遠隔で話し合うことでも構いません。
遺言書があっても、相続人全員の合意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。
そのため、遺言書がある場合でも遺産分割協議を行うべき場合もあります。
なお、遺産分割協議で話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は、後日「言った、言わない」のトラブルを防止する証拠になりますし、相続登記や金融機関等での手続きでも遺産分割協議書が必要になります。
法定相続人の立場ごとに民法で定められた相続分(法定相続分)のとおりに相続する場合も、後からトラブルになることを防ぐため、遺産分割協議書を作成しておくことが一般的です。
(5)相続登記、金融機関に対する手続き等
遺産分割の結果に基づいて不動産の名義変更や、預貯金の払戻し等を行います。
これらの手続きには期限はありませんが、なるべく早く行いましょう。
銀行では、相続が開始すると相続人が被相続人の口座から引き落とせる額が限定されます。
遺産分割協議が整い、協議書を作成したら、その他必要な書類を用意して金融機関へ行きましょう。
銀行によっては、書類ごとに取得すべき時期(発行日から3か月以内のもの等)が設けられていることもありますので注意しましょう。
(6)準確定申告
被相続人が自営業者であった、不動産収入があったなど確定申告をしなくてはならない者であった場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなくてはなりません。
これを怠ると、無申告加算税、延滞税等が課せられますので注意が必要です。
年金収入のみの場合、年金が400万円以下であれば確定申告が不要ですが、確定申告を行うことで源泉徴収された所得税が還付される可能性もあります。
早めに確認するのをお勧めします。
(7)相続税の申告
相続財産が基礎控除の金額を超える場合等には死亡日の翌日から10ヶ月以内申告する必要があります。
こちらも怠ると、無申告加算税や延滞税等が課せられることとなります。
申告が不要と思っていて申告しなかったが、実は申告が必要だったという場合も無申告加算税、延滞税が課せられますので、早期に税理士に確認することをおすすめします。
3、相続でトラブルが発生したときに行うべき手続き

以上の相続手続きがスムーズに進めば良いのですが、ときには何らかのトラブルが発生することもあります。
ここでは、相続でトラブルが発生した場合に行うべき手続きについてご説明します。
(1)遺産分割協議がまとまらないとき【遺産分割調停・審判】
遺産分割協議を行ったものの、相続人同士の意見が合わなかったり、感情的になったりしてもめるケースが少なくありません。
そんなときは、弁護士に依頼して間に入ってもらうことで、話し合いがスムーズに進むようになることもあります。
それでも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停や審判の申し立てを検討することになります。
調停では、専門的な知識を有する調停委員が中立公平な立場で話し合いを仲介し、柔軟な解決が図られます。
調停でも話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所の審判によって遺産分割の方法を定めてもらうことができます。
(2)被相続人に借金があったとき【相続放棄・限定承認】
被相続人に借金があると、借金も相続人に引き継がれてしまいます。
しかし、相続放棄をすれば借金を相続せずに済みます。プラスの遺産よりも借金などのマイナスの遺産の方が多い場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。
ただし、相続放棄をすると借金だけでなく、プラスの財産やその時点では気づいていない相続財産も含めて一切相続できなくなることに注意が必要です。
手放したくない相続財産がある場合は、プラスの遺産の範囲内でのみマイナスの遺産を相続する「限定承認」をするかどうかを検討してみましょう。
相続放棄、限定承認とも、手続きをするためには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述をします。
(3)不公平な遺言書があるとき【遺留分侵害額請求】
例えば、「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言書があった場合、他の相続人は遺産を一切もらえないのかと考えてしまうことでしょう。
しかし、被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲相続人)以外の法定相続人には、「遺留分」として一定割合の遺産の取得が保障されています。
遺留分割合は、直系尊属のみが法定相続人である場合には、相続財産の3分の1、それ以外の場合には、相続財産の2分の1となります。
相続人が複数いる場合には、個々の遺留分は、遺留分割合と法定相続割合に従って定まります。
遺留分を侵害された場合は、侵害された遺留分の金額について、受遺者または受贈者に支払いを請求することができます。
(4)相続人でない人が相続財産を占有しているとき
相続人ではない人が相続財産を占有している場合、相続人は個々の相続財産について所有権を相続していますので、所有権に基づいて返還請求権や妨害請求権を行使することができます。
これに対して占有している側から、これは相続回復請求権の行使であるとして消滅時効(相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間)や消滅時効(た相続開始の時から20年)が主張され、請求が認められなくなる可能性がありますので、上記の返還請求権、妨害排除請求権の行使は早めに行う必要があります。
4、相続手続きを放置するリスク

相続人間に特段の争いがない場合、相続手続きをとらずに放置している人も少なくありません。
しかし、相続手続きを放置することには様々なリスクがあります。
ここでは、特に注意すべき3つのリスクをご紹介します。
相続手続きは面倒かもしれませんが、リスクを避けるためには期限内に適切に手続をしておくことが重要です。
(1)借金を相続するおそれがある
前記「3(2)」でご説明したように、被相続人の借金は相続人に引き継がれてしまいます。
借金を相続しないためには、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。
なお、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過後に借金があることを知った場合でも、「借金を相続したことを知ってから3ヶ月以内」であれば相続放棄が可能な場合もあります。
その場合の手続きは複雑になることが多いので、弁護士に相談されることをおすすめします。
(2)相続できなくなる場合もある
例えば、他人が相続財産である不動産を自分のものだと思って占有している場合、その事実を知ったときから5年以内に返還請求を行わないと相続財産を取り戻すことができなくなる可能性があります。
他にも、相続手続きをしないままでいるうちに、他の相続人が現金など相続財産を使い果たしてしまうこともあるでしょう。
この場合、不当利得返還請求を行うことを検討しますが、実際に使い果たされてしまったもの、売り払われてしまったものを回収することは実際は困難な場合が多いです。
なお、相続開始後から遺産分割前までに使い込みがなされた場合、使い込みを行った相続人以外の相続人全員の同意がある場合には、使い込みがなされた分も相続財産に含めたうえで遺産分割協議を行うことができます(民法906条2項)。
(3)相続財産の売却が困難になる可能性がある
相続財産の中に不動産がある場合、相続登記をしていなければ、売却する際に相続人全員の名義で手続きをする必要があります。
相続人の人数が少なければ問題は少ないかもしれませんが、放置しておくとさらに相続が発生し、その不動産を相続で取得した人の人数が次々に増えてしまいますし、連絡がつかない人がでてくることもあります。
場合によっては不動産の売却が困難になることもあるので、相続登記は早めに済ませておきましょう。
5、相続手続きで困ったときの相談先

相続手続きには複雑なものも多いので、適宜、専門家に相談するのがおすすめです。
ただし、ひと口に相続手続きといっても様々なものがあり、手続きによって専門家が異なります。
(1)弁護士
遺産分割協議がまとまらない場合や、遺言書の内容に不満を持つ人がいる場合など、相続人の間に法的な争いがある場合は、弁護士に相談すべきです。
(2)司法書士
相続財産である不動産の名義変更など、登記に関することは司法書士に相談すべき事柄です。
(3)税理士
相続税の申告や節税対策については、税理士に相談すると良いでしょう。
(4)ワンストップ対応可能な法律事務所への相談がおすすめ
以上のように、手続きによって相談・依頼すべき専門家が異なります。
トラブルやつまずきの内容によっては、複数の専門家に相談するのが適当な場合もありますし、トラブルの中には法律の問題と税金の問題が複雑に絡まりあっているものもあります。
しかしながら、ただでさえ複雑で進めるのが大変な相続の手続きを進めながら、何が問題なのかを分析し、問題ごとに専門家を探すのは大きな負担となるでしょう。
この負担を少しでも軽減するため、弁護士や税理士、司法書士などさまざまな専門家が所属しているワンストップでの対応が可能な法律事務所への依頼を検討することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士はもちろん税理士や司法書士も複数所属しています。
お困りの状況に応じて各種専門家がチームを作り担当しますので、相続に関するすべてがベリーベスト内で完結します。
ぜひベリーベスト法律事務所までご相談ください。
まとめ
相続が開始すると、様々な手続きを期限内に行っていく必要があります。
ひとつひとつ確認しながら、効率よく進めていくことが大切です。
ひとたび相続トラブルが発生すると、手続きを進められないまま時間が過ぎてしまい、どうすれば良いのか、どこから手をつけてよいのかわからなくなってしまうかもしれません。
そんなときは、お早めに相続問題に強い弁護士にご相談の上、適切に対処していきましょう。