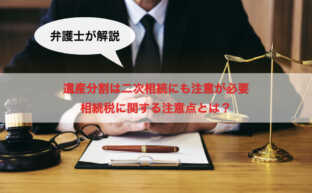相続税は申告期限があるんだった!いつまでだっけ?
- 相続人どうしの話し合いがうまくいかなくて遺産分割の話し合いもできていない状態…。申告期限を延長してもらうことはできる?
- もし、相続税の申告期限に遅れてしまったらどうなるの?
財産を所有していた人が亡くなった場合、その人の親族は相続人として財産の所有権を引き継ぐことになります。
一方で、亡くなった人が残した財産(遺産)の金額が一定額を超える場合には、期限までに相続税の申告をして税金を納めなくてはなりません。
申告期限までに納付ができなかった場合、延滞税や加算税という形でペナルティが課せられてしまうこともありますので注意しておきましょう。
この記事では、以下のような内容について解説いたします。
- 相続税の申告期限に関するルール
- 相続税を期限までに納めなかった場合の罰則
- 相続税の申告期限が延長してもらえるケース
- 相続税の申告をしなくてもOKなケース
初めて遺産相続の手続きにかかわる人の参考になればうれしく思います。
相続税の申告手順について知りたい方は以下のページもご覧ください。
目次
1、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知ってから10カ月以内

相続税の申告期限は、あなたが相続の発生を知った日(被相続人の死亡を知った日)の翌日から起算して10か月となります。
たとえば、3月3日に被相続人が亡くなり、その事実をその日のうちにあなたが知ったとすると、翌年1月3日(死亡翌日の3月4日から起算して10か月目の日)が相続税の申告期限日となります。
なお、申告期限の起算点に関する詳しいルールと、申告期限が土曜日曜であるケースについても確認しておきましょう。
(1)被相続人が死亡した日ではなくそのことを知った日から起算する
相続税の申告期限の起算点は、被相続人が死亡した日ではなく「被相続人が死亡したことを相続人が知った日」とされています。
この点が問題となるのは、家族に死亡を知らせてもらえなかった・長期旅行中で知らせてもらうことができなかった・行方不明で知らせることができなかった、などのケースです。
これらの場合には、「客観的に見てあなたが被相続人の死亡を知りえたかどうか」を基準に判断されることになります(あなた自身が実際に知っていたかどうかではなく、普通の状況なら知ることができた時点から起算されます)
例えば、あなたの自宅に被相続人の死亡を知らせる手紙が来ていたのに見ていなかったというような場合には、その手紙が自宅に届いた日が起算点となるでしょう。
法律のルールを知らなかったとしても、申告期限が延長されるわけではありませんから注意が必要です。
(2)申告期限が土日の場合
申告の期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が申告期限となります。
申告書は税務署へ持参して提出しましょう(郵送による提出もできます)。
税務署に持参するときは、「被相続人が死亡した時の所在地を管轄する税務署」に相続税の申告書を提出します。「相続人の所在地を管轄する税務署」ではないので気をつけましょう。
郵送による提出のケースでは、「消印日」が提出日となりますから、消印日を明確にするために書留郵便か特定記録で送付することをおすすめします。
2、期限までに申告ができなかった場合どうなるの?

もし、相続税の申告期限までに申告ができなかった場合にはどうなるのでしょうか。
結論から言うと、本来納めるべき相続税の金額の他に、ペナルティを課せられてしまう可能性があります。
ペナルティとは、具体的には追徴課税(延滞税と加算税があります)の発生と、相続税額を減らしてもらえる税軽減措置を利用できなくなることの2つが重要です。
それぞれのペナルティの内容について、順番に見ていきましょう。
(1)追徴課税等が発生する
追徴課税とは、本来の税額(本税といいます)の他に取られてしまう税金のことをいいます。
追徴課税には、無申告加算税や重加算税といったようなものがあります。
①納税が遅れたことへの延滞税の発生
延滞税は借金をしたときの利息のようなものです。
正当な理由がなく申告期限までに申告しなかった場合、その日数に応じて延滞税が課されてしまいます。
実際に問題となるのは、税務調査が行われた結果として、申告遅れが発覚し、期限が過ぎた後に申告書を提出したケースです。
延滞税は、本来の期限から2カ月以内の部分と、それ以降の部分を分けて計算します(合算額を納付しないといけません)
- 納付期限から2か月以内の分:年利2.6%(平成31年)
- 納付期限から2カ月以降の分:年利8.9%(平成31年)
②申告が遅れたことへの追徴課税-無申告加算税
より「罰金」としての性格が強い追徴課税が、無申告加算税に代表される「加算税」です。
無申告加算税は、「申告をしなかったことへの罰則」として課されるもので、本税の金額×年利15%(50万円を超える部分については20%)で計算します。
なお、期限後であっても自主的に申告納付を行った場合には、無申告加算税の税率は5%に軽減してもらうことができます。
(2)相続税軽減特例措置を利用できなくなる
期限までに申告納付を行わなかった場合のペナルティとして、追徴課税等の他に各種の相続税軽減特例措置を利用できなくなることが挙げられます。
相続税には、所定の条件が備わった場合に利用できる「納税額を軽減できる特例」がありますが、期限までに申告ができなかった場合には、この特例を利用できなくなってしまうのです。
納税額を軽減できる特例としては、
- 小規模宅地の特例
- 農地の納税猶予
などがあります。
このような特例を利用できなくなると、「期限内に申告をしていれば払う必要のなかった税金」を払わなければならなくなってしまいますから、気をつけましょう。
3、期限までに申告すればいいだけじゃない!正確な税額を申告することが大切

相続税は、期限までに正しい金額を税務署に申告して納付しなくてはなりません。
もし、申告した税額が正確でない場合には、過小申告加算税や重加算税といった加算税が生じる可能性があるので注意が必要です。
(1)申告税額が少ない場合も追徴課税がある―過少申告加算税
申告した税額が少ないケースでは、「過小申告加算税」が課せられる可能性があります。
過少申告加算税は、税務調査の結果として最終的に納付が義務付けられた金額の10%(50万円を超える部分については15%)が課せられます。
(2)財産を隠したり、ごまかしたりして申告した場合は最も重い追徴課税―重加算税
そして財産を隠すとかごまかして申告したケースでは「重加算税」が課されます。
重加算税は、税務調査によって隠蔽(いんぺい)している事実が発覚した場合などに、過少申告加算税や無申告加算税に代わって課されます。
(つまり、重加算税が課せられる場合には、過少申告加算税や無申告加算税は課せられません)
重加算税の計算は、以下のような分類に従って行われます。
- 過少申告加算税に代わって課せられる場合:納税義務額の35%
- 無申告加算税に代わって課せられる場合:納税義務額の40%
4、相続税の申告期限は延長されることもある

相続税は、申告期限までに申告しなくてはならないのが大原則です。
しかし例外的に申告期限の延長が認められるケースが稀にあります。
以下では、例外的に相続税の申告期限が延長されるケースについて解説いたします。
(1)遺贈に関する遺言書が発見された場合
まず「遺贈にかかわる遺言書が発見されたケース」では、相続税の申告を延長できます。
それに「遺贈の放棄があったケース」でも、申告期限を延長することができます。
あまり聞き馴(なれ)ないカテゴリーですが、「遺贈」とは、遺言書で指定をして、「法定相続人でない人」に財産を遺してあげる法的な行為をいいます。
(2)相続人の資格を持つ胎児が生まれた場合
相続人となる胎児がいるケースでは、相続税の申告期限はその胎児が生まれたときから2ヶ月は延長が認められます。
国民の生活関係を規定する「民法」という法律では、相続人に関する規定において、胎児はすでに生まれたものとみなし、相続権を認めています。ですから胎児も相続人のひとりとして相続できるわけです。
しかし、不幸にして胎児が死産のときとか、流産になったケースでは、胎児は法定相続人にはなれません。
(3)遺留分侵害額請求があった場合
そして遺留分侵害額請求があったケースでも相続税の申告期限を延長することができます。
あまり聞き馴れないカテゴリーですが、「遺留分」とは、一定の法定相続人に保証された「最低限度の相続分」をいいます。
被相続人が生前に、ほかの相続人などに対する贈与とか遺贈がなされたため、自分の遺留分が侵害されたときは、遺留分権利者は、「遺留分侵害額請求」をすることができるわけです。
遺留分によって遺産を相続することとなった人は、当然ながら相続した遺産の金額に応じて相続税を負担しなくてはなりません。
一方で、遺留分請求額請求を受けた人(遺言によって財産を取得した人)は、相続する遺産が少なくなりますから、負担すべき相続税の金額も少なくなります。
このとき、遺言で遺産を得た人がすでに相続税の申告納付が完了している場合には、更正の請求(税務署に「税金を納めすぎたので、返してほしい」と申し立てる手続き)を行うことで相続税の一部を還付してもらうことが可能です。
この場合の更正の請求の期限は、「遺留分侵害額請求による弁済額が確定した日の翌日から起算して4か月」とされています。
すでに相続税の納付を行った人が更正の請求によって税金の還付を受けた場合、その反射的な効果によって遺留分侵害額請求によって遺産を得た人は相続税の申告義務が生じることになりますから、上の更正の請求の期限(「遺留分侵害額請求による弁済額が確定した日の翌日から起算して4か月」)内に修正申告を行う義務が生じるでしょう。
(4)相続人の異動があった場合
さらに「相続人の異動があった場合」にも相続税の申告期限は延長されます。
被相続人の意思により「相続人の廃除」がなされるとか、「相続欠格」により法定相続人が相続権を喪失するケースも想定されます。そうなれば相続人が異動されます。
そして相続人が失踪宣告を受けたケース、一度なされた失踪宣告が解消されるケースもあります。
そうなれば、相続人の人数が変化し、相続人が異動します。
これらのケースは、実務としてはあまりみられない少ない事例といえましょう。
5、そもそも相続税申告が不要なケースってあるの?

ここまで、相続税の申告義務が生じるケースについてみてきましたが、そもそも「相続税の申告が不要なケース」もあります。
相続税の申告義務の有無は、遺産の金額がいくらであるかによって決まります。
(1)遺産総額が基礎控除額以下のときだけ
遺産の総額が「相続税の基礎控除額」を下回る場合には、相続税の申告や納付は必要ありません。
少額の遺産についてまで相続税が課税されると、遺族の生活が困窮(こんきゅう)してしまう可能性がありますから、遺産の金額が小さいときには、相続税は発生しない仕組みになっているわけです。
①基礎控除とは
すると「基礎控除」とは何か気になります。「基礎控除」の性格と計算方法を確かめておきましょう。
相続税の「基礎控除」とは、遺産額に税率を掛けるなどして相続税額を算出する前に「遺産額から控除する金額」をいいます。
相続税の基礎控除は、2015年以降は法改正によって範囲が縮小されましたから、必然的に相続税の申告納付が必要となるケースは増加しました。
②基礎控除額の計算方法
それでは、基礎控除額の計算方法はどうでしょうか。確かめましょう。
相続税の基礎控除額は、次の計算方法で計算することができます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数=相続税の基礎控除額
法定相続人とは相続することができると民法という法律で定められた人をいいます。
具体例をあげておきましょう。
- 法定相続人が1人のケース:3,600万円
- 法定相続人が2人のケース:4,200万円
- 法定相続人が3人のケース:4,800万円
- 法定相続人が4人のケース:5,400万円
- 法定相続人が5人のケース:6,000万円
(2)各種特例の利用で相続税がゼロでも申告は必要
上述の通り、遺産の総額が相続税の基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告も納付も必要ありません。
一方で、「各種の税軽減特例を利用した結果として、相続税がゼロとなるケース」では、相続税の申告が必要であることに注意が必要です。
また、これらを利用して相続税の計算を行うためには、必然的に遺産分割が完了している必要がありますから、相続税の申告期限に注意するとともに、遺産分割協議をすみやかに完了すべく手続きをすすめていくことも大切です。
ここでいう「各種の税軽減特例」には、以下のようなものがあります。
- 配偶者の税軽減
- 小規模宅地等の特例
- 農地の納税猶予
以下、それぞれの税軽減特例の内容について簡単に見ておきましょう。
①「配偶者の税額軽減」という特例
亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、「配偶者の税額軽減」という特例措置を受けることができます。
配偶者が法定相続分に従って遺産を相続する場合や、法定相続分とは異なる相続分であっても、その金額が1億6000万円を超えない場合には、相続税は発生しない仕組みとなっています。
この税軽減制度があることによって、配偶者が相続税を負担するケースというのはめったにないといえます。
一方で、この税軽減制度を利用するためには、期限までに相続税の申告を行っていることが条件となりますから、注意が必要です。
②小規模宅地等の特例
「小規模住宅地等の特例」も、相続税の負担軽減効果が高い制度です。
この仕組みは、相続税を納付すると、居住とか事業の運営ができなくなってしまう事態を
避けるための制度です。
ごく大まかにいえば、居住用の建物を建てるために使っている土地については、相続税を計算する際の遺産としての評価額を大幅に(最大で80%)減らしてもらうことができます。
小規模宅地等の特例を活用できる土地は、被相続人が自分で済んでいた宅地に限らず、以下のようなものでも認められます。
- 特定居住用宅地等:住宅用地として使用している土地
- 貸付事業用宅地等:他人に貸している土地
- 特定事業用宅地等:事業に使用している土地
ただし、これらの土地の「相続前の用途」としては、被相続人・「同一生計家族」が居住用とか事業用に使用していたことが要件とされています。
そのため、保養目的の別荘とか、「生計を共にしていない家族」が使用している土地については、特例の活用はできません。
そして、「相続後の宅地の取得・利用状況」としては、「相続前の用途」に応じて宅地の取得者と「利用状況」の要件が設けられています。
ここに利用状況とは、相続税の申告期限までの間、宅地の取得者がその宅地を継続して利用しているかどうかです。土地について面積の上限も規定されていますから、気をつけましょう。
小規模宅地等の特例を利用して相続税の申告を行うためには、不動産の相続実務に関する知識が必要となりますから、専門の弁護士や税理士にアドバイスを受けるようにしてください。
③農地の納税猶予
さらには、「農地の納税猶予」という制度もあります。
農地の納税猶予の特例とはどのような制度でしょうか。
この特例は、これまで農業を営んできた被相続人から農地を相続した相続人が、これからも農業を経営するケースにおいて、相続税の納入が猶予される仕組みです。
この制度については、「被相続人の要件」・「農業相続人の要件」が法定されていますから特例を活用するには、弁護士に相談するようおすすめします。
これらの特例を活用するときでも、相続税の申告を忘れないようにしましょう。
6、準確定申告もお忘れなく

最後に「準確定申告」について確かめてみましょう。
(1)準確定申告とは
そもそも「準確定申告」とはどのような税務手続きでしょうか。
自営業とかフリーランスなどは、勤務先における「所得税の天引き」とか、「年末調整」がなされません。
そこで毎年、年始の1月1日から年末の12月31日までの取得を翌年の「確定申告」という形で税務署に申告してから納税します。
ですから生存している人は、自分でその手続きをとりますが、ある年の途中で死亡すれば、その相続人が手続きしなければなりません。この手続きを「準確定申告」といいます。
「準確定申告」の対象となる所得は、被相続人が死亡した年の1月1日から亡くなった日までに発生していた所得です。
ただ、1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告を終えないまま亡くなったケースでは、その間の所得についても申告する必要があります。
準確定申告を行わないといけないのは、亡くなった人が以下のような条件に該当する場合です。
- 個人事業を行っていた
- 2,000万円を超える給与収入があった
- メインの給与所得以外に20万円を超える所得があった
- 不動産の賃料収入があった
- 株式や不動産などの売却収入があった
- 年の途中で退職したので年末調整を受けてはいない
などのほか、「医療費控除などにより還付を受けることができる」というようなケースが「準確定申告の対象者」とされるでしょう。
(2)準確定申告の申告期限
それでは、準確定申告の申告期限はどうでしょうか。
通常の「確定申告書」の提出期限は、毎年3月15日が提出期限とされています。
これに対し準確定申告の提出期限は、被相続人が死亡した事実を知ったときから4ケ月以内に申告・納税を行うことになっています。
ただ、実際の税務上では、提出する書類について、それぞれ期限がありますから気をつけましょう。
たとえ1日でも期限を過ぎてしまいますと、多額の納税を強いられる可能性がありますから、弁護士や税理士に依頼して期限を厳守されるようおすすめします。
7、相続税についてお困りの際は弁護士または税理士へ相談を

遺産相続では、期限までに必ず手続きを終えなくてはならない事柄が多くあります。
これらは法律の知識がないと処理が非常に難しいだけでなく、手続きを行うための書類の取得に労力が必要なことも少なくありません。
相続税の申告や遺産相続の手続きに不安がある方は、弁護士や税理士といった専門家にアドバイスを受けることを検討してみてください。
まとめ〜適切に相続案件の処理を
今回は、相続税の申告期限に関する法律のルールについて説明いたしました。
本文でも見たように、相続税の申告期限を過ぎてしまうと利用できなくなってしまう税軽減制度がある他、申告期限が過ぎてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティが生じることもあります。
遺産相続の手続きでは、想定していたよりも多くの時間が必要となることも少なくありませんから、早めに手続きを進めていくようにしましょう。