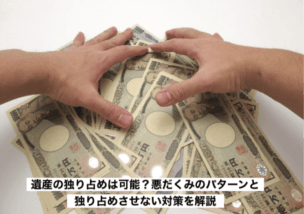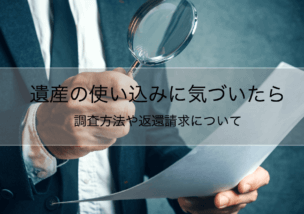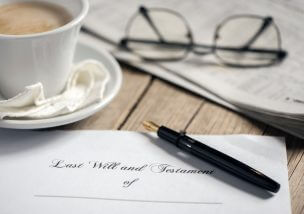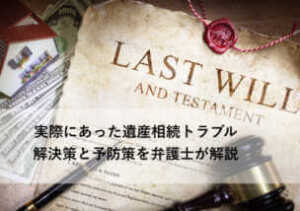
遺産相続トラブルは、決して他人事ではありません。
どんな家庭でも発生する可能性がある問題です。
誰しも遺産相続トラブルは避けたいと思うものですが、消極的な姿勢で遺産相続に臨むと1円の遺産ももらえないことにもなりかねません。
かといって、積極的に権利を主張すると親族間で感情的なトラブルにも発展しかねないという、難しい問題でもあります。
現実に発生する遺産相続トラブルには、いくつかのパターンがあります。
そこで今回は、実際に会った遺産相続トラブルの中から、よく起こりがちな7つの事例をご紹介します。
それぞれの事例について、
- 遺産相続トラブルが発生する原因
- 発生した遺産相続トラブルを解決する方法
- あらかじめ遺産相続トラブルを予防する方法
について解説していきます。
現在、遺産相続トラブルにお悩み中の方や、今後において遺産相続トラブルを予防したい方のご参考になれば幸いです。
目次
1、遺産相続トラブルの実態

まずは、世の中で発生している遺産相続トラブルについて、その実態を確認しておきましょう。
(1)遺産が少ない方がトラブルになりやすい
遺産相続トラブルというと、一部の資産家の家庭だけの問題だとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
裁判所が公表している「司法統計」というデータによると、平成30年に家庭裁判所の遺産分割調停が成立した事件における遺産の価額は、以下の割合となっています。
- 総数 7,507件
- 1,000万円以下 2,476件(33.0%)
- 5,000万円以下 3,249件(43.3%)
- 1億円以下 832件(11.1%)
- 5億円以下 533件(7.1%)
- 5億円超 53件(0.7%)
- 算定不能 364件(4.8%)
こうしてみると、全体の約3分の1(33.0%)は遺産総額1,000万円以下の家庭で遺産相続トラブルが発生していることがわかります。
5,000万円以下まで含めると76.3%にものぼります。
遺産が少なくても遺産相続トラブルは普通に起こりうるのです。
(2)仲の良い親族間でもトラブルは発生する
また、遺産相続トラブルは、もともと仲が悪かった親族間でのみ発生するわけではありません。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたケースの中には、もともとは仲の良かった親族たちというケースも多くあります。
親族間の仲が良くても、いざ親などが亡くなって金品を分ける話になると、とたんにトラブルが発生するケースが少なくないのです。
「うちの子どもたちは兄弟仲が良いから心配はいらない」と考えて、相続対策を何もせずに亡くなる方は今でも多くいらっしゃいます。
何の対策もとっていないからこそトラブルが発生するというケースもあるでしょう。
普段は仲が良くても、また、特にお金に汚い性格ではなくても、お金が絡むと態度が変わってしまうという人間の性質を意識しておくことは大切です。
(3)遺産相続トラブルが発生する主な原因
なぜ、遺産が少ない家庭の方や、仲の良い親族間でも遺産相続トラブルが発生するのでしょうか。
主な原因として、以下の3つが挙げられます。
①平等意識の高まり
昭和22年までは「家督相続」という制度があり、戸主が亡くなった場合には長男がすべての遺産を相続するのが法律上の原則とされていました。
長男が優先的に相続するという風潮はその後も長年続き、現在でもそのような考え方をしている人も少なくありません。
しかし、現在の民法では兄弟の相続分は平等とされています。
そこで、遺産を独占したいと考える長男と、平等に分割すべきだと考える弟・妹との間でトラブルが発生しやすくなっています。
②相続人の生活保障の必要性
現在の高齢者の方の世代は比較的資産を築きやすい時代に働かれ、実際にそれなりの資産を築かれた方も多くいらっしゃいます。
それに対して、その子どもにあたる世代は賃金が上がらない上に増税や社会保障費の負担などによって、資産を築きにくい社会で働いています。
経済的に余裕があれば遺産相続で「譲り合う」ことができても、余裕がなければそういうわけにはいきません。
そんなとき、それなりの資産を有する親が亡くなると、生活の糧を確保するために遺産相続で自分たちの権利を主張してお互いに譲らない、ということになりがちです。
③相続税がかかりやすくなった
相続税制の改正により、2015年1月1日から相続税がそれまでよりもかかりやすくなりました。
具体的には、基礎控除がそれまでの「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されたのです。
これによって、従前よりも相続税がかかる世帯が増え、納税額も大きくなってしまいました。
そうなると、相続する人たちも今までより遺産相続についてシビアに考えるようになり、遺産相続トラブルがさらに発生しやすくなったといえます。
それでは、次項から、実際にあった遺産相続トラブルの事例をご紹介していきます。
2、明らかに不公平な内容の遺言書があるケース
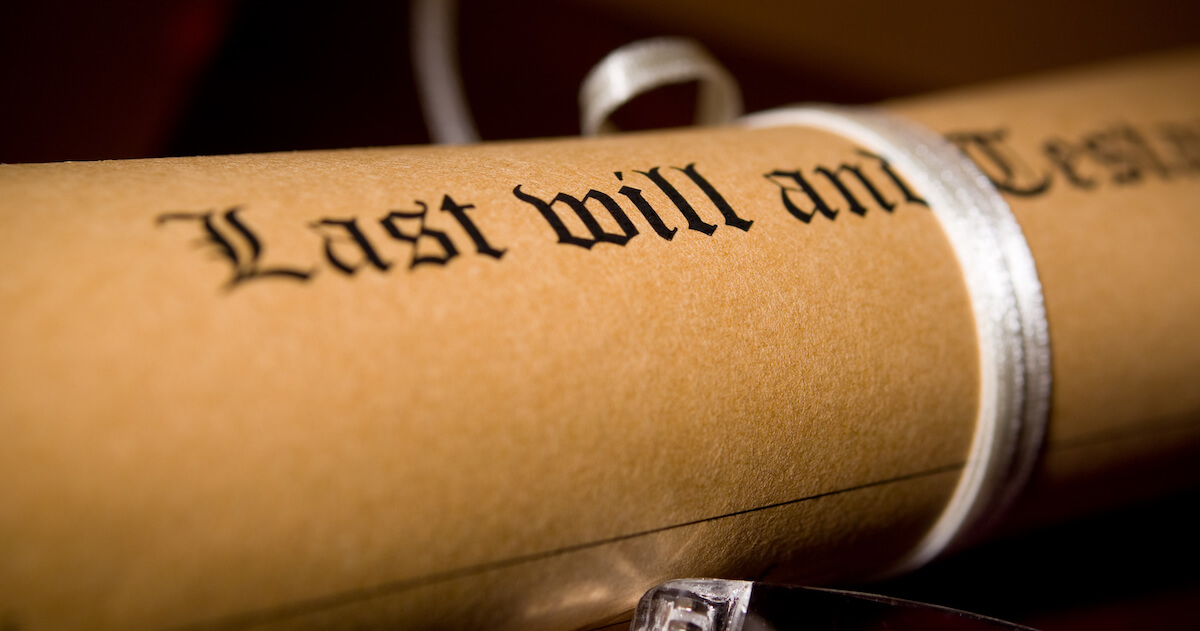
Aさんからご相談いただいたケースでは、お父様が亡くなり、その子どもである長男・次男(Aさん)・長女が相続人となりました。
お父様の遺産は総額で6,000万円ありましたが、そのすべてを長男に相続させるという遺言書が見つかりました。
Aさんとしては、長男がある程度多くの遺産を受け継ぐのは仕方ないとしても、すべてを長男が相続するのは納得できない、自分もいくらか遺産を取得できないかと考えてご相談くださいました。
(1)相続人には遺留分がある
被相続人が作成した遺言書がある場合は、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることに全員が合意しない限り、遺産分割において遺言書に書かれた内容が最優先されます。
長男にすべての遺産を相続させるという遺言書も、方式を満たしている限りは法的に有効です。
しかし、相続人には遺留分というものがあります。
遺留分とは、遺言によっても奪われない、相続人に最低限保障された相続分のことです。
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が保障されているのです。
今回のケースでは、被相続人の子どもである相続人には、相続財産の2分の1が遺留分として保障されています。
したがって、次男であるAさんと長女はそれぞれ6分の1(2分の1×3分の1)ずつの遺留分を長男に対して主張することができます。
この主張をするためには、「遺留分侵害額請求」という法的手続きがあります。
Aさんと長女はそれぞれ、相続財産の6分の1に相当する1,000万円の金銭の支払いを長男に対して請求することになります。
ただ、実際にはこのケースでは、遺留分侵害額の請求の法的手続によることなく、Aさんから依頼を受けた弁護士が長男と話し合うことによって解決できました。
長男が遺産の中から1,000万円ずつをAさんと長女に渡すことに合意したので、その旨の遺産分割協議を成立させました。
長男からAさんと長女に、遺留分侵害額に相当する金員を交付するという内容の合意書を作成するのでなくても、遺言書と異なる遺産分割協議を行うということで解決することもできるのです。
(2)被相続人の生前に遺産相続について話し合っておく
このように、不公平な内容の遺言書をめぐる遺産相続トラブルを防止するためには、被相続人の生前に遺産相続について話し合っておくことが有効です。
被相続人を交えて話し合うことができない場合は、推定相続人同士で話し合っておきましょう。
遺言書で遺産分割の方法が指定されていても、相続発生後に相続人全員が合意すれば、今回の解決例のように遺言書とは異なる内容で遺産分割をすることも可能です。
3、特定の相続人が遺産を独り占めしようとするケース

Bさんからご相談いただいたケースでは、お父様が亡くなった後、長男・次男(Bさん)・三男が相続人となったものの、長男が1億円の遺産を独り占めしようとして話し合いに応じてくれないとのことでした。
なお、お父様の遺言書はありませんでした。
このケースのBさんもやはり、長男が多少は多くの遺産を取得するのはよいとしても、基本的に平等に遺産をわけてほしいと考えて、ご相談くださいました。
(1)法定相続分に従って相続するのが原則
今回のケースでは遺言書がないため、法定相続分に従って遺産を分割するのが原則です。
子どもたちの法定相続分は平等なので、長男・Bさん・三男はお父様が遺した1億円の遺産を3分の1ずつに分割して取得すべきことになります。
ただ、詳しくお話を伺うと、長男はお父様と同居して事業を手伝ってこられましたし、お父様が亡くなった後も家を継いで法要などの費用を要するとのことでした。
そのため、多少は長男が多めに遺産を取得することも合理的であると考えられました。
そこで、Bさんからご依頼を受けた弁護士が遺産分割協議に介入しました。
長男と話し合いを重ねた結果、長男が4,000万円、Bさんが3,000万円、Cさんが3,000万円を取得するという内容で遺産分割協議が成立し、問題は解決しました。
(2)遺産相続のルールを知っておく
現在でも、このケースで見られるように、長男が遺産を独り占めしようとするケースは少なくありません。
このようなトラブルを防止するためには、平等に遺産を分けるべきという基本的なルールを知っておくことが大切です。
ただ、問題は平等な遺産分割に納得しない長男をどのように説得するかという点でしょう。
長男が親の事業を手伝ったり、介護や看護に従事していたような場合で、法的にも長男に寄与分があると考えられる場合には、ある程度は遺産分割において長男の取り分を多くすることにも合理性があります。
事情に応じて、長男の努力を認めてあげることで話し合いが進む場合もあるはずです。
4、思わぬ相続人や受遺者が現れるケース
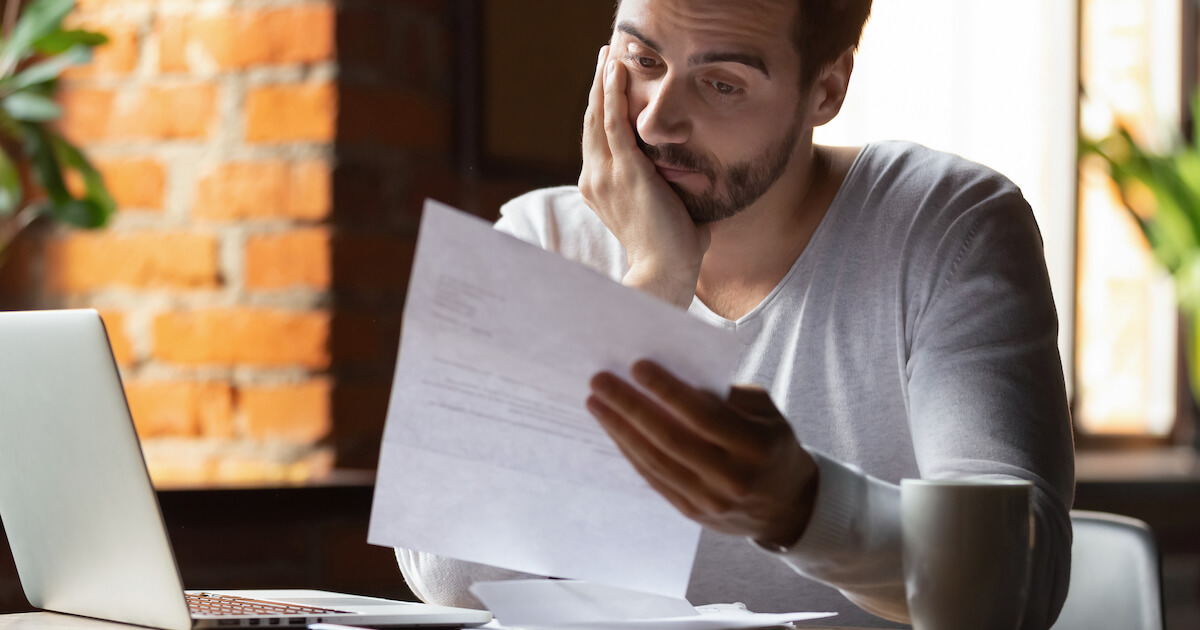
Cさんからご相談いただいたケースでは、お父様が亡くなった後に戸籍謄本を取り寄せたところ、お父様の前妻との間に子どもが一人(Dさん)いたことが判明しました。
それまで、相続人はお母様と長男であるCさん、次男の3人だと思っていたところ、もう一人相続人がいることがわかったのです。
Cさんとしては、お父様と長年音沙汰がなかったDさんに遺産を渡したくないが、どうすればいいのかわからないということでご相談くださいました。
(1)話し合いで妥当な解決を図る
このケースでは、Dさんもお父様の子どもであることには間違いないので、れっきとした相続人に当たります。
そのため、お父様が残した遺産はお母様が2分の1、長男のCさん・次男・Dさんはそれぞれ6分の1ずつに分割して相続するのが原則です。
しかし、詳しくお話を伺うと、CさんがDさんに連絡をとってみたところ、Dさんのお母様はCさんのお父様と離婚された後に再婚され、Dさん自身は裕福に育ったとのことでした。
このような場合、Dさんに遺産を渡したくないという気持ちも理解できます。
そこで、Cさんからご依頼を受けた弁護士は、Dさんと話し合って、取り分を譲歩する気はないかと打診しましたが、Dさんは応じませんでした。
最終的には家庭裁判所に調停を申し立て、Dさんが取り分を半分譲歩することで調停が成立しました。
結果として、お母様が2分の1、残りの2分の1についてCさんと次男が5分の2ずつ、Dさんが5分の1を取得するという内容の遺産分割となりました。
(2)法定相続人を調査しておく
このようなトラブルを避けるためには、早めに法定相続人を調査しておくことです。
被相続人の生存中に、一度戸籍謄本を取り寄せて調査しておいた方がよいです。
その結果、被相続人の前妻との間の子どもの他、認知した子どもや養子縁組をした人などの相続人が判明するのは珍しいことではありません。
相続が開始してから慌てないように、早めに調査しておき、必要に応じて話し合いを開始しましょう。
5、遺産の大部分が不動産のため分割しにくいケース

Eさんからご相談いただいたケースでは、亡くなったお父様が残した遺産が評価額3,000万円の自宅と600万円の預金でした。
相続人は長男・長女・次男(Eさん)の3人です。
Eさんとしては、長男が亡くなったお父様と自宅で長年同居していたため、長男が自宅を相続するのはよいとしても、自分の取り分が200万円の預金だけでは納得できないとのことでした。
しかし、自宅を分割しようとしても難しいため、どうすればよいのかということでご相談いただきました。
(1)代償金を分割で支払う
遺産分割の方法には、次の3種類があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
現物分割とは、遺産そのものを現物で分け合う方法です。
このケースのように遺産の大部分を分けようがない不動産が占める場合にはこの方法をとることはできません。
換価分割とは、遺産を処分して換金し、そのお金を相続人で分割する方法です。
このケースでも自宅を売却して代金を3人の相続人で公平に分けることが考えられます。
しかし、その場合には長男の住む家がなくなってしまうという問題があります。
代償分割とは、遺産を相続人のなかの一人が現物で取得するものの、法定相続分を超えて取得した分については代償金を他の相続人に支払うことによって公平な遺産分割を実現させる方法です。
このケースでは、長男が自宅を取得する代わりに長女とEさんに対して1,000万円ずつの代償金を支払うことが考えられます。
しかし、長男にそれだけの支払い能力がない場合はどうすればよいのかという問題があります。
Eさんからご依頼を受けた弁護士が長男と話し合ったところ、やはり合計2,000万円もの代償金を支払う余裕はないとのことでした。
話し合いを重ねたところ、分割で代償金を支払ってはどうかとの提案に長男が応じました。
月8万円なら家賃を支払うつもりで代償金を支払うとのことで、長女とEさんに毎月4万円ずつ支払うことを約束してくれました。
長女とEさんもこの内容に合意したので、その旨の遺産分割協議書を公正証書で作成し、問題は解決しました。
なお、遺産のうち600万円の預金については長女とEさんとで300万円ずつに分けることとして、長男の取り分だった200万円については長男の代償金から控除することで解決しました。
(2)遺言書を作成しておくのが有効
今回のようなトラブルを避けるには、被相続人に遺言書を作成しておいてもらうのが最も有効です。
ただ、その場合も遺留分の問題はあります。
不動産の遺産分割は難しい場合が多いのが実情です。
場合によっては、不動産を相続する方は換価分割を選択して、取得したお金で新たな住居を見つけた方が円満に遺産分割できる場合もあります。
6、寄与分を主張する相続人がいるケース

Fさんからご相談いただいたケースは、お父様が亡くなって長男と二男(Fさん)が相続人となったところ、長男が遺産のほとんどを取得するといって譲らないとのことでした。
前記「3」でご紹介した「特定の相続人が遺産を独り占めしようとするケース」と似ていますが、少し違っています。
今回のケースの長男は、多少多く貰いたいというのではなく、ほとんどすべてを自分が取得すると言って譲らないというものです。
お父様の事業を長年手伝ってきて資産の形成に貢献してきたことから、寄与分として遺産のほとんどを取得する権利があるはずだというのです。
お父様は自営の酒屋を経営しており、長男もお父様と一緒に長年働いてきました。
お父様が亡くなった時点で遺産は5,000万円ありました。
長男は、Fさんに対して、いわゆる「はんこ代」を500万円渡すものの、残りの4,500万円は自分が取得するといって譲らないとのことでした。
(1)寄与分を明確に算定したうえで話し合う
寄与分とは、被相続人の事業を手伝ったり、介護や看護に努めるなどして被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合に、他の相続人よりも多くの遺産を取得できる制度のことです。
このケースの長男のように、被相続人の事業を長年手伝ってきたような相続人には寄与分が認められる可能性があります。
ただし、何が寄与分として認められるのか、認められるとしても「寄与」した金額がいくらなのかについては、正確に見極める必要があります。
Fさんからご依頼を受けた弁護士が長男と話し合ってみると、長男はたしかに長年、お父様の酒屋を手伝っていたものの、相応の給料は受け取っていたとのことでした。
また、お父様も亡くなる1年前までは仕事をされていたようです。
このような場合は、長男の寄与分が認められるとしても、ごくわずかな金額に限られるというべきです。
仮に、お父様が名義だけの店主であって実際には長男が長年ほとんど無償で経営していたような場合には、相応の寄与分が認められるべきです。
しかし、今回のケースはそうではありませんでした。
長男との話し合いはまとまらず、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになりました。
基本的には、ほぼ平等に遺産を分割すべきケースかとも思われましたが、お父様が亡くなるまで同居して面倒をみた長男の努力も評価して、Fさんが少し譲歩することとしました。
結果として、長男が3,000万円、Fさんが2,000万円を相続することで調停が成立しました。
(2)相続人間のコミュニケーションを密にしておく
このケースのように寄与分を主張しそうな相続人がいるケースでは、相続人間のコミュニケーションを密にしておくことが大切です。
Fさんの立場としては、長男の努力を理解してねぎらいつつも、店の経営状況をそれとなく把握して遺産相続について、できる限り話し合いを進めておくとよいでしょう。
7、遺産を使い込んだ相続人がいるケース

Gさんからご相談いただいたケースでは、お母様が亡くなられ、相続人は長女と二女(Gさん)の二人でした。
お母様は長女と同居していましたが、亡くなる前1年ほどは病気で入院していました。
相続開始後、Gさんがお母様の預金通帳を確認してみると、亡くなる前の1年間に500万円もの預金が引き出されていました。
Gさんが長女を問い詰めたところ、お母様の療養費や生活費に充てたものであるから正当な出費だと言われたとのことでした。
しかし、1年で500万円はどう考えても使いすぎだと考えられるので、その対処法について当事務所にご相談くださいました。
(1)不正出金は取り戻しを求める
このケースのように、被相続人と同居していた相続人が遺産を使い込んでいるケースは少なくありません。
もちろん、被相続人の療養費や生活費のために、被相続人に代わって引き出したお金については問題となりません。
しかし、それを超えて不正に出金されている場合は、引き出した人に対して、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求として取り戻しを求めることができます。
Gさんからご依頼を受けた弁護士は、長女が引き出した500万円のうち、いくらをお母様の療養費や生活費として使ったのかについて説明を求めました。
しかし、長女はレシートや領収証を示すこともなく、全額をお母様の療養費や生活費使ったと言い張るのみでした。
そこで、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合うこととしました。
最終的には、1年間にお母様の療養費や生活費に使った金額はせいぜい300万円程度であろうということで、残りの200万円については相続財産に持ち戻して遺産を分割することとなりました。
お母様の遺産としては、他に300万円の預金が現存していました。
そこで、200万円を持ち戻して500万円を2人で分割し、Gさんは250万円を相続することとなりました。
長女の取り分は、250万円から200万円を引いた50万円です。
この内容で長女もGさんも合意したので、調停が成立し、問題は解決しました。
(2)遺産の使い途を記録しておく
遺産の使い込みをめぐるトラブルを防止するためには、今回の長女の立場としては、遺産の使い途を記録し、レシートや領収証なども保管しておくことです。
そのようにして、不正出金ではないという証拠を確保しておくことが重要です。
Gさんの立場としては、引き出したお金の使い途について説明を求め、不正出金に当たると思われる部分については取り戻しを求めるしかありません。
長女の立場から合理的な説明がない場合は、今回の解決例のように、正当な出金と認められる金額を概算することが考えられます。
その上で、それを超える部分については訴訟によって返還請求または賠償請求をすることができますが、あくまで概算であり、立証していくことは難しいことがあります。
また、お母様から貰ったというような話になったときには、特別受益として調整するしかない場合もあります。
8、遺言書が無効または内容が不明確なケース

Hさんからご相談いただいたケースでは、亡くなったお父様の遺言書が見つかったものの、パソコンで作成されていたために法的に無効なものでした。
遺言書の内容としては、3,000万円の遺産のすべてを長男であるHさんに譲るというものでした。
しかし、遺言書が無効である以上、他の相続人である次男と長女から平等に遺産を分けるよう要求されているとのことでした。
(1)被相続人の意思を尊重しつつ話し合う
自筆証書遺言を作成するには様々なルールがあり、不備があると遺言書が無効となってしまいます。
本文は遺言者自身が手書きしなければならないというルールがあるため、パソコンで作成されたものは無効となってしまいます。
遺言書が無効である以上、原則として法定相続分に従って遺産分割を行わなければなりません。
この点では、次男と長女の言い分が正しいといえます。
しかしながら、無効な遺言書であっても、被相続人の意思が読み取れる以上は、その意思を尊重したいところです。その場合、相続人間で話し合いを行うしかありません。
Gさんからご依頼を受けた弁護士は、次男と長女の理解を求めて、根気よく話し合いを重ねました。
その結果、次男と長女は20%なら譲歩してくれることになりました。
結果として、3,000万円の遺産を長男1,400万円、二男800万円、長女800万円に分割するという内容で遺産分割協議が成立しました。
(2)遺言書を作成する際は専門家に相談する
遺言書は、遺産相続トラブルの予防策として非常に有効なものです。
最近は「終活」も一般化しつつあり、遺言書を作成する人も増えています。
しかし、自筆証書遺言には様々な細かいルールがあるため、せっかく遺された遺言書も方式不備のため法的に無効となるケースがあります。
無効になると、法的には遺言書がないのと同じ条件で遺産分割をせざるを得ないことになってしまいます。
遺言書を作成する際は、弁護士にご相談の上、方式に不備のない遺言書を作成されることをおすすめします。
9、遺産相続トラブルの解決・予防は弁護士に相談を

ここまでご説明してきたように、遺産相続トラブルにはいくつかのパターンがあるものの、それぞれに解決法や予防法は異なります。
解決するためには、相続人間でじっくりと話し合うしかないようなケースも存在します。
このような遺産相続トラブルを解決・予防するには、相続問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
状況に応じて最適な対処法についてアドバイスを受けることができます。
依頼すれば、他の相続人との話し合いを代行してもらえますし、家庭裁判所での調停や審判の手続きでも力を借りることができます。
まとめ
今回は、実際にあった遺産相続トラブルの事例に基づいて、解決法や予防法をご紹介しました。
ただ、同じ類型の遺産相続トラブルであっても、具体的な事情によっては異なる解決法や予防法が必要になることもあり得ます。
遺産相続トラブルでお困りの場合は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。