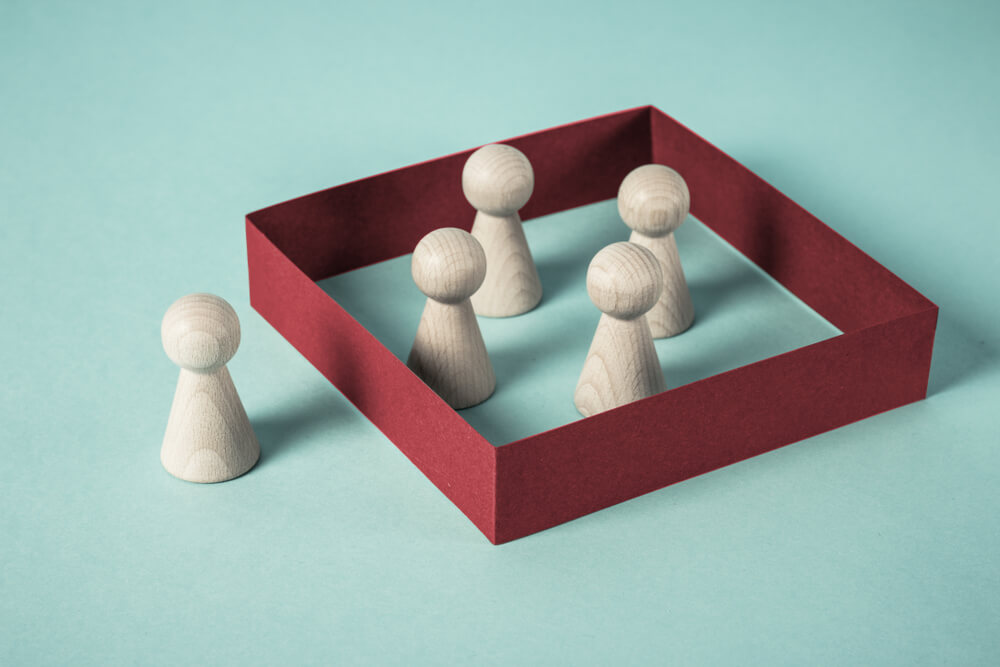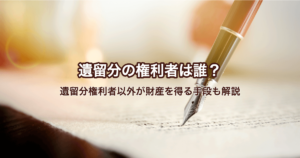
遺留分は相続人に保障された一定割合の相続分ですが、遺留分を有する権利者とは、一体どの範囲の人なのでしょうか。
今回は、
- 遺留分が認められている権利者は一体誰なのか?
ということを中心に弁護士が解説します。
他にも、遺留分に関連する各種問題や遺留分権利者以外の人が財産を得るための対策も紹介していますので、相続でお困りの方の一助となれば幸いです。
遺留分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、遺留分の権利者〜遺留分権者は誰?
(1)兄弟姉妹を除く法定相続人
「遺留分」とは、遺言の自由を制限して、一定範囲の相続人のために法律上必ず留保される相続分の一定割合のことをさします。
遺留分を有する者を「遺留分権利者」といいます。
遺留分を侵害する遺言や贈与があった場合には、遺留分権利者は受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額を請求することができます。
そして、「遺留分権利者」となる人については、民法にその範囲が明記されています。
民法で遺留分権利者と規定されているのは以下の人になります。
- 配偶者
- 子(子が亡くなっている場合の代襲相続人である孫)
- 直系尊属(父母。既に亡くなっている場合は祖父母)
他方、法定相続人とは、亡くなった被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると民法で規定されている相続人のことをいいます。
法定相続人になることができるのは以下の者です。
- 配偶者
- 子(既に亡くなっている場合は孫。)
- 直系尊属(父母。既に亡くなっている場合は祖父母。)
- 兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥姪。)
この法定相続人のうち、兄弟姉妹(甥姪)は、遺留分権利者から除かれています。
なぜ遺留分権利者となれる法定相続人から兄弟姉妹が除外されているのでしょうか。その答えは、遺留分という制度の目的や趣旨と密接に関係しています。
遺留分制度は、被相続人の財産に依存して生活してきた相続人の生活保障を目的とし相続財産の形成に寄与・貢献したことについての評価を行うものです。そのため、被相続人と密接な関係にあった者に限って、相続権の一定割合を遺留分として保障しています。
この点、兄弟姉妹は、亡くなった人とは別の家庭をつくり、家計も別であることが通常ですから、遺留分権利者からは除外されているのです。
法定相続人について詳しく解説はこちらの記事を確認してください。
(2)代襲相続
相続人となるべき子の子(代襲相続人)も、遺留分権利者となることができます。
「代襲相続」とは相続人となるべき者が被相続人の死亡当時すでに亡くなっていた場合に、その亡くなっていた法定相続人の子(被相続人の孫)が相続権を有することになるという制度です。
相続人となるべき者の死亡だけではなく、相続欠格、相続廃除によっても代襲相続は生じます。一方で、相続開始後の相続放棄によっては代襲相続は生じません。
子については、再代襲もあります。再代襲とは、法定相続人の子の子(被相続人のひ孫)が相続することです。
被代襲者である法定相続人が遺留分を放棄していた場合は、その代襲者は遺留分権利者にはならないと考えられています。
代襲相続について詳しい説明はこちらの記事を確認してください。
(3)遺留分権利者からの承継人
遺留分権利者からの承継人も遺留分権利者となります。
遺留分権利者からの「承継人」には、遺留分権利者の「包括承継人」のみならず「特定承継人」も含まれます。
「包括承継人」とは、相続分の譲受人や、法定相続人死亡後の法定相続人の相続人や包括受遺者などです。
「特定承継人」とは、個別の遺留分侵害額請求権を譲り受けた者です。
2、遺留分の権利者がもらえる遺留分割合と計算方法
(1)遺留分の割合
遺留分の割合については、相続人が誰であるかで以下のように異なっています。
- 直系尊属のみの場合 3分の1
- その他の場合 2分の1
その他の場合とは、具体的には「配偶者のみ」、「子のみ」、「配偶者と子」、「配偶者と直系尊属」、「配偶者と兄弟姉妹」の組み合わせがあり得ます。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者のみの場合と同様です。
遺留分の割合についての詳細についてはこちらの記事を確認してください。
(2)遺留分の計算方法
遺留分の割合の計算方法の概要を説明します。
遺留分の計算は、
①遺産の全体に対して、遺留分権利者全体に残されるべき割合(総体的遺留分)に
②各相続人の相続の割合(法定相続分)を掛け合わせて計算します。
つまり、以下の計算式によって算出されることになります。
総体的遺留分×法定相続分=各相続人の遺留分(個別的遺留分)
ただし、単独相続で共同相続人がいない場合には法定相続分は考慮されませんので、総体的遺留分がそのまま個別的遺留分となります。
遺留分の計算方法の詳細はこちらの記事をご確認ください。
3、遺留分の権利者が遺留分を獲得する方法
遺留分権利者やその承継人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
遺留分侵害額請求についての詳細はこちらの記事を確認してください。
4、遺留分の権利者でも遺留分がなくなる場合
(1)相続欠格の場合
「相続欠格」とは、一定の場合に特定の人物の相続権を失わせる制度のことをいいます。
相続欠格事由については民法に規定されており、相続欠格事由に該当すれば相続権を失います。
民法に欠格事由として挙げられているのは以下のような場合です(民法891条)。
- 故意で被相続人や相続人の生命を侵害し、刑に処せられた場合
- 被相続人を殺害した犯人を告訴・告発しなかった場合
- 相続に関する遺言について不正をした場合
- 遺言書を勝手に偽造・隠匿した場合
相続欠格事由がある場合は、相続権を失いますので、当然に遺留分の権利も失います。
相続欠格についての詳細はこちらを確認してください。
(2)相続廃除の場合
「相続廃除」とは、家庭裁判所に請求することで、被相続人が遺留分を有する推定相続人を相続人からはずすことができる手続をいいます。
相続廃除は、推定相続人が被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりする著しい非行があった場合に認められます。
相続廃除が家庭裁判所で認められた場合は、相続権を失いますので、遺留分に関する権利も失います。
相続廃除についての詳細はこちらの記事を確認してください。
(3)事業承継の場合は特別規定がある
事業承継に関しては「事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特則」が定められています。
株式等を承継するにあたり、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株等について、以下の手続をとることができます。
- 遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)
- 遺留分算定基礎財産に算入する際の価額を合意時の時価に固定(固定合意)
「除外合意」が成立すると、会社の後継者は、自社株等を被相続人から承継したとしても、遺留分侵害請求をされることがなくなります。
除外合意をしておくことで、円滑に自社株等を後継者に承継することができるようにするという制度です。
「固定合意」とは自社株の贈与について、その金額を合意した時点の金額に固定するというものです。
固定合意をしておくことで、自社株の評価が基準時以降上昇したことを理由として遺留分侵害額請求がなされることを防止することができます。
除外合意と固定合意の両者を組み合わせることも可能です。
これにより、後継者に自社株や事業用資産を集中的に承継させることが可能になります。
5、遺留分の権利者は遺留分の放棄が可能
(1)被相続人の生前における放棄
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
つまり、遺留分権利者であっても、被相続人の生前には自由に遺留分は放棄できません。なぜなら、遺留分の放棄を無制限に認めてしまうと、被相続人が遺留分権利者に対して遺留分の放棄を強要する、というケースが頻出してしまうリスクがあるからです。
裁判所によって遺留分の放棄が認められれば、相続が開始しても遺留分はありませんから、遺留分侵害額請求をすることはできなくなります。
ここで、遺留分の放棄は相続放棄とは異なりますので、依然として法定相続人であることには変わりありません。そのため、被相続人が遺言を残していない場合には、遺産分割協議には参加しなければなりませんので、ご注意ください。
(2)被相続人の死後における放棄
相続開始後については、遺留分放棄について、家庭裁判所の許可は必要ありません。
遺留分については放棄の特別な放棄の手続きはありませんので、遺留分侵害額請求をしなければ良いということになります。
6、法定相続人でない人が財産を得る方法
それでは、遺留分権利者でも法定相続人でもない場合は、被相続人の財産からなにも得られないのでしょうか。
被相続人を献身的に世話していた長男の妻など、法定相続分がない一定の人も相続に際して財産を受け取ることができる可能性があります。
(1)特別寄与料の請求
これは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより相続財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族に認められる権利です。
特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の特別寄与料(寄与に応じた額の金銭)の支払いを請求することができます。
特別寄与者になれるのは、「相続人ではない被相続人の親族」に限られています。
親族とは以下にあげる者のことを指します。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
特別寄与料についての詳細はこちらの記事で確認してください。
(2)被相続人の生前に対策を受ける
相続人とならない人も、被相続人に生前に対策してもらっておくことで、一定の財産を受け取れるようにしておくことが可能性です。
①遺贈
例えば、遺贈です。
「遺贈」とは、遺言によって被相続人が相続財産を無償で譲り渡すことをいいます。
相続財産から遺贈を受ける人を受遺者といいます。受遺者については法律上特段の制限がありませんので、相続人以外の人に対しても遺贈することが可能です。
そこで、被相続人が生前に法定相続人やそれ以外の人・団体に対して「遺贈する」という旨を遺言書に記載しておいてもらう必要があります。
②生前贈与
また、生前贈与を受けることも可能です。
生前贈与は被相続人が生きている間に財産を譲り渡すことです。
生前贈与の相手方は相続人に限られませんので、それ以外の第三者や団体に対しても行うことができます。
③生命保険金
さらに、生命保険金の受取人を自分にしておくことで、被相続人が亡くなった際に金銭を受け取ることができます。
死亡保険金請求権については、受取人の固有の権利ですので、そもそも相続財産に含まれるものではりません。
例外的に、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が法律の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情があると判断された場合には、特別受益にあたると評価される可能性があります。
まとめ
遺留分は、相続財産のうち、一定の相続人に最低限保障されている権利です。
さらに、遺留分侵害額を算定するには、相続財産を把握したうえで複雑な計算が必要となる場合もあります。
相続に関して分からないことや困ったことがあった場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。