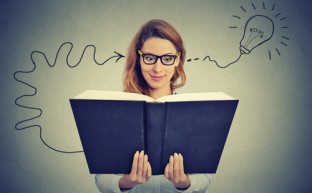限定承認(げんていしょうにん)とは、相続において、得たプラスの財産の範囲内中でのみマイナスの財産を承継する方法です。
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。引用元:民法第922条
後にも解説いたしますが、限定承認を行うことのメリットとしては、
『相続財産を超える債務は相続しなくてもよい』
という点が挙げられます。
いったいどのようなケースにおいて、限定承認は行うべきなのでしょうか?
また、限定承認は、どのような手続きによって行われていくのでしょう?
今回は、
- 限定承認の基本のすべて
について詳しく内容を見ていきたいと思います。ご参考になれば幸いです。
相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
1、限定承認についてわかりやすく基本から解説

(1)相続の承認・放棄制度
相続は、相続される人(被相続人)の死亡によって開始します(民法第882条)。
そして、一切の権利義務を包括的に承継するとされています(同法第896条)。
このように、相続は被相続人の死という相続人にはコントロールができない原因で発生し、また、一切の権利と「義務」までも包括的に承継とされているので、これに対して「嫌だ!」と言えないのでは相続人があまりにも酷であることは想像に難くないでしょう。
そのため、民法では、この承継を確定させることにつき、相続人に選択する自由が与えられています。
それが相続の承認・放棄制度です。
(2)相続承認―2つのパターン
相続の承認には2つのパターンがあります。
単純承認と限定承認です。
①単純承認
単純承認は、一般的に行われる原則的な相続方法で、負債なども含めた全ての相続財産を承継する方法です。
被相続人がプラスの財産のみを保有しているのであれば問題ないですが、仮に借金も抱えていた場合、相続人はそれをも承継する必要があるため、単純承認をした相続人は、その借金を返済する義務も承継することになります。
単純承認の手続きに特別なものはなく、限定承認や相続放棄をしなければ、自動的に単純承認として扱われます(民法第921条)。
②<限定承認
一方、限定承認という方法があります。
限定承認は、仮に被相続人に借金などの負債があったとしても、プラスの財産の範囲でのみ、債務(及び遺贈)を支払うという相続方法です。
つまり、仮に被相続人が多くの借金を抱えていたとしても、被相続人のプラスの財産の中から借金を弁済すればよいため、その相続によってマイナスになることはない、ということです。
もしもプラスの財産が残った場合には、その財産をも相続することができます。
この限定承認を行うには、もちろん条件がありますので、そちらについては下記で解説していきます。
(3)相続放棄
相続財産の承継につき、相続人が承認をしないこと、それが「相続放棄」です(民法第938条)。
相続放棄は「全面的に」遺産の承継を拒否することをいいます。
(4)承認・放棄制度はなんのため?
そもそも、相続自体なんのために法定されているのでしょう?
それは、「人が死亡すればそれまで関係のあった人たちは困る」という人間社会の原則を発端としています。
例えば、大家さんが死亡してしまったら、誰に家賃を払えばいいの?このまま住み続けていいの?と困ります。
こんな風に、人が死亡するとそれまでの関係の維持ができなくなるため、関係者が困る状況に陥るのです。
それを救済するのが「相続」です。
相続を法定することにより、被相続人と同じ関係を継続することができる、ということになるわけです。
このことから、相続の制度は、被相続人と生前なんらかの関係にあった、残された「相手方」のためにあることはお分かりいただけたかと思います。
ですから、「承認・放棄」は、被相続人の権利であればその義務者へ、被相続人の義務であれはその権利者へ向けられたものなのです。
そのため、相続人同士で「これは承認してこれは承認しない」「私は相続、僕は放棄」という話し合い(遺産分割協議)をしただけでは、承認しないとした部分や放棄についても「相手方」には原則である単純承認をしたとみなされます。
つまり、限定承認や放棄とするには、外部から見てもその「限定」「放棄」ぶりが明らかになるように、一定の「手続き」が必要となる、ということです。
2、限定承認と相続放棄の違い

限定承認と相続放棄の違いはイメージしていただけたかと思いますが、それぞれどのような場面で使うのでしょうか。
(1)限定承認の場面
①被相続人の資産状況がわからない
限定承認の主な場面は、被相続人の資産状況がわからない、という場面でしょう。
資産はある程度あるものの、どの程度のマイナスの財産があるのか分からない場合、放棄までしてしまっては資産が無駄になってしまいます。
そのため、資産>負債である可能性があれば、損失は出ませんので限定承認をすべきです。
②負債はあるが手元に残すべき遺産(家宝など)がある場合
負債があるものの、残しておかなければならない遺産がある場合も、限定承認の場面でしょう。
後述する手続きにもあるように、限定承認では原則的にプラスの財産は全て競売により換価しなければなりません。
しかし、「先買権」という制度があり、相続人が手元に残しておきたい財産について、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価をし、相続人がその評価額を支払うことによって、希望した財産を残しておける制度があります。
そのため、希望する財産については手元に残すことが可能です。
もしも相続財産の中に残しておきたい家宝がある場合には、先買権の制度を利用してみるのも有効でしょう。
③相続人が負債のある家業を引き継ぐ場合
相続人が家業を引き継ぐ場合なども、限定承認が有効です。
家業も②と同様、手元に残すべき、残さなければならない遺産の一つです。
単純承認では承継する債務が膨大である場合は、限定承認で一定数抑えることができますので効果的です。
(2)相続放棄の場面
①全くプラスの資産がない
資産<負債が明白であれば、相続放棄をすべきです。
②被相続人との関係が断絶している
プラスでもマイナスでも、被相続人の地位や財産に振り回されたくない。
そんな関係の場合は、相続放棄をしておきましょう。
そうでなければ相続人として今後どんな関係に巻き込まれるかわかりません。
3、限定承認の手続きの流れ

ここでは限定承認の手続きの流れについて、ご紹介していきます。
- 限定承認の申述
- 共同申述
限定承認は、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。
つまり、相続人の全員から同意を得ていない限り、限定承認はできないということです。
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。引用元:民法第923条
限定承認を申述する(申し立てる)先は、被相続人が最後に住んでいた場所(相続が開始された場所)にある家庭裁判所です。
全国の家庭裁判所の所在地は、こちらからご確認ください。
参考:裁判所
②申述に必要な書類
限定承認の申述に必要な書類は、以下のとおりです。
1,限定承認の申述書
2,財産目録
3,被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4,相続人全員の戸籍謄本
5,被相続人の子、またはその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
→被相続人の子、またはその代襲者で死亡している方いる場合
- 申述人が配偶者と直系尊属のケース
6,被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載がを記載されている戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が配偶者のみの場合、または被相続人の配偶者と兄弟姉妹(及びその代襲者である甥姪)のケース
7,被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
8,被相続人の直系尊属の死亡の記載がされている戸籍謄本
9,被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その死亡者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
10,甥や姪が代襲者で、すでに死亡している人がいる場合、その死亡者の死亡の記載のある戸籍謄本
参考:裁判所
③申述期間
限定承認の申述期間は、相続の開始があることを知った日から3ヶ月以内とされています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。引用元:民法第915条
民法第915条但書でもわかるように、3ヶ月という期間内に相続を決定することができない事情(被相続人の債務額の調査が3ヶ月では間に合わなかったなど)がある場合には、その期間をさらに伸ばすことができることも可能です。
伸ばせる期間は家庭裁判所の裁量で、だいたい1ヶ月〜3ヶ月であることが多いようです。
ただ、遠方に住んでいるなどの事情によりさらに延長がなされることもあります。
(3)限定承認の申述受理後の手続き
限定承認の申述が受理された後、相続財産の精算をすみやかに行う必要があります。
- 相続人が1人の場合はその人
- 相続人が複数いる場合には、申述が受理された時に選任された相続財産管理人
が代表をし、相続開始から3ヶ月以内に、限定承認をした事実、また、債権の請求をすべき旨を公告し、その後に精算手続きを行っていきます。
①公告
限定承認者となった人は、限定承認が受理されてから5日以内に、相続財産管理人は10日以内に、『限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨』の公告を官報で行う必要があります。
公告をして債権者に名乗り出てもらうわけです。
官報での公告期間は2ヶ月以上が必要で、この時点ですでにわかっている債権者に対しては、公告とは別に請求申出の催告をする必要があります。
公告は難しいことではなく、インターネットを使って、こちらのサイトから簡単に行うことが可能です。ぜひご利用ください。
参考:全国官報販売協同組合
②相続財産の管理と売却
相続財産を売却しないと債権者への返済が不可能な場合、裁判所の競売を利用して、キャッシュを作る必要があります。
これにより、適正価格で財産を換価すること(財産などを金銭に変えること)ができます。
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。引用元:民法第933条
③相続債権者への弁済
官報公告の手配と弁済のための財産換価手続きが終わったら、相続債権者への弁済を行っていく必要があります。
公告によって請求を申し出てきた債権者に対し、②で解説したように、相続財産の換価処分をした財産を弁済していきます。
この際、全債権者に対して全額を支払うことができないのであれば、各債権者の債権額に応じて、均等な割合でその額を支払っていくことになります。
例:
債権者A→債権額1,000万円
債権者B→債権額500万円
相続人が換価処分できた金額→450万円
この場合、債権者Aと債権額Bの割合は2対1なので、
債権者A→300万円
債権者B→150万円
という割合で、それぞれの債権者に弁済を行うということです。
4、限定承認で負担する税―譲渡所得税

限定承認を行うと、相続が開始された時の時価で、被相続人から相続人へ、相続財産の譲渡があったものとみなされます。
例えば、被相続人が2、000万円で購入した土地を相続したとします。
相続時、その土地の時価が2、300万円に上がっていた場合、300万円の含み益があるとされ、この300万円に対して譲渡所得税が発生するのです。
不動産など価値が流動的な財産を相続した場合、この譲渡所得税が発生することもあるということを理解しておきましょう。
まとめ〜限定承認は弁護士の相談が必須〜
ここまで解説してきたように、限定承認は、非常に手続きが煩雑であることがデメリットとしてあげられるでしょう。
そのため『単純に損がなくなるから限定承認をしよう』と安易に考えることはお勧めできませんが、『自分たちの相続にとって本当に必要なものはどれか』を吟味して、相続を行うようにしてください。
限定承認がベストであるケースもあるはずです。
その際は必ず弁護士に相談をし、最適な相続を、そしてトラブルのない円満な相続ができるように、早めに行動を起こされることをお勧めいたします。