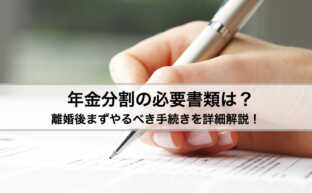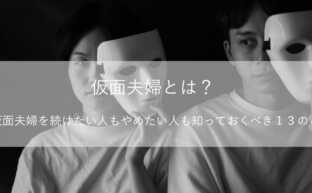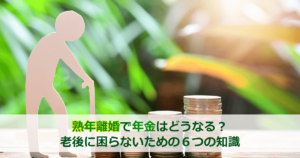
熟年離婚をすると、特に妻側はその後の生活費が気になる場合が多いことでしょう。
老後の生活費で頼りになるのは年金ですが、長年専業主婦をしていた方などは厚生年金がないことが多いと思われます。資産が豊富にある方は別として、国民年金のみで老後の生活を乗り切ることは難しいものです。
しかし、離婚時には年金分割を請求できます。年金分割をすれば、老後の生活費の大きな足しとなる可能性があります。
そこで今回は、
- 熟年離婚時の年金分割とは
- 熟年離婚時に年金分割をする手続き方法
- 熟年離婚時にできるだけ多くの年金を分割してもらうためのポイント
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
この記事が、熟年離婚を考えているものの老後の生活が心配という方の手助けとなれば幸いです。
熟年離婚全般については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、熟年離婚すると年金はどうなる?

熟年離婚をした後、特に手続きをしなければ、自己名義で納めてきた年金の種類と金額に応じて年金を受け取れるだけです。しかし、年金分割をすれば配偶者に支給されるはずの年金の一部を受け取れるようになります。
まずは、年金分割について基本的なことを確認しておきましょう。
(1)熟年離婚なら年金分割をしよう〜厚生年金は分割できる
年金分割とは、婚姻中に配偶者が支払った厚生年金(旧「共済年金」も含まれます。)保険料の納付記録を分割することにより、もう一方の配偶者の年金受給額が増える制度のことです。
夫が会社員や公務員として厚生年金に加入する一方で、妻が専業主婦として国民年金にしか加入せず家庭を支えていた場合、妻の年金受給額は夫よりも相当に少なくなってしまいます。
夫婦として共同生活を続ける限り、通常はそれでも問題は生じません。しかし、妻も家事労働によって家庭を支えてきたのですから、離婚した場合にまで年金受給額に大きな差が付くのでは不公平です。
このような不公平を是正し、離婚後の生活に困窮しそうな人を支援するための制度が年金分割というものです。
(2)しかし年金分割で十分な生活費が得られるとは限らない
かといって、年金分割をすれば安心して生活できるだけの年金がもらえるとは限らないことに注意が必要です。
年金分割といえば、配偶者に支給される年金の半分を自分が受け取れると考えている人がいますが、そういうわけにはいきません。先ほどご説明したとおり、分割されるのは「婚姻中に配偶者が支払った厚生年金保険料の納付記録」だけです。国民年金の部分は分割されないのです。
したがって、年金分割をすることによってご自身の年金受給額が大きく増えるケースもあれば、少ししか増えないケースもあります。場合によっては、まったく増えないケースもあります。
熟年離婚をした後の生活費を考える際には、ご自身のケースで年金分割をすることにより受給額がどれくらい増えるのかを把握しておくことが大切です。
以下で、そのために注意すべきポイントを解説します。
2、熟年離婚でも年金分割できないケースがある

まず、熟年離婚をしても年金分割の請求ができない、請求したとしてもご自身の年金受給額がまったく増えないケースについてご説明します。
注意が必要なのは、以下の3つのケースです。
(1)配偶者が自営業
配偶者が自営業者で、一度も厚生年金に加入したことがない場合は、そもそも配偶者の「厚生年金保険料の納付記録」がありません。そのため、年金分割の請求はできません。
この場合、ご自身が厚生年金に加入したことがあれば、逆に配偶者から年金分割を請求されてご自身の年金受給額が減ってしまうこともあります。
(2)自分の年金保険料が未納
年金分割によって増えた年金を受け取るためには、ご自身が年金の受給資格を満たしている必要があります。なぜなら、年金分割はあくまでもご自身の年金に対して、配偶者の年金の中から一部が加算されるものだからです。
年金の受給資格を満たすには、国民年金保険料を最低10年以上納めていなければなりません。もし、この要件を満たしていない場合は年金を一切受け取れないことになります。
(3)配偶者より自分の収入が高い
ご自身も配偶者もともに厚生年金に加入していて、ご自身の収入の方が高かったという場合も注意が必要です。
この場合も、配偶者から年金分割を請求されると、配偶者の年金受給額が増え、ご自身の年金受給額は減ります。
ただ、年金分割を請求するかどうかは自由ですので、ご自身のみが請求し、配偶者が請求しなかった場合は、ご自身の年金受給額が増えることになります。
3、熟年離婚時に年金分割をする方法

では、熟年離婚時に年金分割をするにはどうすればよいのでしょうか。年金分割の手続きには「合意分割」と「3号分割」の2種類がありますので、それぞれ解説します。
また、年金分割の請求期限にも注意しましょう。
(1)合意分割
合意分割とは、夫婦間の合意によって按分割合(厚生年金の納付記録を何%ずつ分割するかという割合のことです。)を決定する分割方法です。家庭裁判所の調停や審判、裁判で按分割合が決められる場合も、合意分割に含まれます。
按分割合の上限は2分の1、下限は夫婦の標準報酬の合計額に対して、少ない方の標準報酬額が占める割合です。夫婦が合意すれば、この範囲内で自由に按分割合を決めることができます。ただ、実務上は大半のケースで按分割合は2分の1とされています。
請求手続きは、離婚した後に「標準報酬改定請求書」と一緒に、離婚協議書や調停調書、審判書、判決書等の按分割合等を明らかにした書類を年金事務所の窓口に提出します。
その他、必要書類等の詳細は、こちらの記事でご確認ください。
(2)3号分割
3号分割とは、夫婦間の合意や家庭裁判所での手続きなしで年金分割ができる制度のことです。
「3号」というのは、国民年金の「第3号被保険者」のことを意味します。第3号被保険者とは、会社員や公務員で厚生年金に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている人のことです。
専業主婦が離婚時に会社員や公務員の夫に対して年金分割をするのが、3号分割の典型的なケースです。
3号分割における按分割合は、一律2分の1と定められています。
請求手続きは離婚した後に単独で行うことができ、「標準報酬改定請求書」と一般的な必要書類を年金事務所の窓口に提出します。
なお、3号分割で分割できるのは2008年4月1日以降の納付記録のみです。それよりも前の納付記録についても分割を求める場合は、別途合意分割を行う必要があります。
(3)離婚から2年が経過すると請求できなくなる
どちらの分割方法による場合も、請求期限は離婚が成立した日から2年以内です。
離婚後に元配偶者と話し合ったり調停や裁判などで按分割合を決めようとすると、請求期限に間に合わなくなる可能性があります。
合意分割をする場合は、按分割合を決めてから離婚するようにした方がよいでしょう。
4、熟年離婚で年金を少しでも多く分割してもらうためのポイント

熟年離婚で年金分割が可能なケースでは、少しでも多くの年金を分割してもらいたいと考えることでしょう。
そのためには、以下の3つのポイントを検討してみてください。
(1)できる限り3号分割で請求する
年金分割の按分割合は2分の1が上限ですので、一律2分の1と決められており、しかも配偶者との合意が不要な3号分割の方が有利です。
2008年4月1日以降の納付記録を分割することが必要な場合は合意分割を行う必要があります。
離婚調停や審判、離婚裁判でも、よほどのことがない限り按分割合は2分の1となりますが、長年別居していて、その間連絡を取り合うこともなく、生活費のやりとりもなかったような場合には2分の1を下回る可能性もあります。
このような場合や、配偶者との話し合いが進まない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
(2)婚姻期間は長い方が有利
年金分割は配偶者の厚生年金の納付記録を分割するものですので、納付期間が長いほど多くの年金を分割してもらうことが可能となります。
したがって、熟年離婚後の生活費を確保するためには、夫の定年退職を待ってから離婚を切り出すというのも理に叶った選択肢の一つです。
配偶者からDVやモラハラを受けている場合などで、身の危険を感じるような場合は離婚を引き延ばすべきではありません。しかし、老後を見据えて熟年離婚したいという場合は、配偶者の定年退職まで待つのもよいでしょう。
(3)配偶者からの年金分割は拒否する
ご自身にも厚生年金への加入歴がある場合は、できれば配偶者からの年金分割を拒否したいところでしょう。
年金分割の請求権は、離婚原因にかかわらず離婚する人に認められた権利ですので、請求されると基本的に拒否することはできません。拒否するためには、夫婦間の話し合いによって「年金分割の請求をしない」という合意を得る必要があります。
離婚原因について、配偶者側に不倫やDVなどの有責性があれば、このような交渉が可能となる場合も少なくありません。しかし、配偶者側に有責性がなければ、この交渉は難しくなる可能性が高いです。
交渉を有利に進めるためには、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
5、熟年離婚では財産分与が重要!年金分割以外で離婚後のお金を確保する方法

熟年離婚後の生活費を確保する手段は、年金分割だけではありません。離婚する際には、財産分与や慰謝料の請求も考えましょう。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分け合う制度のことです。離婚原因にかかわらず、請求すれば原則として夫婦共有財産の2分の1を取得できます。
離婚に伴う慰謝料は、配偶者が不倫やDVなどの離婚原因を作った場合に、その配偶者の行為によって受けた精神的苦痛を理由として請求できる損害賠償金です。
請求できる金額は事案によってさまざまですが、例えば配偶者の不倫で離婚する場合、協議離婚なら数十万円~200万円程度、裁判上の離婚なら100万円~300万円程度が相場的です。
熟年離婚の場合、既にある程度の財産を築いている場合が多いので、財産分与が特に重要となります。
慰謝料も、婚姻期間が長くなるほど高額化する傾向にありますので、請求できる事由がある場合には請求しましょう。
以下では、財産分与や慰謝料を適正に獲得する方法をご紹介します。
(1)離婚協議
まずは、離婚協議において財産分与や慰謝料を主張します。配偶者と話し合って合意ができれば、財産分与や慰謝料を獲得できます。割合や金額について法律上の決まりはありませんので、交渉次第では高額の財産分与や慰謝料を獲得することも可能です。
ただし、配偶者が離婚を拒否する場合や、不倫・DVなどの有責行為を否定する場合には、交渉が難航する可能性が高いです。
交渉を有利に進めるためには、ご自身の主張を裏付ける具体的な事実を指摘し、その証拠も示すことが重要となってきます。その前提として、冷静に話し合う姿勢も大切です。
しかし、配偶者を説得して自分の主張を押し通すのは難しいことが多いものです。交渉が進まない場合には、弁護士を間に入れて交渉する方がよいでしょう。
(2)離婚調停
離婚協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が中立公平な立場で話し合いを仲介し、必要に応じて相手方を説得してくれることもあるので、当事者だけで話し合うよりも合意に至りやすくなります。
調停で適正な財産分与を獲得するためには、配偶者の所有財産を漏れなくピックアップして調停委員に示すことが極めて重要です。
そのためには、別居する前から配偶者の財産を調査しておくべきであり、それでも判明しない財産があると思われるときは、調停申し立て後に「調査嘱託」などの調査方法を用いることになります。
慰謝料についても、配偶者の不倫やDVなどの証拠を提出すれば、調停委員がこちらの味方になってくれ、交渉が有利に進む可能性が高まります。
(3)離婚裁判
離婚調停でも決着がつかない場合には、家庭裁判所に離婚裁判(訴訟)を提起します。
訴訟は自分の主張を証拠で立証していく手続きです。十分に証明できれば、判決によって財産分与や慰謝料を獲得できます。
証拠がなければ勝訴することはできませんので、配偶者の所有財産や有責行為を証明できる有力な証拠を確保しておくことが必須となります。
6、熟年離婚の切り出し方

熟年離婚を決意した方に向けて、熟年離婚の切り出し方についてご説明します。
(1)離婚の切り出し方
もともと夫婦仲が悪い場合は、いきなり離婚を切り出しても問題ない場合も多いですが、特に表だったトラブルがなかった夫婦の場合は、離婚の切り出し方にも気を配りたいところです。
突然、離婚を切り出された側にとっては寝耳に水の話となりますので、できる限り、冷静に話を聞いてもらえるような状況を選びましょう。
パートナーが落ち着いていて、ゆったりとした気分で過ごしているときに切り出すのがよいでしょう。
急がない場合は、いきなり離婚を切り出すのではなく、「将来的にはお互いのために別々の道を歩みたいと思う」といった話から始めて、離婚したいということを時間を欠けて伝えていくのが理想的です。
(2)離婚を切り出されたら
あなたがもし熟年離婚を切り出され、離婚をしたくない場合は、まずは役所に離婚届不受理申出を出しましょう。そうすれば、勝手に離婚届を出されてしまう事態は免れます。
離婚をしたくないなら、きちんと話し合うことです。重要なのは、相手の気持ちを受け入れること。これを嘘偽りなく行うことは、とても簡単なことではありません。
熟年離婚の場合、すれ違ってしまった期間は長いものです。きれいに取り戻すことは、離婚するよりいばらの道かもしれません。一人で戦うのはとても困難です。どうぞ弁護士を味方につけ、一緒に考えていきましょう。
7、熟年離婚後のお金の問題は弁護士に相談を

熟年離婚したいと考える人は少なくありませんが、配偶者に有責行為があり耐えがたい場合は別として、そうでない場合は離婚することが必ずしも得策であるとは限りません。
離婚するほどの覚悟があるのなら、まずは家を出て一定期間別居してみたり、家庭内別居をしたり、あるいは仮面夫婦、卒婚など、婚姻関係を続けたまま配偶者との関係性を見直すことも可能でしょう。
夫婦関係を続けていくにせよ、離婚をするにせよ、精神的な問題と経済的な問題のバランスを上手にとっていくことがポイントとなります。もっとも納得のいく方法を選択するためには、ご自身の状況を整理した上で、じっくりと検討する必要があるでしょう。
どのように考えればよいのかが分からない場合は、弁護士に相談してみることも一案です。弁護士の豊富な経験に基づき、専門的な観点から有益なアドバイスが得られることでしょう。
熟年離婚での年金分割に関するQ&A
Q1.熟年離婚すると年金はどうなる?
熟年離婚をした後、特に手続きをしなければ、自己名義で納めてきた年金の種類と金額に応じて年金を受け取れるだけです。しかし、年金分割をすれば配偶者に支給されるはずの年金の一部を受け取れるようになります。
Q2.熟年離婚でも年金分割できないケースがある?
- 配偶者が自営業
- 自分の年金保険料が未納
- 配偶者より自分の収入が高い
Q3.熟年離婚時に年金分割をする方法とは?
- 合意分割
- 3号分割
- 離婚から2年が経過すると請求できなくなる
まとめ
熟年離婚をお考えの方であれば、年金分割のことをご存知であった方も多いと思いますが、年金分割の具体的な内容までは知らなかった方も多いのではないでしょうか。
「年金分割できるから大丈夫」と安易に考えて熟年離婚に踏み切ると、老後の生活に困窮してしまうおそれもあります。
熟年離婚をするなら、年金分割だけでなく財産分与や慰謝料を獲得することも重要です。その前に、多くの方はなぜ熟年離婚したいのかを冷静に考えた上で、夫婦の関係性を見直してみる必要性もあると思われます。
お一人で考えていると出口が見つからずに苦しむことになりがちですので、お悩みの際は離婚問題の解決実績が豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。