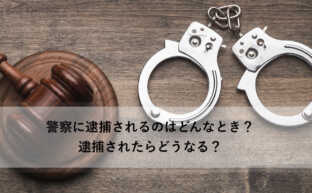痴漢冤罪事件で逮捕されてしまったら、その人は一体どうなってしまうのでしょうか?
本当は痴漢をやっていないのに、無実を訴えても聞き入れてもらえず、起訴されることも十分あります。起訴されてもなお冤罪を晴らすことができなければ、本当はやっていないのに刑事裁判で有罪となり、刑罰を受けることになってしまいます。このような事態を避ける方法はないのでしょうか。
痴漢冤罪で有罪を避ける方法は存在します。弁護士に依頼をして、起訴前と起訴後のそれぞれの段階で効果的に無実を訴えていくというものです。
痴漢冤罪で逮捕されてから起訴されるまでには、不起訴を目指します。そのためには、弁護士を通じて、検察官に対して積極的に無実を訴えていきます。また、起訴されてしまった場合には、弁護士が証拠を精査して、裁判で無実を主張していきます。
それでは、今回は痴漢冤罪事件で逮捕された場合の対処法について、具体例を交えながら書いていきます。
性犯罪とは?種類から逮捕前の事前対策まで弁護士が解説も参考にしていただけると幸いです。
目次
1、性犯罪の冤罪で逮捕|冤罪とは?
痴漢冤罪とは、実際には痴漢などやっていないにもかかわらず、痴漢事件として警察に逮捕され、不利益を受けてしまうことです。冤罪ですから、無実であるのに罪を着せられてしまいます。無実であるにもかかわらず、身柄を拘束され、刑事罰を受けるといった司法による制裁を受けるとともに、家庭が崩壊してしまったり、会社を解雇されてしまったりといった社会的制裁を受けることもあります。
このように、痴漢冤罪に遭うと、刑事的な制裁を受けるとともに、社会的地位・信用を失うという社会的制裁を受けることになる可能性が高いです。
2、性犯罪の冤罪で逮捕|逮捕されるとどうなる?
痴漢冤罪で逮捕されると、警察の留置施設に入ることになります。そして、検察官が、更に捜査をする必要があると認めた場合には、逮捕に引き続いて勾留をされることになります。勾留というのは、逮捕に引き続く身柄拘束のことで、最大10日間、延長をされると更に10日間の合計最大20日間にわたって身柄を拘束されてしまいます。この間も、留置施設に入ることになります。
検察官は、勾留を経て、起訴するか不起訴にするかの決定をします。不起訴となればそこで事件は終了し、身柄拘束からも解放されます。しかし、起訴されてしまうと、今度は被告人として勾留されることになり、また更に身柄を拘束され続けてしまいます。起訴された結果、万が一、痴漢冤罪で有罪判決を下されてしまった場合、上訴をして無罪を獲得しなければ前科がついてしまいます。
3、冤罪での逮捕を防ぐ方法は?
結論から申し上げますと、痴漢冤罪を未然に防ぐ方法に決まったものはありません。それぞれの具体的状況に応じて、臨機応変に対応していくことが重要です。
一例としては、満員電車を避けて電車を利用する、吊革は両手で掴む、女性と密着する車両に乗ることは避ける等痴漢と疑われるようなことを避ける様々な方法が考えられます。
もっとも、様々な場所で痴漢と疑われることがありえるので、ご自身の置かれた状況に合わせて、臨機応変に対応するしかありません。
痴漢冤罪で制裁を受ける可能性を少しでも減らすためにも、痴漢だと疑われた場合、犯行を認めるような言動は絶対にしてはいけません。たとえ相手から強く言われたとしても、無実の罪を着せられているのですから、毅然とした態度で臨みましょう。犯行を認めるような発言だけは、決してしないで下さい。
4、冤罪で逮捕されそうになってしまった場合の対処法は?
痴漢冤罪で逮捕されそうになったとき、まず考えるべきことは、弁護士を呼ぶことです。
痴漢冤罪によって駅員に取り押さえられたら、その時点で逮捕が始まります。駅員に警察官を呼ばれたとき、痴漢冤罪で捕まったことで気が動転していることが多いと思いますから、冤罪であることを主張するために適切な受け答えをすることは困難です。警察官に対して、痴漢冤罪で捕まってしまった人の代わりに適切な法的主張をすることができるのは、弁護士だけです。そのため、痴漢冤罪で逮捕されそうになったら、弁護士を呼ぶということを第一に考えましょう。痴漢をやったのだろうと問われても、弁護士が来るまでは何も話さないという姿勢を取っても構いません。まずは弁護士と話をして、適切なアドバイスを受けるべきです。
昨今、痴漢と疑われた際、すぐに電話で弁護士と話ができ、弁護士が現場に急行するといったサービスを提供する、保険商品もあるようです。疑われた場合に備えて、ご検討されてもよろしいかもしれません。
5、冤罪で逮捕されてしまった場合、弁護士に依頼した方がいい?弁護士に依頼するメリットとデメリット
弁護士に依頼することで、どのようなメリットとデメリットがあるのか、詳しくご説明していきます。
(1)弁護士に依頼するメリット
①早期に明確な方針を得ることができる
すぐに弁護士に依頼すれば、弁護士から刑事手続に関する説明を受けることができます。そして、具体的な痴漢冤罪事件において、今後どのようにして無実を訴えていくのかといった方針を相談することができます。方針が何もない状態で警察官や検察官の取り調べを受けるのは、非常に危険です。特に、痴漢をしたかのような記載のある調書を作成されてしまったら、極めて不利な証拠となってしまいます。
弁護士に依頼して早期にアドバイスを受けることで、このような不利益を回避し、明確な方針の下で濡れ衣を晴らす活動をすることができます。
②勾留をしないように働きかけることができる
弁護士に依頼すると、検察官と裁判官に対して意見書を提出することができます。具体的には、検察官に対しては、勾留請求をしないように求める意見書を提出し、裁判官に対しては、検察官から勾留請求を却下するように求める意見書を提出します。
勾留されると身柄拘束期間が長引いてしまいますから、可能な限り早期の身柄解放を実現するために、早い段階から積極的に活動することができます。
③勾留された場合に不服申立ができる
弁護士に依頼すると、勾留された場合に準抗告という不服申立をするこができます。検察官による勾留請求が認められてしまったとしても、諦めずに身柄解放に向けた活動をしていくことができます。裁判官に対して、勾留する理由も必要もないことを主張し、早期の身柄解放を目指します。
準抗告が認められれば、身柄は解放されます。
④不起訴を目指した活動をすることができる
弁護士に依頼すると、不起訴の獲得を目指して活動することができます。
痴漢冤罪で逮捕され、検察官に起訴されてしまったら、刑事裁判で無罪を獲得するしかなくなります。しかし、より早い段階で無実を主張していく必要があります。弁護人に依頼すれば、痴漢冤罪で逮捕されている人の話をもとに再現実験を行うなど、無実を証明するための様々な活動を行い、検察官に無実を主張していくことができます。検察官に対して積極的に働きかけて不起訴を獲得することは、痴漢冤罪にあった場合には非常に重要な目標になります。
⑤弁護人と面会することができる
弁護士に依頼すると、弁護人となった弁護士と面会することができます。これは接見交通権というもので、弁護人であれば無制限に面会ができます。
弁護人と面会することで、取調べの状況を確認し、取調べに対してどのように対応すればよいのかといった具体的なアドバイスを受けることができます。また、痴漢冤罪で身柄を拘束されている人にとっては、弁護人は家族とやり取りをするための手段になります。
被疑者として留置施設に一人でいると気が滅入りますが、弁護人と面会することで気持ちを強く持つことができることも、メリットであるといえます。
⑥起訴されたら刑事裁判で無罪を主張してもらえる
弁護士に依頼すると、起訴されてしまったケースであれば、刑事裁判で無罪判決を得るための活動をしてもらえます。被疑者段階から事情を知っている弁護士であれば、より充実した公判活動ができます。
痴漢冤罪で起訴されているわけですから、目指すところは無罪判決の獲得です。信頼のできる弁護士と共に裁判で争うことができることは、大きなメリットです。
(2)弁護士に依頼するデメリット
弁護士に依頼するデメリットとして考えられるのは、弁護士費用がかかることです。
着手金と報酬金だけでも、それぞれ30万円以上は必要になります。
6、性犯罪事件での逮捕に強い弁護士の探し方・選び方
次のような特徴のある弁護士が、刑事事件に強いといえるでしょう。
- 逮捕されている場合に不起訴を獲得する
- 逮捕されている場合に釈放・保釈を獲得する
- 裁判となっている場合に無罪を獲得する
- 有期懲役刑を求刑されている場合に執行猶予を獲得する
- 被害者との示談をまとめる
また、刑事事件に強い弁護士事務所は、次のような基準で探すことができます。
- 不起訴率が高いか、不起訴件数が多いか
- ヤメ検(元検察官)の弁護士がいる法律事務所か
- 刑事事件の解決実績が多いか
- 刑事事件の相談実績が多いか
- 弁護士数が多い法律事務所か
- 土日休日対応の法律事務所か
これらの条件に多く当てはまる弁護士、弁護士事務所を探して、依頼をすることをお勧めします。
痴漢冤罪事件において、頼りになる弁護士を探す方法は、過去の記事「刑事事件に強い弁護士とは?不起訴を目指すために必要な知識」と共通しますので、こちらもご参照下さい。
7、冤罪で逮捕された際に弁護士がしてくれること
(1)痴漢冤罪事件で起訴される前、起訴された後
痴漢冤罪にあった場合、起訴される前と、起訴された後で無罪を主張していくことになります。
(2)起訴前の痴漢冤罪の対処方法
検察官に起訴される前の段階で、痴漢冤罪にどのように対処すべきかをご説明します。
①目標は不起訴
痴漢冤罪にあった場合、起訴前にやるべきことは、不起訴を獲得するために活動することです。
起訴されてしまうと、保釈されない限り長期間にわたって身柄を拘束されてしまいますし、痴漢冤罪で有罪となってしまう可能性すらあります。
そのため、起訴前にやるべきことは、まずもって不起訴処分を獲得するための活動です。これは、弁護人が、痴漢冤罪で拘束されている方からお話を聞いて、最大限の活動をしていくことになります。
②弁護人を通じて検察官に無実を訴える
起訴前の段階では、痴漢事件の証拠は全て検察官が持っていて、被疑者・弁護士はこれを見ることができません。よって、被疑者・弁護人は、証拠を検討して無実を主張することができません。
そこで、被疑者・弁護人としては、自ら証拠を集めて、積極的に自分は痴漢などしていないということを訴えていく必要があります。
具体的な方法を考えてみましょう。
痴漢冤罪にあったら、警察官や検察官がいう痴漢の方法を、実際に行って再現実験してみるという方法があります。被疑者は身柄を拘束されていますから、実際に行うのは弁護人です。
例えば、電車の中で、左隣にいる女性の左太ももの内側を触ったという嫌疑をかけられているとしましょう。この場合、女性の身長、被疑者の身長、被疑者の腕の長さ、電車の混雑状況など様々な要素を考慮して実験をします。すると、左隣にいる女性の左太ももの内側を触ったという単純そうに見える例であっても、実際には身長差などから余程不自然な態勢を取らない限り、女性の左太ももの内側を触ることが出来ないということもあります。
このような実験を行い、弁護人が、検察官に対して意見を申し入れます。
そうすることで、本当に被疑者が痴漢を行ったといえるのか怪しくなってきて、嫌疑不十分で不起訴となるといった事例も実際に存在します。
以上ご説明したように、起訴前は、弁護人を通じて不起訴になるための活動をすることが考えられます
(3)起訴後の痴漢冤罪の対処方法
不起訴を目指していたけれども起訴されてしまった場合、刑事裁判ではどのように対応すべきなのかについて、ご説明します。
①無罪を目指す
起訴された罪は痴漢冤罪です。冤罪なのですから、当然、無罪を目指していくことになります。
しかし、刑事裁判で無罪判決を得るのは至難の業です。以下、裁判例を交えながら、痴漢冤罪裁判の対処方法をご説明していきます。
②無罪とされた具体例
実際に痴漢冤罪で無罪とされた例を見てみましょう。
事例1 バスの車載カメラが役に立った事案
これは、バスの車内で痴漢が行われたとされた事案です。最近は、電車やバスに車載カメラが設置されていることも多くなってきました。この事案でも、バスの車内には車載カメラが搭載されており、乗客の状況が映っていました。
車載カメラには映像と共に時間も記録されているため、検察官が具体的に特定した痴漢の行われた時間に、被告人が何をしていたのかがわかります。このような客観的な事実がわかる証拠は、裁判では非常に重要です。痴漢を行ったとされている場所に車載カメラがあるかどうかは、気にすべきです。そして、車載カメラの映像を秒単位で精査すると、痴漢が行われたとされる時間に、被告人は、携帯電話をいじっていたり、吊革を掴んでいたりする状況を発見できることがあります。
そうすると、被告人が痴漢を行ったということに合理的な疑いが生じ、無罪の判決を得ることができる可能性があります。弁護人が検察官から開示された車載カメラの記録を詳細に検討して、立証活動をすることになります。
事例2 DNA型の不一致が認められた事案
次に紹介するのは、被害者とされる女性の下着の繊維と、下着に付着していた細胞様片に関する事情が考慮された事案です。
痴漢の嫌疑で逮捕されると、女性を触ったとされる手から繊維を採取することがあります。この繊維が、女性の下着や着衣などの繊維と一致または類似するかが重要です。これが一致または類似しなければ、被告人は痴漢などしていないと主張することができます。また、被害者とされる女性の下着に細胞様片が付着していることがあります。特に、検察官が、被告人は執拗に被害者女性を下着の上から触ったと主張するような場合には、下着に付着している細胞様片は、被告人のものであると考えるのが自然です。そうすると、その細胞様片からヒト成分が検出された場合、DNA型を調べた結果、被告人のDNA型と一致しなかったとなると、被告人が痴漢を行ったことに強い疑いを抱かせることができます。このような事情があれば、無罪判決を得られる可能性が高くなります。これも、弁護人が、検察官から開示された証拠を検討し、積極的に無罪判決獲得のための立証活動をしていくことになります。
事例3 電子メールの送信時刻が役に立った事案
最後に紹介するのは、電車内での痴漢事件において、痴漢をしたとされる人が送信した電子メールが役に立った事案です。
検察官が起訴をする場合、どのような犯罪があったのかということを、公訴事実で具体的に特定します。公訴事実では、何時何分頃に痴漢をしたということまで特定されます。そこで、携帯電話を使用して電子メールを送信していた場合、その送信時刻が送信履歴に残っていますから、これが有利な事情となる場合があります。
被告人が痴漢をしたとされる時刻の約1分前まで電子メールを作成しており、公訴事実によって特定された犯行の時刻からすれば、電子メールを送信した直後に痴漢をしたことになり、さらに送信した電子メールの内容からして痴漢をしようと考えているとはいえないような場合には、検察官が主張するような痴漢行為を被告人が行ったと考えるのは相当な違和感があります。このように、携帯電話やスマートフォンでメールやLINEのやり取りをしており、その送信履歴が残っている場合には、検察官の主張が不自然であることを主張する有利な証拠となる場合があります。
③その他の対処方法
ご紹介した裁判例のような対処方法以外にも、無罪を主張するための手段は考えられます。その方法をご紹介します。
今の時代は誰でもスマートフォンをお持ちだと思います。電車やバスの車内で、スマートフォンを操作している人はとても多いです。LINEでやり取りをしている人からゲームをやっている人まで、車内でのスマートフォン利用内容は様々です。
そこで、このスマートフォンの解析結果を利用します。スマートフォンを解析すると、何時何分にスマートフォンでどのような操作をしていたかがわかります。痴漢冤罪で、○時○分頃に女性の身体を触ったという罪を着せられた場合、その時刻にスマートフォンで何をしていたかを調べるのです。
スマートフォンを解析した結果、ゲームをやっていたことがわかったとします。スマートフォンのゲームは、両手を使用して遊ぶものも存在します。そのようなゲームをやっていたことが判明すれば、手を使って痴漢をすることはおよそ不可能ですから、刑事裁判で無罪を主張するための重要な証拠になります。
スマートフォンの解析は、民間業者に委託して実施してもらいます。その結果を弁護人が精査し、検察官の主張は成立しないことを立証していきます。犯罪が成立するための立証責任は検察官にありますが、弁護人に依頼することによって、裁判の行く末をただ眺めているだけではなく、こちら側から無罪であることを積極的に主張・立証していくことが可能です。このような活動によって、痴漢冤罪によって不利益を被ることを回避できる可能性が高くなります。
まとめ
痴漢冤罪事件で逮捕された場合の対処法について、ご理解いただけましたでしょうか。可能な限り早期の段階で弁護士に依頼することが重要です。無実を訴えてそれを認めさせることは想像以上に困難ですから、信頼できる弁護士に協力を求めるのがベストです。痴漢冤罪事件には遭遇しないのが一番ですが、もしものときはこの記事の内容を思い出していただけたら、きっと役に立つと思います。