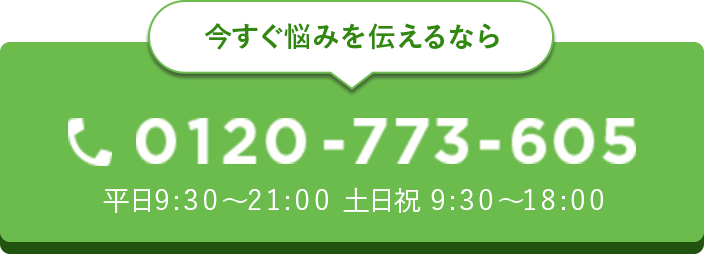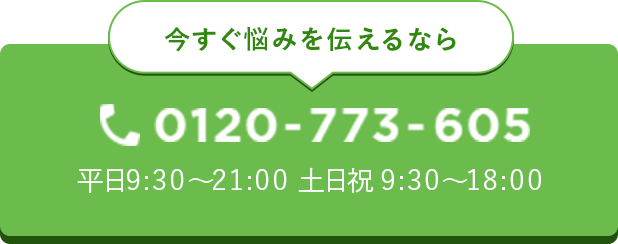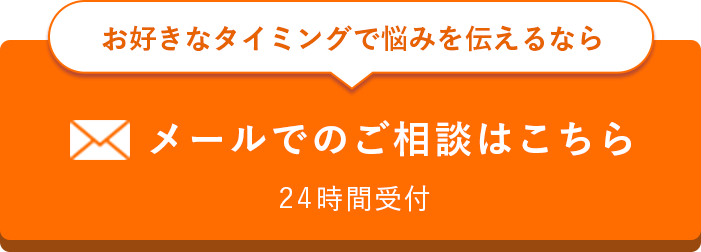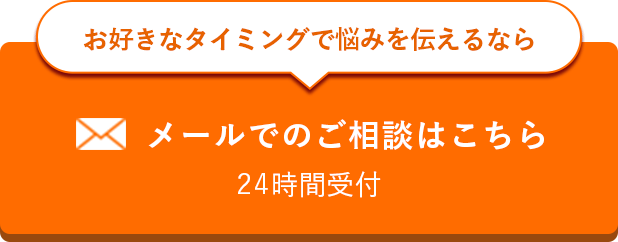過失割合の計算は、どのように行えばよいのでしょうか。
過失割合とは、交通事故が発生した際の双方の過失(不注意によるミス)を割合で示したものです。交通事故の示談では「過失割合」が問題となることが少なくありません。
追突事故のように過失割合が10:0の場合には、追突車(加害者)が交通事故で生じた損害の全額を負担することになりますが、双方に過失がある場合、損害をそれぞれの当事者の過失の程度に応じて分配する必要が生じます。
過失割合を損害賠償額に反映させる場合の計算方法についても、正しい知識をもっていなければ、「こんなはずではなかった」ということになってしまうかもしれません。
そこで今回は、
- 過失割合の計算方法
- 過失割合を決める際に注意すべきポイント
などについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。
交通事故での過失割合でもめてしまうパターンと対処法については以下の関連記事で詳細に解説しています。ぜひご参考ください。
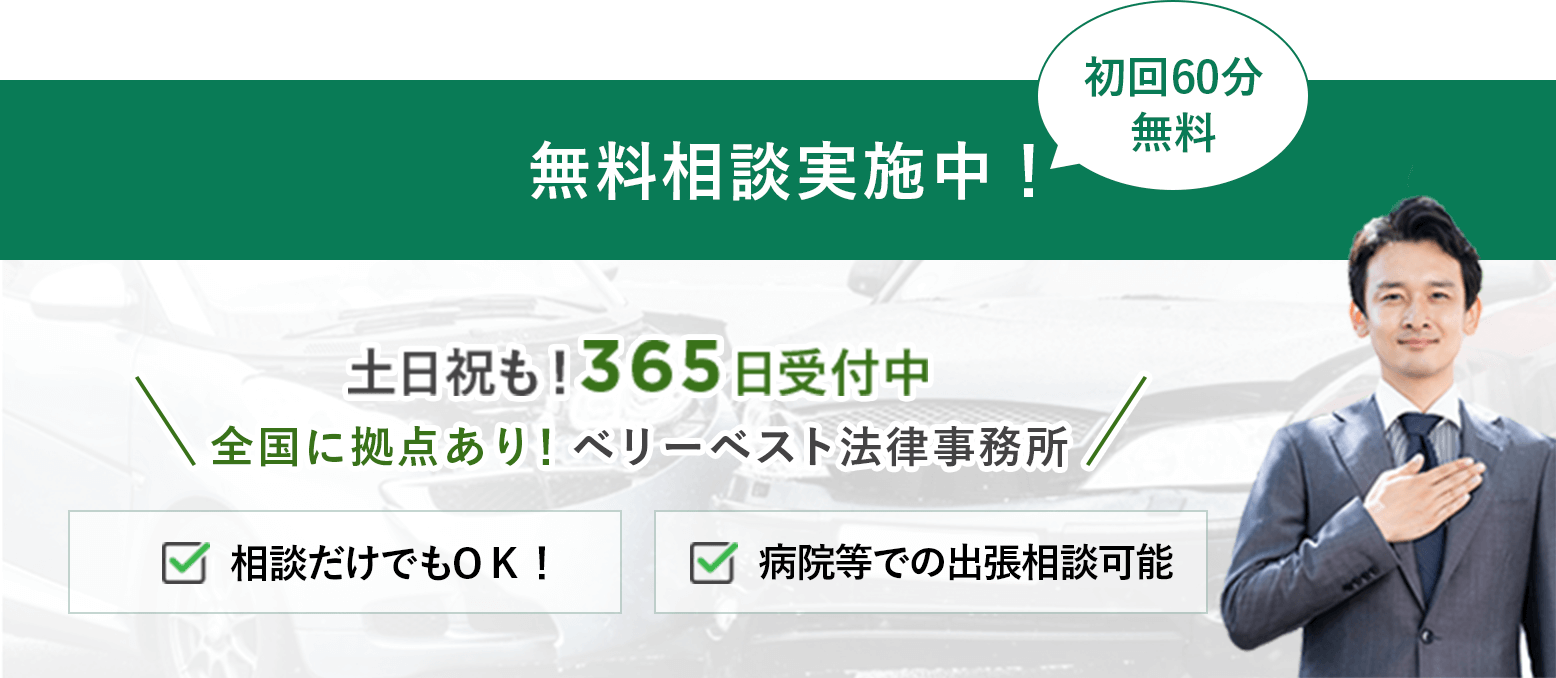

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
1、過失割合を計算するために|過失割合とは?
過失割合とは、わかりやすくいえば、交通事故におけるそれぞれの「当事者の落ち度」の程度を割合で示したものです。
たとえば、
- 信号無視で交差点に進入してきた自動車が横断歩行中の歩行者をはねた場合
- 信号待ちで停車中の車に後方車両が前方不注意で追突したような場合
には、基本的には、歩行者をはねた自動車や後方から追突した自動車が全面的に悪い(過失割合100%)と判断されることになります。
(1)実際の交通事故は双方に過失がある場合も多い
しかし実際の交通事故では、当事者双方に何かしらの過失がある場合も多いといえます。
たとえば、信号機のない交差点での衝突事故(いわゆる出会い頭の交通事故)の場合には、どちらの車両についても交差点進入時の確認に落ち度(過失)があったと判断される場合がほとんどでしょう。
また車両と歩行者との事故と聞くと、「歩行者優先」と考えて歩行者には過失がないとお考えの方も多いかもしれませんが、すぐ近くに横断歩道があったにもかかわらず横断歩道を渡らずに車道を横断していた場合などには、歩行者側にも一定の落ち度(過失)が認められる場合もあります。
(2)過失割合と過失相殺
民法では加害行為によって損害が生じたときでも、被害者側(他方の当事者)にも過失があれば、その程度に応じた過失相殺(かしつそうさい)を行うことが定められています(民法722条2項)。
たとえば交通事故によって、被害者Aに100万円の損害が生じていたときに、被害者側に20%の過失があれば、その過失の程度に応じて加害者側の賠償負担を軽減します。
このケースであれば、加害者が賠償しなければならない金額は、
100万円×(100%-20%)=80万円
ということになります。
以上のように、過失割合は、最終的な損害賠償額に大きな影響を与えるので、交通事故示談においてはとても重要なのです。
2、過失割合を決める要素
それぞれの交通事故示談における過失割合を決める上で参考になる要素は次の3つです。
- 事故の類型
- 事故の態様
- 修正要素
詳しく見ていきましょう。
(1)事故の類型
事故の類型というのは
- 車対車の事故
- 車対二輪車(バイク・原付・自転車)の事故
- 車対歩行者の事故
といったような区別です。
一般的には、歩行者<自転車<バイク(原付含む)<車の順で、基本的な過失割合は重くなります。
自転車よりも自動車の方が事故を起こしたときの被害は当然大きくなりますし、運転免許制度により道路交通法規の遵守が徹底されているので、その分だけ基本的な注意義務の程度も重い(事故を起こしたときの責任も重い)と考えることが、公平だからです。
したがって、「車対歩行者」の事故の場合には、よほどのことがないかぎり車側の過失割合が圧倒的に高くなります。
(2)事故の態様
事故の態様とは、事故の際の道路状況や当事者(加害者・被害者)の動きに着目して事故を分類したものです。具体的には、
- 正面衝突
- 右左折時歩行者を巻き込んで衝突
- 前方車両への追突
といったように分けていきます。
たとえば「交差点における出会い頭の衝突事故」のようなケースでは、信号や一時停止規制の有無、それぞれの道路の幅員(道幅)の違い(広い道路が優先)、衝突時の進路(直進か右左折か)といったさらに細かい要素によって、基本的な過失割合が異なってきます。
(3)修正要素
最終的な過失割合は、(1)(2)に基づいた基本的な過失割合をベースに、それぞれの事故における個別の事情を加味して最終的に決められます。
たとえば次のような事情が認められる場合、過失割合が修正されることになります。
- 速度違反
- 不注意運転(いわゆるながら運転など)
- 無灯火運転(特に自転車)
- 徐行・減速義務違反
- 合図(ウインカー)なし
- 歩行者が児童・高齢者(歩行者有利に修正)
(4)過失割合の具体例
過失割合の決め方についてイメージしやすくするために、具体例を用いて解説してみたいと思います。
事故状況が一番単純という意味で、「路上に駐停車している自動車に後方から進行してきた自動車が衝突したケース」を例に挙げて説明します。
停車中の車に対する後方からの追突事故ですから、事故態様としては、追突した側の車両に100%の過失があるとするのが基本です。
ただし、
- 停車されていた場所が駐停車禁止場所(トンネル、カーブの途中、道路の曲がり角、坂道等)であった
- 停車中の自動車が非常点滅灯等(ハザードランプ、三角反射板等)を点灯させていなかった
- 駐停車の仕方に問題があった(幹線道路等の交通量の多い道路で自動車を駐停車させた場合や道幅の狭い所に駐停車した場合など)
という事情があるときには、駐停車していた側にも落ち度があるので、その分過失割合が加算される(追突した側の過失が減る)ことになります。
しかし追突車両側に、
- 15㎞以上の速度違反
- 著しい過失(ながら運転等の著しい前方不注視等)
といった別の修正要素があれば、一旦減らすことができた追突側の過失割合がまた増えてしまうということもあります。
(5)自分の事故の過失割合を調べるには弁護士に相談するのが一番確実
裁判になった場合に過失割合を決めるための基準となる過失割合(上で解説したこと)は、『別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』という本にまとめて収録されています。
この本は、実際の訴訟の結果を踏まえて裁判官などがまとめたもので、交通事故を取り扱う実務家であれば必ず持っているといってよい本です。
一般の人でもAmazonなどで簡単に購入することは可能ですが、価格も安くないので、自分の事故のケースを調べるためにわざわざ購入するというのは、コストパフォーマンスが悪いかもしれません。
また、購入しても専門知識がなければ正確に読めないということもあるでしょう。
なおネット上には、別冊判例タイムズに記載されている過失割合の内容を紹介した記事もありますが、不正確な記事がないとも限りません。
また、自分の交通事故に当てはまるケースが紹介されていないということもあります。
その意味では、最も確実で正確な調査方法は、やはり弁護士に直接相談して教えてもらう(判断してもらう)ことです。
無料で相談を受けられる弁護士事務所も増えていますので、上手に活用するとよいでしょう。
3、過失割合を損害賠償額に反映させる方法
当事者の中で決定した過失割合は、最終的な損害賠償額に反映されます。
そこで、交通事故の損害賠償における過失割合がどのように最終的な損害賠償額に影響するのかについて、具体的にみていきましょう。
(1)過失割合を考慮したうえで、相手に負担させることのできる損害額の計算方法
ここではイメージしやすくするために、次のようなモデルケースを例に説明していきます。
- 事故の類型:車 対 バイク
- 事故の態様:信号のある交差点において、右折車と対向車線から直進してきたバイクとの衝突事故(信号は双方青)
- 損害額:自動車90万円・バイク10万円
※損害は車両の修理代のみとし、便宜上人損部分は考慮しない
このケースの場合には、基本的な過失割合は、自動車85:バイク15となります。
しかし、バイクに15km以上の速度違反があったということで、過失が10%プラスされて、最終的な過失割合が、自動車75:バイク25になったとしましょう。
この場合のそれぞれが負担すべき損害額は、以下に示すように、それぞれの損害額にそれぞれの過失割合をかけることで決まります。
- バイク側が負担すべき自動車の損害額
→自動車の損害(90万円)×バイク側の過失割合(25%)=22.5万円
- 自動車側が負担すべきバイクの損害額
→バイクの損害(10万円)×自動車側の過失割合(75%)=7.5万円
(2)過失割合が少なくても損害賠償を払う必要が生じる場合も
交通事故の過失割合について注意しておくべきことは、自分の側の過失割合が小さくても、相手側の損害額が大きければ、自分が払う金額もそれだけ大きくなるということです。
また、反対に、自分の側の損害額が小さければ、相手の過失割合がどんなに大きくても、請求できる額というのは少なくなってしまいます。
この点については誤解をされている方も多く、「こちらは普通に交差点を直進していただけで、一方的な被害者ではないにせよ過失が小さい側であるにもかかわらず、こちらの方が額として大きくなるのには納得できない」と言われることもよくあることです。
しかし、残念ながら、あくまで、損害賠償というのは「生じた損害のうち、相手の過失分だけが請求できる」というものですから、相手方がいかに悪かろうと(過失割合が高かろうと)、自分に損害が生じていなければ、相手方に損害賠償を請求することはできないし、逆に、相手の損害が大きければ、こちらの過失割合が低かろうと、それなりの額の賠償をしなければならないのです。
上記のケースであれば、それぞれ、自動車側は損害額(修理代)90万円のうち22万5000円をバイク側に請求でき、バイク側は7万5000円を自動車側に請求できるということになります。
(とはいえ、この22万5000円については、対物賠償保険に入っていれば自分の保険会社が払い込んでくれますので、任意保険に入ってさえいれば、自腹になるわけではありません。)
もっとも、一般的には「過失の少ない側の方が損害額も少ない」というケースの方が多いので、上記のようなケースは珍しいです。
しかし、双方の過失割合が近いケースや、損害額に大きな開きがあるケースでは、特に注意する必要があります。
また、以下の関連記事では交通事故の過失割合において被害者が賠償金を支払わないための対処法について詳細に解説しています。被害者になった場合に賠償金請求で損をしないためにも以下の関連記事もあわせてご参照ください。
まとめ|過失割合に納得できないときには弁護士に相談
以上のように、実際に交通事故が発生した場合の過失割合の計算は、やや複雑で専門的な知識を必要とする場面が多く、過失割合の違いで最終的な結果が大きく変わってしまうことも珍しくありません。
特に人身事故の場合には、損害額が非常に大きくなることがあるため、5%、10%の過失割合の違いが、数百万円、数千万円の違いになることもあります。
また、示談交渉を自分の保険会社に任せた、という場合でも安心すべきではありません。
交通事故の状況を正確に把握しないまま示談が進められ、保険会社同士の話し合いによって適正ではない過失割合で話を進められてしまうこともあるからです。
他方で、弁護士に依頼をすれば、専門家として、適正な過失割合になるよう交渉・裁判等を行ってくれるので、適正な損害賠償額を得ることのできる可能性が高くなります。
相手方や保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合には、示談をまとめてしまう前に、無料相談を上手に活用して弁護士に意見を求めてみるとよいでしょう。