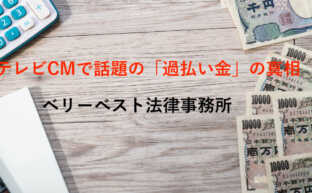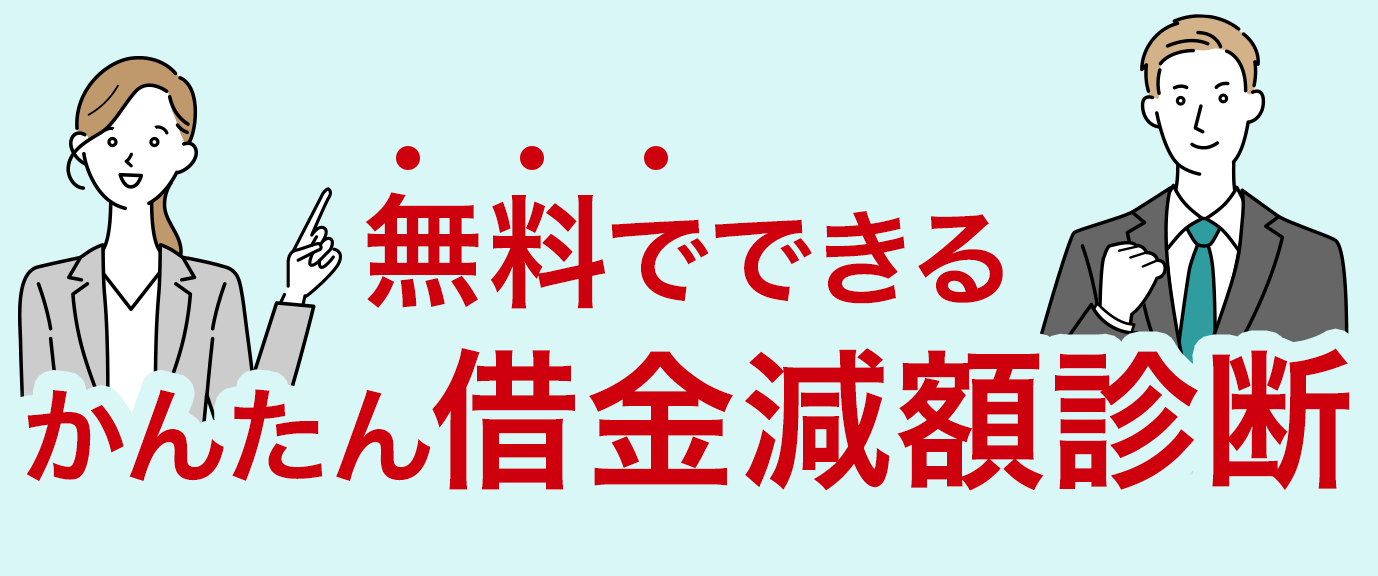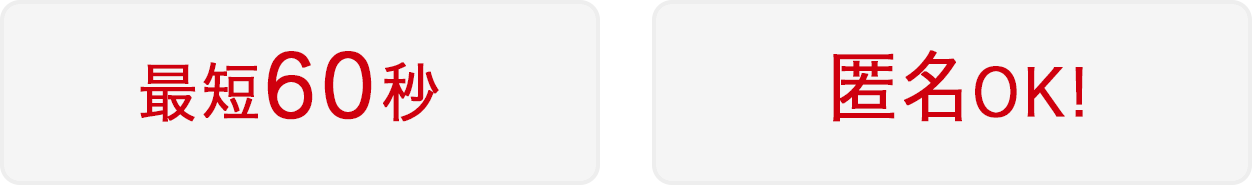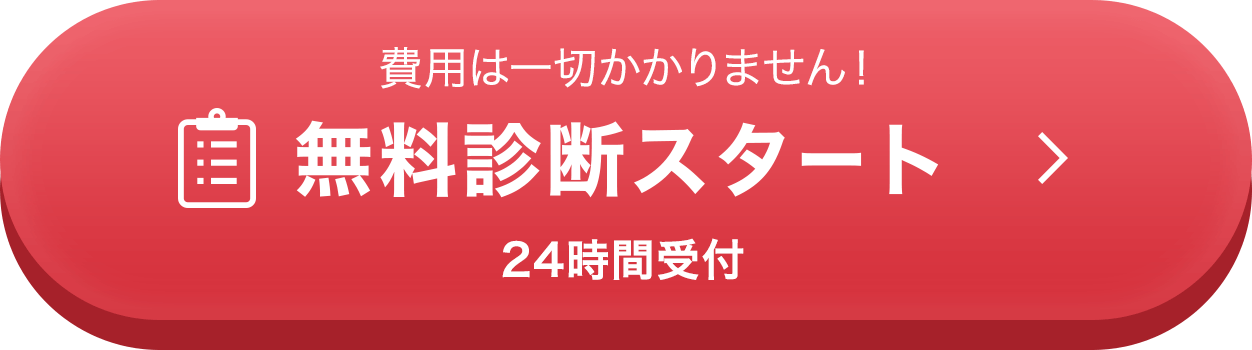過払い金の返還請求に期限があるのをご存知でしょうか。
実は、最終取引日から一定の年月が経つと、どんなに過払い金が発生していたとしても、これを取り返すことができなくなってしまいます。
そこで、今回は、
- 過払い金の返還請求ができる期限はどれくらいなのか
- 一度途中で借金を完済した後にまた借入れした場合に過払い金の返還請求できる期限に変化があるのか
- 返還を請求できる期限を延ばす方法はあるのか
についてご説明したいと思います。
ご参考になれば幸いです。
過払い金に関してはこちらの記事をご覧ください。
1、過払い金の返還請求ができる期間はどれくらいなのか
法律的な話になりますが、貸金業者に対して過払い金を返せと請求できる権利のことを「債権」といいます。
そして、民法という法律で、債権は、永遠に存続するのではなく、一定の期間これを行使しないと消滅してしまうと定められています。
これを消滅時効といいます。
過払い金の返還請求権も債権である以上、一定の期間これを行使しないと、時効で消滅してしまうのです。
では、過払い金の返還請求権の時効期間はどれくらいでしょうか。
これは、権利が行使できる日から10年とされています。
具体的には、過払い金の返還請求権は、借金を完済した時点から行使できるようになると考えられているので、最終取引日から10年の間は過払い金の返還を求めることができますが、10年を経過すると返還請求権が時効で消滅してしまいます。
2、一度途中で借金を完済した後にまた借り入れをした場合の時効について
借入れ(取引)が1回だけというのであれば、いつ時効期間が開始して、いつが時効完成の日なのかということはすぐにわかりますが、一度完済した後に再度借り入れたというような場合(取引が複数の場合)の時効期間の始まりと、時効完成の日はどのように考えればいいのでしょうか。
具体的な例にそって説明していきたいと思います。
たとえば、①平成5年3月1日に借入れを開始して、平成15年2月28日に一度完済し、②平成17年5月1日に再度借入れを開始して、平成26年4月30日に完済したというような場合、過払い金の返還請求権の消滅時効の起算点と完成はいつになるでしょうか。
これは①の取引と②の取引を一連一体の一つの取引と考えるか(考え方①)、2つの別の取引と考えるか(考え方②)によって結論が異なります。
まず、一連一体の取引と考えれば、時効の起算点は、②の最終取引日である平成26年4月30日となり、ここから10年の平成36年4月30日に時効が完成することになります。
それに対して①と②を別の取引と考えると、①の取引については、平成15年2月28日の翌日(平成15年3月1日)が時効の起算点となり、平成25年2月28日に時効が完成し、②については、平成26年4月30日の翌日(平成26年5月1日)が時効の起算点となり、平成36年4月30日に時効が完成することになります。
では、考え方①と考え方②のいずれで時効の起算点と完成を考えるべきなのでしょうか。
これについては、裁判所は、両取引の内容・条件・経緯や前後の取引の間隔の長さ等を考慮して、一連一体の取引と言えるかということを事案ごとに判断します。
取引の内容・条件が同一であったり、間隔が短い場合には一連一体と判断される可能性が高いでしょう。
逆に、取引の内容・条件が異なっていたり、間隔が長い場合には別の取引と判断されるでしょう。
3、請求できる期限を延ばす方法はあるのか
ここまでご覧いただいて、時効が迫っているかもしれない、と思われている方もいらっしゃるでしょう。
最後に、このように時効が迫っている場合、どのようにすればいいのか、時効の完成を遅らせる方法はないかという点についてご説明したいと思います。
まず、時効の完成が迫っている場合には、取り急ぎ「催告」を行いましょう。
催告というと難しそうですが、要するに、過払い金の返還請求を行うという意思を業者に対して表示すればいいのです。
後で、催告があった・なかったという争いになるのを避けるために、催告は内容証明郵便で行うのがいいでしょう。
催告を行えば、時効の進行を半年間停止されることができます。
この間に、過払い金の返還を請求する裁判を提起すれば、時効が中断しますので、無事に過払い金を取り返すことができます。
まとめ
今回は、過払い金請求の時効について説明しましたが、参考になりましたでしょうか。
過払い金は、ご自身が高い利息で債務を支払い続けた結果として請求できるものですから、時効で請求できなくなってしまうのはとてももったいないことです。
請求できる期間に気をつけて、早めに請求しましょう。