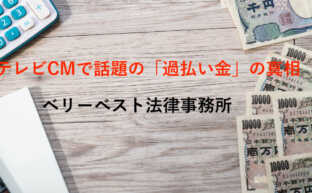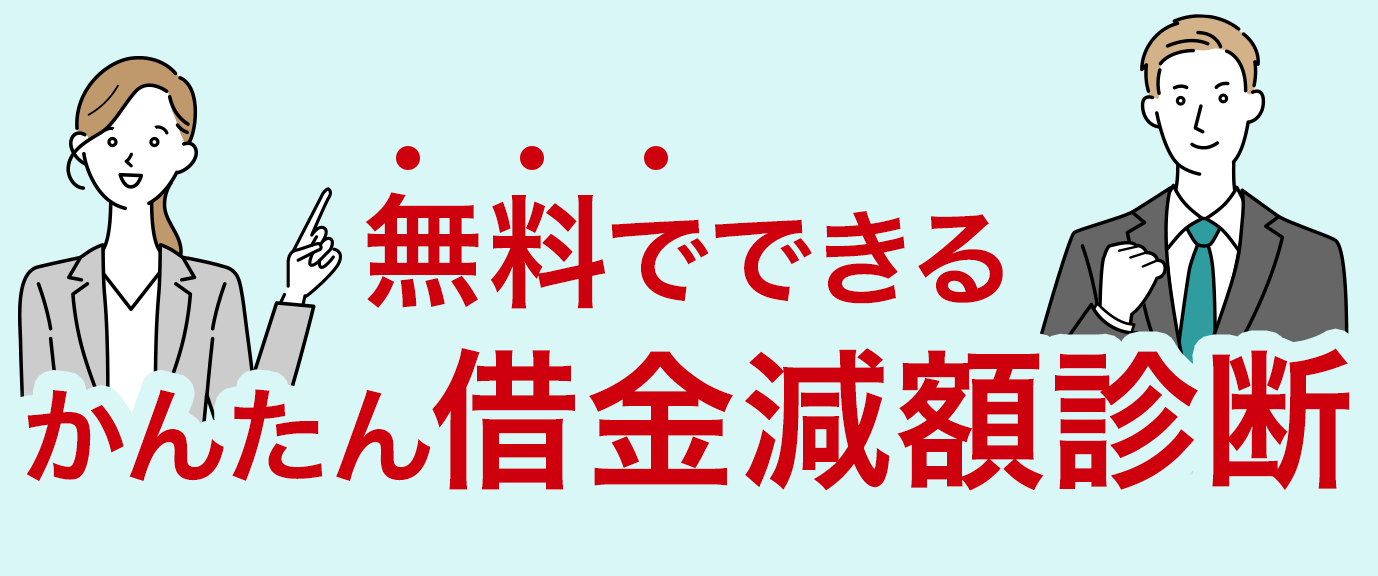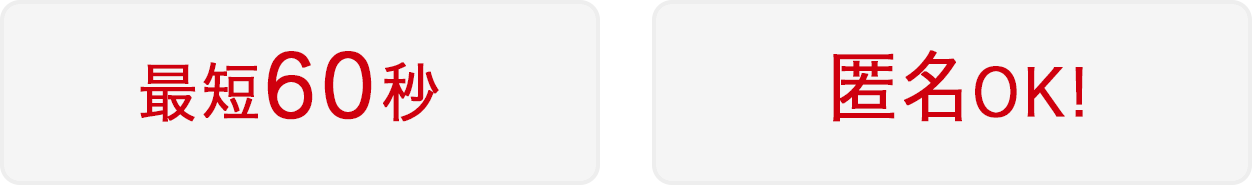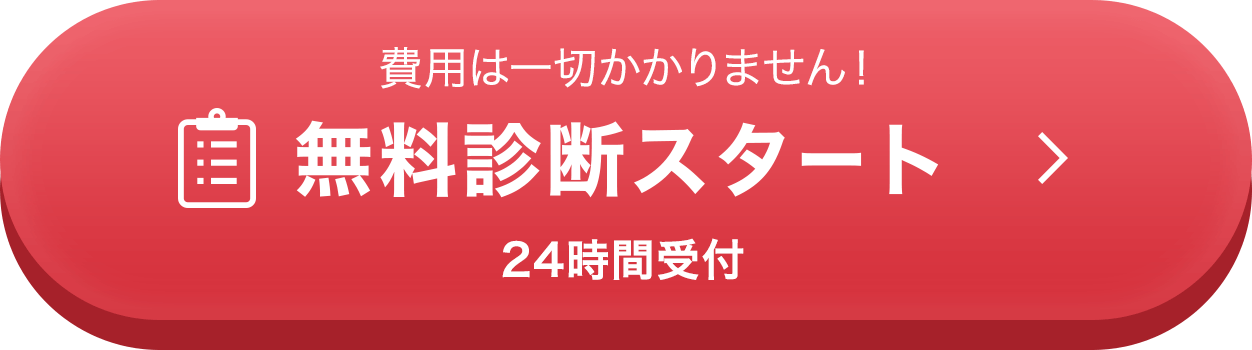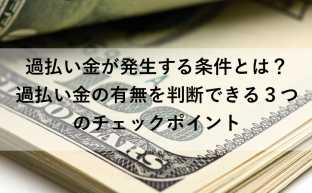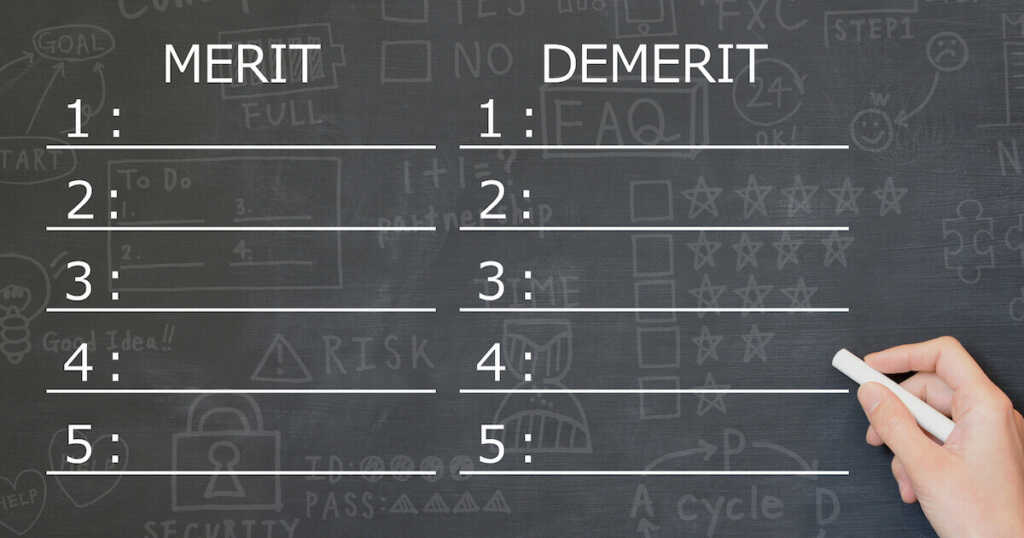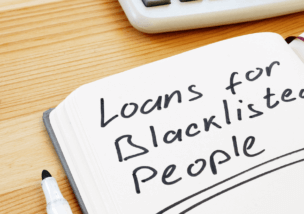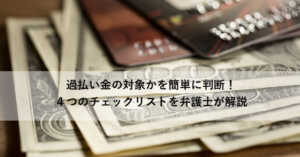
過払い金の対象かを簡単に判断するための方法をご紹介します。
借金を返済中の方や、過去に借金をしたことがある人の中には、ご自身が過払い金の対象となっているかどうかが気になる方も多いことでしょう。
結論から申しますと、過払い金の対象となるのは、以下の4つの要件をすべて満たす場合です。
- グレーゾーン金利で借金をしていたこと
- 2007年より前から借金をしていたこと
- ショッピングではなくキャッシング・借入をしていたこと
- 完済してから10年が経っていないこと
とはいえ、実際にこれらの要件を満たすかどうかを判断するためには、専門的な知識を要する部分もあります。
そのため、一般の方にはなかなか判断が難しいこともあるかもしれません。
そこで今回は、以上4点の詳しい解説を中心として、過払い金の対象かどうかを判断する方法について、累計回収件数69,042件、累計回収金額882億円以上の過払い金を回収して きたベリーベスト法律事務所の弁護士が解説したいと思います(集計期間: 2011年1月~2021年2月末日)。
過払い金に関してはこちらの記事をご覧ください。
目次
1、過払い金請求の対象となっている可能性が高い要件
それではさっそく、過払い金の対象となる借金の要件について詳しく解説していきます。
これらの要件をすべて満たせば過払い金請求をすることが可能なので、以下のご説明は「4つのチェックリスト」として活用していただくこともできます。
過払い金が発生する条件について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
(1)グレーゾーン金利で借金をしていたこと
まず第一の要件は、グレーゾーン金利で借金をしていたことです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利を超えるものの、出資法の上限金利を超えない範囲内の金利のことです。
グレーゾーン金利については、後ほど「2」で詳しくご説明します。
(2)2007年より前から借金をしていたこと
実は、現在では法改正により、グレーゾーン金利は撤廃されています。そのため、新たな過払い金はもう発生しなくなっています。
したがって、ある程度以前から借金をしていることが1つの過払い金が発生する条件となります。
いつ頃から借金をしていれば過払い金発生の可能性が高いのかについては、後ほど「3」でご説明しますが、2007年より前から借金をしているかどうかがひとつの目安となります。
2007年以降に借り始めた場合、過払い金が発生している可能性はゼロではありませんが、あまり期待できないのが実情です。
(3)ショッピングではなくキャッシング・借入をしていたこと
3つめの要件は、クレジットカードのショッピングではなくキャッシングをしていたこと、または消費者金融から借入れをしていたことです。
クレジットカードのショッピングは過払い金の対象とはならないことにご注意ください。
どのような取引が過払い金の対象となるのかについては、後ほど「5」でご説明します。
(4)完済してから10年が経っていないこと
過払い金請求には時効があり、取引終了時から10年経つと時効が完成して消滅し、それ以降は過払いがあっても請求することができません。
今も返済を続けている人は、10年以上返済を続けていても時効は来ていません。
そのため、高い金利の返済を続けていて過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求をすることができます。
また、今既に完済していても、時効が来ていなければ過払い金を請求できる可能性があります。
2007年以前に借金をしたことがある人は早急に確認し、完済してから10年経っていない人は、専門家に相談してみてください。
2、過払い金の対象となる金利とは?
過払い金の対象となる第一要件として、グレーゾーン金利で借金をしていたことを先ほど「1(1)」で挙げました。
ここでは、グレーゾーン金利について具体的にご説明します。
(1)グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、前記「1(1)」でもご説明したように、利息制限法の上限金利を超えるものの、出資法の上限金利を超えない範囲内の金利のことです。
この範囲内の金利は、民事上は違法であるものの刑事罰の対象とはならないことから、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
利息制限法では、借金に適用される金利について、元金の額に応じて次のように上限が定められています。
- 元金10万円未満の場合 年利20%
- 元金10万円以上100万円未満の場合 年利18%
- 元金100万円以上の場合 年利15%
同時に、金融業者は「出資法」という法律で、お金を貸す際の上限金利が29.2%に制限されていました。
これを超える金利でお金を貸すと刑事罰の対象となるため、金融業者も出資法の上限金利は守っていました。
しかし、利息制限法の上限金利に違反しても罰則がないため、多くの貸金業者が29.2%、またはそれに近い金利でお金を貸していたのです。
これが、過払い金が発生する仕組みでもあります。
グレーゾーンと過払い金についてさらに詳しくは、以下の記事をご参照ください。
(2)従来から利息制限法の範囲内の取引は対象外
上記のことを逆に言えば、金融業者は利息制限法に定められた上限金利の範囲内であれば、正当に利息を受け取ることができます。
そのため、利息制限法の範囲内の取引は過払い金の対象外となります。
一部の貸金業者は、グレーゾーン金利が撤廃される前から利息制限法の範囲内でのみ貸付を行っていました。
そのような貸金業者との取引からは、過払い金が発生することはありません。
3、過払い金の対象となる借入の時期とは?
以前はグレーゾーン金利が存在していましたが、法改正に伴い、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。
過払い金の対象となるのは、グレーゾーン金利が存在していたときの借金のみです。
そこで重要となるのは、グレーゾーン金利がいつまで存在していたのかという点です。
(1)2007年より前からの借入は対象となる
2010年6月18日から改正出資法が施行され、出資法上の上限金利も利息制限法と同じ年利20%に引き下げられました。
この時点まではグレーゾーン金利は存在していましたが、貸金業者の大半は、2007年末ころまでに自主的に、借金の金利を利息制限法の範囲内にまで引き下げました。
それまでは多くの貸金業者がグレーゾーン金利で貸付を行っていたため、2007年より前からの借入れは過払い金の対象となります。
(2)2008年~2010年の借入も対象となる可能性がある
2008年以降も改正出資法が施行される2010年6月18日までは、ごく一部ですがグレーゾーン金利で貸付を行っていた貸金業者もいたようです。
そのため、この期間中の借入れも過払い金の対象となる場合がありますが、可能性としては低いでしょう。
とはいえ、可能性はゼロではありませんので、弁護士にご相談の上、ご確認いただくことをおすすめします。
(3)2010年6月以降の借入は対象外
2010年6月18日以降は法律上、グレーゾーン金利が撤廃されたため、それ以降の借入れは過払い金の対象外です。
闇金業者からの借入れは別ですが、消費者金融も含めて正規の貸金業者については、2010年6月18日以降の借入れから過払い金が発生することはありません。
4、過払い金の対象となる借入の期間とは?
次に、どれくらいの期間借金の取引を続けていれば過払い金の対象となるのかについてご説明します。
この問題については、現在も借金を返済中の場合と、すでに完済した場合とに分けて考える必要があります。
(1)返済中の場合
現在も借金を返済中の場合は、グレーゾーン金利での取引を概ね5年以上続けていたかどうかがひとつの目安となります。
グレーゾーン金利で返済を続けていた場合、概ね5年で本来の計算上は借金を完済したことになるのが平均的です。
5年を超えて返済を続けていた場合は引き直し計算をすると完済になって過払い金が発生している可能性が高く、返済期間が5年よりも短い場合は債務が残る可能性が高いです。
ただし、過払い金が発生していない場合でも、本来の計算上は残高が減少するはずです。
なお、以上はあくまでも目安です。借入額や返済額、返済回数、追加借り入れの有無や程度によって計算結果は様々です。正確に判断するためには、弁護士へのご相談をおすすめします。
(2)すでに完済している場合
すでに借金を完済している場合は、1度でもグレーゾーン金利で返済したことがあれば過払い金の対象となります。
ただし、前記「1(4)」でご説明したように、完済してから10年が経過していると過払い金返還請求権が消滅時効にかかっていることに注意が必要です。
5、過払い金の対象となる取引の種類とは?
過払い金の対象となる取引の種類を端的に申しますと、「消費者金融からの借入れ」および「クレジットカードによるキャッシング」です。
以下の取引は対象外となりますので、ご注意ください。
(1)クレジットカードのショッピング
クレジットカードのキャッシングは過払い金の対象ですが、ショッピングは対象外となります。
なぜなら、ショッピングにかかる「手数料」は利息ではなく、分割払い手数料だからです。
過払い金の対象となるのは、金銭を目的とする消費貸借契約(つまり、「借金」)のみです。クレジットカードのショッピングは「借金」ではなく、分割払い契約なので利息制限法の適用はありません。
そのため、過払い金の対象とはならないのです。
これに対して、クレジットカードのキャッシングは「借金」そのものなので、過払い金の対象となります。
(2)各種ローン
住宅ローンや自動車ローンなどのように、物を担保にとったローンのほとんどは利息制限法の範囲内で貸し付けられているため、過払い金の対象外です。
ただし、消費者金融が取り扱っている不動産担保ローンについては要注意です。
2007年以前には、消費者金融は不動産担保ローンでもグレーゾーン金利を適用しているケースが多くありました。
そのようなケースは過払い金の対象となります。
(3)銀行や公庫からの借入
銀行や日本政策金融公庫など政府系の金融機関からの借入れでは、2007年以前から利息制限法の範囲内の低金利が適用されていました。
そのため、これらの借入れは過払い金の対象外です。
6、過払い金の対象から外れる2つのケースとは?
過払い金が発生していても、法律的に、または事実上、請求できないために対象外となるケースが2つあります。
(1)時効で消滅した場合
前記「1(4)」でご説明したとおり、借金を完済してから10年が経過すると、過払い金が発生していても消滅時効にかかります。
その場合、貸金業者に請求しても時効を主張されるため、過払い金を取り戻すことはできません。
ただし、貸金業者から時効を主張されても、実際には消滅時効が完成していないケースもあります。
それは、いったん完済したものの、しばらくして同じ業者から再度借り入れて取引を再開した場合です。
この場合は、最初の完済から10年以上が経過していても、完済前の取引と再開後の取引が一連のものと判断されて、過払い金の対象となる可能性があります。
一連の取引と認められるかどうかについては、様々な事情を考慮する必要があるため、弁護士にご相談ください。
(2)貸金業者が倒産した場合
過払い金が発生していても、請求先である貸金業者が倒産してしまえば過払い金を取り戻すことはできなくなります。
近年、過払い金の返還が負担となって倒産した貸金業者も少なくありません。
倒産に至らなくても、業績が悪化したことにより発生した過払い金の10~20%程度しか返還しない貸金業者もいます。
そのため、過払い金の対象となっている方は、早期に貸金業者に対して請求し、過払い金を回収することが大切です。
なお、貸金業者が倒産した場合でも、他社に吸収合併された場合は、合併後の会社に対して過払い金請求をすることができます。
7、過払い金の対象外と思われがちだが実は対象となるケース
「自己破産をしているから……」、「和解が成立しているから……」、「親の借金だから……」等、様々な理由で過払い金が発生しないと思い込んでしまっている方がいます。
以下では、誤解されがちな過払い金の対象となるうるケースを紹介します。
(1)自己破産の申立てをしたことがある
自己破産をしていても、過払い金請求ができる場合があります。
自己破産手続きを弁護士に依頼した場合にはあまりありませんが、自己破産の申立をする際に過払い金の有無を調査していなかった場合には、過払い金が残っている可能性があります。
また、自己破産をした後に再度、グレーゾーン金利で借金をした場合も、過払い金の対象となります。
(2)和解をしたことがある
過去に、金融業者と任意整理や調停で和解したことがあった場合でも、引き直し計算をする前の和解だった場合には過払い金が残っていることがあります。
こちらも、弁護士に依頼して任意整理をした場合には過払い金が残っていることはあまりないのですが、ご自身で手続きされた場合は、過払い金が残っているケースが少なくありません。
ただし、この場合は、金融業者側が和解によって過払い金も解決済だと反論してくる可能性が高いです。
(3)亡くなった親が借金をしていたと聞いたことがある
過払い金請求権は、相続することができます。もし、亡くなった親が借金をした話をしていたような場合は、過払い金が発生している可能性があります。
その場合、過払い金請求権を相続した遺族が、過払い金を受け取ることができます。
8、過払い金の対象となっているときに行うべき2つのこと
以上の各項目をチェックすれば、過払い金の対象かどうかを判断することができます。
対象となっている場合には、実際に過払い金が発生しているかを調べるために以下の2つのことを行う必要があります。
過払い金の対象となっているかどうかを明確に判断しづらい場合も、以下のことを行ってみた方がよいでしょう。
(1)金融業者から取引履歴を取り寄せる
取引履歴とは、いつ・いくらの借金を何パーセントの利息で借りたかのか、いつ・いくら返済したのかという記録のすべてが記載された書面のことです。
取引履歴は、金融業者のサービスセンターなどに電話をして取引履歴を送るよう依頼すると、概ね2週間以内には自宅宛てに届けられます。
なお、取引履歴の送付を依頼したら脅されるのではないかと心配になる方もいるかもしれませんが、最高裁判所で、貸金業者は取引履歴の開示請求に応じなければならないという判例が出ているので、断られたり脅されることはありませんから、安心して請求してください。
家族に借金をしていたことを知られたくないという人は、弁護士などの専門家に取引履歴の取り寄せを依頼することで、自宅に金融業者から手紙が届いて家族にばれることを防ぐことができます。
(2)引き直し計算をする
取引履歴を入手したり、ご自身で借入金額と返済状況が分かっている場合は、引き直し計算をして過払い金として取り戻せる金額があるかどうかをチェックしてみましょう。
引き直し計算は自分ですることもできます。
例えば、元金100万円を、出資法ギリギリの29%で借り、年間29万円返済する例を考えてみます。
金利29%で借りると、年間29万円の利息が発生することになるので、年に29万円返済しても利息分になるだけで、元金は何年たっても100万円から減りません。
これを、利息制限法の金利で計算し直すと(引き直し計算)、金利は最高でも年15%となるので、年間15万円の利息が発生し、年に29万円返済すると元金は86万円に減ることになります。
この計算を元金がゼロ円になるまで繰り返すと、6年目には完済できる計算になります。
つまり、29%という元の金利のままだと、本来完済した以降の金利を払いすぎていたことになり、これを過払い金として返還請求できることになるのです。
とはいえ、ご自身で引き直し計算をして過払い金の発生をチェックするのは難しい場合が多いです。
インターネットで、無料の過払い金の計算ソフトが多くあげられているのでそちらを利用してみるか、取引明細を持って弁護士などに相談すると、より確実なチェックができるので安心です。
9、過払い金請求は自力でできる?弁護士に依頼するメリット・デメリット
過払い金請求は自力で行うことも可能ですが、納得できる結果を得るためには弁護士に依頼する方が得策となる場合が多いです。
ただ、弁護士に依頼する前にデメリットについても知っておく必要がありますし、その前に、そもそも過払い金請求をするべきかどうかも考えておかなければなりません。
(1)そもそも過払い金請求をするべきか?過払い金請求のメリット・デメリット
過払い金請求にはメリットしかなく、デメリットはないと思われるかもしれませんが、現在、借金を返済中の方は注意が必要です。
①借金を完済していた場合
過払い金請求をする最大のメリットは、払いすぎた利息が戻ってくるということです。
また、借金を完済した金融業者に過払い金請求をしても、ブラックリストには載らないというのも大きなメリットです。
これから住宅ローンやマイカーローンを組むのに過払い金請求をしたために断られたり、今使っている他社のクレジットカードが使えなくなることもありません。
②借金返済中に過払い金請求をして借金が完済になる場合
借金を返済中に過払い金返還請求をする際には注意が必要です。
借金返済中に過払い金請求をする場合で、引き直し計算をすると、借金が全額返済になったうえに過払い金が発生することがあります。
このような場合には、過払い金請求に着手した時点で借金が残っていることから、一旦はブラックリストに載せる貸金業者もあるようです。
ただし、過払い金が発生していた場合には、すぐに完済扱いとして登録されるので、大手の消費者金融では、弁護士から過払い金返還請求書が届いた時点で完済扱いとして登録するようです。
③借金返済中で借金が残る場合
引き直し計算をしても借金が残る場合や、クレジットカードのショッピング枠の利用が残っている場合には注意が必要です。
この場合は、債務整理を行ったことがブラックリストに載ることになり、残った借金の返済期間と、完済から5年の間は、ブラックリストに載ることになります。
この点が、過払い金請求で注意すべきデメリットと言えるでしょう。
(2)弁護士に過払い金請求を依頼した場合のメリット・デメリット
過払い金請求をすることに決めたとして、次に、弁護士に依頼するメリットとデメリットをご紹介します。
①弁護士に依頼した場合のメリット
過払い金の請求には、きちんと書類を揃え、必要な期日に合わせて法的な対応をとることが求められます。
具体的には、取引履歴を取得し、引き直し計算により過払い金の額を確定させたら、貸金業者に対して請求を行います。
もし、相手が取引履歴の提出を渋ったり、返還に応じない場合には裁判に至ることもありますが、この場合は契約書や通帳履歴から引き直し計算を行った後に訴訟を提起し、裁判の期日に裁判所に出向いて主張を述べなければいけません。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きをすべて任せられるというメリットがあります。
また、借金を返済中で取り立てに困っている場合には、弁護士を代理人にすることで取り立てを止めたり、家族に借金をしたことを知られたくない場合には弁護士に業者とのやり取りを任せられるので、秘密裏に解決できるというメリットもあります。
なお、ベリーベスト法律事務所は無料で過払い金の対象となるを診断しています。お気軽にお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所:0120-170-316(通話無料)
②弁護士に依頼した場合のデメリット
弁護士に依頼すると、過払い金請求の費用が必要になる点がデメリットと言えるでしょう。
一般的に、回収した金額の20%程度を弁護士費用とする法律事務所が多いようです。
初回の相談が無料であったり、報酬にも差があるので、過払い金請求の扱いが豊富な弁護士事務所にいくつかあたってみるとよいでしょう。
なお、過払い金請求は、弁護士以外にも司法書士が行うケースもあります。
ただし、司法書士の場合は、過払い金が140万円を超えると代理権がないため、代わりに請求してもらうことなどが出来ないので注意してください。
まとめ
いかがでしょうか。
現在はすでに法改正から時間が経過しており、過払い金が発生していても時効が近付いていると言われています。
もし、ご自身が過払い金の対象となっている場合には、できるだけ早く行動に着手しましょう。
ご自身で何をすべきか分からない、何から手を付けたらいいか分からない場合には、弁護士などの専門家に、まずは御相談されることをおすすめします。