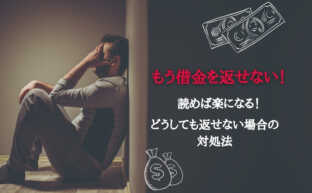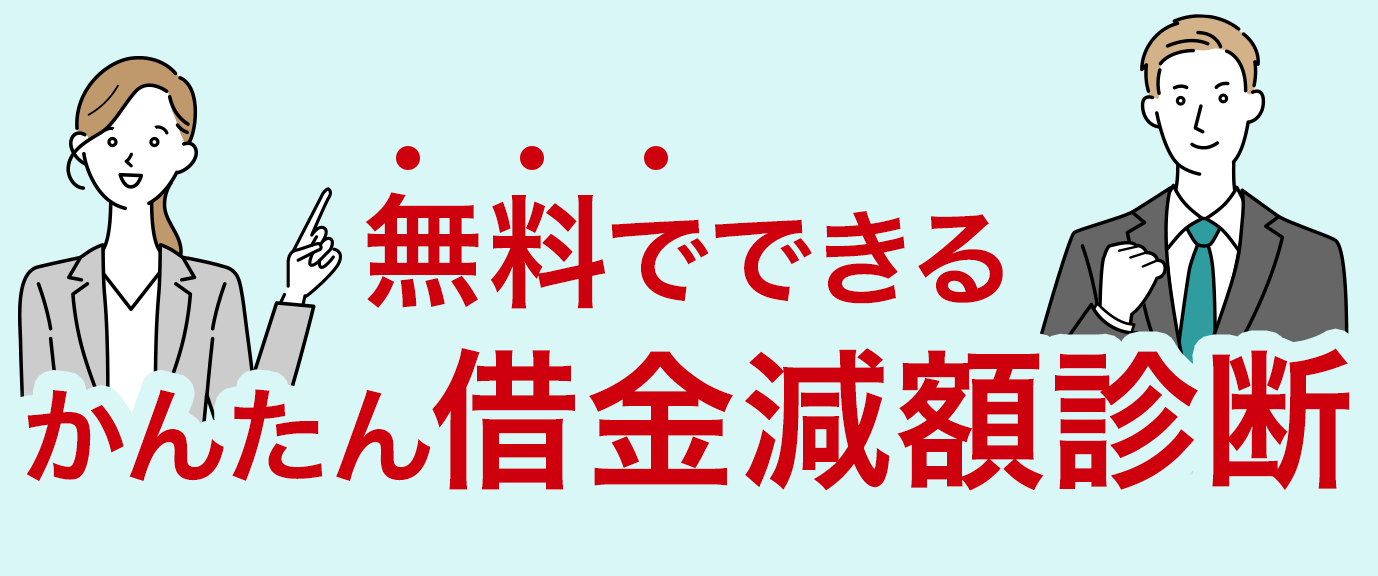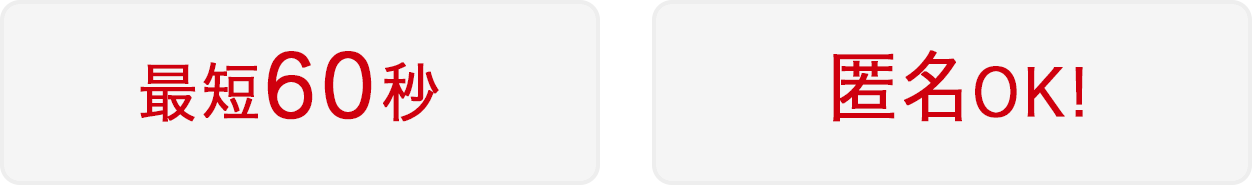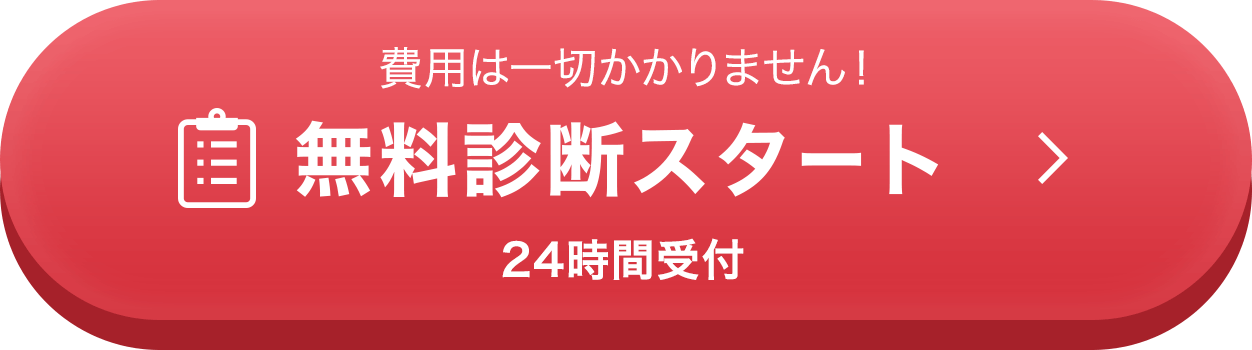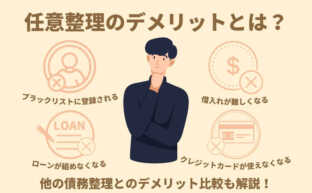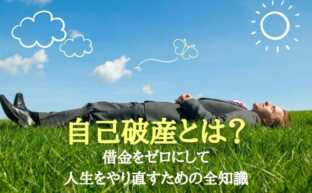借金の時効についてご存知でしょうか?
世の中には、借金をしている方はたくさんいらっしゃいます。借金の返済に現在も苦しんでいる方や、中には借金の返済をしばらく放置している方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、そんな借金の返済を一定期間放置した場合に、借金がチャラになってしまう「時効」という制度についてお話しします。
- そもそも時効とは何なのか?
- どのぐらいの期間で時効が成立するのか?
- どのような手続きが必要なのか?
など、借金と時効についての疑問に、一つ一つお答えしていきます。
借金が返せない場合に取るべき行動全般に関しては、以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、時効で借金をチャラにできる?(時効で借金はなくなる?)
(1)そもそも時効とは何か?
「時効」と聞いて何を想像するでしょうか。多くの方は、ハードボイルドな刑事が「このヤマ(事件)はもう少しで時効にかかる……。」なんてセリフを口にする刑事ドラマなどのワンシーンを想像したのではないでしょうか。
この場合の時効は、刑事上の時効で、「公訴時効」といいます。
時効は刑事上だけではなく、「取得時効」や「消滅時効」と呼ばれる民事上の時効もあります。
民事上の時効は、ある事実状態が所定の期間(これを「時効期間」といいます)継続した場合に、その事実状態に対応する権利関係を認める制度です。このように、時効というのは、事実状態と本来の権利関係が整合しない場合に、事実状態に合わせた権利関係を認めてしまう制度ですので、法の世界ではかなり例外的位置づけになります。
(2)借金も時効で消滅する?
借金の返済にも「時効」はあります。
この場合の「時効」は、先ほど出てきた「消滅時効」と呼ばれるものです。
「消滅時効」というのは、一定期間、ある権利を行使しないなどの事実状態を尊重して、その権利を「消滅」させてしまうというものです。つまり、本来は借金を返さなければならないのに、一定期間借金を返さないという「事実状態」が継続すると、時効により借金の消滅が認められてしまうのです。この「消滅時効」により、消費者金融や友人・親族等からの借金は、消滅する可能性があります。
2、借金の時効の期間は?
(1)2020年3月31日以前の借入
この場合には旧民法が適用されます。
銀行や消費者金融などの貸金業者からの借金は、返済期日の翌日から5年が時効期間、友人や知人、親族など商人でない人からの借金については、返済期日の翌日から10年が時効期間となります。
なお、法人からの借金であっても、信用金庫、住宅金融支援機構、日本学生支援機構、勤務先などからの借入は商行為に該当しないため、時効期間は10年となることに注意が必要です。
(2)2020年4月1日以降の借入
この場合には新民法が適用されます。
時効期間は「権利を行使できると知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができるときから10年間行使しないとき」のどちらか早い方となります。
貸金業者からの借金については、上記と同じく、返済期日の翌日から5年が時効期間となり、友人や知人、親族などからの借金についても、返済期日の翌日から5年です。
なお、時効期間が経過しただけで自動的に借金が消滅するわけではなく、返済義務を免れるためには「時効の援用」を行う必要があります。時効の援用については以下の関連記事をご確認ください。
3、期間が経過しただけでは借金はなくならない!時効で借金を消滅させる手続きとは?
法律上定められている時効期間が経過しても、借金が当然に消滅するわけではありません。時効によって借金を消滅させるには、時効を「援用」しなければなりません。
「援用」というのは、時効制度を利用するという意思を債権者に対して示すことをいいます。時効制度を利用する意思さえ示せばよいので、これに対する債権者の承諾は必要ありません。
4、時効の援用の手続きの流れ
時効の援用の手続きについては、法律上特に決まりはありません。債権者に対して、時効制度を利用する意思を示すことさえできれば、口頭でも書面でも構いません。
もっとも、いつ時効を援用したのかを証拠として残して、後日の紛争を避けるためにも、時効を援用する内容を記載した書面を「内容証明郵便」(確定日付を証明してくれる郵便です。)を利用して、債権者に対して送付するのが一般的です。
5、時効援用時の注意点
時効を援用する際には、以下の点に注意してください。
(1)時効が成立しているのかよく確認する
時効期間の計算間違いには注意してください。時効期間が経過していないのに時効を援用しても、借金は消滅しません。
(2)借金を支払う意思を伝えない
借金を支払う意思を債権者に伝えてしまうと、時効を援用できなくなってしまいますので注意してください。借金を支払う意思と時効を援用して借金を消滅させようとする意思は、矛盾する態度になってしまうためです。
(3)時効の援用は口頭で行わない
時効の援用の手続きについては、法律上特に決まりがありませんので、口頭で行うことももちろん可能です。ですが、口頭で行うと、後々、債権者との間で時効の援用をしたかどうかで争いになる恐れがあるため、「内容証明郵便」を利用して時効を援用するようにしてください。
6、時効の援用が認められないケースとは
具体例としては以下の通りです。
- 裁判による請求
- 督促状
- 借金の存在を認めて返済をしている場合
時効の援用は、必ず認められるわけではありません。
「時効の更新」があると、時効の援用は認められません。「時効の更新」というのは、それまで進行してきた時効期間が「ゼロ」に戻ってしまうというイメージです。振り出し(「ゼロ」)に戻ってしまうのです。
「時効の更新」を生じさせる事情としては、
①請求
②差押え、仮差押え又は仮処分
③承認
の3つが法律上規定されています。
①と②は、権利を有している者が権利の実現に向けた行為であり、③は、権利を行使される者が相手の権利の存在を認めるという行為です。このような事情があると、時効の基礎となる事実状態よりも、本来の権利関係を尊重すべきであり、時効の成立を認めるべきではないと考えられるため、「時効の更新」が生じるとされています。
(1)請求
これは主として、裁判上の請求のことを示します。すなわち、債権者が、債務者に対し、貸金返還請求などの民事訴訟を提起すると、「時効の更新」が生じます。
なお、債権者が、債務者に対し、督促状を送りつけるだけでは、「時効の更新」は生じません。督促状が到達することにより、時効期間の進行はいったんストップしますが、到達してから6か月以内に裁判上の請求などを行わないと、「時効の更新」は生じず、再び時効期間が進行していくことになります。
(2)差押え、仮差押え又は仮処分
これらの手続きは、債権者が自己の権利の行使を実現するために、債務者の財産を確保する手続きであり、債権者が自己の権利を行使する意思が明確となりますので、「時効の更新」が生じるとされています。
(3)承認
承認というのは、債務者が債権者の権利の存在を認める行為をいいます。すなわち、時効期間満了前に、借金を返す意思を債権者に対して示したり、1円でも返済したりすると、債権者の権利の存在を認めたものとみなされ、「時効の更新」が生じます。
なお、時効期間満了後であっても、これらの行為を行うと、時効の利益を放棄したものとみなされ、時効を援用できなくなってしまいますので注意が必要です。
7、時効の援用が難しい場合に借金問題を解決する方法は?
時効の援用によって借金を消滅させるのが難しそうな場合はどうすべきでしょうか。
主に、①任意整理と②自己破産という2つの方法があります。
(1)任意整理
「任意整理」というのは、弁護士が裁判所を介さずに、債権者と直接交渉を行って、支払額や支払方法について合意をするというものです。
任意整理のメリットとしては、①裁判所を介さなくてよい②官報(国が発行する機関誌)に名前が載らない③債務の利息がカットできる、などが挙げられます。また、デメリットとしては、①ブラックリストに載ってしまう②借金の支払いが免責されるわけではない③強制執行手続きを中断することができない、などが挙げられます。
(2)自己破産
「自己破産」というのは、裁判所を介した手続きにより、借金の返済が免責され、経済的に再出発をするというものです。
自己破産のメリットとしては、①借金の返済が免責される②破産手続開始後は強制執行されない③一定の財産を残すことができる、などが挙げられます。デメリットとしては、①ブラックリストに載ってしまう②官報に載ってしまう③免責決定が出るまで士業などの職に就けない、などが挙げられます。
また、自己破産手続きを行う場合でも、借金が免責されないリスクもあります。法律では、「免責不許可事由」というものが定められていて、それに該当してしまうと、免責が認められるかどうかは、裁判官の裁量に委ねられることになります。例えば、ギャンブルや浪費などが「免責不許可事由」に該当します。
借金の時効まとめ
これまで借金と時効について述べてきましたが、忘れてはならないのは、借金は本来返すべきお金であるということです。
時効という制度がある以上、もちろん利用することは可能ですが、それにはリスクもあります。
重要なことは、今後の人生を考えて、自己の借金と向き合い、今ある借金をどうしていくのが自分にとって一番良いのかをしっかりと考えることです。時効という制度は、その一つの選択肢に過ぎないということを忘れてはなりません。