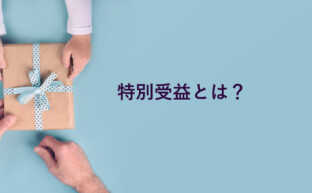遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)されたら、どのように対処すればよいのでしょうか。
遺留分侵害額請求は、民法改正により遺留分減殺請求から変更となりました。
遺言の内容どおりに相続をしたのに、同じ相続人の方から遺留分侵害額請求される可能性があります。
『どうにかして免れたい・・・対策しなければ・・・』
きっとそう思うのではないでしょうか?
遺言にも自分が多く貰えることが書かれており、実際に自分の方が多く貰ってしかるべきだと感じれば、この遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を免れたいとも思いますよね。
そこで今回は、
- 遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされた際にはどのような対応をすべきか
- どうすれば遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を免れることができるのか
について、解説していきます。ご参考になれば幸いです
遺留分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)されたら…拒めるの?
『遺留分』は法律上、一定の相続人に保証されている権利のため、たとえあなたが故人の遺言どおりに財産を多く受け取っていたとしても、相続人から最低保証である遺留分を請求された場合は、その分を相続人に渡す必要があります。
【改正民法1046条1項】
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
仮に、その請求権者が疎遠になっていたとしても、遺留分は相続人の正当な権利になりますので、そのことを理由に拒んだり無視することできません。
ただし、その請求権者の要求が不当なまでに膨大であったりした場合、あるいは請求内容に不動産などの評価が分かれるものが含まれたりする場合には、しかるべき査定を行い、請求を拒むもしくは減額させることはできるかもしれません。
また、遺留分の請求者が、相続人としてふさわしくない人物である場合、そもそも相続できないという可能性もありますので、その内容をしっかりと確認するようにしましょう。
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:民法第891条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:民法第892条
この他にも、相続放棄をした人物に関しても、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の権利はありません。
2、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)への対応方法
それでは、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされた際の対応方法について、ご紹介していきます。
(1)現物返還が原則だった
遺留分侵害額請求と名称変更される前の「遺留分減殺請求」の時は、遺留分減殺請求をした相続人は、その侵害額に対応する財産を取得するとされ、請求をされた場合、当該相続財産現物を返還することが原則でした(改正前民法1036条 現物返還の原則)。
しかし、遺留分侵害をした者が得た財産が、金銭ではなく動産や不動産である場合、これらの額が侵害額を超えていると、金銭で解決(価額弁償)できない場合、いったんそれらを侵害者と被侵害者で共有する、ということをしなければなりませんでした。
(2)遺留分相当額のお金を返還する
この共有状態は実務上非常に不便であり、2019年7月1日からの改正民法では、「侵害額の請求」に改正され、遺留分相当額について金銭の請求ができるようになりました。
つまり、請求された側は動産や不動産を取得した場合でも、金銭で支払わなければならないことになったのです。
(3)もしも内容証明郵便で送られてきたら?
遺留分侵害額請求(旧遺留分滅殺請求)は、口頭でも電話・メールでもできます。
手段に決まりはありません。
それなのに、わざわざ内容証明郵便で送られてくることに『なぜ?』と疑問を感じる方も多いと思いますが、それには意味があります。
それは、
『間違いなく相手に請求の書類が届いていることを証明できる』
ことに加え、
『日付の証明を残すことができること』
です。
というのには、遺留分侵害額請求(旧遺留分滅殺請求)には法律上、下記の二つのことが決められています。
その一つは、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を請求できる期間には制限があることです。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条(前段)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
もう一つは、民法第1048条に続けて記載されている、
第1048条(後段)
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
ということです。
内容証明郵便で送れば、『請求できる期間内に意思表示を行いましたよ』という証明できますよね。
それを証拠として残すために、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を内容証明郵便で送付するのです。
ただし、可能性は低いですが、請求できる期間が過ぎている場合もあるかもしれませんので、念のため日付だけは確認しましょう。
そして、内容証明郵便で遺留分侵害額請求(旧遺留分滅殺請求)された場合、それを拒否することはできません。
もし、無視し続けていたとしても、家庭裁判所に調停を申し立てられるか、地方裁判所で裁判を起こされることになるでしょう。
どちらにしても無視することはできないので、早めに対応をすることが必要となります。
ただし、請求額を鵜呑みにして、急いで支払うべきではありません。
遺留分の計算は複雑です。
まずは、どのように計算をしたのか確認するなど、相手方と協議をするべきです。
こちらも遺留分の計算方法を知っておくべきですので、こちらの記事をご確認ください。
3、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を免れる方法はある?
無視することのできない遺留分侵害額請求(旧遺留分滅殺請求)に対して、免れる方法、減額する方法はいくつかあります。
それについてご紹介しますので、少しでも自分の取り分を多くできるよう、細かく確認してください。
(1)請求できる期間が過ぎていないか確認する
上記にも述べたように、遺留分侵害額請求(旧遺留分滅殺請求)には期間制限があります。
内容証明郵便を含め、請求が届いたら日時を確認しましょう。
万が一、請求できる期間が過ぎているにもかかわらず対応してしまうと、こちらが不利になるケースもありますのでご注意ください。
(2)不動産の評価額を下げる
遺産の中に不動産がある場合は、その不動産の評価額が低くなれば、当然請求者に渡す遺留分は少なくなります。
その土地の評価方法には、以下の3つがあります。
- 固定資産税評価額
各市町村が算定する固定資産税の基準とされる価格のことで、固定資産税を算出する際に使われる価格を言います。
この価格は一般的に、時価よりも低く提示されることが多い(時価の7割が水準)です。
- 路線価
>ある地域の路線や道路に面した土地評価額で、相続税算出時の基準価格になります。
国税庁により毎年7月に、1月1日時点での価格が公表されます。
この価格に関しても一般的に、時価よりも安くなります(>時価の8割程度)。>
- 地価公示価格
地価公示法に基づいて、国土交通省が公示する価格のことです。
その土地の価格を定期的に国が評価し、その都度発表しています。
毎年発表されている評価額のため、時価と大きな差が出ることは少ないですが、土地の価格変動が激しい地域においては、時価と大きな誤差が生じる可能性もあります。
このように、固定資産税評価額や路線価格を示すことで、時価の7~8割に抑えることが可能になり、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の額を少しでも減らすことが期待できます。
(3)特別受益とされる生前贈与を受けていないか確認する
生前贈与とは、生前に被相続人が自分の財産を無償で第三者(主に親族)に渡し、将来被相続人が亡くなったときに相続される財産を減らすことです。
遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の請求者が、この特別受益を受けていた場合、特別受益に相当する額が控除されるなど、遺留分として支払う額を減らすことが可能になります。
また、この生前贈与は、生前に行われたものだけではなく、遺言書によって贈られたものに関しても同様に扱われます。
つまり、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の請求者が特別受益とされる生前贈与を受け取っていた場合、あなたが支払う金額を減額させることができるということです。
(4)その相手は請求する権利があるか確認する
そもそも、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)する権利がある人
- 配偶者
- 子ども
- 直系尊属(祖父母、父母)
のみとなります(兄弟姉妹は対象外)。
ただし、この当てはまる人々すべてにその権利があるとも限りません。
下記を確認しましょう。
①その人の遺留分が侵害されていることが確かか
『自分で考えていたよりももらえる額が少なかった』というだけでは、遺留分を侵害されているとは言えません。
遺留分が侵害されていることが確かな場合のみ、請求する権利が生まれます。
②相続権のある遺留分権利者であること
相続廃除によって相続権を失っている遺留分権利者は、当然ながらその権利を失います。
また、被相続人に子どもがいる場合、その直系尊属(被相続人の父母や祖父母などには遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の権利がなくなります。
つまり、直系尊属がこの権利を行使できるケースは、『被相続人に直系卑属がいない場合』に限られます。
まとめ〜遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)で困ったら弁護士への相談を〜
ここまで述べてきたように、遺留分侵害額請求(旧遺留分滅殺請求)をされたからといって、すべて請求者の請求通りに支払わないといけない、というわけでは決してありません。
もちろん、内容証明郵便などで請求が来たら無視することはできません。
無視していても、先に述べたとおり裁判等にかけられることになりますので、誠実に対応することが賢明です。
ただし、法律などもかかわってくる複雑な内容かつ、人生にとって重要な相続に関することなので、相手方は弁護士をつけていることも考えられます。
したがって、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされた場合、個人で対応することよりも弁護士をつけて対応することをおすすめいたします。
前述の通り、遺留分の計算は複雑ですので、相手方の計算は適切なのか、こちらも弁護士に確認してみるべきです。
そうすることにより、相手方の弁護士との遺留分額の調整も、弁護士同士でスムースに運んでくれることが期待できるでしょう。
『故人の生前には自分のほうが介護した』
『一緒に暮らした』
『世話をした』
など、さまざまな事情はおありでしょう。
請求者に言われるがままではなく、少しでも渡すものを少なくしたいのであれば、一度弁護士に相談してみましょう。全力で対応してくれるはずです。