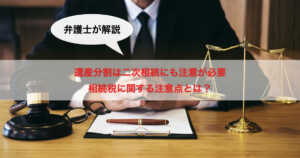
相続人間で遺産分割を行う際には、相続税がどのくらいかかるかがひとつのポイントになります。できるだけ多くの資産を相続するためには、相続税の金額や費用はなるべく負担したくないところです。
特に親が初めて亡くなるケースでは、被相続人である親についての相続だけでなく、健在であるもう片方の親についての二次相続も考慮に入れたうえで、トータルでの相続税の金額を抑えることが重要になります。
この記事では、二次相続を見据えた相続税の考え方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続税の内容に関しては以下の記事に詳しく掲載されておりますので是非ご覧ください。
1、二次相続とは?
トータルで見た相続税の金額を抑えるためには、「二次相続」を見据えた遺産分割をする必要があります。
「二次相続」という言葉が聞き慣れない方もいらっしゃると思いますので、まずは二次相続についての基本的な知識を押さえておきましょう。
(1)両親が順番に亡くなる場合の二番目の相続のこと
「二次相続」は法律上の用語ではありませんが、一般的には、両親が順番に亡くなることを想定した場合に、後から亡くなる親を被相続人とする相続のことを指すことが多いです。
多くの場合、両親は子どもよりも先に亡くなります。
そのため子どもから見ると、自分が生きている間に、先に亡くなる親と後に亡くなる親の2回の相続を順次経験することになります。
このうち、先に発生する相続を「一次相続」、後に発生する相続を「二次相続」と呼ぶことが多いです。
(2)一次相続・二次相続のそれぞれに相続税が課税される
相続税は、人が亡くなるたび(相続が開始するたび)に課されますので、一次相続と二次相続の両方で相続税が課税されます。
遺産分割における相続税対策は、最終的に残される子どもの利益の観点から、できるだけ多くの資産を子どもの世代に引き継げるようにするという考え方を基本としています。
したがって、一次相続と二次相続で課税される相続税の金額を、トータルで低く抑えられる方法による遺産分割をしたいところです。
2、二次相続の相続税は高額になる可能性が高い
一般に、二次相続の段階で課税される相続税は、一次相続における相続税の金額よりも高額になることが多いとされています。
その理由としては、以下の点が挙げられます。
(1)法定相続人の数が減る|基礎控除の減額
相続税には「基礎控除」が設定されており、基礎控除の金額に達するまでの相続財産は非課税となります。
この基礎控除の金額が大きいほど、課税される相続税の金額は軽減されるのですが、基礎控除の金額は法定相続人の人数によって決まることになっています。
<基礎控除の計算式>
基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
一次相続では、被相続人の配偶者である親が健在です。
これに対して二次相続の場合には、両親がどちらも亡くなっています。
したがって、一次相続の場合に比べると、二次相続では少なくとも1人、法定相続人の数が減ることになります。
また、一次相続と二次相続の間に、他にも亡くなった推定相続人がいる場合には、さらに法定相続人の数が減ってしまいます。
つまり、二次相続では一次相続よりも基礎控除の金額が減ってしまうため、必然的により高額の相続税が課税されることになるのです。
(2)配偶者の税額軽減が使えない
一次相続の段階では、両親のうち片方は健在ですから、残された方の親は引き続き生活を営んでいく必要があります。
相続税を原因として、残された方の親の生活環境が激変してしまうとしたら酷な話です。
このような事態を防ぐため、相続税の課税については「配偶者の税額軽減」が設けられています。
配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が相続する財産のうち、以下の金額のいずれか多い金額に達するまでの分については、相続税が課税されないという特例です。
<配偶者の税額軽減の金額(以下の2つのうちいずれか多い金額)>
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
一次相続の段階では、配偶者の税額軽減を活用することによって、全体での相続税額を抑えることができます。
しかし、二次相続の段階では、被相続人となる親の配偶者もすでに亡くなっていますので、配偶者の税額軽減を利用することができません。
そのため、配偶者の税額軽減を利用できた一次相続の段階よりも、二次相続について課税される相続税は高額になってしまうのです。
(3)相続する子どもが親と別居していた場合は、自宅の土地について小規模宅地等の特例が使えない可能性が高くなる
被相続人が所有している自宅において、配偶者や親族が居住している場合には、自宅の土地・建物を処分することは難しいケースが多いでしょう。
それにもかかわらず、自宅について相続税が満額課税されてしまうと、相続人が納税資金を用意することは困難になってしまいます。
そこで設けられたのが「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例が適用される代表的な相続財産には、
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地等
- 被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等
があります。
小規模宅地等の特例が適用されるこれらの資産については、330㎡を限度として、相続税の金額が80%減額されます。
上記の宅地等について、被相続人の配偶者が相続するケースであれば、無条件で小規模宅地等の特例を利用することができます。
そのため、一次相続において配偶者が自宅の土地を相続するケースでは、小規模宅地等の特例を利用可能です。
これに対して、被相続人の配偶者ではない同居親族が当該宅地等を相続するケースでは、原則として、
- 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続き建物に居住していること
- その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
の2つの要件を満たす必要があります。
また、被相続人と同居していない親族が取得する場合には、
- 被相続人に配偶者も同居の親族もいない
- 3年以内に自己所有の家に住んだことがない
- 3年以内に3親等以内の親族の家に住んでいない
- 3年以内に特別な関係の法人が持つ家に住んでいない
- 相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがない
- その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している
の要件を満たす必要があります。
つまり、被相続人の死亡前から当該宅地等に住んでいる相続人がいない場合には、被相続人の自宅の土地について小規模宅地等の特例を利用することができない可能性が高くなります。
小規模宅地等の特例を利用できない場合には、被相続人の自宅の敷地について相続税の減額が行われないため、一次相続よりも相続税が高額になることがあります。
3、相続税は一次相続・二次相続トータルで考えるべき
遺産分割時の相続税対策に関しては、一次相続の段階から、二次相続を見据えた相続税のシミュレーションを行い、トータルでの相続税額を抑えられるような方法を検討すべきです。
(1)子どもに、より多くの財産を残せるようにしたい
相続においては、やはり子どもに対してより多くの財産を残すという観点が重要です。
もちろん、一次相続の段階では、残される配偶者の生活を保障することも大切であることは言うまでもありません。
しかし、後の世代に財産を引き継げば、資産の活用可能性も広がりますし、より多くの家族・親族の利益にも繋がります。
そのためには、一次相続の段階から、二次相続までのトータルでの相続税額を考えた対策を検討しておくのが良いでしょう。
(2)一次相続・二次相続の相続税シミュレーション
実際のケーススタディを用いて、一次相続・二次相続のトータルでの相続税額を計算してみましょう。
<事例>
- 一次相続の相続人は配偶者A、子B・C
- 一次相続の課税対象となる財産(課税価格の合計額)は1億円
- 二次相続では、子B・Cが半分ずつ財産を相続
- 一次相続から二次相続までの間に、Aが相続した財産は消費されない(評価もそのまま)
- 基礎控除と配偶者の税額軽減以外の控除や特例は利用しない
上記の事例の一次相続において
①配偶者がすべての相続財産を相続する場合
②法定相続分どおりに配偶者が2分の1、子が4分の1ずつ相続する場合
の2パターンに分けて、二次相続までのトータルでの相続税額を計算してみます。
<パターン①:配偶者が100%相続>
◎一次相続
一次相続における相続分はAが1億円、BとCが0円です。
(a)課税遺産総額の計算
相続税の金額を計算する際には、まず課税価格の合計額から基礎控除の金額を差し引き、課税遺産総額を求めます。
課税遺産総額
=1億円-(3000万円+600万円×3)
=5200万円
(b)各法定相続人の仮の取得金額の計算
次に、課税遺産総額が法定相続分どおりに相続されたものと仮定して、各法定相続人の取得金額を計算します。
Aの取得金額:2600万円
Bの取得金額:1300万円
Cの取得金額:1300万円
(c)相続税の総額の計算
各取得金額について、相続税の税率表にしたがった税率と控除額を適用して、それぞれの相続税額を求め、それらをすべて合計して相続税の総額を求めます。
参考:「相続税の税率」(国税庁)
相続税の総額
=(2600万円×15%-50万円)+(1300万円×15%-50万円)+(1300万円×15%-50万円)=630万円
(d)各法定相続人の相続税額の計算
パターン①では、配偶者であるAがすべての財産を相続するため、(c)で求めた相続税は全額Aに課税されます。
ただし、Aが相続する課税遺産総額(基礎控除後)は5200万円ですので、全額配偶者の税額軽減の対象となります。
したがって、一次相続で課税される相続税は0円です。
◎二次相続
一次相続で相続税が課税されなかったため、一次相続の1億円がそのまま二次相続でも相続の対象となります。
一次相続の場合と同様の手順で、B・Cに対する相続税の課税額を調べてみましょう。
(a)課税遺産総額の計算
課税遺産総額
=1億円-(3000万円+600万円×2)
=5800万円
(b)各法定相続人の仮の取得金額の計算
Bの取得金額:2900万円
Cの取得金額:2900万円
(c)相続税の総額の計算
相続税の総額
=(2900万円×15%-50万円)+(2900万円×15%-50万円)
=770万円
(d)各法定相続人の相続税額の計算
BとCで半分ずつ財産を相続するため、相続税も上記の総額が半分ずつBとCに課税されます。
したがって、B・Cに課税される相続税額は各385万円です。
◎一次相続・二次相続トータルの相続税額
パターン①では一次相続で0円、二次相続で770万円の相続税が課税されました。
したがって、一次相続・二次相続トータルの相続税額は770万円です。
<パターン②:配偶者が50%、子が25%ずつ相続>
◎一次相続
一次相続における相続分はAが5000万円、BとCが2500万円ずつです。
(a)課税遺産総額の計算
(b)各法定相続人の仮の取得金額の計算
(c)相続税の総額の計算
(a)から(c)までは、パターン①と同じです。
したがって相続税の総額は630万円となります。
(d)各法定相続人の相続税額の計算
パターン②では、配偶者であるAが50%、子であるBとCが25%ずつの財産を相続するため、相続税もこの割合に従って按分されます。
ただし、Aが相続する課税遺産総額(基礎控除後)については、全額配偶者の税額軽減の対象になるため、Aに課税される相続税は0円です。
したがって、一次相続で課税される各相続人に課税される相続税は次のとおりとなります。
A:0円
B:145万円
C:145万円
計:290万円
◎二次相続
一次相続でAが相続した遺産は5000万円、Aに課税された相続税は0円なので、二次相続ではAのもとに残っている5000万円が相続の対象となります。
この前提で、B・Cに対する相続税の課税額を計算してみましょう。
(a)課税遺産総額の計算
課税遺産総額
=5000万円-(3000万円+600万円×2)
=800万円
(b)各法定相続人の仮の取得金額の計算
Bの取得金額:400万円
Cの取得金額:400万円
(c)相続税の総額の計算
相続税の総額
=400万円×10%+400万円×10%
=80万円
(d)各法定相続人の相続税額の計算
パターン①と同様、BとCで半分ずつ財産を相続するため、相続税の課税も半分ずつです。
したがって、B・Cに課税される相続税額は各40万円です。
◎一次相続・二次相続トータルの相続税額
パターン②では一次相続で290万円、二次相続で80万円の相続税が課税されました。
したがって、一次相続・二次相続トータルの相続税額は370万円です。
以上より、一次相続で配偶者が100%財産を相続したパターン①よりも、法定相続分どおり(配偶者50%、子25%ずつ)相続したパターン②の方が、トータルの相続税額が安くなりました。
4、二次相続に備えた対策の具体例とは?
一次相続の段階から二次相続までを見据えた相続税対策を考える際、具体的に考えられる方法の具体例を紹介します。
(1)一次相続の段階である程度子どもに財産を移しておく
計算例のパターン①とパターン②の比較からもわかるように、一次相続の段階である程度子どもに財産を移しておく方が、トータルでの相続税額は安く抑えられる傾向にあります。
「一次相続で配偶者の税額軽減できるだけ多く使った方が良いのではないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、現実のシミュレーションでは逆の結果になることが多いです。
詳細なシミュレーションについては、ベリーベストグループに所属する税理士にご相談ください。
(2)一次相続後、二次相続前に暦年贈与を活用して子どもに財産を移す
一次相続から二次相続の間に、「暦年贈与」という方法で、毎年少しずつ資産を子どもに移すことも有効です。
暦年贈与とは、毎年110万円の贈与税の非課税枠を利用して、無税で少しずつ子どもに財産を移す方法です。
ただし、暦年贈与をする際には、後に相続税の税務調査などで「定期贈与」(一括贈与と同様に贈与税が課税される)として贈与税が課税されないように注意する必要があります。
暦年贈与の活用を検討する際にも、ベリーベストグループに所属する税理士にご相談いただければ安心です。
(3)配偶者が相続した現預金を他の資産に転換して評価額を下げる
不動産を相続する際の相続税は、原則として不動産の路線価や固定資産税評価額に基づいて課税されます。
不動産の路線価や固定資産税評価額は、一般的に購入価格や市場価格よりも低くなる物件もあります。
そのため、一次相続で配偶者が相続した現預金で不動産を購入しておくと、相続税対策になる場合があります。
ただし、不動産は大きな買い物ですので、事前にベリーベストグループの税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。
まとめ
子どもに財産を多く残すという観点からは、一次相続の段階から、二次相続を見据えた相続税対策を行うことが重要です。
ベリーベストグループには、相続に関する経験が豊富な弁護士・税理士が多数所属しています。
二次相続を見据えた相続税対策をご希望の方は、ぜひベリーベストグループにご相談ください。








