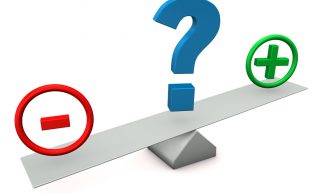苦労して働いて手に入れたマイホームや、これまで築き上げてきた事業を、同居の子供に継いでほしいと考える方は多いでしょう。
しかし、同時にその場合にかかる「相続税」について心配になる方も多いのではないでしょうか。
できるだけ多くの財産を家族に残したいとお考えの方にとって、相続税の「小規模宅地の特例」は重要なポイントになります。
そこで今回は、
- 小規模宅地の特例とは
- 小規模宅地の特例を適用できる条件
- 相続税は、小規模宅地の特例を適用することでどのくらい安くなるか
について、相続に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
非課税となる贈与税の仕組みについては以下の関連記事をご覧ください。
不動産の相続税について、税理士法人ベリーベストの公式YouTubeチャンネルにて動画にまとめております。ぜひあわせてご確認ください!
Youtube 【不動産の相続税】相続税を決定する3つのポイントを徹底解説!
目次
1、小規模宅地の特例とは?

「小規模宅地の特例」とは、相続税の特例の中でも最も重要な特例と言ってよいでしょう。この特例を活用するかしないかで相続税の額が数千万単位で異なることもあります。
小規模宅地の特例を適用すると、亡くなった人(被相続人)が住んでいた自宅を同居の親族が相続する場合、一定の要件を満たせば土地の評価額を80%減額して相続税を計算することができます。
この特例は、平成30年改正で要件が厳格化されました。小規模宅地の特例をご存じの方も、もう一度要件を確認しておきましょう。
(1)制度背景
被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地というのは、それを相続した人のその後の生活基盤となる重要な財産です。
その財産に高額な相続税がかかると、土地を手放さざるを得なくなるかもしれません。そのため、自宅や事業を継いだ親族の生活を守るために、軽減措置が設けられています。
(2)小規模宅地の特例が適用される土地
まずは、対象になる土地が次の2つの条件を満たしている必要があります。
- 被相続人・被相続人と生計を共にする親族が、住んでいた、または、事業に使っていた土地であること
- 建物等の敷地であること
小規模宅地の特例が適用できる土地は、用途によって次の3種類があります。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
小規模宅地の特例が適用される面積の上限と減額割合が以下のとおり定められています。
土地名称 | 特定居住用宅地等 | 特定事業用宅地等 | 貸付事業用宅地等(*1) |
限度面積 | 330㎡ | 400㎡ | 200~400㎡ |
減額割合 | 80% | 80% | 50~80% |
(*1)貸付事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で異なります。
なお、複数の種類の宅地がある場合には特例を併用することもできます。
ただし、その中に貸付事業用宅地等が含まれる場合は適用できる面積は制限され、「特定居住用宅地等の面積×200/330」「特定事業用宅地等の面積×200/400」「貸付用事業用宅地」の合計が200㎡以下でなければいけません。
2、小規模宅地の特例を適用するための条件について

ここでは、小規模宅地の特例を適用する条件について、宅地の種類ごとに見ていきましょう。
(1)特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人等が居住していた家屋の敷地のことです。
次の①~③の親族が相続する(または遺贈を受ける)ことが条件になり、さらにそれぞれ条件があります。
①配偶者
配偶者は、特定居住用宅地等を相続または遺贈で取得すれば、特例を適用できます。
つまり、いったん取得すれば、相続税の申告までに売ってしまったとしても特例を適用できます。
②同居している親族
同居している親族が特定居住用宅地等を取得した場合、相続税の申告期限まで引き続きその家屋を所有し、かつ居住していなければいけません。
③「家なき子」親族
以下の条件すべてに該当するいわゆる「家なき子」と呼ばれる親族が特定居住用宅地等を取得した場合は、相続税の申告期限まで引き続き所有している場合にも、特例を適用できます。
この「家なき子」の条件は、平成30年度に改正されました。改正後の条件は以下の4つです。
- 被相続人に配偶者や同居の親族がいない
- 宅地を相続した親族は、被相続人死亡の3年前から、自己・自己の配偶者・3親等以内の親族・特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがない
- 被相続人が亡くなった時に居住していた家屋を所有したことがない
- 相続税の申告期限まで所有している
ただし、平成30年3月31日の時点で以下の改正前の「家なき子」の条件を満たしていれば、令和2年3月31年までに発生した相続に限り特例が認められます。
- 被相続人に配偶者や同居の親族がいない
- 宅地を相続した親族は、被相続人死亡の3年前から、自己または自己の配偶者が所有する家屋に住んだことがない
- 相続税の申告期限まで所有している
(2)特定事業用宅地等
特定事業用宅地とは、亡くなる直前に被相続人等の事業に使われていた宅地のことです。
ただし、亡くなる前3年以内に新たに事業に使われるようになった宅地で一定の規模以下のものを除きます。
例えば、被相続人が事業に使っていた宅地の場合は、相続税の申告期限までにその事業を引き継ぎ、かつ、申告期限までその事業を営んでいることが特例を適用できる条件となります。
(3)貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等には、被相続人が貸付事業に使っていた宅地の場合と、一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業に使われていた宅地の場合などがあり、それぞれ特例が適用される条件はことなります。
例えば、一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業に使われていた宅地の場合、宅地を相続した親族が、相続税の申告期限のときにその法人の役員であることと、相続税の申告期限まで所有していることが特例を適用できる条件となります。
3、小規模宅地の特例を適用するための書類について

小規模宅地の特例を適用するためには、相続税の申告をしなければいけません。
ここでは相続税の申告書類と添付書類について詳しく解説します
(1)必要な添付書類
小規模宅地の特例の適用を受ける場合、次の添付書類が必要になります。
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の住民票
- 戸籍謄本(被相続人が亡くなってから10日以上経った後に取得したもの)
- 遺言書または遺産分割書のコピー
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続する不動産の登記事項証明書
- 賃貸借契約書等(別居の親族が特例の適用を受ける場合)
この他、被相続人が死亡時に老人ホーム等の施設に入所していた場合には、要介護認定証や入所時の契約書のコピーなどを提出する場合もあります。
また、申告期限までに遺産分割ができなかった場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することもあります。
(2)必要な申告書類
相続税の申告書類には多くの種類があります。
小規模宅地の特例の適用を受ける場合には以下の申告書類に必要事項を記入して提出します。
- 第11表 相続税がかかる財産の明細書
- 第11の2表の付表1~4 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
4、小規模宅地の特例の申請期限について
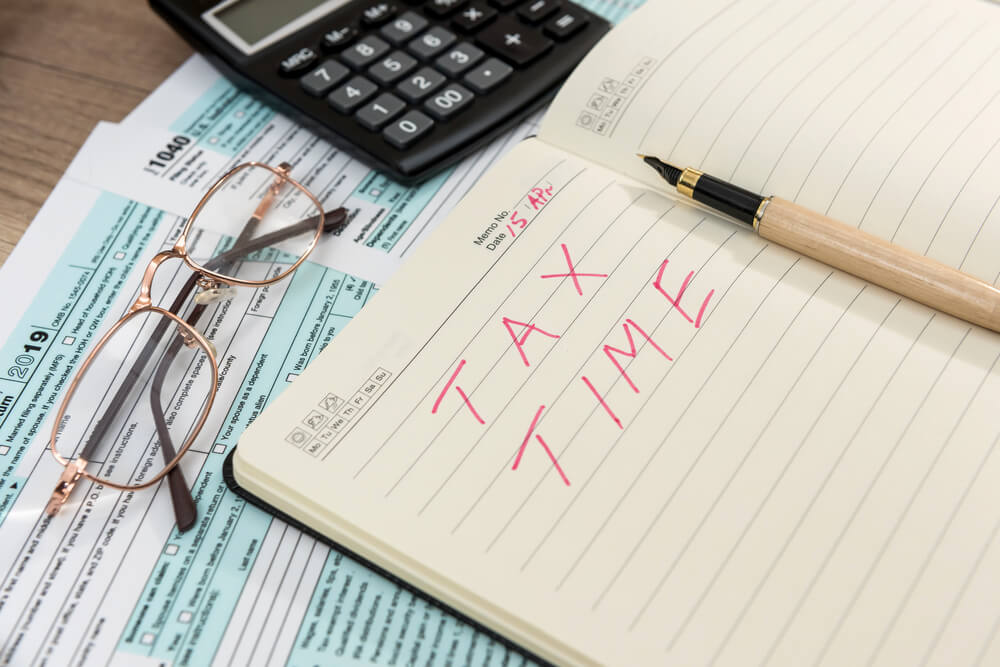
小規模宅地の特例を適用するには、原則として被相続人の死亡から10ヶ月以内に相続税を申告する必要があります。
この10ヶ月の間に、遺産分割をすませ、申告書類を作成し、添付書類を集めなければなりません。
(1)特例適用後の税額が0円になるときも申告は必要
小規模宅地の特例を適用すると相続税が0円になる場合であっても、申告しなければ特例を適用したことにはならないことに注意が必要です。
0円だから申告も不要と誤解し申告しなかった場合は、申告期限後であってもすみやかに申告することで小規模宅地の特例は適用できます。
(2)申告が遅れても特例を適用することができる
申告が遅れてしまった場合でも、期限後に申告することで小規模宅地の特例を適用できます。
ただし、この場合は無申告加算税や延滞税が相続税に上乗せされてしまうので、注意が必要です。
(3)申告期限から3年以内に遺産分割できないと特例を適用できないことも
相続税の申告期限までに遺産分割ができなかった場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後日遺産分割ができたときに小規模宅地の特例を適用できます。
ただし、この場合は法定相続分で遺産を分けたものとして仮の申告をすることになります。
このときには小規模宅地の特例は適用できないので、特例を適用しない税額を納める必要があります。
遺産分割した日の翌日から4ヶ月以内に申告をやり直すことで、払いすぎた税額を返してもらえます。
申告期限から3年が過ぎても遺産分割ができないと、特例が適用できない場合もあります。
早めに弁護士に相談して、スムーズに遺産分割することをおすすめします。
なお、やむを得ない事情がある場合には、3年を超えて期限を延長することも可能です。
5、【ケーススタディ】小規模宅地の特例あるなしでは相続税はどう変わる?

ここでは、具体的なケースをあげて、小規模宅地の特例を使うとどのくらい相続税が変わるのかについてご説明します。
(1)相続税評価額は自宅か貸家で変わる!
宅地が相続財産としてどう評価されるかが、相続税の額を決める上での大きなポイントになります。
土地の上にアパートなどの貸家がある場合は、評価額は自宅がある場合よりも減額されます。
相続税対策としてアパートを建てることを勧められることが多いのはこのためです。
相続税評価額は、固定資産税評価額から計算できます。
固定資産税評価額は、毎年役所から送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。
また、土地のある地域の役所で固定資産評価証明書を取得することもできます。
固定資産税評価額は地価公示価格の約7割程度、相続税評価額は地価公示価格の約8割程度です。
そこで、相続税評価額は次の式で計算できます。
相続税評価額 = 固定資産税評価額 ÷ 0.7 × 0.8
自宅(自用地)の場合は、この計算式で相続税評価額の目安がわかります。
貸家(貸家建付地)の場合には、次の式で計算します。
相続税評価額 = 自用地としての評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
借地権割合とは、土地のあるエリアごとに指定されている30%~90%の数値です。
国税庁のホームページにある路線価図・評価倍率表で調べることができます。
借家権割合とは、貸家のとき減額される割合で、一律30%と定められています。
賃貸割合とは、課税時点での入居率のことです。
このように、アパート等の貸家の場合には、自宅の場合よりも評価額が大きく減額されます。
(2)100坪の土地で自宅がある場合
ここでは、わかりやすくするために330㎡(約100坪)の土地の上に自宅があるケースについて計算してみましょう。
【東京都内に自宅を所有していた場合】
面積:330㎡
地価公示:432,000円/㎡(東京都全域 住宅地の平均価格)
土地の上に被相続人名義の自宅があり、被相続人が居住していた
参考:東京都財務局「令和3年地価公示 区市町村別用途別平均価格表」
①小規模宅地の特例を適用できた場合
特例を適用しない場合の相続税評価額は公示価格の約8割となり、次のとおりです。
相続税評価額 = (43.2万円×330㎡)×0.8 = 約1億1405万円
小規模宅地の特例を適用できると、330㎡まで評価額が80%減額されるため、特例適用後の評価額は次のとおりです。
特例適用後の相続税評価額 = 1億1405万円×(1-0.8) = 2281万円
②小規模宅地の特例を適用できなかった場合と差を計算してみた
①の計算から、小規模宅地の特例を適用できなかった場合の評価額と比べると、
1億1405万円 - 2281万円 = 9124万円
9124万円も評価額が違うことがわかります。
実際の相続税の計算には、他の特例や控除、配偶者の税額軽減などで計算が複雑になるので、最終的な相続税額の違いを比較することは困難です。
仮に相続税の税率を30%とすると(参考:国税庁 相続税の税率)、評価額の9000万円の違いは、相続税に2700万円も差が出る可能性があるということがわかります。
6、小規模宅地の特例を受けるための最も良い方法とは

小規模宅地の特例を最も有効に活用するには、次の2点に注意しましょう。
- 特例を適用できるように、遺産分割時に誰がどの土地を相続し、事業を承継するかを決めておく
- 被相続人の自宅以外に事業等で使っていた土地がある場合は、それぞれの土地の評価額や軽減割合を考慮して最も節税効果の高い方法で特例を併用する
とはいえ、これらの点に注意するには、小規模宅地の特例について詳しく知っていなければいけません。
これを知らずに遺産分割すると、相続税が高くなってしまう可能性もあります。
最良の方法で小規模宅地の特例を適用するためには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
また、相続税申告の手続きは上述のとおり必要な書類も多く、とても複雑な手続きです。
遺産分割協議書の作成から相続税の申告までを専門家に任せた方が安心です。
専門家である税理士に相続税の申告を依頼するときにかかる費用は遺産総額により異なります。
例えば、上記のケーススタディで土地とその他の相続財産の総額が2億円あった場合、基本料金は88万円(税込)となります(参考:税理士法人ベリーベスト|料金表)。
上で計算したとおり、小規模宅地の特例を適用することで相続財産の評価額が9000万円以上も違うのであれば、専門家に頼んで最もよい方法で特例を適用して申告してもらうメリットは大きいでしょう。
まとめ
小規模宅地の特例を適用することで、土地の相続税評価額を80%減額することができ、相続税の負担を大幅に減らすことができます。
特例を有効に適用するには、条件を満たすように遺産分割し、適切に特例を適用して相続税を申告する必要があります。
小規模宅地の特例を適用するかどうかで、場合によっては数千万円単位で相続税が異なる場合もあります。
どのように特例を適用するのが最良の方法であるかはケースにより異なりますので、相続の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。