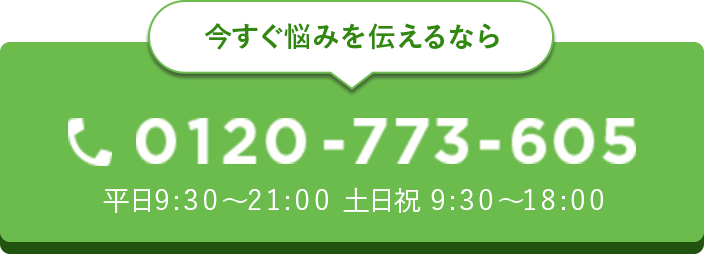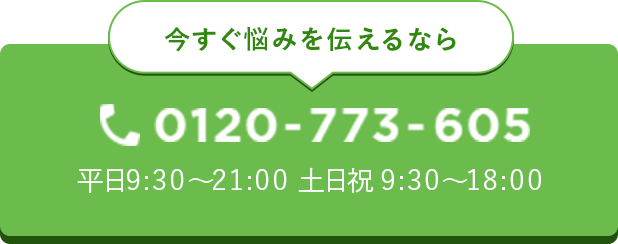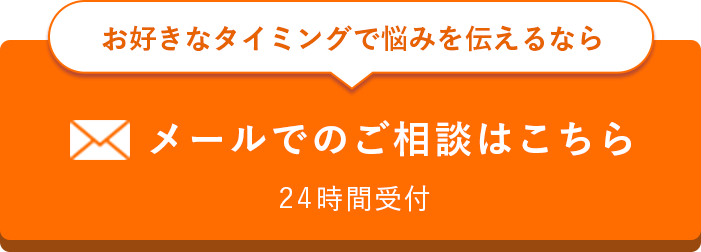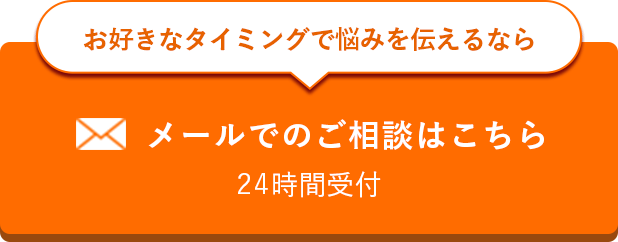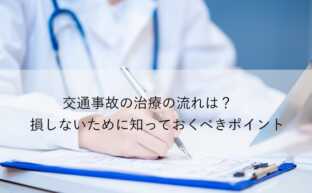むちうちは追突事故でもなり得る症状です。
交通事故の法律相談を受けていると、信号待ち中の追突事故等によってむちうち症になってしまったという方が非常に多くいらっしゃいますが、むちうち症がどういうものなのかを正確に知っている方はあまりいらっしゃらないのではないかという印象があります。どのような治療をするのがよいのか迷っている方、なかなか痛みが治まらず心配している方、保険会社との対応の仕方に戸惑っている方も多いと思われます。
ここでは、知っているようでよく知らない追突事故でのむちうち症についてご説明します。今後の治療等のご参考にしていただければ幸いです。
むちうちのリハビリでの慰謝料請求で損しない知識に関しては以下の関連記事もご覧ください。
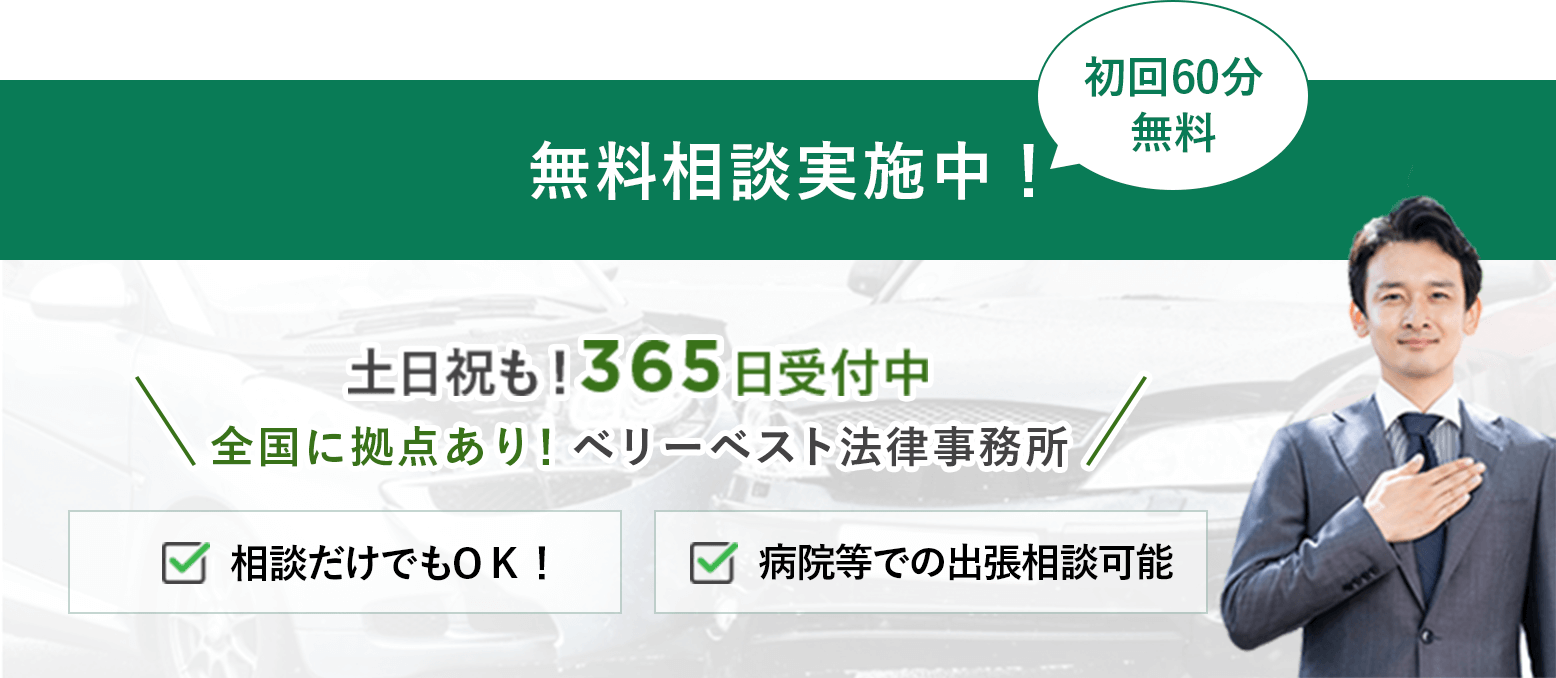

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、むちうちは追突事故でも…むちうちとは
まず、「むちうち症」というのは、正式な病名ではありません。むちうち症とは、「自動車の追突事故などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状」を総称したものといえます。
そのため診断書等では、外傷性頚部症候群・外傷性頭部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷等、様々な診断名が付けられています。
病院の診断書に上記のような病名が記載されていたら、いわゆる「むちうち症」であると考えてよいでしょう。
2、むちうちのパターンと症状
むちうち症は、以下の5パターンに分類することができます。
(1)頚椎捻挫型
むち打ち損傷の中でも最も多く、全体の70〜80%を占めているといわれています。
【主な症状】
- 首の周りにある筋肉や胸・背中の筋肉の緊張
- にぶい痛みや首、肩のこり
- 首を動かすと痛む(運動痛)又は押されると痛む(圧痛)
- 腕や手・指がだるい又はしびれたり力が入りにくい(上肢感覚異常、脱力感)
- 頭痛、めまい、吐き気
(2)バレーリュー症候群
衝撃によって首を損傷した際に、首の交感神経(興奮する時の神経)が刺激を受けたことによって何らかの症状を引き起こしたり、脊髄に血液を送り込むのに重要な首の横にある椎骨動脈やそこから頭部へと続いている脳底動脈に障害が起こって、症状が出現する状態です。
【主な症状】
- 頭痛(代表的な症状)
- めまい、耳鳴り、目のかすみ、視力低下
- 後頭部の痛み、首や肩の痛みやこり
- 左右どちらかの顔の痛み
- 疲れやすい
(3)神経根型
椎間孔(上下の椎骨の下椎切痕と上椎切痕の間にできる孔)の内外における神経根の圧迫によって症状が起きる状態です。
【主な症状】
- 頭から手・指までの感覚異常、痛みやしびれ
- 咳やくしゃみ、首を後ろに反ったり左右に捻じったりすると症状が強くなる
- 後頭部のモヤモヤ
(4)脊髄型
首の脱臼骨折を合併している場合や、元々首に自痛を持っている方(頚椎症や後髄靭帯骨化症)は脊髄を痛めることがあります。
【主な症状】
- 腕や手、指先のしびれ
- 足のしびれ、歩行障害
- 排尿、排便しにくいといった膀胱直腸障害
- ごく軽い下肢の知覚障害や腱反射の亢進
(5)脳脊髄液減少型
脳脊髄液という髄液が脈絡叢というところで作られているのですが、衝撃によってそれを覆っている、くも膜という膜に傷が付き、そこから少しずつ漏れてしまう状態です。むちうち症が何年も続いて治らない方はこの脳脊髄液の漏れが原因という可能性があるとも言われています。
【主な症状】
- 立っていたり座っていたりすると起こる頭痛(横になると楽になる事がある)
- 頭から手足まで出てくる様々な痛み
- 疲れやすい、睡眠不足、常にダルい
- 天候に左右される頭痛やめまい、耳鳴り
- 自律神経症状
- 集中力や思考力
- 女性では、月経困難など
この他にも様々な症状などが出現します。
3、むちうちの治療方法
むちうちの治療は、病院の整形外科で受けることとなります。整骨院への通院も出来ますが、整骨院の先生(柔道整復師)は、医学的判断・医療行為ができませんので、整骨院をメインに通院する場合であっても、少なくとも週1回は病院に通院することが大切です。
むちうち症の具体的な治療方法としては、頚椎牽引・温熱療法・電気治療等の物理的刺激を体外から与えて行う物理療法、可動域訓練・筋力強化等の身体を動かす運動療法、鎮痛剤・消炎鎮痛剤を服用する薬物療法等があります。
むちうち症が数か月以上継続している場合は、疼痛緩和を専門に行っているペインクリニックへ行き、星状神経節ブロック注射等(ブロック療法)の治療方法もあります。
なお、鍼灸や整体等は、医師の指示があるような場合は別として、むちうちの治療として認められない(治療費が支払われない)ので、注意が必要です。
4、むちうちが治癒するまでの期間は?
むちうち症の治療期間としては、約3~6か月間が目安となります。多くの場合は、これくらいの治療期間で、痛み等が完全になくなるか、または気にならない程度に緩和されます。
では、6か月間を過ぎても痛み等が治まらない場合は、どうなるのでしょうか。痛み等が続く限り治療を継続して、相手方には治療費を支払って欲しいところですが、残念ながらずっと治療費の支払を受けることは出来ません。
6か月以上痛み等が続く場合は、一般的に、現在の医療ではこれ以上症状を改善することのできない状態になったと考えられています。この状態を「症状固定」といいます。治療は症状を改善するためのものですから、症状固定となった場合は、以後の通院は治療とは認められず、その費用を相手方に請求することもできなくなるのです。
なお、症状固定となった場合であっても、通院を継続することには問題ありません。相手方に治療費の請求はできませんが、健康保険等に切り替えて通院することには問題ありません。
5、追突事故でむちうちとなった場合の保険会社とのやり取り
追突事故に遭った場合の保険会社とのやりとりは以下のとおりとなります。
(1)加害者が任意保険会社に連絡
加害者が任意保険会社に加入していて保険を使う場合、加害者が保険会社に連絡すれば、保険会社の担当者から被害者に連絡が来ます。
(2)治療費等の対応
交通事故で怪我を負って通院する場合、通常、保険会社に病院を伝えれば、保険会社が治療費の対応をします。このように任意保険会社が自賠責への請求分を含めて対応することは「一括対応」と呼ばれます。
また、通院交通費や休業損害等についても請求する場合には、必要書類を揃えて保険会社に提出することになります。
追突事故でむちうちとなった場合には、事故の程度や個体差にもよりますが、上述のとおり、多くは3~6か月程度で治癒又は症状固定となり、以降の治療と交通事故との因果関係が認められなくなるため、そのタイミングで治療費の支払いが打ち切りとなります。通院交通費や休業損害が補償されるのも、その時までとなります。
しかし、場合によっては、保険会社が症状固定の段階に至る前に一括対応を打ち切ることがあります。その場合には、健康保険等に切り替えて通院を継続し、立替えた治療費を請求する必要があります。また、その前提として、保険会社から治療の必要性の立証を求められることがありますので、そのときは主治医に協力してもらうなどして、症状固定時期や治療の必要性について立証していく必要があります。
(3)後遺障害等級認定の請求
治療を長く続けても症状が残ってしまう場合、症状固定となり、後遺障害の等級認定の請求をすることもあります。
請求方法には、保険会社に任せる方法(事前認定)と被害者自身で請求する方法(被害者請求)があります。
(4)損害額の算定
怪我が治ったり、症状固定となり後遺障害等級認定の結果が出たりすると、ようやく総損害額の算定ができる状態となります。
被害者側は、休業損害証明書や各種領収書など請求に必要な書類を保険会社に提出します。保険会社は、自社の基準で賠償額を計算し、それを被害者に提示してきます。
(5)賠償額の合意
保険会社の提示額に納得できなければ、保険会社と示談交渉をすることになります。場合によっては、ADRの利用や弁護士への依頼なども検討することになるでしょう。
(6)保険金の支払い
最終的に賠償額の合意にいたれば、保険会社から賠償金の支払いがなされます。
6、むちうちになってしまった場合に後遺障害の認定を受ける方法
6か月程度治療を続けてもむちうち症が治らなかった場合、後遺障害認定を受けられる場合があります。ここでは、被害者請求による、むちうち症の後遺障害認定の手続の流れについてご説明します。
(1)後遺障害診断書の作成
まずは、後遺障害診断書を作成してもらわなければなりません。
症状固定の時期に、主治医に、後遺障害診断書の作成を依頼して作成してもらいます。神経学的所見やレントゲン・MRI等画像上の異常所見がある場合には後遺障害診断書に記載してもらうべきでしょう。
(2)必要書類の提出
次に、後遺障害等級認定の申請に必要な書類を収集し、加害者の加入する自賠責保険会社に対し、以下の必要書類を提出します。
- 自動車損害賠償責任保険 支払請求書兼支払指図書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書及び診療報酬明細書
- 印鑑証明書
- 後遺障害診断書
(3)自賠責保険会社から損害保険率算出機構の自賠責調査事務所への請求書類の送付
上記必要書類を受け取った加害者側の自賠責保険会社は、請求書類に不備がないかをチェックした上で、損害保険率算出機構の自賠責調査事務所に書類を送付します。
(4)自賠責損害調査事務所での請求内容の調査
自賠責損害調査事務所が、以下の内容を調査します。
- 自賠責保険の支払対象となる事故か
- どのような後遺障害が残っているか
- 残っている障害と事故との因果関係があるかどうか
(5)自賠責調査事務所の調査結果報告
自賠責調査事務所が、加害者側の自賠責保険会社に対して、調査結果を報告します。
(6)後遺障害の認定
自賠責調査事務所の調査結果を踏まえて、加害者側の自賠責保険会社が被害者に残存した症状について後遺障害等級の認定を行います。
7、治療が打ち切られたらどうすればいい?
(1)治療費の打ち切りとは?
交通事故のご相談の中でも「「保険会社から治療費を打ち切る」と言われてしまった」といういわゆる治療費の打ち切りに関するご相談は少なくありません。
治療費を打ち切るというのは、それまで加害者側保険会社が被害者の通院する病院に対して直接治療費を支払っていたもの(一括対応)をやめるということです。そのため、保険会社が治療費を打ち切ると、被害者は通院する際に病院で治療費を支払わなければならなくなります。
このように聞くと、本来保険会社が支払うべき治療費を支払わないなんてけしからん!と思われる方もいらっしゃると思いますが、治療費を支払わないという保険会社の不誠実な態度はさておき、実は保険会社の打ち切りによって被害者の治療費の請求権が消滅するわけではありません。
本来交通事故による賠償請求は、交通事故によって生じた「損害」を請求するものであって、治療費については基本的には被害者が治療費を病院に対して支払った時点(あるいは受診して治療費が発生した時点)で「損害」となります。そして、治療費の請求権を有しているのは被害者であって、病院ではありません。
したがって、治療費を打ち切られた=これ以上治療費の請求ができないということではないのです。
また、治療費の打ち切りは、あくまで治療費の打ち切りなのであって、直ちに治療をやめなければならないということではありません。多くの場合では、健康保険に切り替えて、通院を継続していただくことになるかと思います。
(2)交通事故後の治療費を請求することができなくなる事由
上述のとおり、加害者側の保険会社からの治療費の打ち切りは、それによってその後の治療費を請求することができなくなるということではなく、被害者が加害者側に治療費を請求することができなくなるのは、以下の2つの場合です。
①完治(治ゆ)
症状が改善し、もはや治療を継続する必要がなくなった場合です。治療を継続する必要がありませんので、完治(治ゆ)した後に、仮に病院で受診してもその治療費は加害者側に請求することはできません。
②症状固定
治療を継続しても症状が改善しなくなる状態を、「症状固定」といいます。交通事故でいつ症状固定となるかについては、けがの程度によってケースバイケースであり、実際に治療をしている主治医の判断が重要視されることではありますが、例えば、交通事故によって発症することが多いむちうち症の場合には、事故から6ヶ月というのが一つの目安と考えられます。
症状固定となると、もはやその症状はこれ以上治療を継続しても改善がみられない状況にあるので、治療行為と当該交通事故との間の因果関係が切れるため、症状固定後の治療費は加害者側に請求することはできないとされています。
以上より、症状が残存していて、主治医がまだ治療の必要(治療の効果)があると言っているにも関わらず、加害者側の保険会社から治療費を打ち切られたというような場合には、治療をやめずに継続されることをお勧めします。
(3)打ち切りに対するケース別対処法
①ケース1:追突されて頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けたが、治療開始から2か月後に治療費の打ち切りを打診された
(対処法)
保険会社と交渉しましょう。一般的に症状固定時期として受傷後2か月というのは早いと思いますが、保険会社の担当者は車両修理費用が低額であるから受傷状況としては軽微なものであったと考えられるなどと言って、事故から2か月程度で治療費の打ち切りを打診してくることが有ります。
しかし、症状固定時期については主治医の意見を無視できません。
そこで、主治医に症状固定時期(今後も治療を継続することで軽快する可能性があるのか)という点を確認し、保険会社に対し、主治医の意見をぶつけて交渉するのが良いでしょう。
②ケース2:追突されて頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けたが、治療開始から4か月後に治療費を打ち切られた。
(対処法)
健康保険に切り替えて、治療を継続し、追って治療費を保険会社に請求しましょう。既に治療費を打ち切られてしまった場合、一括対応の復活を求めることは極めて困難です。
しかし、症状固定に至っていなければ、打ち切り後の治療費も後で保険会社に請求することができます。
そこで、主治医に症状固定時期(今後も治療を継続することで軽快する可能性があるのかという点)を確認し、症状固定までは健康保険で通院を継続し、後ほど治療費を請求するのが良いでしょう(なお、請求した際に保険会社がすぐに支払うか否かは保険会社の判断もありますので、それでも支払われない場合には訴訟などで争っていくことになります。)。
③ケース3:追突されて頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けたが、治療開始から6か月後に治療費を打ち切られた又は打ち切りの打診をされた。
(対処法)
主治医に症状固定に至っているか確認して、至っているのであれば後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請をしましょう。一般的には頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状固定時期は受傷から6か月程度と言われています。そのため、症状固定に至っているのであれば、残存する症状について後遺障害等級認定の申請を行うために主治医に後遺障害診断書を作成してもらうのが良いでしょう。
なお、症状固定後の通院については、治療費を加害者側に請求することはできませんが、健康保険に切り替えて通院を継続することはもちろん可能ですので、症状が強く残っている場合には症状固定後も通院することをお勧めします。
(4)治療が打ち切りされてしまった(しまう)場合に弁護士にするメリット
最後に、治療費の打ち切りをめぐって、弁護士へ依頼するメリットを検討してみましょう。
①保険会社対応を任せることができる
治療に専念したいのに保険会社から連絡が毎日のように来る、保険会社の担当者の対応・態度が悪い、相手の言うままにして大丈夫なのか等々、治療費の打ち切りをめぐっては様々な悩みが生じることは多くあると思います。
弁護士に依頼すれば以上のような問題点を解決することができるでしょう。保険会社からの連絡には弁護士が対応しますので、治療に専念することができますし、今後の流れについても説明を受けることができますので、不安が解消されるのではないかと思います。
②保険会社の主張に対抗できる
治療費の打ち切りに関しては、保険会社からは様々な主張がされます。
法的根拠のない主張をしても、保険会社が受け入れることはまずありません。また、治療費の打ち切りをめぐっては医学的な知識も必要になってくることが多く、個人で保険会社に対抗するのは困難ですので、保険会社に対抗するには、弁護士に依頼することが必要でしょう。
③後遺障害等級認定の申請のサポートを受けることができる
仮に治療費が打ち切られる時期に症状固定に至っていれば、残存している症状について後遺障害等級認定の申請を行うことになりますが、後遺障害等級認定の申請には被害者が自ら行う被害者請求の方法で行うことを強くお勧めします。もっとも、被害者の方がご自身で準備を行うことは大変かと思いますし、適正な後遺障害等級認定を受けるためには医学的な知識も必要となってくることが多いので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
まとめ
今回は追突事故等でなりやすいむちうち症についてご説明させていただきましたが、いかがでしたか。
この記事が少しでも多くの被害者の方のお力になれればと願っています。