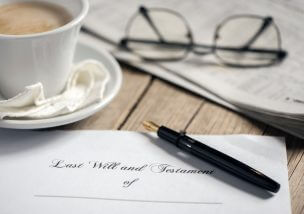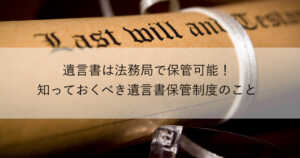
遺言書は法務局で保管ができることをご存知でしょうか。
遺言書は、作成するだけでなく、作成した後の管理・保管も大変です。
自分の意思を示したいときちんとした遺言書を作成したとしても、ちゃんと保管できなかったために日の目を見ないということは、実は珍しいことではありません。
- どこにしまったのかわからない
- 何かの手違いで処分してしまった
- 遺言書を遺族が見つけられない(遺言書の存在に気づかない)
といったことだけでなく、きちんと保管していかなかったために、改ざん・改変されてしまうこともあるでしょう。
実際に、改ざんがなかったとしても「誰かが改ざんしたかもしれない」という不安を相続人に与えてしまえば、遺言を残したことが逆に家族や兄弟内で相続トラブルの原因となることもありえます。
新しく運用が開始される法務局における自筆証書遺言書保管の制度は、これらの問題点を克服するためにとても便利な手続といえます。
そこで、今回は、この法務局における自筆証書遺言書保管制度の概要について解説します。
遺言書全般の概要について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
1、遺言書は法務局で保存できる!自筆証書遺言書保管制度とは?

法務局における自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で作成された自筆証書遺言書を全国にある法務局(遺言書保管所)で保管してもらう制度です。
公的な機関に遺言書を管理・保管してもらえるようになることで、遺言書をめぐる相続トラブルを防止する効果があります。
【参考】あなたの大切な遺言書を法務局(遺言書保管所)が守ります(法務局作成制度チラシ)
(1)自筆証書遺言書保管制度の運用開始日
法務局における自筆証書遺言保管制度は、遺言書保管法が施行される令和2年(2020年)7月10日から運用されています。
(2)法務局で保管してもらえる遺言書の種類
民法で認められている遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
このうち、法務局における遺言書保管制度の対象となるのは、自筆証書遺言のみです。
公正証書遺言は、遺言を公証役場で保管してもらえる仕組みとなっているため法務局で保管してもらう必要性もないといえますが、秘密証書遺言は、この制度の対象外となるので注意しましょう。
(3)遺言書保管の手数料
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する際には、政令で定められた所定の手数料を収入印紙にて納付する必要があります。
遺言書保管申請の手数料額は、1件につき3,900円です。
公正証書遺言を作成するよりもかなり安い金額に設定されています。
2、自筆証書遺言書保管制度を利用する4つのメリット

法務局における自筆証書遺言書作成制度を利用することには次の4つのメリットがあります。
(1)作成した遺言書が形式無効になることを回避できる
遺言書には形式的な要件が多くあり、それが欠けていると遺言書は無効となってしまいます。
一般の人が遺言書を自分で作成する場合、専門知識がないことが原因で形式的な要件を満たしておらず、せっかく作成した遺言書が無効となってしまうことが少なくありません。
法務局における遺言書保管制度を利用すると、申請の際に、署名や日付、押印があること等の形式的な要件がみたされているかについて確認がされますので、形式的な要件の不備による遺言書の無効を回避することができます。
(2)紛失のおそれがなくなり、発見しやすくなる
自筆証書遺言書保管制度ができる前は、公正証書以外の方式による遺言書は、遺言者(遺言書を作成した人)などが、自分で遺言書を保管する必要がありました。
そのため、相続開始までの間に遺言書を紛失してしまったり(どこにしまったかわからなくなる)、遺言書を誤って処分してしまったりするということが起こり得ました。
また、紛失・滅失を防ぐために厳重に保管したために、実際に相続が開始された時に相続人に遺言を見つけてもらえないこともあります。
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、公的な機関が遺言書を保管してくれるため、紛失や滅失のリスクがなくなります。
また、実際に相続が開始された時には、相続人が法務局で確認することで遺言書の存否や内容を確かめることができますので、相続人に法務局で保管していることを伝えておけば、発見されないというリスクもほぼなくなります。
(3)改ざん・改変のおそれがなくなる
遺言書の存在は、相続人にとっては重大な関心事です。遺言書が残されているケースでは、法定相続分とは異なる遺産分割の内容が記されている可能性も高く、有利な相続人と不利な相続人が発生する可能性が高くなるといえるからです。
そのため、遺言書が残されていることが分かれば、改ざん・改変の疑いなどを原因に相続争い(遺言を認めないと主張する相続人が現れるなどのトラブル)が起きてしまう可能性があります。
また、不利な内容が書かれていると感じた相続人が遺言書を隠匿したり、改ざんや改変をしてしまうリスクもあります。
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用することで、相続人が改ざんや改変、隠匿することを防ぐことができますので、これらのリスクも回避することができます。
(4)検認手続が不要
自筆証書遺言がのこされていた場合には、原則として必ず家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。
検認とは、遺言の存在及び内容を確認し、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
これは遺言の有効・無効を判断する手続きではないことには注意が必要です。
しかし、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合には、この検認手続が不要です。
検認手続を省略できれば、相続開始後速やかに遺産分割の手続を開始できます。
相続人の負担を軽くするためにも、自筆証書遺言書保管制度を利用することは有効です。
3、自筆証書遺言書保管制度を利用するときの流れ

自筆証書遺言書保管制度を利用するときの基本的な流れは下記のとおりです。
なお、制度の内容や申請手続きについてご不明な点がある場合は、法務局にお問い合わせください。
遺言書の内容については、法務局はアドバイスできませんので、内容についてもご相談されたい場合には、弁護士にご相談ください。
(1)申請手続
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用するときには、管轄の遺言書保管所(法務局)で申請手続を行う必要があります。
①申請することのできる法務局
自筆証書遺言書保管制度を利用できるのは、以下のいずれかの法務局です。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
②遺言の保管申請は遺言者本人の出頭が必要
自筆証書遺言書保管制度の申請手続は、遺言者(遺言を作成する人)本人が、管轄法務局に直接出向いて手続を行う必要があります。
また、申請手続に際しては、遺言者の本人確認が必要となるので、本人確認書類(写真付きの身分証明書)の持参が必要になります。
なお、法務局における自筆証書遺言書保管制度では、公正証書遺言の場合のような出張対応は現在のところ予定されておらず、代理申請も認められていません。
したがって、入院中、施設などに入所中、病気といった事情で本人が法務局に出向けない場合には、この制度を利用することはできないので注意する必要があります。この場合には、公正証書遺言の利用を検討しましょう。
③保管することのできる遺言書
法務局における遺言書保管制度は、自筆証書遺言の場合のみ利用することができます(秘密証書遺言の方式では利用できません)。
そのため、申請手続の際には、政令であらかじめ定められた様式にしたがって作成された遺言書を用意し、「封のされていない状態」で提出する必要があります。
(2)遺言書の保管方法
保管の審査がされた遺言書は、法務局の施設内において原本が保管されるだけでなく、その画像データなどもあわせて保管されます。
法務局において保管される期間は、下記のとおりになります。
- 遺言書 : 遺言者の死亡後50年
- 画像データ : 遺言者の死亡後150年
- 遺言者の生死が明らかでない場合には,遺言者の出生の日から起算して120年
(3)保管後の閲覧・撤回・変更~遺言者の生存中にできる手続
遺言者は、法務局に遺言を保管してもらった後も、次のような手続を請求することができます。
①保管された遺言の閲覧
遺言者は、法務局で保管されている遺言書について、その原本および画像データの閲覧を請求することができます。
なお、遺言者の生存中は、遺言者以外の人(推定相続人など)による閲覧は認められませんので、遺言の内容が他人に漏れる心配はありません。
②保管された遺言の撤回
遺言者は、法務局に遺言を保管してもらった後でも、自由にその内容を撤回することができます。
ただ、この撤回は法務省へ預けることをやめるというだけで遺言の効力自体がなくなる訳ではありませんので注意が必要です。
遺言を撤回する手続がなされた場合には、その遺言書は遺言者に返還され、画像データは消去されます。
ただ、この撤回は法務省へ預けることをやめるというだけで遺言の効力自体がなくなる訳ではありませんので注意が必要です。
遺言自体を撤回したい場合には、破るなどしたうえで廃棄するようにしましょう。
③保管された遺言の内容の変更(再提出)
保管の手続を済ませた遺言書の内容を変更したい場合には、保管されている遺言書を撤回した上で、新しい遺言書を再提出することになります。
保管した遺言書を書き換えるという手続はありません。
(4)遺言者(被相続人)死亡後の流れ
遺言者が死亡した場合には、保管されている遺言書の証明書(遺言書情報証明書:遺言書の写しに該当する書類)の交付および、遺言書の閲覧を請求することができます。
※遺言書保管制度を利用した場合は、遺言書の原本が相続人などに交付されることはなく、法務局でそのまま保管され続けます。
①証明書の交付、遺言書原本の閲覧を請求できる人
これらの請求手続を行うことができるのは、次の条件に該当する人などです。
- 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(欠格・廃除により相続権を失った者・相続の放棄をした者も含みます)
- 受遺者またはその相続人
- 遺言によって認知するとされた子(胎児の場合にはその母)
- 遺言書によって指定された遺言執行者
- 遺言によって相続を廃除された推定相続人
- 遺言によって祖先の祭祀を主催すべきと指定された者
なお、これらの者によって証明書の交付請求などがなされたときには、法務局によって、遺言書の保管がなされている旨が他の相続人・受遺者・遺言執行者にも通知されます。
②遺言保管制度の注意点
遺言保管制度は、相続人などによって証明書の交付請求がなされた場合などには、他の相続人に対しても遺言書が保管されている事実を通知してくれますが、最初の閲覧請求は相続人などのイニシアチブによって行われなければなりません。
ただし、遺言者が保管を申請する際に、「死亡時通知」を行うことを希望していた場合には、法務局は、遺言者が指定した1人に対して、遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していることを知らせる旨の通知を行います。
遺言書を見つけてもらえるか不安だという場合には、この死亡時通知を活用されるとよいでしょう。
まとめ
近年では、遺言を残す人が増えています。
遺言書は、自分の残した財産の分配などについて自らの意思を伝えるとても重要な仕組みです。
法務局における自筆証書遺言書保管制度ができたことで、自筆証書遺言の弱点が改善されることになるので、ますます遺言は簡単に、活用しやすくなっています。
しかし、自筆証書遺言書保管制度では、法務局は遺言書の形式面の審査は行いますが、内容については審査しませんし、相談にも乗ってくれません。
形式は整っていても内容に問題があれば、遺言書が無効となってしまったり、相続人の間に紛争が生じたりする原因にもなりかねません。
せっかく作成する遺言書で相続人の紛争を招いてしまっては意味がありませんので、遺言書を作成する際には、相続人の紛争対策として弁護士にご相談されることをおすすめします。