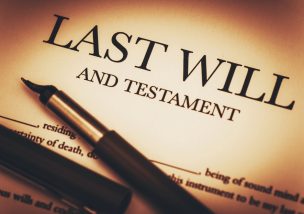遺言書についての手続きには、どのようなものがあるのでしょうか。
家族が遺言書を残して亡くなったときには、どうしてもその中身が気になってしまいます。
しかし、相続がはじまった(家族が亡くなった)からといって、すぐに遺言書を開封してはいけません。
遺言書が残されていた場合には、きちんとした手続きを経てからでないと遺言書の中身を確認することはできないからです。
そこで、今回は、
- 遺言書を見つけたとき(家族が遺言を残して亡くなったとき)の手続きの進め方
について解説していきます。
遺言書を見つけたときには、不要なトラブルを生じさせないためにも落ち着いて対応しましょう。
遺言について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、遺言書の手続きについて知る前に|遺言書の3つの種類
遺言書を見つけたときの手続きは、遺言書の法律上の形式、遺言書の保管場所によって異なります。
遺言書には、次の3つの方式があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自宅で発見された場合の遺言書は、自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言のいずれかですが、ほとんどの場合は、自筆証書遺言です。
公正証書遺言は、遺言書を作成した公証人(公証役場)で保管されることになり、秘密証書遺言が利用されることはあまりないからです。
2、自宅で遺言書を見つけたときには勝手に開封してはいけない
自宅で亡くなった家族の遺言書を見つけたときには、すぐに開封してはいけません。
自筆証書遺言、秘密証書遺言を開封するためには、「検認」と呼ばれる家庭裁判所での手続きを経なければならないからです。
(1)検認とは?
検認とは、相続人全員に対して、「遺言が残されていること」および「遺言の内容」を通知するために、家庭裁判所で行われる手続きのことです。
遺言の検認は、遺言の通知と確認を目的とした手続きですので、遺言の有効・無効を判断するための手続きではありません。
遺言の効力を争いたいときには、別途裁判手続きなどをとる必要があります。
(2)検認が必要なのはなぜ?
遺言書には、法定相続分とは異なる相続割合での財産分与が指示されている可能性があるだけでなく、非嫡出子の認知や、相続人の廃除(の取消し)といった、相続人の利害に大きな影響を与える内容が記されている可能性もあります。
そのため、遺言には常に「改ざん・変造」などのリスクがあります。
そこで、相続人全員の面前で遺言の内容・状態を確認し、後の改ざん・改変を防止するために検認が実施されるのです。
公正証書遺言の場合に検認が不要となるのは、公証役場に原本が保管されているため、改ざんなどのリスクがないからです。
(3)検認を行う前に開封したらどうなるの?
遺言書を検認前に開封してしまった場合には、5万円の過料(刑事罰の一種。ただし、前科とはならない)となる場合があります。
遺言書を作成するときには、「検認が必要なことを知らない開封してしまう相続人」があらわれないように、封書の目立つところなどに注意書きを残しておくとよいでしょう。
万が一、検認前に遺言書が開封された場合でも、遺言書が無効になるということはありません。
むしろ、検認前に開封したことで遺言が無効になってしまうとすれば、「簡単に遺言を無効できてしまう」ことになりかねないので、逆に問題です。
また、遺言書を勝手に開封したことが、相続人間にいざこざを生じさせる原因となることもあります。
「自分に有利なように内容を書き換えた(遺言書をすり替えた)のではないか」といった疑いをかけられないようにするためにも、遺言書を見つけたときには、慌てて開封せずに冷静に対処する必要があります。
(4)相続法改正で遺言の検認が不要な自筆証書遺言も
令和2年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる新しい制度の運用がはじまっています。
法務局に保管してもらった場合には、検認が不要となります。
法務局で原本を保管するので、改ざん・改変の恐れがないからです。
検認が必要であることは、自筆証書遺言を残す際の大きなネックの1つでもありましたから、法務局で保管してもらえるようになれば、今まで以上に遺言を残しやすくなるといえます。
3、家庭裁判所での検認手続きの流れ
自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
(1)検認を申し立てる家庭裁判所
検認の申立てをする家庭裁判所は、被相続人(遺言者:亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
管轄する家庭裁判所は、下記サイトで確認することができます。
- 裁判所の管轄区域(裁判所ウェブサイト)
(2)検認を申し立てることができる人
検認を申し立てることができるのは、下記の人です。
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
(3)検認の申立てに必要な費用
検認手続きの申立てには、遺言書1通につき、収入印紙800円を納める必要があります。
さらに、収入印紙とは別に、裁判所が申立人、その他の相続人などに連絡をする際に用いる郵便切手を予納する必要があります。
予納郵券の種類・枚数は、裁判所ごとによって異なるので、それぞれのケースを管轄する家庭裁判所に問い合わせて確認してください。
(4)申立てに必要な書類
検認の申立てに必要な書類は、下記のとおりです。
- 検認申立書
- 遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
なお、代襲相続などが発生する場合には、さらに追加書類(亡くなっている人の除籍謄本など)が必要となります。
※申立書の記載例(裁判所ウェブサイト)
(5)検認手続きの流れ
検認の申立てがあると、提出書類に問題がなければ、申立後1ヶ月ほどで、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が送られてきます。
検認は、相続人全員の立ち会いの下で行われることが理想ですが、欠席者が生じた場合でも手続きは実施されます。
なお、申立人本人については、出席が確保されるように、裁判所が日程調整をしてくれます。
検認当日には、遺言書(当然未開封のもの)と印鑑を持参します。
裁判所立ち会いの下、遺言書を開封し、日付、筆跡、署名、内容などを確認した上で、検認証明書発行の申請をして、手続きは終わりです。
検認証明書は、遺言の内容にしたがって、登記の手続き、銀行口座の名義変更などを行う際には、必ず必要となるものです。
発行の申請は忘れないようにしましょう。
なお、検認証明書の発行には1通150円(収入印紙)の手数料がかかります。
4、遺言書の内容に不満があるときの対処方法
遺言を検認した結果、内容に不満がある場合や、遺言が正しく作成されたかどうか疑わしいと感じる場合もあるかもしれません。
そのような場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
(1)相続人全員の同意があれば遺言書とは異なる内容で遺産分割することも可能
遺言書があるときには、遺産分割はその内容にしたがって行われるのが原則です。
たとえば、遺言書の存在に気づかずに遺産分割協議を終えた後に遺言書が見つかった場合には、遺言書の内容にしたがって遺産分割をやり直さなければなりません。
しかし、相続人および受遺者の全員が同意している場合に限っては、遺言書の内容とは異なる内容(全員が同意している内容)で遺産分割を行うことができます。
(2)遺言書の内容に問題があるときに行える手続き
遺言の内容が遺留分を侵害している場合や、遺言それ自体に問題があるという場合には、訴訟手続きによって、遺言の効力を否定してもらうことなどもできます。
①遺言内容が遺留分を侵害しているとき
問題のある遺言内容の典型例は、遺留分を侵害する遺産分与を指示しているときです。
遺言内容が遺留分を侵害している(たとえば、妻の相続分が相続財産の1/4に達しない場合)には、他の相続人・受遺者に対して、遺言で示された分与額と遺留分との差額分の支払いを求めることができます(遺留分侵害額請求)。
たとえば、相続財産全体が2000万円、相続人は妻、長男、長女である場合に、遺言では「長男への遺産分与を100万円しか認めなかった」というケースであれば、長男の遺留分である250万円との差額150万円について、妻(母)と長女に支払うよう求めることができるというわけです。
②遺言書が不正に作成されたことが疑われる場合
遺言書が正しい方法で作成されていないことが疑われるときには、「遺言無効確認の訴え」を提起することで、遺言そのものを無効にすることができる可能性があります。
たとえば、「被相続人は認知症であるので遺言書を作成できるはずがない」、「他人に騙されて(おどされて)遺言書を書かされた疑いがある」、「検認された自筆証書遺言は、遺言者(被相続人)以外の者が記入したものである」といった場合には、民事裁判で遺言それ自体の効力を争うことができるということです。
ただし、民事訴訟で遺言の無効を認めてもらう(勝訴判決を得る)には、「遺言が正しく作成されていない」ことを裏付けられる客観的な証拠が必要です。
有力な証拠を確保するには、専門的な知識経験が必要です。
遺言の効力を争いたいというときには、弁護士に相談・依頼しましょう。
5、遺言書について不安なことがあるときには早めに弁護士にご相談ください
遺言書を開封するには、家庭裁判所での手続きが必要です。
裁判所の手続きは、平日の日中に開催されるので、どうしても都合が付けられないということもあるかと思います。
そのような場合には、弁護士を代理人として立てることも可能です。
相続手続きを弁護士に依頼すれば、依頼人(相続人)は、面倒な手続きもから解放され普段通りの生活のまま、相続手続きを終えることができます。
また、遺言書に何かしらの問題がある場合にも、弁護士がいればスムーズに対応できます。
遺言書について、不安なことがあるときは、ちょっとしたことでもベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
まとめ
遺言書があるときには、誰でもその内容が気になってしまいます。
早く内容を確認したいという気持ちもあると思いますが、慌てず落ち着いて、きちんとした手続きを経ることが、他の相続人との信頼関係を壊さずに、円滑に相続を進めていく上でとても重要です。
また、遺言の内容に疑義があるときには、相続財産が散逸してしまう前に、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。