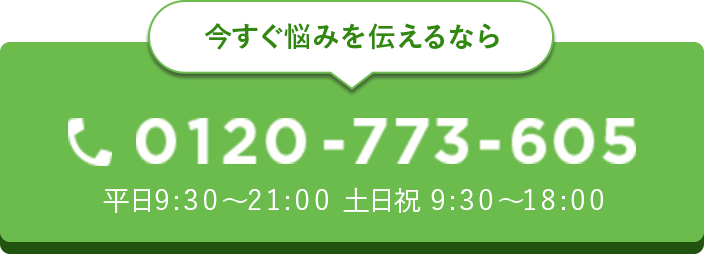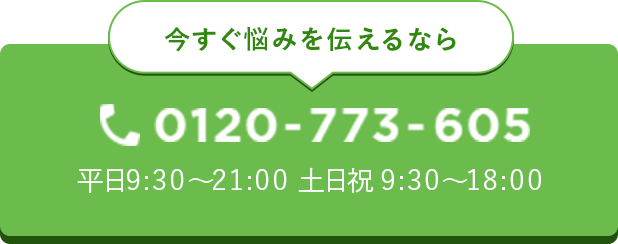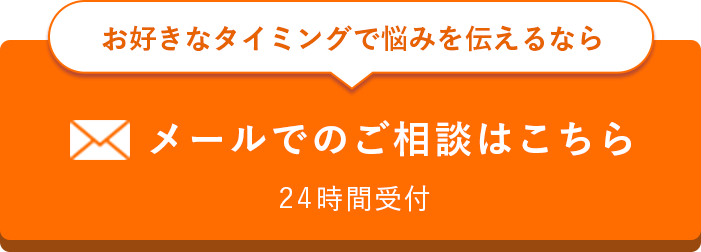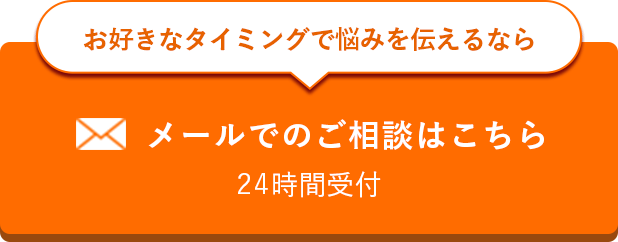事故に遭遇した場合の過失割合は、いつ、どうやって決まるのでしょうか。
過失割合が決まらなければ、どの程度賠償がなされるのかがわからず、生活の見通しもつけられないのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 事故の過失割合とは
- 事故の過失割合は、いつ、どうやって決まるのか
- 過失割合に納得できない場合はどうすればいいのか
といった問題について解説していきます。
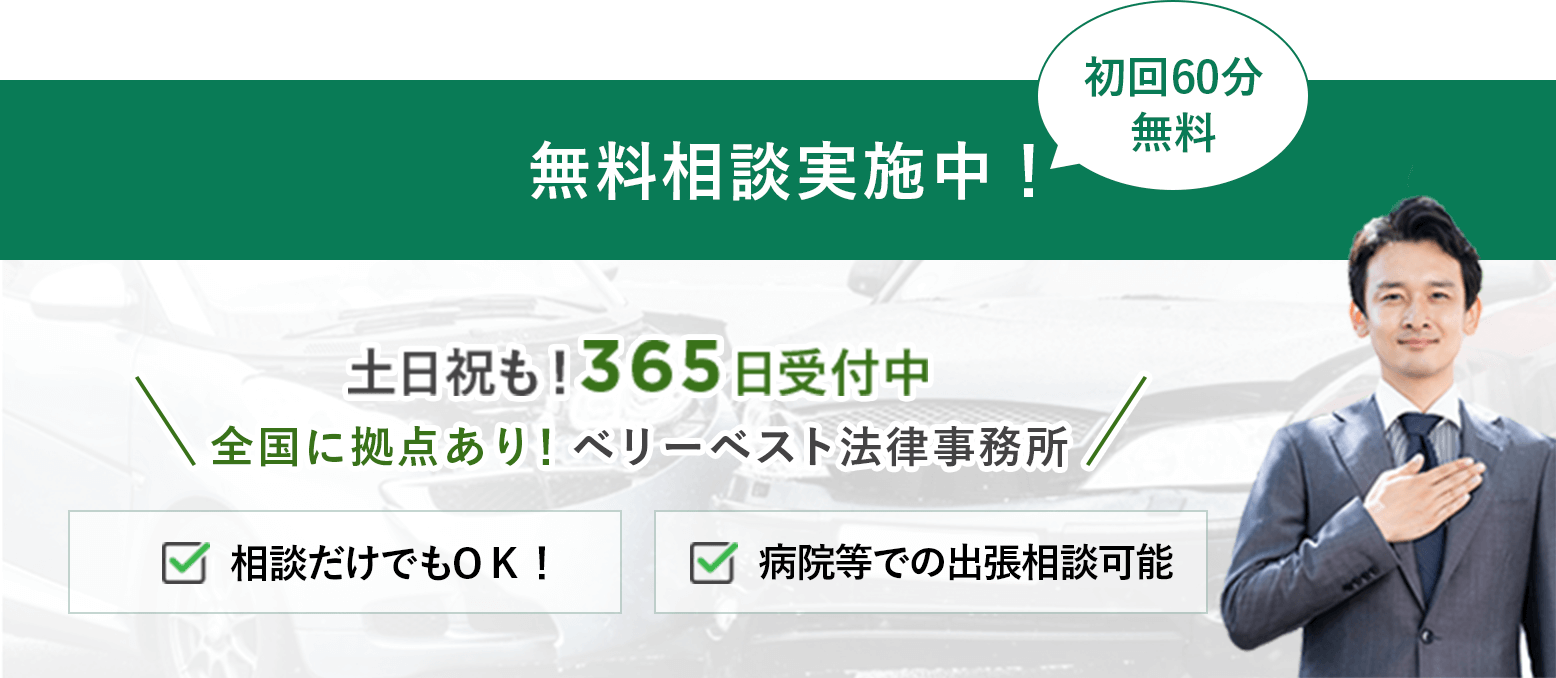
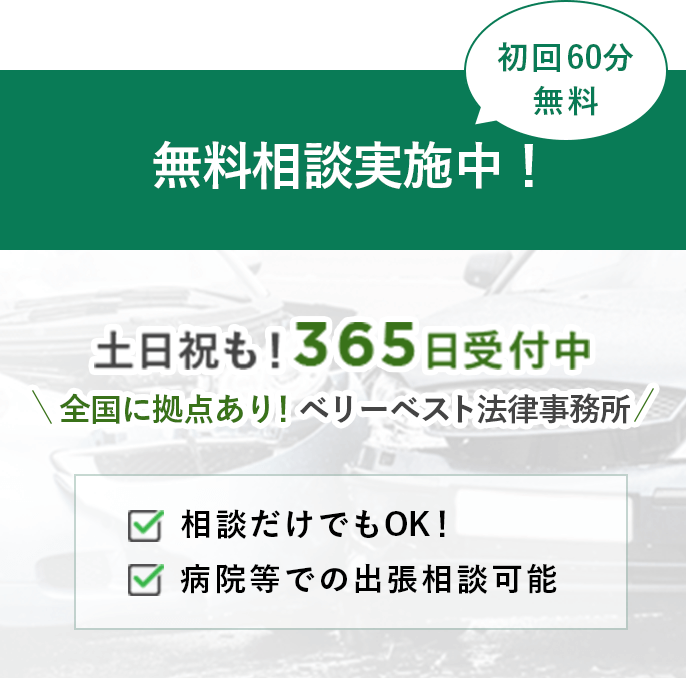
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
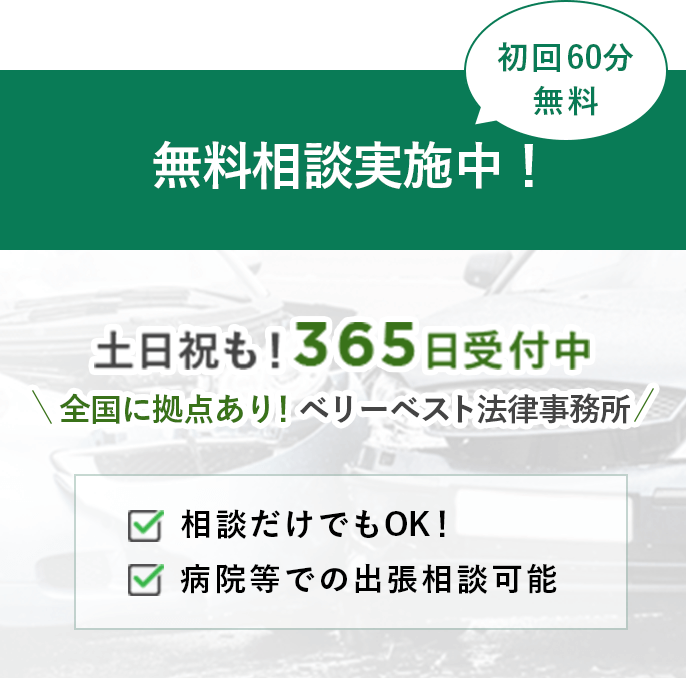
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
1、事故の過失割合とは?どうやって決まるのか
(1)過失割合が損害賠償額にもたらす影響
過失割合とは、事故が起こった場合に加害者と被害者のそれぞれにどの程度の過失があったのかを「〇〇対〇〇」という割合で示したもののことです。
事故では、多くのケースで被害者にも多少の過失(落ち度)が認められるものです。その場合、加害者に100%の責任を負わせることは不公平なので、被害者の過失の程度に応じて損害賠償額が減額されます。このことを「過失相殺」といいます。
例えば、事故によって被害者に総額300万円の損害が発生した場合、過失割合において被害者に10%の過失が認められれば賠償額は10%減の270万円となります。
このように、過失割合は損害賠償額に直結する重要な問題です。
(2)過失割合はどうやって決まるのか
上記のように重要な過失割合ですが、誰が過失割合を決めるのかというと、通常は加害者側の保険会社と被害者、または加害者側と被害者側の保険会社同士の協議によって決められます。それぞれの意見が噛み合わない場合などは、民事裁判を起こして裁判所に決めてもらいます。
保険会社が介入しない場合は、事故の当事者が話し合って過失割合を決めることになりますが、本記事では保険会社が介入することを前提として解説を進めます。
(3)過失割合の判断材料は?
過失割合は、事故の発生状況、自動車の損傷状況などを確認した上で、加害者と被害者のどちらがどの程度事故発生の原因を作ったのかを判断して決められます。
ただし、個別の事故の1件1件について一から過失割合を協議するのでは時間がかかり過ぎますし、ケースごとに判断が異なって不公平となるおそれもあります。
そこで、実務では過去の裁判例を分析・研究して作成された過失割合図を参照して過失割合を決めています。
具体的には、「民事訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」という本に事故の様々な類型ごとの過失割合図が掲載されています。
保険会社でも裁判所でも、基本的にはこの本を参照して過失割合を決めているのです。
2、事故の過失割合はいつ決まるのか
では、過失割合はいつ決まるのでしょうか。
まずは、保険会社における実務の流れをご紹介します。
(1)基本的には損害額が確定した後
過失割合は、いつ決めなければならないという決まりはありません。実際には、損害額が確定した後に過失割合が決まることが多いといえます。
ただし、保険会社内では事故直後の間もない時期に、過失割合について自社の見解をほぼ決めていることに注意が必要です。
次に、損害額が確定するのはいつかということをご説明します。
(2)物損事故の場合
物損事故の場合、車の損傷については修理をするかどうかをまず決める必要があります。
そのためには、まず修理額を決定します。事故車両を修理業者に見てもらった上で、いくらで修理するかという協定を保険会社と修理業者の間で結びます。
次に、その車の時価を調べます。時価を調べるには、有限会社オートガイドというところが毎月発行しているオートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)を参照するのが一般的です。
そして、修理の協定額が時価(+買替え諸費用)よりも低い場合は修理額を、修理の協定額が時価(+買替え諸費用)よりも高い場合は時価(+買替え諸費用)相当額を保険会社から被害者へ賠償するのが原則です。
修理と時価賠償のいずれを選ぶかを保険会社と被害者との間で合意したときに、物損の損害額が確定することになります。
(3)人身事故の場合
人身事故の場合は、被害者はまず負傷の治療を受けることになります。治療によって治癒したら、そのときに損害額が確定します。
もっとも、治療を続けても完治しない場合、被害者は後遺障害等級の認定申請を行うことができます。この場合は、後遺障害等級が確定したときに損害額が確定することになります。
3、事故の過失割合が決まるまでの準備、交渉過程や期間
次に、事故の過失割合が決まるまでにしておくべき準備、決まるまでの交渉過程及びそれぞれの過程に要する期間の目安をご説明します。
(1)証拠を収集する
基本的には保険会社と過失割合について交渉することになりますが、保険会社の見解と自分の意見が食い違う場合は、単に自分の考えを伝えたところで保険会社の見解が変わることはありません。交渉に向けての準備として、自分の意見を裏づける証拠を事前に収集しておくことが大切です。
そのための主な証拠としてまず考えられるのは、実況見分調書など警察の捜査記録ですが、それらの記録だけでは自分の言い分の裏付けとして不十分な場合は、別途証拠を集めなければなりません。他の証拠としては、ドライブレコーダーの映像、事故現場に残ったブレーキ痕や車の損傷状況を撮影した写真、目撃者の証言などが考えられます。
(2)保険会社と交渉する
前記2(1)でご説明したように、保険会社は、過失割合について、事故直後の間もない時期に自社の見解を決めてしまいます。
過失割合について当事者の意見が食い違う場合は、そこから交渉を行います。
過失割合が決まらないと示談金額も決まりませんので、どんなに遅くとも示談交渉で最終的な決着をする時点では過失割合が確定している必要があります。
もっとも、被害者側が「自分に落ち度があるのが納得できない」「落ち度はあるかもしれないが、それほど大きくないはず」と主張することも多々あり、このような場合、示談交渉がなかなかまとまらず、長期化するケースもあります。
示談交渉に要する期間は、通常は2~3ヶ月以内ですが、お互いの主張が平行線となり長引く場合は、裁判を起こすことも考えなくてはならないでしょう。
(3)最終的には訴訟を提起する
保険会社との話し合いがまとまらない場合、訴訟を提起することになります。裁判は平均して1年程度の期間を要し、1年を超えるケースも少なくありません。
しかし、弁護士に依頼した上で裁判になった場合にはメリットもあります。
1つめのメリットとして、判決になれば、事故日から支払の日まで、損害賠償金に「遅延損害金」という利息相当額がつきます。
また、2つめのメリットは、判決になれば、損害賠償金の約10%相当の「弁護士費用相当額」を上乗せしてくれることが通常です。
つまり、弁護士費用を一部加害者に負担させることができることになりるのです。これらの費目が示談交渉段階で払われることはまずありませんので、訴訟を提起するメリットといえるでしょう。
(4)消滅時効に要注意
当事者の意見が食い違う場合は、過失割合が決まるまでに長期間を要することが少なくありませんが、損害賠償請求権には、損害及び加害者を知ったときから5年の消滅時効があることに注意が必要です(なお、2020年4月1日以前に発生した事故ですでに3年の時効期間が経過しているものについては、原則として消滅時効により損害賠償を請求することはできません)。
時効の成立が間近に迫ってしまったときは、相手方に対して内容証明郵便による請求書を送った上で、裁判を起こすなどして時効を中断する手続をとることが必要になることがあります。
4、提示された事故の過失割合に納得がいかないときは弁護士に相談を
保険会社が提示してきた過失割合は絶対というわけではなく、誤っている場合も多々あります。できる限り支払い額を減らしたいとか、加害者側の意向から、保険会社が加害者の過失割合を低く提示してくることはよくあることといえるからです。
こちらの意見を保険会社に認めさせるためには、証拠に基づいて説得的な主張をしなければなりませんが、過失割合の算定は非常に難しい上に、保険会社も事故の示談交渉のプロなので、一般の方が対等な交渉を行うのは難しいものです。
過失割合は損害賠償額に直結する問題なので、被害者にとっては過失割合が決まるまで不安な気持ちが続いてしまうものです。
だからといって、早期に決着をつけるために、妥協して合意することだけは避けるべきです。納得がいかないまま承諾し、示談を成立させてしまうと、その後に示談内容を覆すのは非常に難しくなるからです。
そこで、的確に証拠を収集し、説得的な主張を展開するためには、弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。弁護士の力を借りることで迅速に示談交渉を行い、早期に過失割合をこちらに有利な内容にすることが期待できます。
また、弁護士が代わりに保険会社と示談交渉や裁判をしてくれますので、煩わしい交渉事などから解放されることにもなります。
過失割合についてお困りであれば、交渉の長期化を防ぐためにも、できるだけ早く、事故案件を数多く取り扱い、実績も豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。