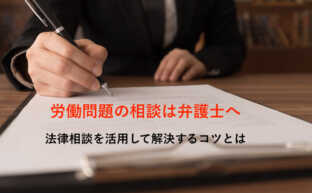労働基準局の力を借りて、労働環境の改善をしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし「どこに相談すればいいのか」が分からないとお困りのこともあるかと思います。
そこで今回は、
- 労働基準局とは?
- 労働基準局への相談について
- 労働問題はどこに相談すれば良いか?
等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。
ご注意下さい。
本ページはベリーベスト法律事務所のコラム記事です。
労働基準監督署(労働局、労働基準局)のWEBサイトではございません。
労働問題について解決したいと考えている方は以下の関連記事もご覧ください。
1、労働基準局とは?
みなさまは「労働基準局」とはどのようなものか、ご存知でしょうか?
多くの方が「労働基準監督署」や「都道府県労働局」と同じものだと考えているのではないでしょうか?
しかし、これらは3つとも、異なる機関です。
まずは、「労働基準局」とはどのような機関なのか、みてみましょう。
労働基準局は、厚生労働大臣の指揮監督のもと労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌する厚生労働省の内部部局です。
労働基準局は、都道府県労働局や労動基準監督署から見ると上部組織にあたるため、下部組織である都道府県労働局や労動基準監督署を指揮監督する立場にあります。
そこで、労働局や労働基準監督署が、法令違反を疑われる業者に立入調査するときなどには、労働基準局による指揮監督を受けることとなります。
また、労働基準局そのものにも捜査権限があるので、必要に応じて調査に立ち会ったり、自ら違反企業への捜査を展開したりすることもあります。
労働基準局は、厚生労働大臣の指揮監督のもと労働基準法の施行に関する事項をつかさどっていることから、労働契約、賃金、労働時間、労働者の安全及び衛生、並びに災害補償等ほぼ全ての労働問題を統括しています。
労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などの法令の施行を行ったり、法令の行政的な解釈についての通達を出したりすることもあります。
2、労働基準局と都道府県労働局の違いは?
ここまで読んでも「わかりにくいなぁ」と感じる方のために、他の機関と比較したときの労働基準局について、みてみましょう。
労働基準局は都道府県労働局と名前もはたらきもよく似ているので、混同されることが多いですが、この2つは、何が違うのでしょうか?
(1)上部組織と下部組織
労働基準局と都道府県労働局の大きな違いは、両者がそれぞれ、厚生労働省の上部組織と下部組織であることです。
労働基準局は、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものの、都道府県労働局の指揮監督権限を有することから、都道府県労働局の上部組織であるといえます。
これに対し、労働局は、労働基準局の指揮監督を受けることからすると、労働基準局の下部の組織であるといえます。
(2)中央の機関か都道府県の機関か
労働局は、各都道府県に設置されており、それぞれの労働局が「〇〇労働局」などと呼ばれます。
取扱事務は、労働相談や労働保険料の徴収、労働法違反企業の摘発や労働者への仕事の紹介、失業予防などです。
労使間でトラブルが発生したときには、労働紛争解決のあっせんも行っています。
つまり、各地域において具体的に労働紛争などの相談をしたり、話合いのあっせんを受けたりする場所は「都道府県労働局」であり、「労働基準局」ではありません。
労働基準局は、中央に位置する機関であり、労働局の活動を指揮監督する立場です。
3、労働基準局と労働基準監督署の違いとは?
次に、労働基準局と労働基準監督署の違いを、みてみましょう。
この2つも非常に名前がよく似ていることから、混同されることが多いですが、内容はまったく異なる組織です。
労働基準監督署も、労働局と同様、労働基準局の下部組織です。
労働基準監督署は、主に管内の企業が適切に法律を守って運営されているか、企業を監督する機関です。
労働基準監督官は捜査権限を持つので、違反が発覚すると、調査をしてその企業の法的責任を追及することができます。
また、労災保険の徴収や労災の認定なども行っています。
これに対し、労働基準局は、中央から各地の労働基準監督署のこうした活動に対し、指揮監督をする立場です。
労働基準局は、東京都の厚生労働省内に1つだけある「中央の機関」であるのに対し、労働基準監督署は、各都道府県や地方に複数存在する厚生労働省の出先機関です。
個別の相談や事件に対する対応は、労働基準局ではなく各地の労働基準監督署で行われています。
以上をまとめると、
- 「労働基準局」
- 「都道府県労働局」
- 「労働基準監督署」
の違いは、以下の通りと言えます。
- 労働基準局は、厚生労働省内の上部組織、中央組織であり、原則として、直接相談をしたり、和解あっせんをしてくれたり立入調査をしたりするところではない
- 労働トラブルが発生したときや労災が発生したときなどの個別的な対応は、各地の都道府県労働局や労働基準監督署で行っている
ここが重要なところですので、是非とも押さえておきましょう。
4、労働基準局の役割は?
個別の相談や調査などの対応を、地方の労働局や労働基準監督署が行っているとしたら、労働基準局は一体何をしているの?と疑問を持たれることがあるかもしれません。
労働基準局の役割をみてみましょう。
(1)都道府県労働局や労働基準監督署を適正に機能させる
労働基準局の重大な役割の1つは、各都道府県労働局や労働基準監督署を適正に機能させることです。
確かに個別の紛争などに対する対応は都道府県労働局や労働基準監督署が行っていますが、何の基準もなく、それぞれが個別に動いていると、地方によって対応がばらばらになってしまいます。
また、監視の目が行き届かなくなると、地方の企業と癒着などが起こり、不正が横行してしまう可能性もあります。
そのようなことのないよう、国の中心から全国の都道府県労働局、労働基準監督署を指揮監督しているのが、労働基準局です。
労働基準局があるからこそ、各地の都道府県労働局や労働基準監督署が適正に機能していると言っても良いでしょう。
(2)法令の施行や通達の発令
労働基準局は、労働関係法令の施行を統括する立場にあるといえます。
法令内容を具体的に解釈した「通達」の発行業務も行っています。
「通達」を出すことにより、地域ごとに労働関係法令の施行方法等に差がないようにしています。
(3)労働関係についての総合的な施策
労働基準局は、労働関係を規律する上位機関として、労働関係についての総合的な施策を担当します。
たとえば、労働条件の改善、労働者の安全や健康の確保、労災補償などを所掌しています。
5、労働基準局で相談できる?
ここまでお読みいただいたみなさまの中には、
- 「じゃあ、労働基準局ではどのようなことが相談できるの?」
- 「どうやったら労働基準局で相談することができるの?」
と考えた方がおられるかも知れません。
しかし、労働基準局は、基本的には、一般の労働者からの相談を受け付ける機関ではありません。
労動基準局は、都道府県労働局や労動基準監督署を指揮監督する機関ですから、個別の国民からの問合せや相談、苦情申し立てには基本的に応じていないのです。
個別の相談は、お近くの都道府県労働局や労働基準監督署に行く必要があります。
6、労働問題の相談先
労働基準局では労働問題の相談ができないとなると、残業代不払い問題やブラック企業のトラブルは、どこで相談したら良いのでしょうか?以下で、各種の相談先と概要を説明します。
(1)労働基準監督署
まずは、各地の労働基準監督署で相談することができます。
労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関として、個別の労働問題に対応しているからです。
たとえば残業代が支払われていない場合、労働基準監督署に相談をすると、勤務先に是正勧告を行い、勤務先が残業代を払ってくれるようになることなどがあります。
(2)都道府県労働局
都道府県労働局に相談することも可能です。
都道府県労働局では、労働者に対するアドバイスだけではなく、個別の紛争の解決のため、話合いのあっせんなども行っています。
(3)厚生労働省 労働総合相談コーナー
厚生労働省の「労働総合相談コーナー」というサービスを利用する方法もあります。
「労働総合相談コーナーは」、全国の労働基準監督署や都道府県労働局等に設置されていて、これらの機関と連携して、ワンストップで労働問題を解決することができます。
こちらのページから、お近くの相談場所を検索しましょう。
(4)法テラス
弁護士を通じて交渉や裁判を行いたいと考えているものの資力があまりないという場合には、法テラスでの相談が有効です。
法テラスは、法務省の管轄の機関で、経済的に余裕のない方へ向けた法律的支援を目的とする機関です。
法テラスでは、弁護士による無料相談を受けたり、弁護士費用の立替サービスを受けたりすることができます。
自分では証拠の集め方が分からない場合や会社と交渉することが難しい場合、労働審判や労働訴訟を起こしたい場合などには、是非とも利用すると良いでしょう。
法テラスに相談することによるデメリットはありませんが、法テラスでは相談する弁護士を選べないため、法テラスに相談した場合には必ずしも労働問題に強い弁護士に相談できるとは限らないという点には注意が必要です。
(5)弁護士
他方で、個別の弁護士事務所でも、労働相談を受け付けています。
最近では、残業代請求を専門的に取り扱っている事務所などもあるので、自分の抱えている労働トラブルに強そうな弁護士を探して、相談を申し込んでみましょう。
弁護士事務所で相談をするときには、「無料相談」を受けられることがあります。
無料相談は実施している事務所と、実施していない事務所があるので、ホームページの内容を確認して、無料相談ができる事務所を探すと良いと思います。
弁護士に相談し依頼をすると、すぐに代理人となってもらって勤務先に対して各種の請求をすることができますし、労働審判や労働訴訟などの裁判手続きを依頼することもできます。
労働問題に強い弁護士を選ぶと、早期に適切なアドバイスを受けられるので、相談した場合のメリットが大きいと言えるでしょう。
まとめ
今回は、労働基準局について解説しました。
労動問題に関して、基本的に労働基準局で相談を受けることはできないため、ご自身での対応が難しい労働問題の解決のためには、労働基準監督署、都道府県労働局、または個別の弁護士事務所などに相談を行う必要があります。
労動問題の相談先に迷った際には、この記事を参考にしてご自分の状況に合った相談先を選んで頂ければと思います。