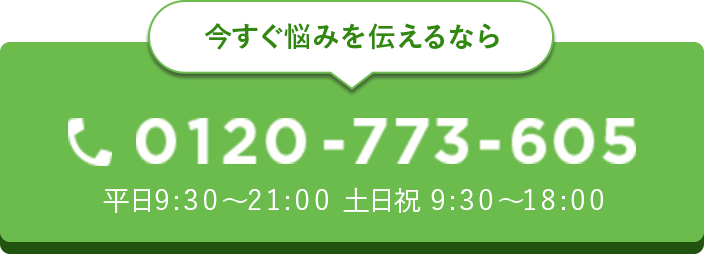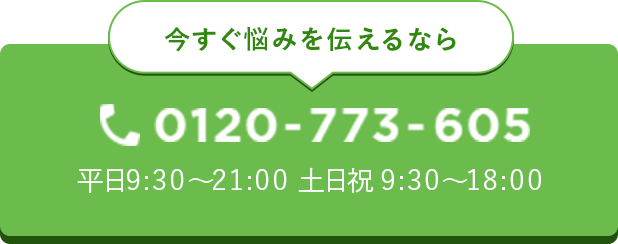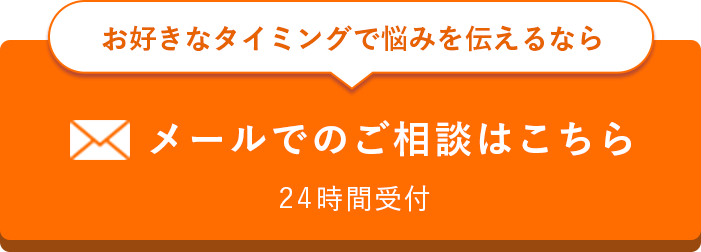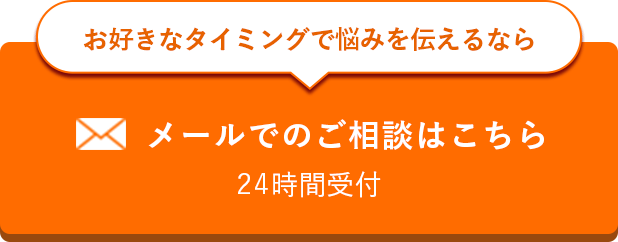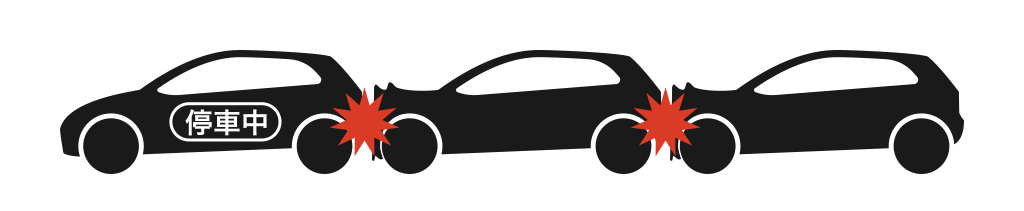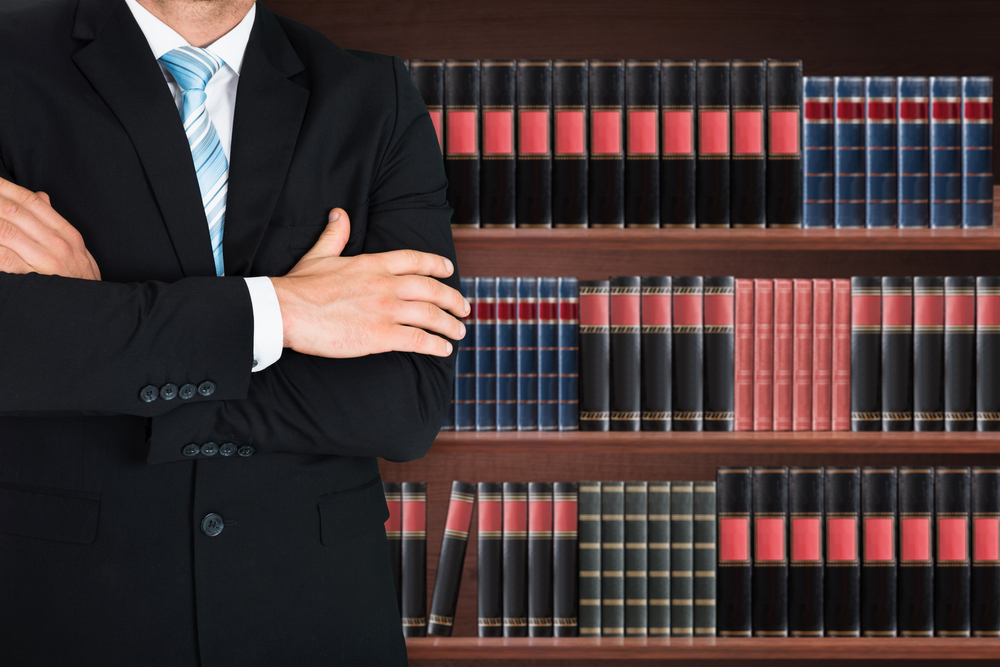玉突き事故は、3台以上の自動車が追突事故の当事者となるケースです。
玉突き事故の場合、被害者と加害者という2者の単純な関係に振り分けることが難しく、責任の所在が複雑になり、誰が誰にどのくらいの損害賠償請求できるのか、非常にわかりにくいです。
まずは玉突き事故がどのような交通事故か正しく理解して、正しい対処方法や過失割合などの重要なポイントを把握しておきましょう。
今回は、
- そもそも玉突き事故とは何か
- 玉突き事故の責任の所在
- 玉突き事故の過失割合
を解説していきます。ご参考になれば幸いです。
また、以下の関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説しています。突然の交通事故で遭遇されてお困りの方は、以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。
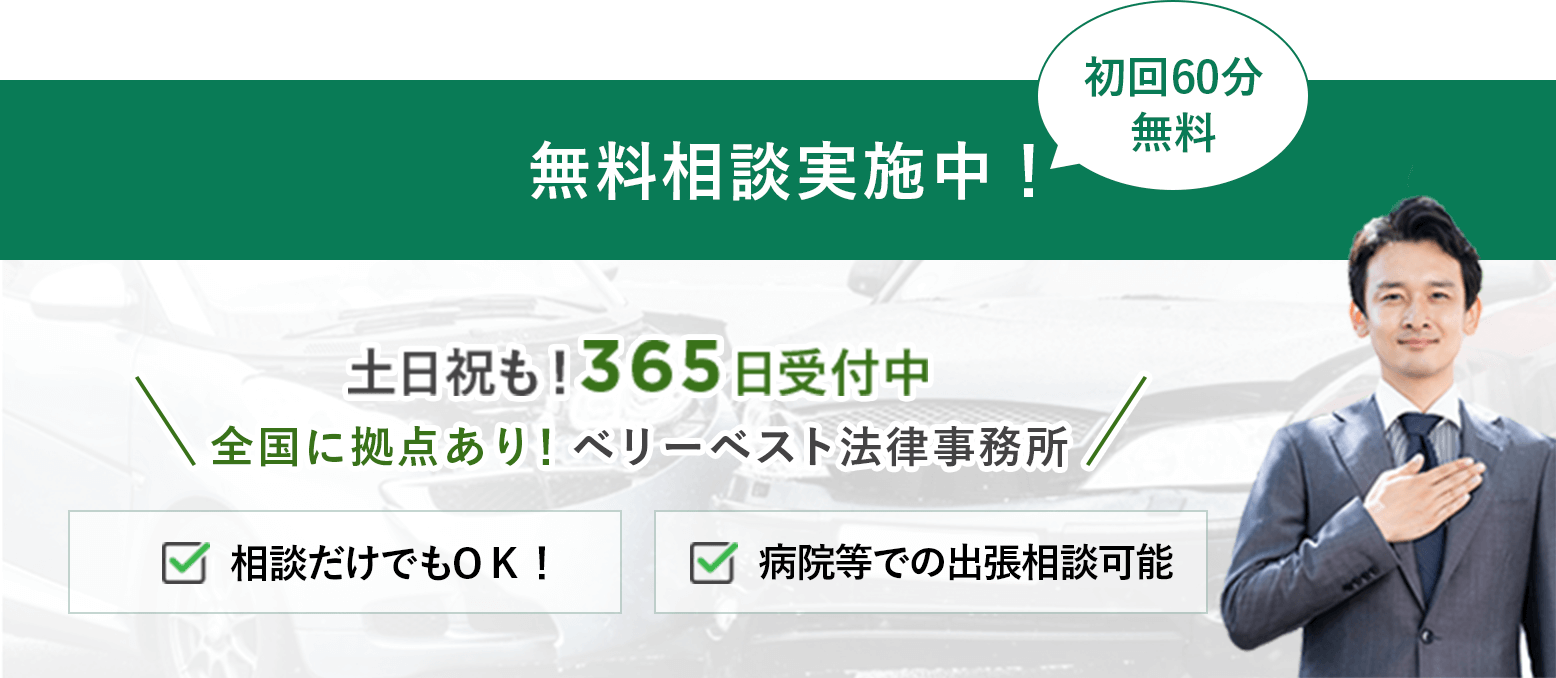

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、玉突き事故とは?
そもそも玉突き事故とはどのような交通事故のケースか、見てみましょう。
玉突き事故は、前方の車に対して後ろから来た車が追突し、前方の車が前に押し出されてさらにその前の車に追突する交通事故です。
その車がさらに前の車に追突するケース(当事者が4台以上となるケース)もあります。
玉突き事故の原因の多くは、後方の車の運転手による前方不注意や車間距離を十分とっていなかったこと、前方の車による急ブレーキなどです。
2、玉突き事故の責任の所在は複雑!
玉突き事故の場合、誰がどのくらいの責任を負うことになるのでしょうか?
これについては、ケースバイケースです。
- 前方の車は走行していたのか停車していたのか、停車している場合はその理由
- 前方の車が急ブレーキをかけたための追突かどうか、かけた場合はその理由
- 適切に車間距離をとっていたかどうか
- 一般道か高速道路か
などにより、各車両の過失割合は変わってきます。
そのため、玉突き事故が発生したときには事故当事者の責任の所在が複雑で、形式的に「過失割合の基準」を適用しようとしてもうまく当てはまらない可能性があります。
3、ケース別|具体的な玉突き事故の責任
以下では、事例別に、玉突き事故当事者の責任をみていきましょう。
(1)停車している車に追突した場合
前方に車が合理的な理由により停車しているところに後方の車が追突して交通事故につながった場合には、基本的に後方車両の過失割合が100%となります。
(2)急ブレーキをかけた場合
前から2番目の車両が急ブレーキをかけたために3番目の車両が2番目の車両にぶつかり、2番目の車両がさらに前の1番目の車両にぶつかった場合には、危険回避のためでない限り急ブレーキをかけた2番目の車両にも過失が認められます。
(3)高速道路上の場合
高速道路上では、停車や急ブレーキが禁止されています。
そこで、高速道路上で理由なく停車していたり急ブレーキをかけたりしたために後方車両が追突して玉突き事故が発生した場合には、一般道路の場合に比べ、前方車両にも高い過失割合が認められる可能性が高くなります。
ただし、停車していた場合でも、法律に従った方法で停まっていた場合は別です。
たとえば、渋滞中に前方車両がハザードランプを付けながら停車したところ、後方車両が高速で走ってきて追突し、玉突き事故となったら、停車していた前方車両の過失割合は基本的には0%でしょう。
(4)1番目の車が急ブレーキをかけたけれども、1番目の車は衝突されなかった場合
1番前の車が急ブレーキをかけたために2番目に走っていた車両も急ブレーキをかける結果となり、そのことが要因で3番目に走っていた車が2番目の車に追突した交通事故を考えてみましょう。
この事案で2番目の車が踏みとどまり、1番目の車に衝突しなかったら、責任割合はどうなるのでしょうか?
この場合、事故の根本的な原因は、1番目の車の急ブレーキですから、1番目の車両に高い過失が認められても良さそうなものですが、2番目の車が1番目の車に追突していない以上、1番目の車は、そもそも交通事故の当事者になりません。
そこで、1番目の車の過失割合は、基本的に0%になり、高い過失割合が認められるのは、3番目の追突した車両となります。
4、玉突き事故に遭ってしまった場合の対応の流れ
もしも玉突き事故に遭ってしまったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
まずは、車両を降りてけが人がいないか確かめましょう。
もし負傷している人がいたら応急処置を行い、必要に応じて救急車を呼びます。
そして、警察に通報して現場に来てもらい、実況見分に立ち会いましょう。
それが終わったら保険会社に連絡を入れて、病院に行っておくべきです。
その後、治療を継続して、完治または症状固定して治療が終了したら他の事故当事者の保険会社と示談交渉を進めます。
示談が成立したら、損害賠償金を受け取ることになります。
5、玉突き事故に遭った場合にもらえる保険金の内訳は?
玉突き事故に遭った場合には、さまざまな損害が発生する可能性があります。
ケースにもよりますが、具体的な保険金の内訳は以下のようなものです。
(1)被害者が怪我をしたケース
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費用
- 通院交通費
- 休業損害
- 器具・装具の費用
- 入通院慰謝料
(2)被害者に後遺障害が残ったケース
被害者に後遺障害が残ると、上記(1)に足して以下の2種類の保険金を請求できます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
(3)被害者が死亡したケース
被害者が死亡した事故では、以下のような損害が発生します。
- 葬儀費用
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
以上のように、ひと言で「玉突き事故」とは言っても、被害者の死傷結果によって発生する損害が異なるので、ケースに応じて具体的な損害の内容を検討する必要があります。
6、玉突き事故に遭った際の過失割合の計算方法は?
次に、玉突き事故の場合、過失割合がどのようになるのかを説明します。
玉突き事故は、基本的に3者以上が当事者となる「追突事故」ですので、「追突事故の過失割合」を基準にして計算をします。
(1)前方の車両に問題行動がなかった場合
一般道路上の追突事故では、基本的に後方車両に責任が認められます。
前方の車両が合理的な理由で停車していた場合や、特に問題なく走行していた場合に後方車両が追突すると、基本的に後方の車両の過失割合が100%です。
たとえば3番目の車が前方不注視や車間距離不足で問題なく走行又は駐停車していた2番目の車にぶつかり、その2番目の車が押し出されて問題なく走行又は駐停車していた1番目の車にぶつかった場合には、3番目の車のみに責任が発生します(過失割合は、1番目:2番目:3番目=0:0:100)。
ただし玉突き事故の場合、2番目の車が1番目の車との間にきちんと車間距離をとっていなかったために事故につながる可能性もあります。
そういったケースでは、2番目の車にも過失割合が認められるでしょう。
(2)前方の車両が急ブレーキをかけた場合
このように、基本的には後方のぶつかった側の車両に過失は認められることが基本ですが、前方の車両に過失が認められれば前方車両の過失割合が増えていきます。
一番多い過失としては「急ブレーキ」です。
前方車両が急ブレーキをかけた場合には、前方の車両の過失割合は30%が基本とされています。
後方の車両の過失割合が70%となりますので、つまりは急ブレーキをかけた前方車両よりも後方車両の過失割合の方が依然として高いのです。
これは、後方車両が十分な車間距離をとっていなかったことに過失が認められるという考え方があるためです。
そこで、1番目の車両が急ブレーキをかけて2番目の車両が1番目の車両に衝突し、3番目の車両が2番目の車両に衝突した場合などには、上記の通り1番目の車両にも過失は認められますが、過失割合の大きさとしては、やはり後方車両の過失が大きく、1番目の車<2番目の車<3番目の車となります。
(3)高速道路上で自己の過失によって停車していた場合
高速道路上で自らの過失(交通事故など)によって停車している車があるときに後方車両に追突されて事故が起こると、停車していた前方車両に高い過失割合が認められます。
具体的には前方車両の過失割合が40%程度、後方車両の過失割合が60%程度となります。
玉突き事故の場合にも同じ考え方です。
(4)高速道路上で、自分に過失のない要因で駐停車していた場合
高速道路上において、自らに過失のない理由により道路上に駐停車していたところ、後方車両に追突されるケースがあります。
この場合の基本の過失割合は前方車両が20%、後方車両が80%となります。
(5)高速道路上で、自分に過失のない要因でさらに駐停車の方法にも過失がない場合
高速道路上であっても、自らが起こした交通事故が要因ではなく、三角表示灯を置くなどして過失なく対応していたにもかかわらず後方車両が追突した場合には、前方車両の過失割合は0%、後方車両の過失割合が100%となります。
(6)高速道路上で急ブレーキをかけた場合
高速道路上で前方車両が急ブレーキをかけると、一般道に比べ前方車両により高い過失割合が認められます。
具体的には、前方車両の過失割合が50%程度、後方車両の過失割合が50%程度となります。
7、玉突き事故の過失割合に納得いかない場合の対処法について
玉突き事故の過失割合は、2当事者の交通事故のように単純ではなく、ケースごとの検討が必要です。
もしも過失割合に納得ができない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
このような場合、まずは「追突事故の基本の過失割合」を調べましょう。
玉突き事故の場合、当事者が3名以上いるので一見複雑ですが、基本的には2当事者間の追突事故のケースにおける過失割合を適用するからです。
判例タイムズなどの書籍を参照するのも良いですが、玉突き事故の場合、これを見ても、どれにあてはめ得て良いのかわからないことがあるかもしれません。
そのようなときには、法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めるのがもっとも得策です。
弁護士に対して事故の状況を正確に説明すれば、弁護士がケースごとの過失割合を算定するでしょう。
相手の保険会社が主張している過失割合に不満がある場合には、弁護士に示談交渉を依頼して、適正な過失割合をあてはめるように話を進めることも可能です。
どうしても折り合いがつかなければ、裁判で適切な過失割合を決定することも可能ですので、諦める必要はありません。
まとめ
今回は、玉突き事故について説明しました。
玉突き事故は法律関係が複雑であり、誰にどのくらいの賠償金を請求できるのかがわかりにくいです。
適切に過失割合を算定して、高額な賠償金を獲得するためには専門家である弁護士による助けが必要です。
今回のご説明内容を参考に、まずは交通事故に強い弁護士に相談をして、損をしないように示談交渉を進めていきましょう。