
「養育費の支払いが滞って困っている!強制執行したい!」
養育費の支払いに関するトラブルは、計算や延滞、未払いなど様々な形で現れることがあります。
この記事では、養育費の強制執行に関する基本的な知識から、弁護士の役割や手続き、審判に至るまでの流れと、養育費の強制執行が失敗した時の対処法などについてご紹介します。
養育費の強制執行について正確な情報を得て、問題解決のための手段を見つけるお手伝いができれば幸いです。
目次
1、養育費を払ってもらえないときは強制執行で回収できる!
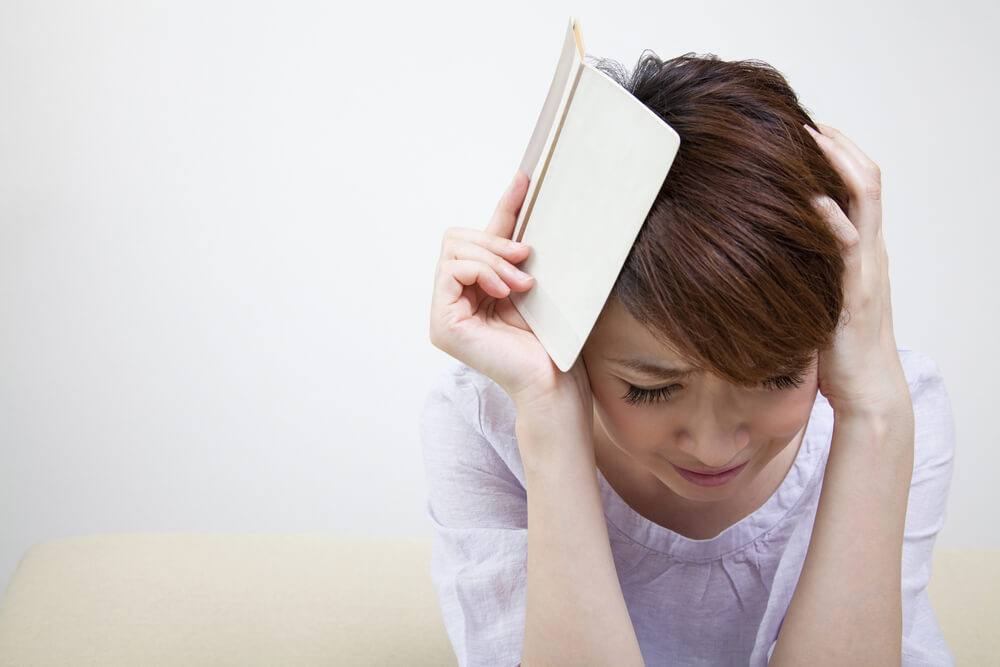
未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取った親(親権者)は元パートナー(非親権者)に対して養育費を請求する権利があります(民法第766条1項、第877条1項)。
しかし、現実には養育費をきちんと取り決めて離婚する夫婦はそれほど多くありませんし、取り決めたとしても約束どおりに養育費を支払わない元パートナーも多くいます。
このような場合、法律の手続きによらずに実力で相手方からお金を回収することは禁止されています。
このことを「自力救済の禁止」といいます。
もし、無理やりにお金を回収しようとすれば、窃盗罪や脅迫罪、強盗罪などの罪に問われたり、民事上も損害賠償責任が発生する可能性があります。権利があっても、その内容を実現する手段がなければ「絵に描いた餅」となってしまいます。
そこで法律では、相手に支払いを強制する手段として「強制執行」という制度が設けられています。
決められた手順に従って強制執行を申し立てれば、相手の財産を差し押さえることができ、そこから強制的に養育費を回収することができるのです。
2、養育費の強制執行をする前にやっておかなければならない3つのこと

養育費の強制執行は、誰もがすぐに利用できるわけではありません。
強制執行を申し立てるためには、その前に準備しておかなければならないことがいくつかあります。
以下で、3つの準備事項をご説明します。
(1)債務名義を取得する
強制執行をするための法律上の条件として、「債務名義」というものを取得する必要があります。
債務名義とは、法律的に確定した請求権の存在、範囲、債権者、債務者を公的に証明する文書のことです。
養育費の強制執行に使える債務名義としては、以下のものがあります。
これから債務名義を取得する方は以下の関連記事もご確認ください。
①公正証書
当事者間で養育費について取り決めた場合に、その内容を記載した離婚協議書や合意書などの書面を公正証書化していれば債務名義となります。
ただし、「養育費の支払いが不払いになったら、強制執行をしてもよい」という旨の記載(「執行認諾文言」といいます。)が付されていることが必要です。
②調停調書
家庭裁判所の調停で養育費を取り決めた場合に発行される書面です。
③審判書
調停で話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所が審判で養育費について決定します。
審判で養育費の支払いが命じられた場合に発行される「審判書」も債務名義となります。
④判決書
離婚裁判で、離婚を求めた側が勝訴し、養育費の支払いも認められた場合に発行される「判決書」も債務名義となります。
ただし、確定した判決の内容が記載されたものでなければなりません。
判決書が裁判所から相手に送達された日の翌日から2週間以内に相手が控訴をしなければ、判決は確定します。
⑤和解調書
離婚裁判を起こした場合でも、必ずしも判決が言い渡されるわけではなく、和解が成立することもあります。
和解をすると「和解調書」が発行されますが、そこに養育費の支払いについて記載されている場合は債務名義となります。
(2)相手の居場所を確認する
強制執行を申し立てる際には、相手の居場所を確認しておく必要があります。なぜなら、裁判所が発布する「差押命令」が相手に送達されなければ、養育費を取り立てることは認められないからです(民事執行法第155条1項)。
そのため、相手の現住所を把握する必要がありますし、相手が現住所に住んでいない場合には実際に住んでいる場所(居所)を調べなければなりません。
相手の所在がわからない場合の対処法については、後ほど「6」(1)で解説します。
(3)相手の財産を把握する
強制執行によって相手の財産のうちどれを差し押さえるのかについては、申し立てる側が特定する必要があります。
裁判所が相手の財産を調べて差し押さえてくれるわけではありません。
そのため、元パートナーがどのような財産をどれくらい持っているのかを把握することが重要となります。
強制執行(差押え)のできる財産としては、大きくは不動産、動産、債権の3つがあります。
①不動産
具体的には、土地、建物のことをいいます。
元パートナーが持ち家を所有している場合は差押えが可能ですが、住宅ローンが残っていてオーバーローン状態の場合には差し押さえても養育費の回収はできないことに注意が必要です。
②動産
不動産以外の物のことです。具体的には、時計や宝石など、売却することによって金銭となるものをいいます。
③債権
相手(債務者)が他人に対して持っている請求権です。
具体的には、給料と預貯金等があげられます。
多くの人は勤務先から給料を受け取る債権や、預金口座のある銀行から払い戻しを受ける債権を持っています。
そのため、養育費の強制執行をするときは相手方の給料や預貯金を差し押さえることが多いです。
3、養育費の強制執行は容易になった!法改正の内容

以前は、養育費を請求する側が強制執行を申し立てようと思っても、元パートナーの財産を把握できないために事実上諦めなければならないケースが多く発生していました。
しかし、2020年4月1日から改正民事執行法が施行されたことにより、以前よりも財産調査が容易になっています。
(1)第三者から情報を取得できるようになった
元パートナーの勤務先や預金口座について、以前は本人から直接聞き出さなければ把握するのは難しい実情でした。
しかし、改正民事執行法によって、裁判所を通じて市区町村の役所や金融機関等に対して、元パートナーの「給与支払者情報」や「預金口座情報」などの開示を求めることができるようになりました。
さらに2021年5月1日からは、法務局に対して元パートナー名義の不動産に関する情報の開示も求めることができるようになっています。
これらの制度を活用することで、元パートナーの財産状況がまったく分からないという方でも強制執行を申し立てることが可能となっているのです。
(2)財産開示を拒否する相手方に刑事罰が適用されるようになった
強制執行に備えて相手の財産を調査する方法としては、裁判所を通じて債務者自身に財産を開示させる「財産開示手続」という制度もあります。
この制度は2003年に導入されましたが、相手が財産開示を拒否したり、虚偽の情報を開示した場合の罰則が軽かった(30万円以下の過料という行政処分のみ)ことから、実効性が十分ではありませんでした。
しかし、この点についても2020年4月1日から施行された改正民事執行法により、「6か月以上の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が設けられました。
現在では財産開示を拒否したり、虚偽の情報を開示することは犯罪とされていますので、財産開示手続を利用することによっても相手の財産を把握しやすくなっています。
4、養育費の強制執行をするなら給料と預貯金口座の差押えが狙い目!

先ほどもお伝えしたように、養育費の強制執行で一番回収できる可能性が高いのは、給料と預貯金口座の差押えです。
もっとも、預金があまりない方もいらっしゃるので、相手が働いているのであれば、給料の差押えが一番効果的であるといえるでしょう。
(1)差押えとは?
先ほどから「差押え」という言葉を使っていますが、ここでは差押えの正確な意味を確認しておきましょう。
差押えとは、何からの債務を抱えている私人の所有財産について、裁判所が本人による事実上・法律上の処分を禁止し、確保する処分のことをいいます。
分かりやすくいうと、差押えを受けた人は、自分の財産であってもそれを自由に使えなくなるということです。
差押えの対象となった財産の中からまず債務が支払われ、その後に残った部分についてのみ所有者が自由に使えることになります。
例えば、給料は通常なら労働者が全額受け取ることができますが、差し押さえられると勤務先から労働者に対する支払いが禁止され、労働者は差し押さえられた分を差し引いた金額しか受け取れなくなります。
預金口座を差し押さえた場合も、口座名義人による払い戻しも引き落としも停止され、残高の中から債務が支払われます。その後に残った預金については、口座名義人が自由に使うことができます。
(2)給料を差し押さえるときの注意点
給料を差し押さえた場合には、元パートナーに給料が支払われる前に、勤務先から直接養育費を回収することができます。
ただし、給料の全額を差し押さえることはできないことに注意が必要です。
労働者にとって給料は生活の糧ですので、一定の範囲については差押えが禁止されているからです。
養育費の未払いを回収するために差押さえをする場合は、原則として給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1については差押えが禁止されています。
もっとも例外的に、給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1が33万円をこえる場合、差押え禁止金額の上限は33万円となります。
ちなみに、給与債権は一度差し押さえてしまえば、毎月差し押さえる必要はありません。翌月以降発生する将来の給料に対しても差押えの効果が及びます。
例えば、養育費の未払いが100万円あり、元パートナーの給料から税金・社会保険料・通勤手当を引いた金額が30万円だとすれば、1か月に差し押さえることができるのは15万円となります。これが100万円に達するまで、元パートナーの勤務先からあなたに対して毎月お金が支払われます。
しかし、元パートナーが退職してしまうと、差し押さえの効果はなくなってしまいます。
なお、給料の差押えは会社に通知されることになります。そのため、支払いがない時点で給料を差し押さえる旨の通知をすればあきらめて支払いに応じることも多いので、まずは通知して交渉してみるとよいでしょう。
(3)預金口座を差し押さえるときの注意点
預金口座を差し押さえる場合に注意すべきことは、口座にお金が入っていなければ差し押さえても結果的に養育費を回収できないということです。
特に給料の受取口座の場合は時期によって預金額が変動する可能性が高いので、申立てのタイミングを図ることが重要です。
例えば、給料日が25日なら、その日または直後の時期を狙って強制執行を申し立てることが重要となります。
強制執行を申し立ててから差押えの効力が発生するまでには、数日~1週間程度のタイムラグがあります。早すぎると給料日前に差押えの効力が発生してしまい、その月はほとんど養育費を回収できないという可能性もあります。
そのため、給料日の2~3日前に強制執行を申し立てるのが安全かつ効果的といえます。
5、養育費の強制執行を自分でやる場合の手順

では、実際に養育費の強制執行を申し立てる方法と、差押えによって養育費を手にするまでの手続きを流れに沿ってみていきましょう。
弁護士に依頼すれば難しいことは何もないのですが、ここでは自分でやる場合の手順をご紹介します。
(1)必要書類をそろえる
強制執行を申し立てるためには、まず、以下の書類を準備することが必要です。
①債務名義を証明する書類
前記「2(1)」でご説明した公正証書・調停証書・審判書・判決書・和解調書のことです。
公正証書については、強制執行認諾文言が付されていることが必要です。
調停調書・審判書・判決書・和解調書については、その正本に「執行文」が付与されていることが必要です。
執行文とは、「債権者は、債務者に対し強制執行をすることができる」という記載のことです。裁判所へ「執行分付与の申し立て」を行うことで付与されます。
②確定証明書
判決書については、その判決が確定していることの証明書も必要です。
裁判所へ「判決確定証明申請」をすることで、証明書が発行されます。
③送達証明書
調停調書・審判書・判決書・和解調書が相手方へ送達されていることの証明書も必要です。
裁判所へ「送達証明申請」をすることで、証明書が発行されます。
④請求債権目録
請求する債権の内容について記載した書面です。養育費を請求する権利の内容について書くこととなります。
記載する内容は、債務名義(判決書か、公正証書か、等)によって異なってきます。
裁判所のホームページにて、書き込み式で簡単に作成できる書式を記載例とともにダウンロードできます。
ダウンロードページについては、後ほどご紹介します。
⑤差押債権目録
差し押えする債権の内容について記載した書面です。
給与を差し押さえる場合には、給与を支払う会社や給与の金額などについて記載します。
預金を差し押さえる場合には、口座について記載します。
こちらも、後ほどご紹介する裁判所のページから書き込み式の書式を記載例とともにダウンロードして使用できます。
⑥当事者目録
給与を差し押さえる場合には、申立人、相手方、そして相手方の勤務先会社について書いていきます。
こちらも、後ほどご紹介する裁判所のページから書き込み式の書式を記載例とともにダウンロードして使用できます。
⑦住民票
当事者の現在の住所が債務名義に記載されている住所と異なる場合に必要となります。
住民登録をしている市区町村の役所で取得します。
⑧資格証明書
差押え先(「第三債務者」といいます。)が法人の場合には、その法人の代表者事項証明書(商業登記簿謄本)が必要です。
給料を差し押さえる場合は相手方の勤務先会社、預金を差し押さえる場合は口座がある金融機関の代表者事項証明書を法務局で取得します。
⑨宛名付き封筒
申立債権者(あなた)の宛名を記載した長形3号の封筒を用意します。
⑩書式のダウンロード
以上の必要書類のうち、債務名義正本に付与される執行文、判決の確定証明書、送達証明書については、裁判所へ申請して取得する必要があります。
これらの申請書の書式は裁判所のページからダウンロードできますので、以下の文字をクリックしてページを開き、ダウンロードしてみてください。
請求債権目録・差押債権目録・当事者目録のダウンロードページはこちらです。
(2)強制執行申立書の作成・提出
以上の必要書類がそろったら、申立書を作成して一緒に裁判所へ提出することによって申し立てを行います。
申立先は、相手方(元パートナー)の住所地の地方裁判所です。
差し押さえの申し立てにあたっては、「債権差押命令申立書」というものを記載する必要があります。書式は以下の裁判所のページからダウンロードできますので、ご利用ください。
なお、申立手数料として収入印紙代(基本金額は4,000円)、郵便切手代(裁判所により異なりますが、2,500円前後)がかかりますので、用意しておきましょう。
(3)裁判所による差押命令
提出した申し立て書類に不備がなければ、裁判所から「債権差押命令」が発出されます。これが出れば、相手方の有する債権が差し押さえられたということです。
債権差押命令は、債務者(相手方)と第三債務者(相手方の勤務先会社や口座のある金融機関)にも送達されます。この時点で、第三債務者が債務者へ弁済することは禁止されます。
つまり、勤務先会社は給料のうち差し押さえられた金額については相手方に支払ってはなりませんし、銀行は相手方に払い戻したり引き落としたりできなくなります。
(4)差押え先から取り立て
差押えが行われた後は、ご自身で差押え先(第三債務者)に対して取り立てを行い、差し押さえられた印額を直接支払ってもらいます。
取り立てというと抵抗を感じる方も多いかもしれませんが、裁判所によって決められたことですので、あなたから第三者債務者へ連絡をとり、支払い方法を指示するだけで応じてもらえます。
第三債務者の方から連絡してきてくれることもよくあります。
給料を差し押さえた場合は、あなたへの振込口座を指定すれば、相手方の勤務先会社から毎月、債権額に達するまでお金が振り込まれます。
預金を差し押さえた場合は、その口座の残高から差押で認められた債権額があなたに一括で支払われます。
口座の残高が足りなかった場合、不足分についてはさらに相手方に対して支払いを請求できます。
ただ、任意に支払ってもらえない場合はさらに財産を調査して強制執行を申し立てる必要があるかもしれません。
なお、強制執行の申し立てからお金を回収するまでの期間は、順調にいけば2週間もかかりません。
時間がかかるとすれば、第三債務者との連絡に手間取った場合や、第三債務者からの支払いがスムーズにいかない場合です。
もっとも、金融機関は差押え手続きにも慣れているので、すぐに支払ってくれます。
それに対して、一般的な会社の場合は差押えを初めて経験する場合も多いので、手間どることもあるかもしれません。
場合によっては、あなたの方から、法律上の手続きなのでこちらに支払ってもらっても大丈夫だということを説明してあげることで、スムーズに支払ってもらえることもあります。
(5)裁判所への報告
取り立てによって債権を全額回収できたら、「取立完了届」を裁判所へ提出します。
一部しか回収できなかった場合は、「取立届」を提出します。
取り立てが完了するまでは今回の強制執行手続きは終了しませんので、不足分について別途強制執行を申し立てる場合は、今回の手続きを取り下げる必要があります。
その場合は、取立届と一緒に「取下書」も提出します。
このとき、「債務名義等還付申請書」も提出すると、今回の申し立てで裁判所へ提出していた債務名義の正本が返還されますので、次の強制執行申し立てで使用することができます。
以上の書類の書式も裁判所のページからダウンロードできますので、ご利用ください。
6、養育費の強制執行が失敗したときの対処法

せっかく養育費の強制執行を申し立てても、ときにはうまくいかないこともあります。
書類に不備がある場合には、裁判所から指摘されますので、指示に従って訂正・補充をすれば受理されます。
一方、以下のような場合には差押命令が発出されても養育費を回収することができません。
それぞれの場合について、対処法を解説していきます。
(1)相手の所在がわからない場合
住民票を調査して申し立てても、相手方がその場所に住んでいない場合には差押命令が送達されないため、第三債務者から取り立てることはできません。
このような場合、通常は裁判所から一定の期間内に相手方の居場所を調査して差押命令の送達場所を申し出るように指示されます(民事執行法第145条7項)。
指定された期間内に申し出ることができなければ、差押命令は取り消されてしまいます(同条8項)。
相手方の住民票を取得するのは難しくありませんが、実際の居場所を見つけ出すことは容易でない場合が少なくありません。
探偵に依頼して調査する方法もありますが、最低でも数十万円は費用がかかりますから、費用対効果は慎重に判断する必要があります。
場合によっては、逃げ隠れするような元パートナーからの回収はあきらめて、シングルマザーが利用できる社会保障制度に頼る方が得策かもしれません。
なお、最近普及しつつある「養育費保証サービス」を利用すれば、元パートナーが逃げ隠れした場合のリスクを回避して、一定期間は養育費を確保することが可能となります。
ただし、養育費保証サービスを提供している業者と契約する際にも元パートナーの協力が必要です。
そのため、養育費保証サービスを利用するなら離婚時か、離婚後間もない時期に契約しておいた方がよいでしょう。
(2)給料を差し押さえたのに相手方が退職した場合
先ほどもご説明したように、給料を差し押さえても元パートナーが退職してしまうと、その差押えの効力は消滅してしまいます。
この場合、新たな勤務先の給料や別の財産について改めて強制執行を申し立てる必要があるでしょう。
元パートナーから新たな勤務先を教えてもらえない場合は、改正民事執行法による「第三者からの情報取得手続」や「財産開示手続」を再度申し立てることになります。
もっとも、元パートナーが退職後すぐに別の会社で働いているとは限りませんので、2~3か月ほど時間を置いてから申し立てた方がよいでしょう。
(3)預金口座を差し押さえたのに残高が足りない場合
預金口座を差し押さえた場合は、給料を差し押さえた場合のように差押え先から毎月お金を払ってもらえるわけではなく、取り立ては1回きりとなります。
つまり、口座の残高が足りない場合には「回収不能」として差押え手続きは終了します。
その後に入金があっても、そのお金については新たに差し押さえない限り回収することはできません。
もし、預金口座を差し押さえたのに残高が足りなかった場合には、再度強制執行を申し立てることになります。同じ口座に対して何度申し立てても構いません。
ただし、元パートナーは一度差押えを受けると、新規に口座を作成してメインバンクをそちらに変更している可能性が高いです。
そのため、再度強制執行を申し立てる際には、やはり改めて「第三者からの情報取得手続」や「財産開示手続」を利用して財産調査を行いましょう。
7、養育費の強制執行には弁護士によるサポートが有効

この記事でご説明した手順に従えば、ご自身でも養育費の強制執行を行うことは可能です。
ただ、手続きは少し複雑ですので、慣れないと大変です。
正しくできたとしても、必要書類の取得や申立書・目録類の作成に手間取っているうちに差押えのタイミングを逃してしまうおそれもあります。
特に、1度差押えに失敗した場合には、元パートナーも「差押えで回収されまい」と考えてさまざまな防御策をとってくるので、2度目、3度目の差押えは難しくなる可能性が高いです。
そのため、養育費の強制執行をお考えなら、最初から弁護士に相談するのがおすすめです。
強制執行手続きに慣れた弁護士に相談すれば、どのような財産をどのようなタイミングで差し押さえれば養育費を回収しやすいのかについて、具体的にアドバイスしてくれます。
また、依頼すれば複雑な手続きはすべて弁護士が代行してくれますので、あなたは安心して養育費が回収されるのを待つことになります。
もし債務名義がなかったとしても、債務名義の取得から相談にのってくれることでしょう。
ぜひ、強制執行を申し立てる前に弁護士に相談して、アドバイスだけでも受けてみましょう。
養育費の強制執行に関するQ&A
Q1.養育費を払ってもらえないときは強制執行で回収できる?
未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取った親(親権者)は元パートナー(非親権者)に対して養育費を請求する権利があります(民法第766条1項、第877条1項)。
Q2.養育費の強制執行をする前にやっておかなければならないことは?
強制執行を申し立てるためには、その前に準備しておかなければならないことは以下の3つです。
- 債務名義を取得する
- 相手の居場所を確認する
- 相手の財産を把握する
Q3.養育費の強制執行を自分でやる場合の手順は?
養育費の強制執行を申し立てる方法と、差押えによって養育費を手にするまでの手続きは以下です。
- 必要書類をそろえる
- 強制執行申立書の作成・提出
- 裁判所による差押命令
- 差押え先から取り立て
- 裁判所への報告
まとめ
強制執行は未払いの養育費を強制的に回収できる強力な手段ですが、法律で定められた手順を踏む必要があります。
申し立てても確実に養育費を回収できるという保証はありません。強制執行で効率よく養育費を回収するには、コツがいります。
未払いの養育費を早期に回収できないと、生活に困ってしまう方も少なくないのではないでしょうか。
ですので、お困りのときはお早めに弁護士までご相談ください。
弁護士の力を借りて未払いの養育費を効率よく回収し、お子さまと一緒に安心して生活していきましょう。
















