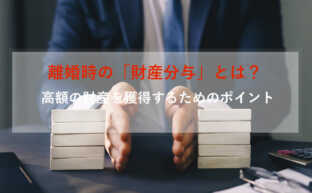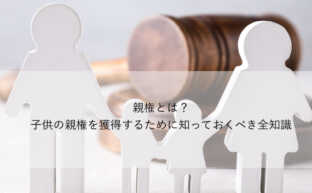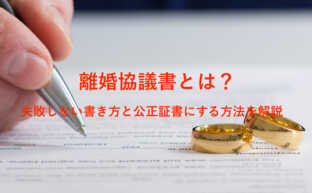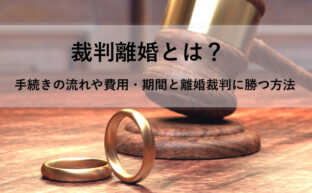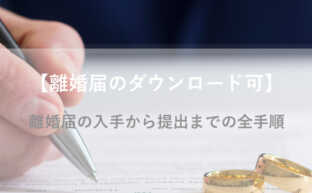離婚したい・・・
幸せな結婚をしたはずなのに、心の中で何度もこのようにつぶやいたことがあるのではないでしょうか。
一度は愛し合って結婚した相手であっても、一緒に生活していると様々なすれ違いが生じてくるものです。離婚したいと思ったことがある人は、数多くいるはずです。
しかし、いくら離婚したいと思っても、すぐに離婚できるものではありません。
慌てて離婚を切り出しても相手方は簡単には応じないでしょうし、離婚できたとしても不利な離婚条件を押し付けられてしまう可能性が高いものです。
理不尽な離婚を回避するためには、離婚を切り出す前にしっかりと準備をしておく必要があります。離婚後の生活のことも考えておかなければなりません。
さらに、離婚してから後悔することがないように、本当に離婚してよいのかについても、慎重に判断すべきでしょう。
そこで今回は、多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、
- 離婚したい全ての理由に共通する感情
- スムーズに離婚したい場合の離婚の準備
- 離婚したいことを切り出す方法
などについて解説していきます。
日頃離婚問題を解決している私どもの経験を踏まえて、「離婚をしたい」と思い立った時に知っておくべきことをまとめていますので、ぜひ参考になさってください。
目次
1、離婚したい!全ての理由に共通する◯◯感とは

あなたは、どのような理由で離婚したいと思われたのでしょうか。
なかには、「こんな理由で離婚してもいいのかな…」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
まずは離婚したい理由について解説します。
(1)離婚したい理由は主に12個
離婚したい理由は人によって様々ですが、主なものとして次の12個のものが挙げられます。
- 性格があわない
- 異性関係
- 暴力をふるう
- 酒を飲みすぎる
- 性的不調和
- 浪費する
- 病気
- 精神的に虐待する
- 家族をすててかえりみない
- 家族との折り合いが悪い
- 同居に応じない
- 生活費を渡さない
あなたが離婚したいと思われる理由も、おそらく、以上の12個のどれかに該当するのではないでしょうか。
実は、以上の12個は、家庭裁判所の離婚調停申立書に記載されているものです。
離婚調停を申し立てるときには、以上の中からどれかを選ぶことになります。
複数を選んでもかまいませんし、その他の理由がある場合には別途、理由を記載する欄もあります。
もし、「何となく離婚したい」と思われている方がいたら、一度、以上のリストも参考にしてなぜ離婚したいのかを考えてみましょう。
(2)全ての理由に共通する「否定感」
どの理由を選ぶ場合でも、心の奥底には「否定感」が横たわっているのではないでしょうか。
ここにいう否定感とは造語ですが、自分の存在を否定されているような気持ちを指しています。
以下のとおり、全ての理由について、「自分は否定されている」という共通性を見いだすことができます。あなたの場合も突き詰めていうと、このような否定感に苦しまれているのではないでしょうか。
①性格が合わない
何を言ってもあなたの主張を認めてもらえないことで、自分の存在を否定される気持ちになることでしょう。
②浮気
相手が自分以外の人を求めているという現状に、自分の存在を否定される気持ちになるはずです。
③暴力
暴力を振るうということは力をもって自分の言い分を通すということですから、あなたの存在が否定されていることに他なりません。
④酒を飲み過ぎる
酒を飲んでもシラフと変わらない場合は、問題になりません。
酒を飲むことで人格が変わる場合には、「性格が合わない」「暴力」「精神的虐待」などと同じような状況になるでしょう。
また、酒を飲み過ぎることで「浪費」「家庭を顧みない」「浮気」など別の問題につながることもあります。
⑤性的不調和
日本の民法では、結婚している人は配偶者とのみ性的関係を結ぶこととされており、他の人と性的関係を結ぶことは違法とされています。
そのため、配偶者との性的関係が満たされたものでなければ、存在を否定された気持ちになることでしょう。
⑥浪費
夫婦はお互いに協力して生活費の負担を分担しなければならないにもかかわらず、生きていくのに必要なお金を勝手に使われると、相手方はあなたのことを考えていないのだな、という考えに行き着きます。
⑦病気
病気そのものは責められないことが多いですが、「看病」という特殊な行動を事実上にせよ強制されることによって好きなことを制限されるため、存在を否定されているような感覚に陥ります。
⑧精神的虐待
精神的虐待は、まさに言葉をもって存在や人格を否定する行為です。
いわゆる「モラハラ」では、存在や人格を直接否定するような言葉を浴びせられるケースが多いです。
⑨家族を顧みない
仕事のしすぎ、遊びや趣味に没頭している、生活費を渡してくれない、など様々なパターンがありますが、家族を顧みない相手方に共通していることは、自分のことしか考えず、家族のことを考えていないということです。
家族にとっては、まさに存在を否定されている状態にあるといってよいでしょう。
⑩家族との折り合いが悪い
これで悩む場合、相手方は実家を優先しているケースがほとんどでしょう。
あなたのことよりも実家を優先されれば、存在を否定された気持ちになるのも無理はありません。
⑪同居に応じない
夫婦には法律上の同居義務がありますが、法律を持ち出さなくても、夫婦なら単身赴任など特別な事情がない限りは一緒に生活するのが当然のことでしょう。
そのような事情がないのに同居に応じないということは、一緒にいたくないということであり、あなたの存在が否定されているということでもあります。
⑫生活費を渡さない
「浪費」の場合と同様、生きていくのに必要なお金を渡してくれないということは、相手方があなたのことを考えていないということであり、存在を否定されています。
2、幸せな結婚をしたけど「離婚したい」と思ったら進めておくべき準備とは?

前項の解説を参考にされて「離婚したい」という決意が固まったのなら、離婚するための準備を始めましょう。
スムーズに離婚するために進めておくべき準備は、以下のとおりです。
(1)希望する離婚条件をしっかりと検討する
離婚する際には、様々なことを取り決めなければなりません。
どのような条件で離婚したいのかについては、離婚を切り出す前にしっかりと考えておくべきです。
検討が必要な離婚条件として、以下のものがあります。
①財産分与
離婚にあたっては、夫婦が共同で築いた財産を分ける「財産分与」を請求できます。
結婚後に作った預貯金や購入した不動産の名義がどちらか一方になっていても、基本的に財産分与の対象となります。
もっとも、マイナスの財産の方が多い場合、たとえば、夫婦の財産は自宅だけだが、オーバーローンであるといったようなときは、分けるべきものがないため、財産分与で金銭を得られることはありません。
財産分与について詳しいことは、「財産分与で離婚時に高額獲得する8つのポイントを弁護士が解説」をご覧下さい。
②慰謝料
離婚の原因が相手方にある場合は、慰謝料をもらうことができます。
しかし、慰謝料がもらえるような離婚の原因は限られます。
そもそも慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。
この慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するための損害賠償の性質を持っていますので、法律的な損害を加えたと言えるような事由(離婚原因)がなければいけません。
具体的には、不貞やDVなどです。
単なる性格の不一致では慰謝料をもらうのは難しいでしょう。
慰謝料について詳しくは、「離婚慰謝料請求の金額の相場と300万円以上もらう方法」をご覧下さい。
③年金分割
離婚にあたっては、将来もらう年金を分割してもらえます。
これは、年金をもらう段階で、婚姻期間に応じて相手方がもらうべき年金(いわゆる2階部分)の一部をこちらに振り分けてもらう仕組みです。
年金分割について詳しくは、「離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための全手順」をご覧下さい。
④親権
未成年のお子さまがいる場合には、離婚の際に父母のどちらか一方を親権者として決めなければなりません。
お子さまが小さい場合には、母親が親権者となるケースが多いのが実情です。
ただし、親権者を決める際には、あくまでも子どもを養育するためにどちらが望ましいかということが重視されますので、必ずしも母親が親権者になるとは限らないことに注意が必要です。
また、お子さまが15歳以上の場合には、お子さま自身の意思も重視されます。
親権について詳しくは、「親権とは?子供の親権を獲得するために知っておくべき8つのこと」をご覧ください。
⑤養育費
離婚してあなたが未成年のお子さまを引き取る場合には、相手方に対して養育費を請求できます。
養育費の金額は、子どもの年齢や人数宇、父母それぞれの年収を考慮して決められるのが一般的です。
養育費について詳しくは「養育費の相場はどのくらい?適正な養育費を獲得するための全知識」の記事をご参照ください。
(2)有利な離婚条件で離婚するための証拠を確保する
有利な離婚条件で離婚するためには、証拠が重要となることが多いです。
相手方の不貞やDVを理由に慰謝料を請求する場合なら、その事実を証明できる証拠を確保する必要があります。
不貞の事実を証明できる有力な証拠としては、2人でラブホテルに出入りする写真やメール・SNSでのやりとり、携帯電話の通話履歴、配偶者や不倫相手の発言を録音したものなどがあります。
DVの場合は、暴力を受けた場面を録画・録音したデータ、怪我をした場合の診断書や病院の領収証、日記などが主な証拠となります。
これらの証拠がなければ、相手方に事実を否定された場合に慰謝料をもらうことができなかったり、そもそも離婚が認められない可能性もあります。
財産分与や養育費を請求する場合にも、相手方に収入や資産を隠されると適切な金額を請求できなくなってしまいます。
そのため、離婚を切り出す前に相手方の給与明細や通帳をコピーしたり、その他の財産についても証拠となる書類をコピーしたり、現物を写真に撮るなどしておきましょう。
(3)離婚後の生活設計を考えておく
離婚した後は経済的に自立して生活していかなければなりませんので、離婚後の生活設計も考えておきましょう。
具体的にはまず、前述した財産分与や慰謝料、年金分割、養育費など相手方に請求できるお金はしっかりと獲得できるように準備をしておくことです。
また、離婚をすれば当然別居となりますので、離婚後の住まいも早期に確保しましょう。
専業主婦の方はできるだけ早めに仕事を探した方がよいでしょうし、現在仕事をしている人でも、より収入の高い職場への転職を検討した方がよいかもしれません。
さらに、いわゆる「母子手当」など、公的な扶助がもらえる可能性がありますので、国や自治体からどのくらいのお金がもらえるのかについてもしっかりと調べておきましょう。
この点については、後ほど「8、離婚後の生活のために知っておきたい補助金・助成金」でご説明します。
(4)離婚後の精神的な自立も重要!
これまで知らず知らずに配偶者を頼っていたことがあったことを否めない方も少なくないでしょう。
しかし、離婚後は一人で全てに対応しなければなりませんから、精神的な自立も重要になります。
上手な離婚の仕方については、こちらの記事もご覧ください。
3、離婚したいことを切り出す方法は?

準備が整い、いざ離婚の話を切り出すにはどのようにすればいいでしょうか。
これは、別居前か別居後かによって変わってくるでしょう。
(1)別居前に切り出す場合
別居前であれば、直接相手に話をすることになると思いますが、一番重要なことは、感情的にならないことです。
感情的になってしまうと、つられて相手も感情的になり、なかなか話が進みません。
切り出す前に、伝えたいことをリストにしておくなどの工夫で感情的にならないように心がけましょう。
手紙を書いて渡すのも良い方法です。
(2)別居後に切り出す場合
別居後は、離婚を切り出すことに対する心理的なハードルも低くなりますので、比較的冷静に切り出しやすくなるでしょう。
基本的には、電話でもメールでも手紙でも、ご自身が伝えやすい方法で伝えれば大丈夫です。
ただし、慰謝料を請求するには「事実を知ってから3年以内」という期限があることに注意が必要です。
そのため、別居してからある程度の期間が経過している場合は、3年以内に請求したという証拠を残すために、最初だけでも内容証明郵便を利用して離婚と慰謝料などを求めるようにしましょう。
4、離婚したい場合の離婚手続き〜相手の反応によって手続きは変わる!
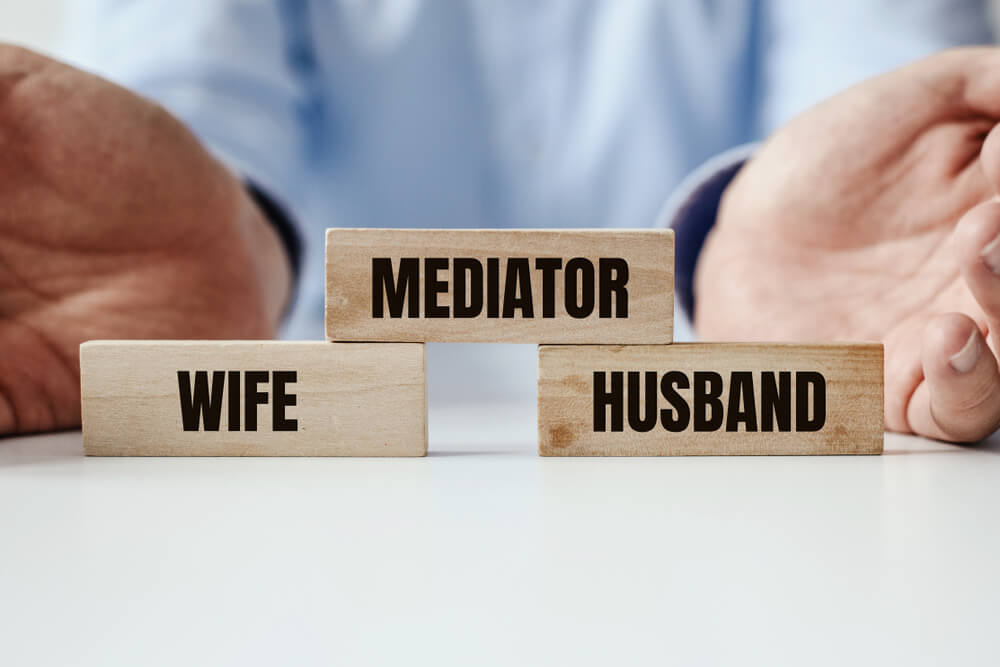
離婚を切り出した後の相手方の反応については、様々なパターンが予想されます。
いずれにしても、相手方の反応によって離婚手続きは以下のように変わります。
(1)相手方が離婚に応じれば協議離婚
相手方も離婚を望んでいた場合や、そうではなくても話し合いによって離婚に応じた場合は、離婚届を提出することで離婚できます。
このように、夫婦の話し合いで離婚が成立することを「協議離婚」といいます。
協議離婚をする場合には、離婚条件についても冷静かつ慎重に話し合って取り決めましょう。
譲れる部分は譲った方がよいですが、早く離婚したいからといって譲歩しすぎると離婚後に後悔してしまう可能性が高いので注意しましょう。
離婚条件についても話し合いがまとまったら、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書は離婚の条件について合意したことについての覚書です。
離婚協議書を作成することで、紛争の蒸し返しを防ぐことができますし、万が一条件が履行されないときの備えにもなります。
離婚協議書には特に決められた形式があるわけではありませんが、当事者双方の署名押印、作成年月日は入れるようにしましょう。
せっかく離婚協議書を作っても署名押印がないと相手に取り決めた内容を実際に求めることができないケースがあります。
また、費用はかかりますが、離婚協議書を作る場合、公正証書にしてもらうことをお勧めします。
公正証書とは公証役場で公証人が作成するものです。
公正証書は判決と同様の強い法的効力を持っていますので、万が一不履行になった場合も比較的容易に差し押さえができるなどメリットが大きいものです。
詳細については、「離婚協議書とは?失敗しない書き方と公正証書にする方法」をご覧下さい。
(2)相手方が離婚に応じなければ離婚調停
夫婦間での話し合いがまとまらず、相手方が離婚に応じない場合には離婚調停を申し立て、調停委員を介して離婚に向けた話し合いを行うことになります。
離婚調停は、基本的には話し合いの手続きではありますが、調停が整わなかった時は裁判や審判という手続きに移行することがありえますから、これらの手続きを見越した準備を行うことが必要です。
具体的には、あなたの言い分を家庭裁判所に信用してもらえるように、詳細な事実に基づいて主張を組み立てて、それらの事実を証明できる証拠を準備することが重要になります。
したがって、調停を申し立てる際には、あるいは申し立てられた場合には速やかに弁護士にご相談されることをおすすめします。
また、離婚調停を申し立てる際に既に別居されている場合には、婚姻費用の請求に関する調停も併せて申し立てるようにしましょう。
申し立てた月から一定の生活費を相手方から受け取れるようになります。
5、離婚したいのにスムーズに離婚協議が進まない場合のテクニック

離婚協議がスムーズに進めばよいですが、現実にはもめてしまうケースも多いものです。
ここでは、そんなときに活用できるテクニックをご紹介します。
(1)離婚自体を拒まれる場合
相手方に離婚自体を拒まれる場合は、離婚条件について譲歩してみるのもいいですが、どれだけ譲歩しても絶対に離婚しないという相手方もいます。
また、譲歩しすぎると離婚後に後悔することにもなりかねません。
離婚を拒む相手方に対して最も有効な方法は、別居をすることです。
別居をすることでお互いに「相手のいない生活」を定着させ、徐々に離婚に向かうことが可能になる場合もあります。
また、別居すること自体、夫婦関係が破たんしている証となります。
そのため、別居期間が長くなればなるほど、調停や裁判で離婚が認められる可能性も高くなります。
(2)親権を互いに譲らない場合
相手方が親権を譲らない場合も、まずは離婚条件で譲歩してみたり、面会交流に積極的に応じることを約束するなどして交渉することが考えられます。
それでも親権を譲らない相手方に対して最も有効な方法は、やはり、あなたが子どもを連れて別居をすることです。
調停や裁判では、「現状維持の原則」といって、父母が離婚する際にはできる限り子どもの生活環境に大きな変化を与えないように、原則として現に子どもを養育している側が親権者に指定されます。
(3)財産分与や慰謝料、養育費など金銭面でまとまらない場合
金銭面で話し合いがまとまらない場合は、柔軟な支払い方法を交渉してみましょう。
財産分与や慰謝料などはまとまった金額を請求する場合が多いため、相手方も「そんな金額は払えない」ということになりがちです。
そこで、分割払いを提案してみれば、ある程度大きな金額でも合意できる場合があります。
ただし、その場合は長期間の支払いを確保するために、公正証書で離婚協議書を作成しておくことが重要です。
一方、養育費については、逆に一括払いを提案してみてもよいでしょう。
例えば、毎月○万円を支払ってもらう代わりに、住宅を譲渡してもらうということが考えられます。
住みなれた家に離婚後も家賃なしで住み続けることができれば、子どもの養育も楽になることでしょう。
ただし、住宅ローンが残っている場合、相手方の支払いが滞れば住み続けられなくなるということも頭に置いておかなければなりません。
以上のように離婚協議を進めるテクニックもありますが、どうしても協議が進まない場合にはある程度のところで打ち切って、離婚調停を経て離婚裁判に進んだ方がよい場合もあります。
離婚裁判では、あなたの言い分に筋が通っていて証拠も揃っていれば、あなたの主張を全面的に認めてもらうことも可能になります。
6、離婚届の書き方・出し方

協議離婚の場合も、調停離婚や裁判離婚の場合も離婚が決まったら離婚届を提出する必要があります。
協議離婚の場合は双方が記入しますが、調停離婚と裁判離婚の場合は一方だけが記入して提出できます。
離婚届の用紙は、市区町村の役所の窓口で受け取ることができます。
書き方に不明点があれば窓口の方に質問すればすぐに教えてもらえます。
詳しくは「【離婚届のダウンロード可】離婚届の入手から提出までの全手順」をご覧下さい。
7、離婚にはリスクや心身の疲弊も!修復できないか再度よく考えてみる

離婚したいと思っても、実際に離婚するには様々なリスクや心身の負担が伴います。
「こんなことなら離婚しなければよかった」と後悔しないためにも、離婚を切り出す前にいま一度、修復できないかをよく考えてみるのも大切なことです。
(1)離婚で発生する様々なリスク
離婚をしたら、まず金銭的に苦労するリスクがあります。
特に専業主婦の方については、離婚後の収入が全くなくなることもあるでしょう。
さらに、離婚をすれば住まいも別に探さなければなりませんが、これにもまとまった資金が必要になります。
他方、男性は、離婚にあたって財産分与を求められたり、離婚後養育費を支払わなければならないなど、思っている以上に経済的な負担が生じる可能性があります。
(2)離婚は心身の疲弊が伴う
離婚の手続きはスムーズに進むとは限りません。
話し合いがまとまらないと調停、裁判と移行しなければならず、離婚までに数年かかるということもままあることです。
また、離婚は当事者だけの問題ではなく、お子さんやときには両家の親族をも巻き込んだ大きな紛争になる可能性も十分に考えられます。
これらに対応する心理的、肉体的な負担は馬鹿になりません。
このように、離婚には様々なリスクや手続きを進める上での心身の疲弊が想定されます。
このようなリスクや心身の疲弊といった負担を負ってまで離婚を進める覚悟はあるのか、一度しっかりと考えられた方がいいでしょう。
これらについて受け入れるのが難しいということであれば、修復の方法はないか検討する方がいいでしょう。
8、離婚後の生活のために知っておきたい補助金・助成金

前記「2(3)」でも少しお話しましたが、離婚後には母子手当など公的扶助を得られることがあります。
特にシングルマザーになる場合には活用することをお勧めします。
公的な補助金・助成金のうち代表的なものは次のとおりです。
(1)児童手当
児童手当とは、 0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当です。
申請先は各市区町村の役所です。支給される金額は以下の通りです。
3歳未満の場合:月額 10,000円
3歳以上の場合:第1子と第 2子は月額 5,000 円、第 3子以降は月額10,000 円
(2)児童扶養手当
離婚などによって父母いずれかからしか養育を受けられない子どもを対象とする手当です。 申請先は各市区町村の役所です。
金額については以下の通りです(2020年度の金額です)。
①子どもが一人の場合
全部支給の場合
月額 43,160円
一部支給の場合
所得に応じて月額 43,150円~10,180 円
※全部支給か一部支給かも所得によって決まります。
②子どもが二人の場合
対象児童が2人の場合、上記金額に全部支給の場合は10,190円、一部支給の場合は10,180円~5,100円が加算されます。
③子どもが三人以上の場合
対象児童が 3人以上の場合、上記金額に1人につき、全部支給の場合は6,110円、一部支給の場合は6,100円~3,060円が加算されます。
(3)児童育成手当
児童育成手当とは、18歳の3 月31日までの子どもを養育する一人親を対象とする手当です。
申請先は各市区町村の役所です。
金額は、月額 13,500円です。
ただし、所得制限があります。
(4)母子家庭等の住宅手当
母子家庭等の住宅手当は各自治体(市区町村)が独自に設けている母子家庭等への支援制度です。
すべての自治体で実施されているわけではありませんが、多くの自治体で何らかの支援が行われています。
多くの場合、20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭に対して家賃の一部が給付されます。
申請先は各市区町村の役所です。
支給条件や金額は各役所にお問い合わせ下さい。
(5)ひとり親家族等医療費助成制度
ひとり親家族等医療費助成制度は、母子家庭等の医療費の一部を助成する制度です。
受給条件や受給額等詳細は各市区町村の役所にお問い合わせ下さい。
(6)生活保護
離婚後にどうしても生活費が足りない場合は、生活保護を受給することも検討してみましょう。
仕事をしていたり、元配偶者から養育費を受け取っている場合でも生活保護は受給できます。
ただし、給料や養育費として受け取っている金額は、保護費から差し引かれます。
相談・申請先はお住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当です。
9、今すぐに離婚したい場合は弁護士へ相談を

離婚するためには、様々な準備をした上で、離婚後のお金のことも考えておくことが重要です。
それはわかってはいても、「今すぐに離婚したい!」という方も少なくないことでしょう。
いったん離婚したいと思うと、すぐにでも相手方と縁を切りたい、顔も見たくない、話したくないという気持ちになるのも無理はないと思います。
慌てて離婚することはおすすめできませんが、今すぐに相手方との接触を断って離婚の手続きを進めることができる方法はあります。
それは、弁護士に相談し、依頼することです。
そうすれば、弁護士があなたの代理人として相手方とのやりとりをすべて代行します。
したがって、あなた自身はもう、相手方と接触する必要がなくなるのです。
法律のプロである弁護士が味方になれば、有利な離婚条件を獲得しやすくなりますし、協議離婚書の作成や調停・裁判といった面倒な手続きもすべて任せることができます。
今すぐ別れたいなら、弁護士を味方につけることをおすすめします。
離婚事件について詳しい弁護士の探し方については、「離婚に強い弁護士に出会うために知っておくべき7つのこと」をご覧下さい。
離婚したい場合に知っておきたいことまとめ
以上、離婚に向けては意外にたくさんのことを知っておかなければならいので驚かれた方も多いでしょう。
しかし、離婚は人生の重大な決断ですので、このページを参考にしていただきしっかりと準備をして進めることをお勧めします。
最近では、離婚問題の相談について初回の相談料を無料としている法律事務所もあります。
費用をかけずに法的なアドバイスが受けられるので、一度弁護士にご相談されてみるのもよいでしょう。