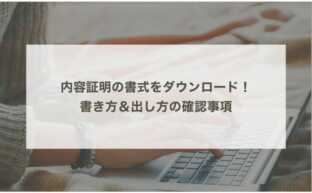発注者から工事代金を回収する方法は、基本的には一般的な債権回収のノウハウと同じです。
そこで今回は、
- 未払いの工事代金を回収する方法
- 工事代金が未払いとなるケース
- 工事代金の時効に関する注意点
などについて詳しく解説していきます。
目次
1、未払いの工事代金を発注者から回収する方法
早速、未払いの工事代金を発注者から回収する方法として、どのようなものがあるのかをみていきましょう。
債権を回収するためには、以下の順で請求手続きを進めていくのが通常です。
(1)催促して交渉する
工事代金の支払期限が過ぎても支払われない場合には、まず相手方に催促をします。もし、相手方から「支払うお金がない」と言われた場合は、可能な範囲で支払期限の延期や分割払いなどに応じるのもよいでしょう。
交渉によって円満に解決できれば、
- 手間
- 時間
- 費用
の負担を軽減できますし、最も望ましい解決方法といえます。
相手方が反応しない場合は、繰り返し催促をすることが必要です。電話や文書の送付だけでなく、訪問による催促も行ってみましょう。
早朝や深夜に訪問したり、脅迫的な口調で催促することは慎まなければなりませんし、相手方から退去を求められたり、訪問を拒絶されたような場合には従うべきです。ですが、粘り強く、電話、書面、訪問等、許容される範囲内で請求して心理的なプレッシャーをかけることで、支払に応じてくれる場合もあるでしょう。
(2)弁護士名義で内容証明郵便を送付する
催促をある程度繰り返しても支払おうとしない相手方に対しては、次のステップとして、弁護士から弁護士の名前で内容証明郵便を送付することが有効です。
弁護士から請求してもらうことでこちらの本気度を伝えることができますので、相手方への心理的なプレッシャーはさらに強いものとなります。
相手方が「支払わなければ裁判を起こされて大変なことになる」と考えて、早期に支払ってくることが期待できます。
(3)支払督促を申し立てる
支払督促とは、簡易裁判所に申し立てることにより、一応の証拠書類で債権債務の存在が認められれば、裁判所が相手方に支払いを命じる手続きのことです。
相手方が弁護士からの内容証明郵便を受け取っても反応しない場合は、裁判手続きが必要となりますが、支払督促は簡易な手続きで利用できますので、相手方が根拠もなく支払を拒んでいるような場合には、支払督促を申し立てることも考えられます。
裁判所から送達された支払督促が相手方に到達した後、2週間以内に相手方が異議を申し立てなければ支払督促が確定し、強制執行の申し立ても可能となります。
なお、相手方が期限までに異議を申し立てた場合は、通常の訴訟手続きに移行します。
(4)裁判を起こす
裁判(通常訴訟)で未払いの工事代金を請求することも、もちろん可能です。
裁判を起こすには、訴状を作成し、工事代金の請求権が発生していることを証明できる証拠(工事請負契約書など)と一緒に裁判所へ提出します。
相手方が裁判に出頭せず、答弁書も提出しない場合は、訴状に記載した主張をすべて認める内容の判決が言い渡されます。
相手方が反論を記載した答弁書を提出するなどして争ってきた場合は、双方が主張と証拠を出し合い、裁判期日を重ねていきます。適切な主張を行い、その主張を証拠で的確に証明できた側が最終的に勝訴することになります。
工事代金の未払いで相手方が争ってくる場合、建築物の欠陥や手抜き工事などを主張してくる可能性が高いです。
そのような建築紛争に発展した場合は、自己の主張を立証するハードルが高くなり、裁判の期間も長引く傾向があることに注意が必要です。
(5)強制執行で回収する
裁判手続きを経ても相手方が未払いの工事代金を支払わない場合には、強制執行を申し立てて回収することが可能です。
強制執行とは、債務名義がある場合に債務者の財産を差し押さえて、それでも債務者が支払わない場合には差押物件を換価し、その中から債権を回収することができる手続きです。
債務名義とは、債権債務の存在が公的に証明された書類のことであり、確定した支払督促や判決書などがこれに当たります。
強制執行を申し立てるためには、差し押さえ可能な相手方の財産を把握する必要があります。未払いの工事代金を回収するためには、工事した建築物の差押が考えられますが、住宅ローンの抵当権がすでに付いているといった場合には、差し押さえて換価しても抵当権が優先してしまいます。その他に差し押さえやすい相手方の財産としては、給与債権や預金口座などがあります。
2、工事代金が未払いとなるケース
工事代金が未払いとなる場合、どのような理由が考えられるのでしょうか。理由に応じて債権回収のアプローチが変わってくることもあるので、未払いの理由を把握することは大切です。
一般的に、工事代金が未払いとなりやすいのは以下のようなケースです。
(1)発注者の資金繰りが悪化した
発注者が、工事を発注する際には支払い可能と判断していても、その後に資金繰りが悪化して工事代金を支払えなくなるというケースがあります。
個人の施主の場合は、住宅ローン等の審査がスムーズに通らず、予定どおりの融資を受けられないといった事態も考えられます。
このような場合には、発注者が破産などの倒産手続きをとる前に、速やかに工事代金を回収することが重要となります。
状況によっては、交渉の上で支払期限の延期や分割払いなどに応じるのもよいでしょう。ただし、長期間の分割払いに応じると、途中で支払いが途絶えてしまう可能性もあります。できる限り早期に工事代金を回収することを第一に考えるべきです。
(2)工事の内容に発注者が納得していない
発注者が完成した建築物の引き渡しを受けても、
- 建築物に欠陥がある
- 仕上がりが予定と違う
などと、工事内容に関するクレームを述べて工事代金の支払いを拒むケースもあります。
本当に欠陥がある場合には補修工事で対応することになります。
ただ、本当は欠陥などないにもかかわらず、資金繰りが悪化したために支払期限の延期や工事代金の減額を狙って、工事内容に関するクレームを述べてくるようなときには、早期に検査を実施した上で、補修を要する欠陥がなければ速やかに債権回収の手続きを進めていくべきだといえます。
(3)追加工事の代金に争いがある
建築工事では、当初の予定にはなかった追加工事が行われることもよくあります。追加工事が行われると多くの場合には工事代金が増額されますが、発注者が最終的な金額に納得できない場合には未払いとされることがあります。
追加工事を行う際には、発注者と改めて十分な打ち合わせを行い、見積書や変更契約書も作成しておくべきです。これらの手続きに万全を期していれば、追加工事の代金を巡る争いは起こらないはずです。
しかし、現実には納期の問題もあるため、追加工事については口頭の説明と口約束のみで済ませたり、書類を作成したとしても簡素で曖昧な内容の書類のみで、工事が進められることも少なくありません。
その場合には、工事完成後に発注者から
- 「そんな費用がかかるとは聞いてない」
- 「追加工事の必要はなかった」
などと主張されることがあります。
見積書や契約書がなければ、追加工事の必要性と適正な追加工事費用を立証することが難しくなる可能性もあります。
(4)元請業者が下請代金を支払わない
下請け業者の場合は、元請業者が下請代金を支払ってくれないという問題に悩まされることがあります。
その理由はさまざまであり、元請業者の資金繰りが悪化するケースもあれば、施主が工事代金を支払わないことを理由に下請代金も未払いとされるケースもあります。
この場合の対処法は、後ほど「4」で詳しく解説します。
3、工事内容や追加工事の代金に争いがあるときの対処法
ここからは、発注者が工事代金を支払わない場合の対処法をケース別に解説していきます。
発注者の資金繰りが悪化した場合の対処法は、前記「1」でご紹介したとおりです。
ここでは、工事内容や追加工事の代金に争いがあるときの対処法についてご説明します。
(1)工事が完成すれば代金請求は可能
前記「2」(2)でもご説明しましたが、請負契約では仕事を終了すれば報酬の請求が可能ですので、建築工事を請け負った場合は、工事が完成して引渡を行えば工事代金を請求できます。
まずは発注者と工事代金の支払いについて交渉すべきですが、発注者が単なる不満で頑なに支払いを拒むときは、前記「1」の各手順を進めていくとよいでしょう。
すなわち、弁護士に依頼して弁護士から内容証明郵便を送付し、それでも支払わなければ支払督促または裁判を経て、最終的には強制執行で相手の財産を差し押さえて工事代金を回収することが可能です。
(2)住宅性能評価制度を利用する
住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、住宅の性能について国に登録された第三者機関が、国土交通大臣の定めた共通基準をもとに評価する制度です。
住宅の施工前に設計図書を確認する「設計住宅性能評価」と、施工中および完成後に確認する「建設住宅性能評価」の2種類の評価があります。
この制度は住宅取得者を保護するために創設されたものですが、第三者機関による評価の結果、住宅に欠陥がないという内容の評価書を取得することができれば、発注者からのクレームを封じることが可能となります。
施工業者と発注者の双方にとってメリットがありますので、この制度の利用も検討するとよいでしょう。
(3)裁判外紛争処理手続(ADR)を利用する
未払いの工事代金を請求する裁判で建築紛争に発展した場合、裁判が終了するまでに2年以上を要するケースも珍しくありません。当然ながら、裁判が終了するまでは工事代金を支払ってもらうことはできません。
ですが、建築紛争の解決手段には、より簡易的なものとして「裁判外紛争処理手続(ADR)」もあります。
裁判外紛争処理手続とは、民事上のトラブルについて、訴訟手続によらずに中立公正な第三者が関与して調停やあっせんなどによる解決を図る手続きです。
この手続きには強制力がないものの、裁判よりも
- 手間
- 時間
- 費用
の負担が軽く、かつ、柔軟な形で解決できる可能性があります。
建築紛争に関する代表的な裁判外紛争処理手続機関として、以下のところが挙げられます。
- 建設工事紛争審査会
- 日本不動産仲裁機構
- 弁護士会の住宅紛争審査会
早期の解決を望む場合には、上記のいずれかの機関に問い合わせてみるとよいでしょう。
4、元請業者が下請代金を支払わないときの対処法
次に、元請業者が下請代金を支払わないときの対処法をご説明します。
(1)元請業者へ直接請求する
下請け業者と施主は直接の契約関係にありませんので、下請代金を請求する相手は元請業者です。
元請業者から下請け業者への下請代金の支払期限は、建設業法で次のとおり定められています。
- 原則…元請業者が施主から工事代金を受け取ったときから遅くとも1ヶ月以内(同法第24の3第1項)
- 元請業者が特定建設業者の場合…下請け業者が元請業者に対して、完成した目的物の引き渡しを申し出た日から遅くとも50日以内(同法第24条の6第1項)
特定建設業者とは、下請け工事1件の工事代金が4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)となるケースにおける元請業者のことです。
元請業者が建設業法の定めに違反して下請け代金を支払わない場合には、前記「1」の方法で元請業者に対して支払いを請求していくことになります。
元請業者が特定建設業者に該当しない場合で、施主が工事代金を支払わない場合には、基本的には元請業者が前記「1」の方法で施主に対して支払いを請求するように催促することになります。
元請業者が裁判を起こした場合は、その裁判に参加して元請業者を補助することも可能です(民事訴訟法第42条)。
(2)行政庁に勧告を求める
特定建設業者に該当する元請業者が下請代金を支払わない場合には、行政庁の勧告によって救済されることがあります。
建設業法第41条2項では、下請け業者が当該工事のために使用している労働者に対して賃金の支払いを遅滞した場合には、国土交通大臣または都道府県知事(当該特定建設業者の許可をした者)が、当該特定建設業者に対して、賃金相当額を立て替え払いすることなどを勧告することができると定められています。
したがって、下請代金が支払われないために従業員への給料が支払えないような場合には、国土交通省または都道府県庁の担当課に勧告を申し出ることによって、給料相当額の立て替え払いを求めることができます。
5、工事代金の時効に注意しよう
工事代金の請求権には消滅時効があります。時効が完成してしまうと、請求しても支払ってもらえなくなるので注意が必要です。
(1)工事代金の時効期間
工事代金の時効期間は5年です(民法第166条1項1号)。
時効期間の起算点は原則として工事が完成した日の翌日ですが、契約で、請負代金をいつから請求できるか、別の定めをしている場合はその日の翌日となります。
2020年3月31日までに請負契約を締結した場合は、旧民法の規定が適用されますので、時効期間は3年となります。
この期間内に工事代金を回収するか、または次にご説明する方法で時効期間をリセットする必要があります。
(2)時効期間をリセットする方法
時効期間が経過する前に一定の行為をしておけば、時効の完成を猶予したり、それまでに進行していた時効期間をリセットすることができます。時効期間がリセットされると、そのときから時効期間が改めて進行を始めます。これを時効の更新といいます。
時効の完成猶予や更新となる行為は、主に以下のとおりです。
- 裁判で請求する
- 支払督促を申し立てる
- 仮差押えを申し立てる
- 発注者と交渉し、支払いを約束する書面にサインをしてもらう
- 発注者に未払いの工事代金の一部でもよいので支払ってもらう
仮差押えとは、裁判の後に差し押さえるべき相手方の財産を保全するために、裁判をする前に行う裁判上の手続きです。
なお、発注者に対して支払いを催告すると、6ヶ月間だけ、時効の完成が一時猶予されます。
催告とは、裁判や支払督促によらず、支払いを請求する行為のことを意味します。通常は、催告した事実とその時期に関する証拠を残すために、配達証明を付けて内容証明郵便を送付します。
時効完成が間近に迫っているときは、とりあえず発注者宛に配達証明付で内容証明郵便を送付し、それから6ヶ月以内に裁判または支払督促を申し立てることで時効の完成を阻止することができます。
債権回収と時効の問題については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
6、工事代金の未払いを防止するためにできること
工事代金が未払いになってしまうと、回収できるとしても
- 手間
- 時間
- 費用
の負担が重くなることが少なくありません。できる限り、工事代金の未払いは防止したいところです。
そのためには、契約時に以下のポイントに注意しましょう。
(1)契約書を確実に作成する
まずは、契約書を確実に作成することが極めて重要です。
中小規模の建設会社や、個人の工務店などでは契約書を作成しないか、簡易な契約書しか作成しないところもあるようです。しかし、契約書を的確に作成しなければ、トラブルの元となります。
そもそも、建設工事の請負契約については、契約書を作成して相互に交付しなければならないことが建設業法第19条1項で定められています。
同項には、契約書に記載すべき事項も定められていますので、必ず漏れのない契約書を作成し、相手方にも交付しましょう。
当初の契約だけでなく、追加工事の際にも契約書を作成・交付すべきです。
この作業を怠ると、建物の完成後に発注者から
- 「仕上がりがイメージと違う」
- 「追加工事は必要なかった」
などのクレームとともに、工事代金の未払いを招きやすくなります。
(2)見積もりを正確に行う
見積もりについても、当初の契約段階ではもちろんのこと、追加工事の際にも正確に行い、発注者に見積書を交付して十分に説明し、納得を得ることが重要です。
建設工事では、どうしても実際の工事代金が当初の見積額と異なってくることもあるかと思います。
しかし、大雑把な見積もりでは、完成後に発注者から「こんなに費用がかかるはずはない」といったクレームとともに、工事代金の未払いを招きやすくなります。可能な限り、正確で具体的な見積もりを出すようにしましょう。
なお、建設業法では、契約前の見積書の交付については、注文者から請求があったときにのみ見積書を交付すればよいこととされています(同法第20条2項)。しかし、行き違いによるトラブルを回避するためには、見積書を交付して説明することを徹底した方がよいでしょう。
(3)前払いや出来高払いを採用する
工事の完成後に代金を一括で支払ってもらうのではなく、前払いや出来高払いで契約すれば、工事代金の取りっぱぐれをある程度は防止することができます。
前払いや出来高払いを採用する場合は、支払時期と方法を契約書に記載する必要がある(建設業法第19条1項5号)ことにご注意ください。
7、工事代金の未払いが発生したら弁護士に相談を
工事代金が未払いとなっても、最終的には裁判と強制執行で回収できます。しかし、裁判で建築紛争に発展すると回収するまでに長期間を要することもあります。
そのため、工事代金が未払いとなった場合には、できる限り建築紛争に発展する前に、発注者との交渉によって回収することが望ましいといえます。
ただ、支払いを拒む発注者との交渉は容易でないことも少なくありません。スムーズに交渉を進めるためには、弁護士に依頼することが得策です。弁護士が専門的な観点から冷静に交渉することで、早期の解決が期待できます。
発注者が交渉に応じない場合でも、内容証明郵便の送付から支払督促や裁判や強制執行手続きまで、弁護士に任せることができます。裁判で建築紛争に発展した場合も、弁護士の全面的なサポートが受けられます。
困ったときは、まず弁護士に相談し、状況に応じて適切な対処法を選択することをおすすめします。
まとめ
工事代金は安価なものではありませんので、未払いが発生すると業者にとっては死活問題となることもあります。多くの場合は、早期解決がポイントとなることでしょう。
発注者に催促しても「払う・払わない」の押し問答になると、時間だけが過ぎていくことになりがちです。「払いたくても払えない」と言われる場合も同様です。
そんなときは、弁護士に依頼して請求手続きを粛々と進めることが得策です。
トラブルが長引く前に、弁護士に相談してみることをおすすめします。