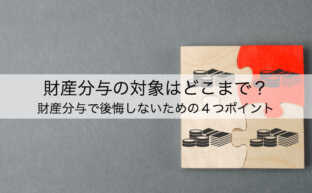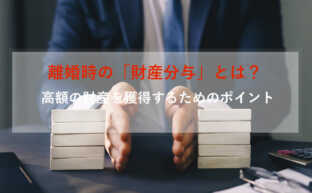離婚を決断すると、愛しいペットの置かれる状況は気になることでしょう。
通常、離婚後にペットはどちらが引き取るのか、引き取れない場合は再会できるのか、そしてペットの養育権をどのように決定すべきか、といった疑問が浮かびます。
この記事では、離婚とペットに関する問題について詳細に説明します。離婚後にペットを引き取る方法、面会交流や養育費の可能性、そしてベリーベスト法律事務所の弁護士が実際の解決事例を交えて解説します。
離婚とペットに直面している方々にとって、この記事が有用で、問題解決の手助けとなることを願っています。
目次
1、離婚時のペットの存在-法律ではどうなっている?
離婚の際のペットの扱いは気になるところ。
子どものように可愛がっていても、法律上、人間の子どもとは別の扱いです。
法律ではペットの扱いはどうなっているのでしょうか。
(1)ペットは家族?-「子ども」とは異なる
動物は、法律上は「物」として扱われます。
愛するペットも残念ながら「物」であり、「子ども」とは異なるのです。
どんなに愛情を注いで我が子同然に接していても、法律上の「家族」として扱われることはありません。
したがって、離婚時に夫婦のどちらがペットを引き取るかという問題は、子どもの「親権争い」とは根本的に異なるということを、まずご理解ください。
(2)ペットは財産分与の対象となる
では、離婚時にペットはどのような扱いになるのかというと、財産分与の対象となります。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同して築いた財産を、離婚時に分け合うことです。
ペットも法律上は財産分与の対象となる物ですので、財産分与でどちらが所有権を取得するかという問題となります(もっとも、婚姻前から飼っていたのであれば財産分与の対象とはならず、離婚後は婚姻前の飼い主に帰属することになります。
2、離婚時にペットの引き取り権を決める際の判断基準
離婚時に夫婦の双方がペットの引き取りを希望する場合、財産分与の問題となりますので、基本的には話し合って決めることになります。
話し合いがまとまらない場合は調停や裁判で決めることになりますが、その際には以下の要素を総合的に考慮して決められます。
(1)どちらになついているか
第一のポイントは、ペットがどちらになついているかという点です。
なついていない側にペットを取得させると飼育放棄のリスクが高く、なついている側の方がスムーズにペットを飼育できると考えられます。
そのため、当然ながら、なついている側が有利になります。
(2)どちらが主に飼育してきたか
どちらが主にペットを飼育してきたかという点も、重要な判断要素です。
これまでの飼育実績は、ペットに対する愛情や飼育能力の表れと考えられます。
多くのケースでは、主に飼育してきた方にペットもなついているでしょうから、その場合にはかなり有利になります。
ただ、一応の飼育はしていても世話が不十分であった場合には不利となる可能性もあります。
虐待の傾向が見られるような場合には、ペットを取得することは難しいでしょう。
(3)離婚後の飼育環境はどちらが整っているか
現実的な問題として、離婚後の飼育環境が整っているかどうかも重要です。
たとえば、婚姻中は一戸建ての住宅でペットを飼育していたものの、離婚後に引っ越す(あるいは別居時に引っ越した)マンションがペット不可の物件であれば、飼育環境が整っているとはいえません。
ペットをスムーズに飼育できる環境が整っていない場合は、飼育放棄のリスクがあると考えられるので、ペットを取得するのは難しいと言えます。
3、離婚時のペットの引き取り権を決める方法
次に、離婚時にペットの引き取り権を決めるための具体的な方法を解説します。
(1)よく話し合って決めるべき
ペットの引き取りは、第一に当事者でよく話し合って決めるべきことです。
話し合いにおいては、感情ばかりを主張するのではなく、どちらが引き取るのがペットにとって幸せかを考えることがポイントです。
たとえば、幼い子どもがいる夫婦の場合、妻が子どももペットも引き取るとなると、子どもの養育に手一杯でペットの世話にまで手が回らないということも考えられます。
逆に、夫がペットを引き取る場合でも、残業や休日出勤が多くて散歩もままならないようでは、ペットにとって幸せとはいえないでしょう。
(2)話し合いがまとまったら必ず書面化を!
話し合いがまとまったら、口約束だけで終わらせるのではなく、合意した内容を速やかに書面化しておきましょう。
書面を作成して証拠化しておかないと、後で「言った・言わない」のトラブルが発生するおそれがあるからです。
離婚時のペットの引き取りについて合意できた場合に作成すべき書面は、「離婚協議書」です。
離婚協議書は、公正証書にすることをおすすめします。
公正証書にしておけば、もしも相手が約束を守らなかった場合に、裁判を起こすことなく強制執行できるだけの効力があるからです。
なお、弁護士に依頼すれば、文面の作成から公証役場への案内まで、すべての面倒な作業を代行してもらえます。一例として、離婚協議書の雛形を用意しましたので、参考になさってください。
この雛形の文例では、ペットの養育費(飼育費)や面会交流についても盛り込んでありますが、これらの問題については後ほど詳しく解説します。
(3)話し合いがまとまらない場合は調停へ
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、その中でペットの引き取りについても話し合うことになります。
調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めていきます。調停委員を味方につけることがポイントとなりますので、前記「2」でご紹介した条件を自分が満たしていることをしっかりと調停委員に説明しましょう。
(4)最終的には裁判で
調停でも話し合いがまとまらない場合には、離婚裁判で決める必要があります。
裁判では、自分がペットの引き取り手としてふさわしいということを証拠で証明できた方が勝つことになります。
そのため、前記「2」の条件を満たしていることを証拠化して裁判所に提出することがポイントとなります。
4、離婚時にペット引き取り権を獲得するための戦法
ペット引き取り権を獲得するためには幾つかの戦法があります。
もしも配偶者と揉めているなら参考にしてください。
(1)ペット中心で!ペットが快適に暮らせることを主張
ペット中心に考えた主張をしてこそ、調停や裁判に発展した場合にも有利になります。
例えば、あなたの仕事が残業がない場合で、夫の仕事は残業が多いなどを理由にして犬の散歩に毎日はいけないのでは?と主張する方法です。
また、これまで主に飼育していた場合は、具体的な飼育方法についても主張できます。
ペットの好き嫌いや、苦手な場所や行動などを主張して、「自分ならペットのストレスを軽減して飼うことができる」と主張する方法です。
(2)ペット相当分の財産を譲る
お互いにペットを譲らない場合には、他の財産に関して、ペット分を差し引いた財産分与にすることで、配偶者が納得する可能性があります。
それでも相手が納得しない場合や、他に分与する財産が特にない場合には、自分がペットを引き取る代わりにある程度の金銭を相手に支払うことも有効です。
財産分与においてこのような形で支払う金銭のことを「代償金」といいます。
ペットをどうしても引き取りたいなら他の財産で譲歩しておきましょう。
5、離婚時に引き取れなければペットにはもう会えない?
万が一、離婚時にペットを引き取れなかった場合、もう会うことはできないのでしょうか。
上記では、引き取り権を獲得するための交渉材料として相手方に面会交流を認めることを提案しましたが、ここでは、相手方がペット引き取った場合に面会交流を求める方法について解説します。
(1)基本的に面会交流権はない
残念ながら、ペットについて法律上の権利としての「面会交流権」は認められていません。
子どもについては民法で面会交流権が認められていますので(同法第766条1項)、正当な権利として請求し、法的手段によって強制的に実現することもある程度は可能です。
しかし、ペットについては請求する法的根拠もなく、実現するための法的手段も基本的にはないのです。
(2)面会交流を求めるにはよく話し合うこと
しかし、ペットを引き取った相手方と合意できれば、自由に面会交流を行うことができます。
したがって、離婚して離ればなれとなったペットに会うためには、相手との話し合いによって面会交流を取り決める必要があります。
相手方が面会交流を渋る場合には、自分の希望だけを主張するのではなく、相手方にとってのメリットを提案することが有効です。
6、離婚時にペットを引き取ったら養育費も請求できる?
ペットに対する養育費の請求は法的にはできません。基本的にはないものと考えてください。
子どもについては民法で養育費の請求権が認められています(同法第766条1項)が、ペットの場合は法律上の請求権は認められていないのです。
財産分与でペットの所有権を取得した以上、養育費(飼育費)は所有者が負担していく必要があります。
7、離婚時にどちらもペットの引き取りを望まないときの注意点
ここまでは離婚時に双方がペットの引き取りを主張する場合の問題について解説してきましたが、中にはどちらもペットの引き取りを望まないこともあるでしょう。
婚姻中は2人で協力して飼育できていたものの、離婚後は時間的にも経済的にも余裕がなくなるため、引き取りを望まない人も少なくありません。
特に男性の場合、相手方に育ててもらって、たまに会わせてほしいと考える人が多いと考えられます。
まとめ
離婚時のペットの引き取りは財産分与の問題とはいえ、実際の話し合いは親権争いの場合と同じくらいに大変です。
相手ともめたときは、弁護士に相談することをおすすめします。相談者の事情に応じて、交渉を有利な流れで進めるための専門的なアドバイスが得られます。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代行してもらえますし、調停や裁判でも全面的にサポートしてもらえるので、愛するペットを取得できる可能性が高まります。
また、ペットだけでなく離婚問題全般についても弁護士は相談に乗ってくれます。財産分与や慰謝料についても当然、弁護士がついていることで有利な解決が可能となるでしょう。
無料で相談できる法律事務所も多いので、まずは相談だけでも行ってみてはいかがでしょうか。