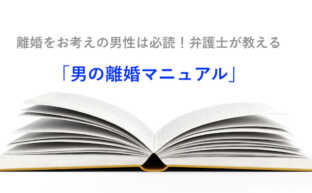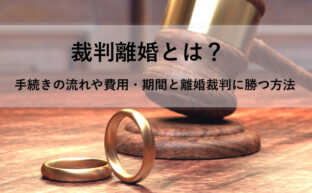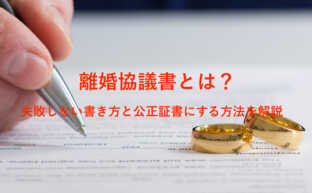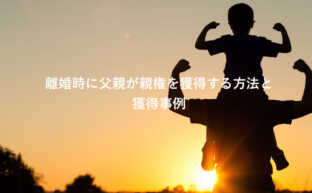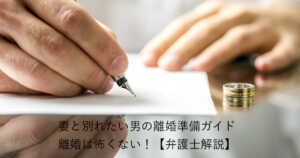
妻と別れたい男の離婚準備について、どのようなステップを踏めばいいかについて悩んでいますか?男性が離婚の準備をする際には、注意深く計画を立てることが不可欠です。なぜなら、慰謝料(浮気などの違反行為による場合も含めて)、養育費、財産分与などの観点から、男性の経済的負担が重要な要素となることが多いからです。
特に妻が離婚に同意しづらい状況の場合、慎重な対応が求められます。しかし、安心してください。この記事では、男性のための適切な離婚の準備について詳しく解説し、離婚に対する不安を払拭します。
さらに、離婚したい男性に参考になる内容は以下の記事でも紹介しています。
また、離婚したい方向けの内容全般は以下の記事にまとめていますので併せてご参考ください。
目次
1、妻と別れたい男の離婚準備はまず何から始めればよい?

妻と別れたい男の離婚準備について、まず何から始めればよいのかを確認していきましょう。
- 離婚条件の確認
- 離婚後の生活をイメージ
- 離婚したいと妻に伝えて話し合う
- 財産分与について
- 親権や養育費について
- 慰謝料の有無について
- 婚姻費用について
(1)そもそも離婚するための条件を満たしているのか確認
男性側が離婚を望んでいても、女性側が離婚に応じてくれるとは限りません。
話し合いで離婚するのが難しい場合、離婚するには離婚するための条件を満たしていることが必要になります。
離婚するための条件は、以下のとおりです。
- 相手方に不貞行為(配偶者以外の異性との肉体関係を持つこと)があったとき
- 相手方から悪意で遺棄(正当な理由なく生活費を渡さないなどの行為)されたとき
- 相手方の生死が3年以上明らかでないとき
- 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
このうち、多くの場合は「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」に該当するかどうかが争点となります。これは、婚姻関係が破綻しており、関係性の再構築の見込みがないことを指します。
(2)離婚後の生活をイメージして支出や環境の変化を考える
妻と別れたい男の離婚準備を進めるにあたっては、離婚後の生活を具体的にイメージしましょう。
- 離婚後の経済的支出
- 環境の変化
についても考えておく必要があります。
たとえば、今家族で住んでいる家から自分だけ出て行く場合は、一人で暮らす物件を探しておく必要があります。
(3)離婚したいと妻に伝えて話し合う
離婚準備が進んだら、離婚したい旨を妻に伝えましょう。
夫婦関係の険悪な状態が続いていれば、妻側も離婚を覚悟しているケースもあります。
一方、妻側が離婚を拒否しており、そもそも話し合いにならない場合は、調停手続に進む必要があります。
調停とは、調停委員が第三者として介入し、話し合いによって合意を目指す手続きです。調停委員が介入することで、財産分与などのもめやすい離婚条件について、意見のすり合わせを行なってくれます。
(4)財産分与について
離婚する場合、大きく争点になるものの一つが財産分与です。
夫婦が結婚してから形成した財産は夫婦の共有財産として財産分与の対象になります(逆に、結婚前から夫婦の一方が個人的に有していた財産や結婚後でも相続や贈与を受けた財産は特有財産として財産分与の対象となりません)。
(5)子供がいる場合〜親権や養育費について
子供がいる場合は、以下のことも離婚準備として考えておく必要があります。
①親権はどちらが獲得するのか
まずは子供の親権についてです。
日本では、夫婦が婚姻関係にあるときは共同親権となりますが、離婚した場合は共同親権が認められておらず夫婦のどちらか一方が親権を有することとなります。
親権を妻に渡す場合は、以下の
- 養育費
- 子供との面会
の点についてしっかり考えておきましょう。
②養育費の額や支払い方法
妻に子供の親権を渡す場合でも夫婦それぞれが子供の親である、という事実に変わりはありませんから、夫は子供の養育費を支払う必要が生じます。
養育費の額については養育費算定表(養育費算定表では、子供の年齢や人数、両親の収入から養育費の金額目安が記載されています)を元に計算しますが、具体的な金額については個々のケースにより異なります。
養育費の
- 金額
- 支払い方法
についてもおおよその目安の金額を確認し準備しておきましょう。
(6)慰謝料の有無について
離婚の原因が夫婦のどちらにあったとしても、慰謝料の支払いについては準備をしておく必要があります。
たとえば離婚の原因が夫側の浮気などの場合は、慰謝料はほぼ確実に支払う必要が生じます。そうでなかったとしても、離婚は妻に精神的苦痛を生じさせるケースが多いので、金額の大小はあれど、慰謝料の支払いを覚悟しておいた方が良いでしょう。
2、妻と別れたい男の離婚準備は離婚の種類毎に異なる

妻と別れたい男の離婚準備は離婚の種類ごとに異なります。
離婚は、基本的には
の3種類があります。
離婚訴訟では,
- 親権者の決定
- 養育費
- 財産分与
などについても裁判所で決めてもらうよう提起することができます。
それぞれの詳しい内容については、以下の関連記事もあわせてご参照ください。
(1)妻と話し合い合意に至った〜協議離婚における離婚準備
妻との離婚の話し合いが合意に至った場合、
- 共有財産の把握
- 離婚を長引かせないこと
などがポイントになります。
人間の気持ちはうつりやすいものですので、離婚の準備を進めていく中で妻の気持ちが変わり「やっぱり離婚しない!」と突然言い出す可能性もあります。
妻の気持ちが変わらないうちに早めに離婚の準備を進めていきましょう。
(2)妻と話し合い合意できなかった〜調停離婚における離婚準備
妻が離婚に反対し話し合いでは離婚の合意ができなかった場合、調停離婚の準備を進めていく必要があります。
離婚に関する調停は、
- 相手方の住所地の家庭裁判所又
- 当事者が合意で定める家庭裁判所
などに申し立てます。
(3)調停でも合意に至らなかった〜裁判離婚における離婚準備
調停でも合意に至らなかった場合は、最終手段として裁判手続に進むことになります。
裁判手続に進みそうな場合は、弁護士に必ず相談しましょう。
裁判でも離婚できなかった場合は、新たな離婚事由が増えない限り離婚は難しいです。
弁護士と相談しながら
- 妻にとって不利な事情の整理
- 証拠の準備
を進めていきましょう。
3、男性が離婚を準備するにあたり覚悟しておいた方が良いこと

(1)子供がいる場合親権を失うかもしれない
男性が離婚を準備するにあたっては、子供の親権を失う可能性を覚悟しておきましょう。
現在の日本では、多くの場合、母親が親権を有する傾向にあります。
また、子供が小さい場合は、それだけで母親が有利になります。
妻と離婚するということは、子供とほとんど会えなくなるということを覚悟しておきましょう。
どうしても子供の親権が欲しい場合は、
- 母親が子供を育てることは子供にとって悪影響が生じること
- 父親である自分が子供を育てた方が子供のためになること
を主張、立証していく必要があります。
(2)金銭的負担
離婚をするとなれば、
- 財産分与
- 養育費の支払い
などで金銭的負担が大きくなります。
子供とはほとんど会えなくなるにもかかわらず金銭的負担だけを負い続けることにやるせなさを感じる人も少なくありません。
離婚を決意するのであれば、金銭的負担を覚悟しておきましょう。
4、妻と別れたい男性は弁護士に相談を

妻と別れたい男性は、自分の判断で行動する前に一度弁護士に相談することをおすすめします。
(1)妻と直接離婚の話し合いをしなくて済む
あなたの中で妻との離婚を決意したということは、
- 妻とこれ以上話したくない
- 関わりを持ちたくない
という気持ちがあるかもしれません。
離婚の話を進めていく上で、細かい取り決めなどは妻と決めていかなければなりませんが、弁護士に依頼しておけば、弁護士があなたの代理人として妻と様々な連絡や取り決めを進めてくれます。
(2)財産分与の算定
離婚の話し合いを進めていく上で複雑になるのが財産分与の算定です。
- どの財産が結婚後の共有財産になるのか
- 財産分与の対象となる財産には何が該当するのか
- どのように評価額を決めるのか
など、複雑な側面もあります。
弁護士に依頼をしておけば、財産分与の算定も弁護士が行うので、手間が省けるという点は大きなメリットになるでしょう。
(3)慰謝料や養育費の算定
慰謝料や養育費の算定をしてもらえることも弁護士に依頼する大きなメリットです。
慰謝料や養育費の総額は決して安いものではないので、妻の言いなりにならないようしっかりとした算定を行っていきましょう。
まとめ
以上、妻と別れたい男の離婚準備についての解説でした。
女性は経済的側面を男性に頼っていることが少なくないので、いくら男性が離婚を望んでいても妻が離婚を承諾しない可能性があります。
財産分与や慰謝料・養育費等に関して経済的負担を負ったとしても、男性が妻と離婚して自分の望む人生を生きていけるように、離婚を検討している人はお気軽に弁護士にご相談ください。