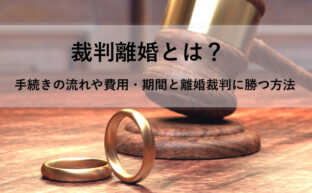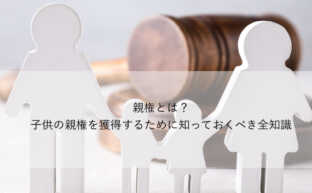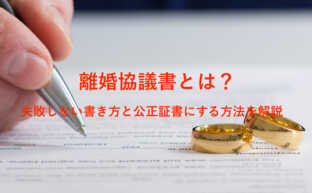協議離婚とは、夫婦での話し合いだけで離婚を成立させていく離婚方法です。「離婚しましょう」「わかった」という合意をして離婚届を出す、というごく一般的な離婚の方法です。
離婚をする夫婦の約90%が協議離婚をしています。裁判所に頼ることなく当事者だけで離婚するので、離婚すること自体と離婚条件に相手と合意ができている場合に適した離婚方法です。
離婚をお考えの方なら誰しも、スムーズに離婚を成立させたいと思われることでしょう。ただ、夫婦での話し合いがスムーズに進むとは限りませんし、話し合う際に知っておかなければならないルールもいくつかあります。
そこで今回は、
- 協議離婚とは
- 離婚の話し合いの際に知っておくべきルール
- 協議離婚が進まない場合の対処法
などについて、離婚相談の経験豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
協議離婚についての大切なポイントを押さえれば、離婚手続きなどもスムーズに対応できるため、この記事で協議離婚の知識を身につけて対策しておきましょう。
目次
1、協議離婚とは

では早速、協議離婚とは何かについてみていきましょう。
協議離婚の他にどんな離婚方法があるのかもご説明しますので、協議離婚の特徴をよくご理解いただけることでしょう。
(1)当事者の話し合いだけで成立させる離婚
協議離婚とは、夫婦の当事者同士が話し合いを行い、合意した後に離婚届を役場に提出する離婚方法です。結婚が当事者同士の合意でできることから、離婚も当事者の合意のみで行うこの協議離婚が基本と言えます。
ポイントは、夫婦が離婚することと離婚条件について合意できるかどうかと、合意で取り決めた離婚条件が適切かどうかにかかっています。
(2)「話し合い」で合意できない場合は?
当然、話し合いで合意できない場合もあります。
- 相手が離婚を拒否している
- 相手が、離婚はするけど財産は渡さないと言っている
- 相手が、離婚はいいけど子どもだけは渡さないと言っている
など、スムースにいかないケースもあるわけです。そんなときは、夫婦(当事者)では離婚は無理。「第三者」に関与してもらう方法へ進みましょう。
(3)第三者が関与する離婚もある
離婚に関与する「第三者」とは、家庭裁判所のことです。家庭裁判所が関与する離婚には、主に「調停離婚」と「裁判離婚」の2種類があります。
①調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所から選任された「調停委員」が間に入り、離婚の協議を進めてくれる離婚方法です。
第三者である調停委員が間に入ることで、話し合いに応じてくれなかった配偶者でも冷静に話し合い進められることを狙いとしています。
調停委員が中立・公平な立場から当事者双方に対して助言や、ときには説得を交えて話し合いを進めてくれるので、実のある協議を進めやすくなります。
調停離婚(離婚調停)の詳しくは、こちらのページをご覧ください。
②裁判離婚
裁判離婚とは、「裁判官」という第三者が間に入り、当事者双方が提出した主張と証拠を精査して、強制的に白黒をつけてもらえる離婚方法です。
「調停委員」はあくまでも互いの意見の調整をつけるだけの立場ですから、調停(話し合い)がまとまらないということもあり得ます。
そんな場合の離婚方法が「裁判離婚」です。裁判所が下す判決には強制力がありますので、相手の同意がなくても離婚することが可能となります。
裁判官とはいえ、全くの他人がひと組の夫婦に対して「離婚しなさい」「離婚してはならない」などと強制できるのはなぜかというと、法律に基づいて判決を下す権限が裁判官にあるからです。
法律上、次の5つの離婚要件(法定離婚事由)のどれかがある場合には、判決による強制的な離婚が認められています(民法第770条1項)。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
性格の不一致などこれら5つに該当しない場合は、基本的には裁判離婚は認められないので、協議離婚で決着をつける方が得策ということになります。
なお、裁判離婚は調停を経た後でなければできないこととされています(調停前置主義)。
2、協議離婚のメリット・デメリット
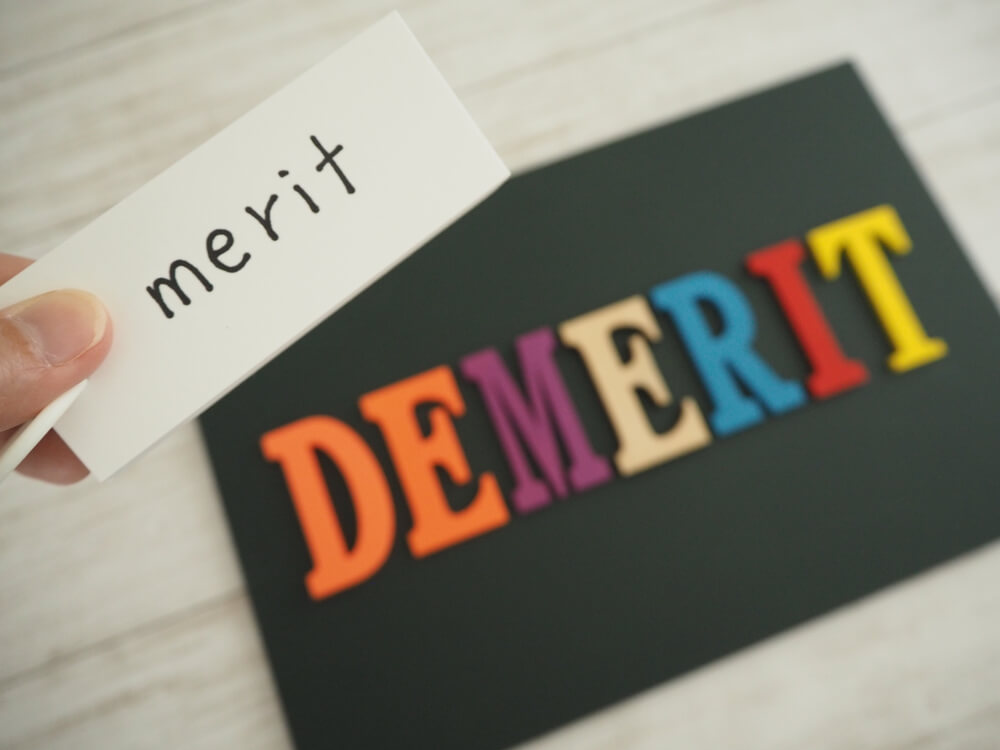
離婚方法には、
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
の3つがあることがわかりました(審判離婚もありますが、実務上ほぼ使われませんので割愛しています)。
本項では、協議離婚で離婚にこぎつけることのメリット、そしてデメリットについてみていきましょう。
(1)メリット
協議離婚の主なメリットは下記5点です。
- 理由を問わない(当事者間で合意が取れれば離婚できる)
- 合意ができれば離婚までの期間が比較的に短い
- 費用がかからない
- 手続きが簡単(基本的に離婚届を書いて出すのみ)
- 慰謝料や養育費、財産分与について裁判相場よりも有利な条件で離婚ができる可能性がある
前4つのメリットは、皆さんもご理解いただいているものと思います。
最後のポイント「慰謝料や養育費、財産分与について裁判相場よりも有利な条件で離婚ができる可能性がある」について解説をしましょう。
調停離婚や裁判離婚になってしまうと、「公平」を観点として第三者が介入することになります。ですから、お金については特に、一定の基準が設けられているのです。
養育費であれば、支払う側の収入がいくらの場合はこれくらい、受け取る側の収入がいくらの場合はこれくらい、子どもが2人であればこれくらい、とある程度の金額が決まっています。
慰謝料も、どのような理由によって慰謝料を請求しているのかにより、金額もある程度先例に従うことになります。
財産分与に関しては、原則として夫と妻とで折半と決められているわけです。
ですが、協議離婚であれば、お互いに納得さえしていれば、これらに縛られる必要はありません。自由に取り決めることが可能です。
(2)デメリット
協議離婚にはデメリットも存在します。主なデメリットは下記4点です。
- 離婚したいくらい嫌いな相手と話し合いをしなければならない
- 馬が合わないため話がスムーズに進まない
- 夫婦間の力関係が出てしまい、不利な条件で離婚に合意させられる可能性がある
- 条件を決めることを忘れがち
前の3点どれをとってもですが、二人だけでは限界であるということが協議離婚のデメリットです。
そもそも「協議」というのは、話し合いながら意見を合わせていくことですから、合わないと思っている相手とするのは基本的には至難の技。
一方がかなり我慢しているか、お互いに常識的に歩み寄る努力ができているか、の場合にのみ成立しうると言えるでしょう。お互いが言いたい放題、自我を通すという関係であれば、協議はかなり難しいのです。
そして4点目「条件を決めることを忘れがち」。
これは若い夫婦にありがちですが、協議離婚では「離婚するかしないか(離婚の成否)」だけを焦点に話し合いをしてしまい、「条件」について全く触れないことが起こり得ます。
条件とは、親権の帰属や財産分与などのことですが、確かに、親権は文句なく母親になり、財産も特にないので話し合いなどしない、ということはよくあることです。しかし、浮気を原因とした場合の「慰謝料」、そしてお子さんがいる場合はお子さんのためにもっとも大切な「養育費」について決めないのは、離婚を多く取り扱う弁護士から見ると口惜しい気持ちでいっぱいになります。
3、協議離婚で知っておくべきルール|協議離婚で話し合うべきこととは?

話し合いの方法にルールはありませんが、話し合うべき内容については法律上のルールを知っておくことが重要です。話し合いで合意すれば自由に決めることが可能とはいえ、ルールを知らなかったのでは大切な条件を決めることを忘れたり、決めたとしても一方的に不利な条件となっていることに気付かなかったりすることになりがちだからです。
協議離婚で話し合うべき「条件」は、大きくは以下の3つです。
- 子どもについて
- 財産について
- 不法行為の清算について
以下、1つずつみていきましょう。
(1)子どもについて
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、必ず夫か妻、どちらが親権を持つのかを決めなければなりません(日本では共同親権が認められていません)。
親権をどちらが持つかを決める際には、これまで主にどちらが子育てをしてきたのか、今後の養育環境はどちらの方が整っているか、子どもの年齢、子ども自身の意思など、様々な事情を総合的に考慮します。
そして、今後どちらが子育てをする方が子どもの成長のために望ましいかという観点から決めます。
調停離婚や裁判離婚では、「現状維持の原則」(これまでの養育状況をできる限り変更しない方がよい)と「母性優先の原則」(子どもの身の回りの世話をするスキルは一般的に母親の方が長けている)とが重視されるため、妻が親権者に指定されるケースが圧倒的に多いのが実情です。
ただ、子どもが15歳以上の場合は子ども自身の意思が重視されるため、子どもの意思により夫が親権者となるケースも増えてきます。
協議離婚では自由に決めて構いませんが、「どちらが子どものためになるか」という視点は忘れないようにしましょう。
親権者が決まったら、「養育費」についても取り決めるべきです。
夫婦は離婚しても子どものとの関係は切れませんので、離婚後も子育てに要するお金は分担して負担していかなければなりません。
そのため、親権者となった側の親は相手方(非親権者)に対して養育費の支払いを請求できます。
養育費の金額は各家庭の実情に応じて取り決めることが望ましいですが、意見がまとまらない場合には、裁判所が公表している「養育費算定表」を参照して取り決めることが一般的です。
この算定表には、両親それぞれの年収、子どもの人数・年齢に応じて適切と考えられる養育費の金額が掲載されています。
一方、非親権者には、離婚後も子どもと定期的に会って親子の交流を図る「面会交流」を求める権利があります。
子どもにとっては両親から愛情を受けて育つ方が望ましいので、適切な頻度で面会交流を行うように取り決めた方がよいでしょう。
面会交流の頻度は月に1回、半日程度が相場的ですが、両親の合意で自由に決めて構いません。
極端に言えば毎日でも可能ですし、毎週土日は子どもが非親権者の家で過ごすといった内容にすることも可能です。
ただ、子どもに過度な負担がかからないように配慮することは不可欠です。
(2)財産について
夫婦でいる間に築いた財産は、離婚時に分け合うことができます。このことを「財産分与」といいます。
財産分与では、原則として夫婦の財産を折半するのが原則です。
どちらかが圧倒的に稼いでいた、という場合はそれが考慮されることもありますが、基本的には2分の1の割合です。これは、お互いの相互扶助により財産を築き上げたと考えられているからです。
また、夫婦でいる間に納めた年金保険料も分与の対象となります。婚姻中の年金保険料の納付記録を分割することを「年金分割」といいます。
例えば夫が会社員で妻が専業主婦だった場合、夫の年金を分割することで妻がもらえる年金が増えることになります。婚姻中に納めた厚生年金(旧共済年金)の納付記録を、やはり0.5ずつに分割するのが一般的です。
年金分割は老後の生活を支えるために重要な事柄なので、忘れずに取り決めるようにしましょう。
ただし、国民年金の部分は分割されないことにご注意ください。
そのため、夫の年金を分割しても、夫に支給される年金の半分を妻がもらえるようになるわけではありません。
また、夫が自営業者等で国民年金にしか加入していなかった場合は、年金分割を求めることはできません。
(3)不法行為の清算について
離婚のきっかけは様々ですが、好きで結婚した同士であれば、なんらかの問題があった場合も多いもの。
- 浮気
- DV・モラハラ
- 生活費を渡さない
- 正当な理由なく同居に応じない
- セックスレス
など、苦痛を与えるような行為(不法行為)があったことを原因とした離婚では、法律上「慰謝料」が発生します(民法第709条、第710条)。
慰謝料の相場は数十万円~300万円程度と幅広いですが、不法行為の内容だけでなく、婚姻期間、離婚時の年齢、子どもの有無、夫婦双方の収入や社会的地位など様々な要素を総合的に考慮して決めます。
協議離婚では「被害者側がいくらなら納得できるか」「加害者側がいくらまで支払えるか」で意見をすり合わせていくことになるのが実情ですが、法外な金額を要求しても話し合いがまとまるものではありません。
ちなみに、浮気・不倫を理由として離婚する場合には、慰謝料額を200万円程度と取り決めるケースが多くなっています。
また、慰謝料を請求するなら、その根拠となる証拠を確保しておくことが重要です。
協議離婚は裁判ではないので証拠が不可欠というわけではありませんが、相手が不法行為の事実を否定して慰謝料の支払いを拒否する場合には、証拠を突きつけなければ話し合いが進みません。
不倫・浮気のケースで言えば、2人でラブホテルに出入りする動画像や、メール・SNSなどのやりとりで肉体関係があったことが分かるものなどが重要な証拠となります。
4、協議離婚が進まない!相手が協議してくれない時の進め方

相手が話し合いに応じなければ、協議離婚を進めることはできません。話し合いが進まないというケースも、大別すれば次の2つのケースに分けられます。
- 相手が離婚そのものに頑なに応じない
- 離婚条件で折り合えない
このような場合には調停へ進むのも一つの方法ではありますが、協議離婚のメリットを享受するために、以下の対処法を試してみましょう。
(1)離婚そのものを拒否されている場合
相手が話し合いに一切応じないときは、離婚そのものに反対していることが多いものです。
その場合には、夫婦関係が冷め切っているにもかかわらず離婚に応じない理由は何かを探ることが重要となります。
直接話し合えない場合は、メールや手紙などで自分の思いを伝えて、話し合いを試みると返事が返ってくることもあります。
それでも事態が進まない場合は、別居をしてみることが有効です。
別居すれば相手もことの重大性を認識し、何らかの働きかけをしてくる可能性があります。
そうでなくても、別居生活が続くと夫婦としての実態がなくなっていくので、相手の気持ちも次第に離婚を受け入れる方向に変化することが期待できます。
すぐに別居することが難しい場合は、「家庭内別居」という選択肢もあります。
とにかく、相手に対して「もう夫婦としてやっていくつもりはない」という意思を明確に示し、距離をとることで、時間はかかるかもしれませんが協議離婚できる可能性が高まるはずです。
(2)離婚条件に応じない場合
話し合いで自由に離婚条件を決めることができるのが協議離婚のメリットですが、離婚条件については自分の希望もあれば相手の希望もあります。
自分の希望を全面的に通すことは難しいので、多少の譲歩は必要となります。
ただ、譲歩しすぎると一方的に不利な条件を押しつけられ、後悔することにもなりかねません。
前記「3」の解説を参考として、譲れない一線を決めた上で、譲歩する姿勢を示しつつ話し合いを進めるとようにしましょう。
とはいえ、相手が相手自身の希望に固執し、話し合いが進まないことも少なくありません。
そんなときは、上記(1)と同じように別居や家庭内別居で相手との距離をとってみるのがよいでしょう。
(3)弁護士に間に入ってもらう
当事者だけでの話し合いが難しい場合には、弁護士に間に入ってもらうという方法があります。
家庭裁判所に間に入ってもらうと、もはや協議離婚にはなりませんが、弁護士に間に入ってもらえば協議離婚を目指すことも可能です。
弁護士は依頼者に代わって相手と冷静かつ論理的に話し合います。
相手も、弁護士が相手なら冷静に話すことがあります。
弁護士が法律のルールを説明して相手を説得することによって、協議離婚の成立が期待できるでしょう。
また、弁護士が介入することによって相手が諦めの境地に入り、離婚の方法に話し合いが進むこともよくあります。
5、自分が協議離婚に応じたくない場合の対処法
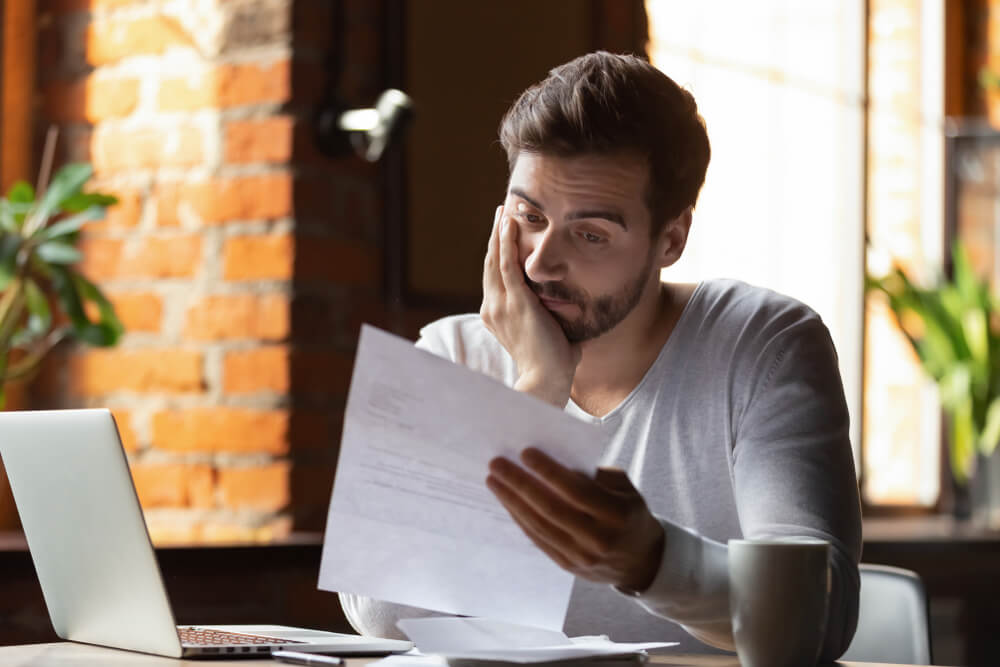
逆に、相手から離婚を持ちかけられたけれど応じたくない場合、どうすればいいのでしょうか?
それは、ひたすら拒み続けること、です。
ただし、自分に法定離婚事由がある場合は、裁判に持ち込まれてしまえば離婚を余儀なくされることでしょう。
そうなることを避けるためには、なぜ相手が離婚をしたいと思ったのか、その原因を突き止め、あなた自身が変わることが必要です。夫婦関係を再構築するためには、自分が変わる覚悟を決めることと、根気よく相手に対して働きかけていく努力が重要となります。
もっとも、
- 嫌いになった、愛せなくなった
- 他に好きな人ができた
というように、なんら自分に具体的な原因もなく相手の心が離れてしまった場合は、あなたがすべき努力が見つからないかもしれません。
夫婦関係の修復が可能かどうかを見極める視点も持たなければ、報われない努力をしてしまうおそれもあります。
もはや夫婦関係の修復が難しいという場合には、別の道を考えた方がご自身にとってもよいのかもしれません。
夫婦関係の修復が可能なケース・難しいケースについては、こちらの記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
ただ、夫婦関係の修復が難しいからといって、すぐに諦める必要はありません。
カウンセラーから専門的なアドバイスを受けることで、自分では思いつかなかった対処法が見つかることもあります。
一人で悩みを抱え込むよりも、カウンセリングを利用してみるとよいでしょう。
6、なかなか協議がまとまらない!先に別居しても大丈夫?

なかなか協議離婚がまとまらない場合に、先に別居する夫婦は数多くいます。
別居することで離婚につながりやすくなることは、先ほどもご説明しました。ただし、別居する際には注意しておかなければならないルールがあります。
まず、勝手に別居を始めることは原則として控えましょう。夫婦には同居する義務があるため(民法第752条)、勝手に家を出て行くと、場合によっては不法行為であるとしてあなたが慰謝料を請求されるおそれがあります。
ただし、相手が不倫・浮気やDV、モラハラなどをして、夫婦として同居していくことが困難な状況を作り出した場合は、勝手に別居してもこのような問題はありません。
また、別居が長引くと他に交際したい異性が現れることもあるかと思いますが、別居中の恋愛も基本的に控えるべきです。
夫婦には互いに貞操を守る義務があるため、離婚成立前に他の異性と交際すると配偶者から不貞行為を主張され、慰謝料を請求されるおそれがあります。新たな恋愛は離婚後にする方が無難です。
そして、離婚のための別居であっても、離婚が成立するまでは相手から「婚姻費用」という名の生活費をもらうことができます。相手の収入の方が高い場合には、適切な金額を請求するようにしましょう。
7、協議が調ったら離婚協議書を作成

離婚のための協議が整ったなら、離婚協議書を作成することをお勧めします。
確かに離婚自体は協議書がなくてもできます。ですが、大事な離婚「条件」につき、言った・言わないが発生するのは避けたいところ。条件を記した離婚協議書で合意した条件内容を確実に残しておきましょう。
また、可能な限り、公正証書にしておくといいでしょう。離婚協議書を公正証書にすることで、条件の義務者が条件に違反した場合、強制執行できるようになります。
離婚協議書を公正証書にする方法については下記記事をご覧ください。
8、協議離婚における離婚届提出のベストタイミング

法律上は、夫婦が離婚について合意さえすれば、いつでも離婚届を提出することができます。
しかし、離婚届を提出するのは、離婚条件について納得できる合意をして、離婚協議書を作成した後にすることが重要です。
離婚条件のうち親権以外の条件については、離婚後に請求することも可能ではあります。
しかし、離婚が成立した後では相手が真剣に話し合いに応じなくなる可能性が高いため、適切な条件を獲得することが難しくなります。これでは、協議離婚のメリットを十分に享受することができません。
なお、協議離婚で離婚届を提出する際には、証人2名の署名が必要です(調停離婚と裁判離婚では証人は不要です。)。
ただ、証人は成年(満18歳以上)であれば誰でもよいので、誰に証人を頼むかで悩む必要はありません。家族でも上司でも友人でも構いませんので、頼める人に頼んで、速やかに離婚届を提出すればよいでしょう。
まとめ
協議離婚とは夫婦の話し合いで離婚を成立させる離婚方法です。離婚の理由が何であれ、合意が取れれば離婚ができるメリットがあります。
しかし、その反面、離婚に関わる条件を夫婦で全て決めていかなければいけません。養育費や財産分与などの煩雑な問題も、夫婦間で解決する必要があるのです。
思うように進まない場合は、協議離婚でも弁護士に相談した方が金銭面の相場がわかり、スムーズに話し合いが進む可能性が高いでしょう。
また、相手が話し合いに応じない場合や離婚を拒否している場合でも弁護士に相談することで戦略を考えてもらえます。離婚するべきか迷っているケースでも、無料相談であなたの心に寄り添ったアドバイスをしてもらえるでしょう。
もしも離婚をする際は、本記事を参考に、事前に準備をして協議離婚でも不利益なく話し合いを進めていただけたらと願います。