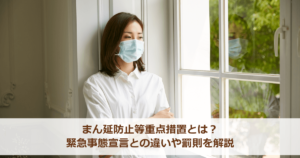
まん延防止等重点措置とは、新型インフルエンザ等の感染症のまん延を防止するために首相が発出する対策のことです。
具体的な措置の内容は、対象となる地域の都道府県知事に委ねられています。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、これまでに全国の多くの地域に対して数度にわたり、まん延防止等重点措置が発出されました。
そのたびに、国民の仕事や日常生活に対する様々な制限が要請されてきましたので、不便な思いをした人も多いことでしょう。
ただ、「まん延防止等重点措置」という言葉はよく聞くものの、正確な内容をご存知の方は多くないと思われます。
「まん延防止等重点措置」が、「緊急事態宣言」とどのような点が異なるのかについても、気になるところでしょう。
今回は、
- まん延防止等重点措置はどのようなときに発出される?
- まん延防止等重点措置で要請される内容とは?
- まん延防止等重点措置による要請に違反したときの罰則は?
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
2022年1月以降に発出されたまん延防止等重点措置は、同年3月21日にすべての地域で終了しましたが、今後も発出される可能性が十分にあります。
本記事をお読みいただくことにより、まん延防止等重点措置に関する理解を深めていただければ幸いです。
目次
1、まん延防止等重点措置とは

まん延防止等重点措置は、『新型インフルエンザ等対策特別措置法』(以下「特措法」といいます。)で定められている制度です。
特措法は、平成25年から施行されていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大に対して国や地方公共団体がより的確な対策をとれるようにするため、2021年2月3日に改正されました(施行は同月13日から。)。
まん延防止等重点措置は、この法改正によって新設された制度となります。
まずは、まん延防止等重点措置がどのような意味を持つ制度であるのかを解説します。
(1)まん延防止等重点措置の意味
まん延防止等重点措置は、新型コロナウイルス感染症等の感染症について、特定の地域で感染者が急増する局面で、その地域での感染症のまん延防止のため集中的に対策を講じる措置です。
特定の地域における感染爆発を防止するために、都道府県知事はその地域の住民や事業者に対して、さまざまな要請をすることができます。
以上のように、まん延防止等重点措置は感染爆発の「予防」を目的とした措置です。
緊急事態宣言を発出せざるを得ない事態に至らないよう、その前段階で発出されるという位置づけにあるのです。
(2)対象となる地域
まん延防止等重点措置の対象となる地域は、都道府県単位ではなく、都道府県知事が指定する特定の区域です。一般的には、市区町村単位で指定されます。
どのような区域が指定されるのかというと、感染者が急増しつつあり、このままでは国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められる区域です。
簡単にいうと、国や地方公共団体が対策を講じなければ感染爆発に至るおそれがある区域ということができるでしょう。
2、まん延防止等重点措置はどんなときに発出される?

まん延防止等重点措置を発出すべきか否かについては、首相や都道府県知事が主観的に判断するのではなく、目安となる客観的な基準が策定されています。
ここでは、まん延防止等重点措置が発出される基準について解説します。
(1)政府の新型コロナ対策分科会が提示した「レベル」が指標となる
政府の新型コロナ対策分科会では、新型コロナウイルス感染症への警戒度をレベル0~4の5段階に分けた「レベル分類」を策定し、公表しています。
警戒度はレベル0が最も低く「感染者ゼロレベル」とされており、レベル4が最も高く「避けたいレベル」です。
レベルの判断は、都道府県ごとに感染の状況や病床使用率等の医療ひっ迫の状況、その他にもさまざまな要素を総合的に考慮して行われます。
基本的には、都道府県ごとにレベルを判断することが想定されていますが、状況によっては市区町村単位できめ細かく判断されることもあります。
なお、政府の新型コロナ対策分科会は以前に、警戒度を5段階の「ステージ」に分類した基準を打ち出していました。
その後、ワクチン接種率の向上や治療薬の開発、医療提供体制の強化が進みました。
新規陽性者でも軽症者の割合が増加してきたことなどから、感染拡大の防止を図りつつも、国民の日常生活や社会経済活動の回復を促進すべきという方向性が示されています。
警戒度を評価する基準も新たな視点で策定し直す必要性が生じ、2021年11月8日、新型コロナ対策分科会が上記の「レベル分類」を新たに打ち出しました。
その後、各都道府県でレベル分類が用いられるようになったのです。
(2)レベル2以上で発出される可能性がある
政府の新型コロナ対策分科会が提示した「レベル分類」の内容は、以下のとおりです。
レベル | 発出の目安 | 状況(国の目安) | 都の指標 |
|
レベル4 (避けたいレベル)
|
緊急事態宣言
| 一般医療を大きく制限しても、新型コロナウイルス感染症への医療に対応できない状況 | 確保病床数を超えた療養者の入院が必要
|
|
レベル3 (対策を強化すべきレベル)
| 一般医療を相当程度制限しなければ、新型コロナウイルス感染症への医療の対応ができない状況
| 3週間後に必要とされる病床が確保病床数(7,229床)に到達 又は病床使用率や重症者用病床(510床)使用率が50%超
| ||
まん延防止等重点措置
| ||||
レベル2 (警戒を強化すべきレベル)
| 段階的に対応する病床数を増やすことで、医療が必要な人への適切な対応ができている状況 | 3週間後の病床使用率が確保病床数(7,229床)の約20%に到達
| ||
| ||||
レベル1 (維持すべきレベル)
| 安定的に一般医療が確保され、新型コロナウイルス感染症に対し医療が対応できている状況 |
|
| |
レベル0 (感染者ゼロレベル) | 新規陽性者数ゼロを維持できている状況
|
|
|
「都の指標」の欄には、東京都の例を掲載しています。指標は、各都道府県の状況に応じて、新規感染者数や病床使用率等の数値が掲げられているのです。
レベル2の中でも、感染者数や病床使用率がひっ迫してくるとまん延防止等重点措置が発出される可能性があります。
もっとも、これはあくまでも目安に過ぎず、実際には地域の様々な事情を総合的に考慮してまん延防止等重点措置が発出されます。
そのため、レベル1からレベル2に上がったばかりの段階であっても、新規感染者数が急増しているような状況では、まん延防止等重点措置が発出される可能性があるでしょう。
3、まん延防止等重点措置で住民・事業者が要請を受ける内容

まん延防止等重点措置が発出されると、都道府県知事が当該都道府県内で特定の区域の住民や事業者に対して、さまざまな要請をすることができるようになります。
本章では、住民や事業者が受ける主な要請内容を紹介します。
(1)住民に対する要請内容
住民に対しては、新型コロナウイルスへの感染防止に必要な「協力」を要請されます。
主な要請内容として、以下のようなものが挙げられます。
- 不要不急の外出の自粛
- 外出する場合も、混雑している場所や時間を避けて行動する
- 不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛
- 営業時間の変更を要請した時間以降の飲食店等への出入りの自粛
- 飲食店等を利用する場合、同一グループ・同一テーブルでの会食は4人以内とする
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用の自粛
- 基本的な感染防止対策の徹底(「三つの密」の回避、マスクの着用、手洗い、うがい、人と人との距離の確保など)
住民に対する要請は、あくまでも協力の要請に過ぎないので、外出や飲食店等の利用を全面的に禁止するような要請を受けることはありません。
(2)事業者に対する要請内容
事業者に対しては、新型コロナウイルスへの感染防止に必要な「措置を講じること」を要請されます。
主な要請内容として、以下のようなものが挙げられます。
- 飲食店等の営業時間を午後8時までに短縮すること
- 飲食店における酒類の提供を停止すること
- 昼間に営業するスナック等でのカラオケの使用を自粛すること
- イベントの開催に人数制限を設ける
- 在宅勤務やテレビ会議、時差出勤などを積極的に活用すること
テレビニュースや新聞等の報道を見ていると、飲食店に対する時短要請や酒類の提供停止の要請が中心的となっている印象を受けるかもしれません。
実際は、さまざまな業種の事業者が何らかの要請を受けています。
ただし、まん延防止等重点措置では、休業要請はできないものとされています。
4、まん延防止等重点措置による要請に違反した場合の罰則は?

都道府県知事からの要請に従わない場合、罰則があるかどうかは気になるところでしょう。
この点については、住民の場合と事業者の場合とで異なります。
(1)住民に対する罰則はなし
住民が要請に従わなかったとしても、罰則はありません。
特措法上、都道府県知事は住民に対しては必要な協力を要請できるのみであり、住民が従わない場合には、強制的に何らかの措置を命じる権限が与えられていないためです。
(2)事業者に対しては罰則がある
事業者の場合は、以下の場合に20万円以下の過料に処せられることがあります。
- 命令に違反したとき(特措法第80条1号)
- 立ち入り検査の拒否等をしたとき(同条2号)
都道府県知事は、要請を受けた事業者が正当な理由がないのに要請に応じない場合は、感染症まん延防止のため、必要に応じて要請にかかる措置を講じるよう命じることができます(同法第31条の6第3項)。
この命令を出すかどうか判断するために、事業場への立ち入り検査等を行う権限も与えられています(同法第72条1項)。
過料とは行政罰であり刑事罰ではないので、科せられたとしても前科がつくわけではありません。
しかし、裁判を経ることなく科せられることに注意が必要です。
要請に従わなくても命令を受けない「正当な理由」とは、近隣に食料品店などがなく、その店が営業しなければ地域住民の生活維持が困難となる場合など、限られた事由が想定されています。
「店の経営が悪化している」「客が帰らないため午後8時に閉店できない」といった理由は、「正当な理由」に当たらないとされていますので、ご注意ください。
5、まん延防止等重点措置と緊急事態宣言の違い

緊急事態宣言も、特措法に基づき首相が発出する措置です。
しかし、緊急事態宣言は、予防というより新型コロナウイルスへの感染がまん延してしまった状況において、その事態を収束させることに主眼を置いた措置となっています。
まん延防止等重点措置との具体的な違いは、以下のとおりです。
| 緊急事態宣言 | まん延防止等重点措置 |
発出の目安
| レベル3~4 ※ただし、感染状況や医療のひっ迫状況等を総合的に考慮して判断 | レベル2~3 ※ただし、感染状況や医療のひっ迫状況等を総合的に考慮して判断 |
対象地域
| 都道府県単位
| 都道府県内で知事が指定する一部地域 |
要請内容
| ・全面的な外出自粛 ・休業要請 等も可能 | ・不要不急の外出の自粛 ・営業時間の時短 ・酒類の提供の停止 など |
罰則
| ・命令に応じない:30万円以下の過料 ・立ち入り検査の拒否等:20万円以下の過料 | ・命令に応じない:20万円以下の過料 ・立ち入り検査の拒否等:20万円以下の過料 |
国会への報告
| 発出や期間延長、区域の変更等について国会への報告が必要 | 法律上、報告義務はない
|
実施期間
| 2年以内(延長が可能だが、1年以内に限られる) | 6ヶ月以内(6ヶ月ごとに何度でも延長が可能) |
以上のように違いはありますが、どちらも感染症の拡大から国民生活や国民経済を守るために発出されるという点では同じです。
どちらが発出された場合でも、感染を防ぎ、感染したとしても他人に移さないよう、1人1人が対策を徹底することが大切です。
6、まん延防止等重点措置の内容は一律ではない!発出されたら情報確認が重要
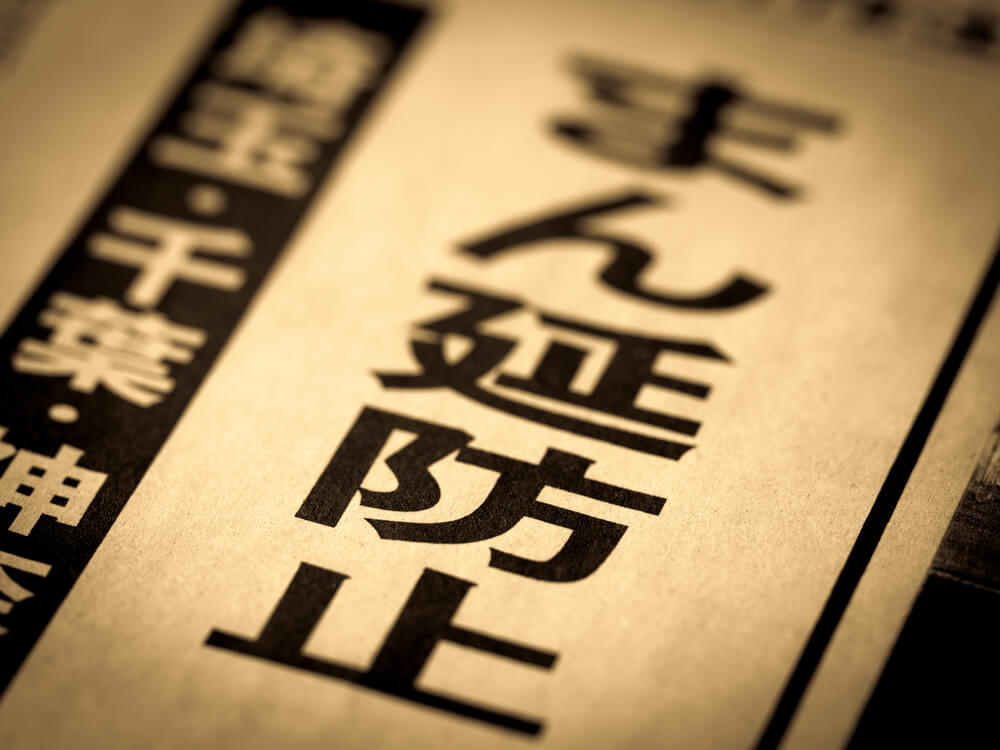
まん延防止等重点措置は、感染症がまん延するおそれのある特定の区域において、集中的に対策を施すための措置ですので、全国一律に発出されるものではありません。
発出された場合の要請内容も、全国一律のものではないのです。
感染状況や医療のひっ迫状況も日々変動しますので、新型コロナウイルス感染症の拡大が落ち着くまでは、テレビニュースや新聞等で日頃から状況を確認しておきましょう。
まん延防止等重点措置または緊急事態宣言が発出された場合には、お住まいの自治体のホームページ等で要請内容を確認し、感染を広げないための行動を心がけましょう。
養育費の相場2人の場合に関するQ&A
Q1.まん延防止等重点措置の意味とは?
まん延防止等重点措置は、新型コロナウイルス感染症等の感染症について、特定の地域で感染者が急増する局面で、その地域での感染症のまん延防止のため集中的に対策を講じる措置です。
Q2.まん延防止等重点措置で住民・事業者が要請を受ける内容とは?
- 不要不急の外出の自粛
- 外出する場合も、混雑している場所や時間を避けて行動する
- 不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛
- 営業時間の変更を要請した時間以降の飲食店等への出入りの自粛
- 飲食店等を利用する場合、同一グループ・同一テーブルでの会食は4人以内とする
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用の自粛
- 基本的な感染防止対策の徹底(「三つの密」の回避、マスクの着用、手洗い、うがい、人と人との距離の確保など)
Q3.まん延防止等重点措置による要請に違反した場合の罰則とは?
住民が要請に従わなかったとしても、罰則はありません。
まとめ
新型コロナウイルスへの感染拡大は、「第○波」が収束しても、ほどなくして次の波がやってくるのが実情です。
今後も、しばらくの間はいつ・どの地域にも、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発出されてもおかしくない状況が続くでしょう。
国民1人1人が日頃から情報を確認しつつ、基本的な感染防止対策を徹底することが重要です。
コロナ禍で「収入が減少した」「解雇された」「生活が苦しくなった」等々の困りごとがあれば、さまざまな支援を受けられる可能性があります。
まずは、お住まいの自治体の担当課や弁護士に相談してみましょう。


