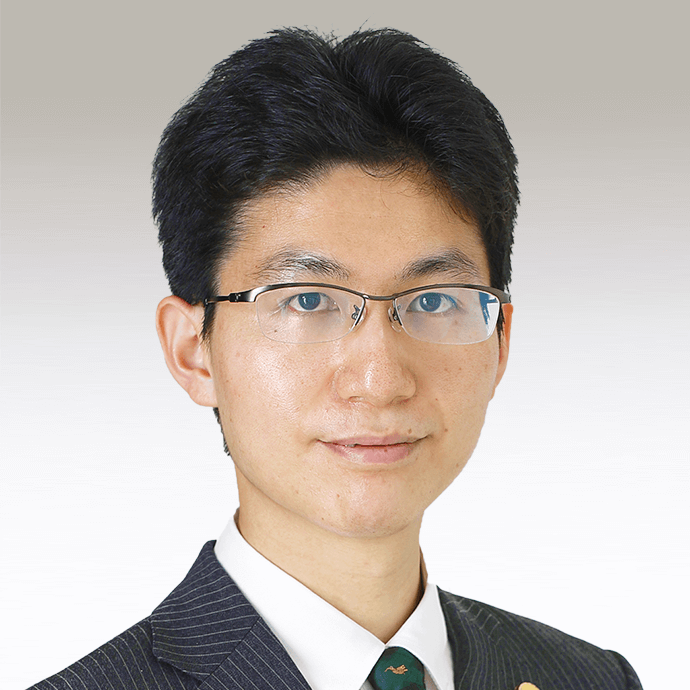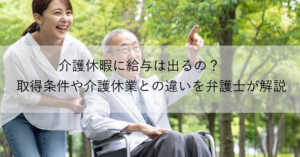
「介護休暇をとりたいけど給与面が心配」とお悩みではないですか?
介護のために必要がある場合には、年5日(対象家族が複数であれば10日)の介護休暇を取得できます。
ただし、介護休暇をとった際に給与を受け取れるかは会社によって異なります。状況が許すのであれば、給付金が出る介護休業を検討するのもひとつの手といえるでしょう。介護と仕事を両立するためには、それぞれの制度について十分に理解しておくことが必要です。
そこで今回は
- 介護休暇には給与が出る?
- 介護休暇を取得する条件
- 介護休暇と介護休業の違い
などについて解説します。
この記事が、介護と仕事の両立にお悩みの方のための手助けとなれば幸いです。
また、介護にお悩みの方は以下の記事も参考にしてください。
目次
1、介護休暇には給与が出るのか?

まずは、介護休暇について、給与が出るのかも含めて基本的な知識をおさえましょう。
(1)そもそも介護休暇とはどのような権利なのか
介護休暇とは、要介護状態の家族の介護を目的として取得できる休暇です。
年次有給休暇とは別に年に5日(要介護状態の家族が2人以上いれば10日)取得できます(育児介護休業法16条の5)。
介護休暇を活用すれば
- 家庭における介護
- 通院への付き添い
- 施設の見学
- 買い物
- 役所での手続
など、介護に必要な世話をすることが可能です。
(2)給与が出るかは会社によって異なる
介護休暇をとったときに給与が出るかどうかは、法律では定められていません。
会社に支払う義務が課せられていない以上、無給とされているケースも多いです。
- 有給か
- 無給なのか
は会社の規定によって異なるため、就業規則や雇用用契約書等の確認が必要になります。上長などにもたずねてみましょう。
2、介護休暇を取得したい!取得条件について

ここからは介護休暇の取得条件を紹介します。
ご自身の場合にあてはまるかをご確認ください。
- 家族が要介護状態であること
- 労働者自身についての条件
(1)家族が要介護状態であること
介護休暇を取得するには「対象家族」が「要介護状態にある」ことが必要です。
①対象となる家族の範囲
制度の対象になるのは、以下の範囲の家族を介護する場合に限られます。
- 配偶者(事実婚の場合を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
- 配偶者の父母
②要介護状態の意味
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態をいいます。
具体的には、以下のいずれかを満たさなければなりません。
- 介護保険制度の要介護状態区分で要介護2以上
- 次のチェック表で、「2」が2つ以上または「3」が1つ以上該当し、その状態が継続すると認められる
| 1 | 2 | 3 |
10分間ひとりで座る | 自分でできる | 支えがあればできる | できない |
立ち止まらず、座り込まずに5m程度の歩行 | つかまらずできる | つかまればできる | できない |
ベッドと車いす、車いすと便座の間などの乗り移り | 自分でできる | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的な介助が必要 |
水分や食事の摂取 | 自分でできる | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的な介助が必要 |
排せつ | 自分でできる | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的な介助が必要 |
衣類の着脱 | 自分でできる | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的な介助が必要 |
意思伝達 | できる | ときどきできない | できない |
外出すると戻れない | ない | ときどきある | ほとんど毎回ある |
物を壊す、衣類を破く | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある |
周囲の人の対応が必要なほどの物忘れ | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある |
薬の内服 | 自分でできる | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的な介助が必要 |
日常の意思決定 | できる | 重要な意思決定はできない | ほとんどできない |
参考:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 介護休業制度」
(2)労働者についての条件
対象となる労働者の範囲は広いです。
- 契約社員
- 派遣社員
- パート、アルバイト
など正社員以外の雇用形態であっても介護休暇を取得できます。ただし日雇い労働者は取得できません。
また、労使協定で以下の労働者は介護休暇を取得できないと定められているケースがあります。
- 入社してから6ヶ月に満たない
- 所定労働日数が週2日以下
3、実際に介護休暇を取得するには何をすればよいのか

条件を満たしていることを確認したら、会社のルールにしたがって申請しましょう。
法律上は口頭での申請も可能ですが、書面の提出について社内ルールがあれば、そちらで申請しましょう。
家族の介護の必要性が予想されたら、事前に申請方法などを上長に確認しておくとスムーズに進むかもしれません。
また、以下に紹介するように、制度改正により介護休暇が使いやすいものになっています。
積極的に活用を検討してみてください。
4、介護休暇を利用しやすい環境が整えられ始めた〜1時間単位での取得

近年法改正があり、介護休暇の利用が促進されています。
新しい制度の内容を解説します。
- 1時間単位で介護休暇を取得できるようになった
- 中抜けについて
- 労働者によって介護休暇の取得時間が異なるのか?
(1)【令和3年1月から】1時間単位で介護休暇を取得できるようになった
令和3年(2021年)1月から、1時間単位で介護休暇を取得できるように制度が改められました。
従来は1日または半日単位でしか休暇が認められていませんでした。
「2時間だけ利用したい」というケースでも半日休暇を取得するしかなく、その分だけ休める回数が少なくなっていたのです。
現在の制度では1時間単位で取得できるようになったため、短時間の休暇を頻繁にとることもできます。
また、以前は1日の所定労働時間が4時間以内の労働者は取得できないとされていましたが、その制限はなくなりました。
介護休暇を取得しやすい方向に制度改正がなされたといえます。
(2)中抜けは可能なのか
法律上、中抜けして介護休暇をとる権利までは認められていません。
「昼間の2時間だけ中抜けし、用事をすませて戻る」ことは要求できないとされます。
ただし、会社が中抜けを認めるとのルールを設けていれば問題ありませんので、この点も確認してみてください。
(3)労働者によって介護休暇の取得時間が異なる?
1時間単位で取得する際には、労働者によって取得できる介護休暇の総時間数が異なります。
①所定労働時間によって総時間数が変わる
1時間単位で取得するときの時間数の上限は、所定労働時間数の5日分(対象家族が複数いれば10日分)までです。
たとえば、所定労働時間が5時間の労働者が1時間単位で取得するときは、合計で5時間×5日=25時間までとなります。
②所定労働時間に端数(30分など)がある場合
所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合には端数を切り上げて計算します。
たとえば、所定労働時間が
- 7時間15分
- 7時間30分
- 7時間45分
の場合はいずれも1日8時間としてカウントします。
したがって1時間単位でとる場合には8時間×5日=計40時間の取得が可能です。
5、給付金も出る!長く休みをとりたいなら介護休業を~介護休暇との違い

先ほど説明したように、介護休暇は無給となってしまうリスクがあります。
これに対して介護休業であれば、給付金の受給が可能です。
- 介護休暇
- 介護休業
の違いを解説します。
(1)まとまった時間をとれる
介護休業は、対象家族1人につき合計93日まで取得可能です。介護休暇は年5日なのに対し、介護休業は通算で93日です。毎年与えられるものではないので注意してください。
介護休業は3回まで分割して取得できます。
例えば
- 93日を1度にまとめてとる
- 46日と47日に分けてとる
- 31日ずつ3回に分けてとる
など、都合に応じて変えられます。
介護休暇と比べてまとまった時間をとれるのが介護休業の特徴です。
(2)介護休業給付金で減収をカバーできる
介護休業中の給与については、介護休暇と同じく法律では定められていません。
支払われるかは会社の規定によります。
会社が給与を支払わないとしても、条件を満たせば雇用保険から給付金が支給されます。
金額は最大で休業前の賃金の67%です。
給付金を受け取れる介護休業では、減収を一定程度カバーし金銭的な不安を多少は和らげることができます。
(3)取得条件はやや厳しい
介護休業を取得する条件は、介護休暇に比べるとやや厳しいです。
具体的には、対象家族に関しては介護休暇と同様ですが、労働者の雇用期間について条件が変わります。
正社員であれば問題なく取得できるものの、期間を定めて雇用されている場合は以下の全ての条件に該当しなければなりません。
- 入社から1年以上
- 「取得予定日から数えて93日を経過する日」から6ヶ月を経過するまでに労働契約の期間が満了することが明らかとはいえない
契約更新が見込まれない場合には、介護休業は取得できません。なお「入社から1年以上」の条件は、令和4年(2022)年4月より撤廃されます。
申請は、希望通りの期間に介護休業を取得するためには、書面で2週間前までにしなければなりません。介護休業は期間が長いため、介護休暇に比べて条件が少し厳しくなっています。
介護休業については以下の関連記事で詳しく解説しています。
6、会社に介護休暇をとれないと言われたら?

介護休暇を取得しようとしたのに会社に拒否されたらどうすればよいのでしょうか?
(1)会社は介護休暇を拒否できない!
介護休暇の申請があれば、会社は拒否できません。
拒否されるケースでは、担当者が育児介護休業法の規定を理解していない可能性があります。
また、介護休暇の取得を理由として不利益な待遇をすることも許されていません。
(2)納得できない対応をされたら弁護士にご相談を
例えば
- 事情を説明しても介護休暇を取らせてくれない
- 介護休暇を取ったら降格させられた
といった理不尽な対応をされたら、弁護士にご相談ください。
弁護士は、
- 制度の説明
- 対処法のアドバイス
- 会社との交渉
といったお手伝いができます。
介護休暇は労働者に認められた権利です。泣き寝入りせずにすむよう、弁護士の力を借りてはいかがでしょうか。
まとめ
ここまで、介護休暇について
- 給与支給の有無
- 取得条件
- 介護休業との違い
などを解説してきました。
介護休暇は介護をしながら働く方にとっては必要不可欠な制度です。正しい知識をもとにフルに活用しましょう。
もし職場の理解が不十分であれば、ひとりで悩まずにお早めにご相談ください。