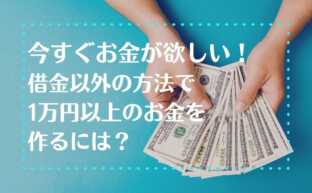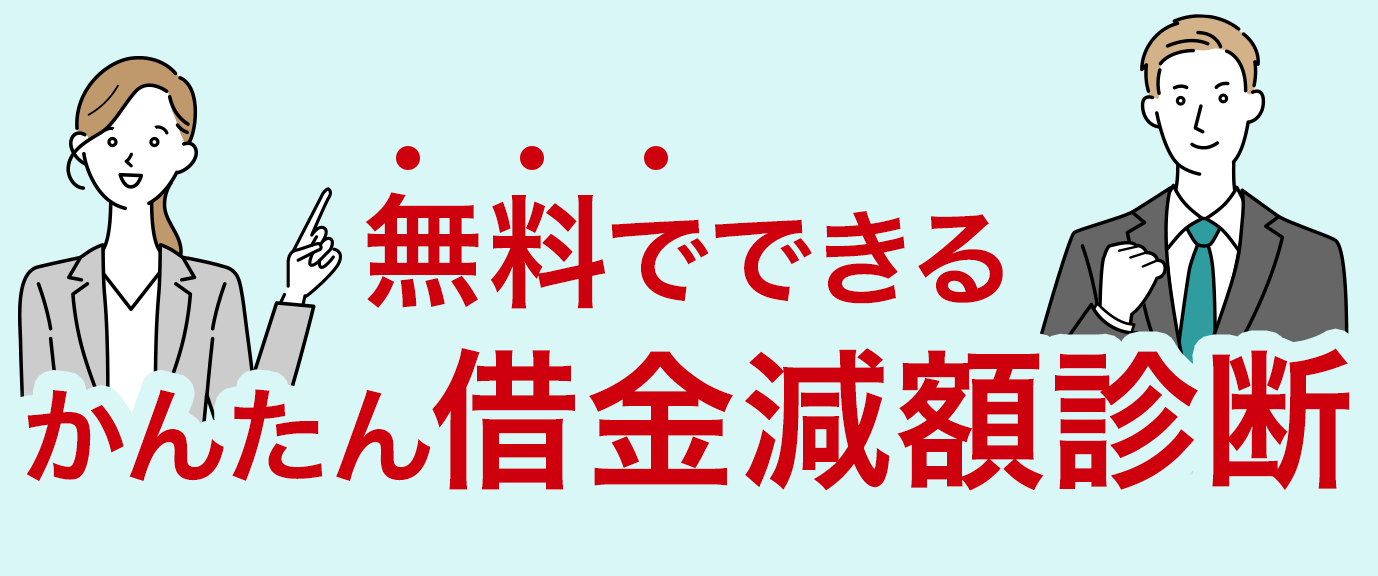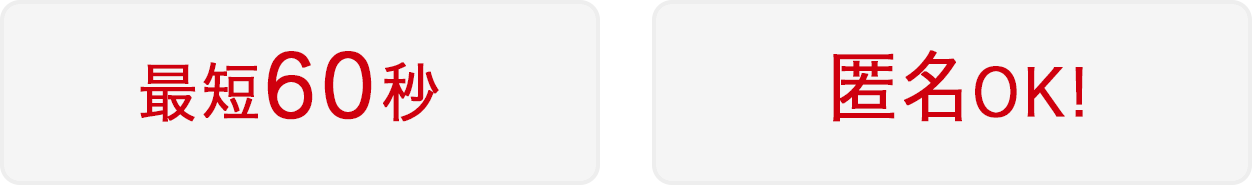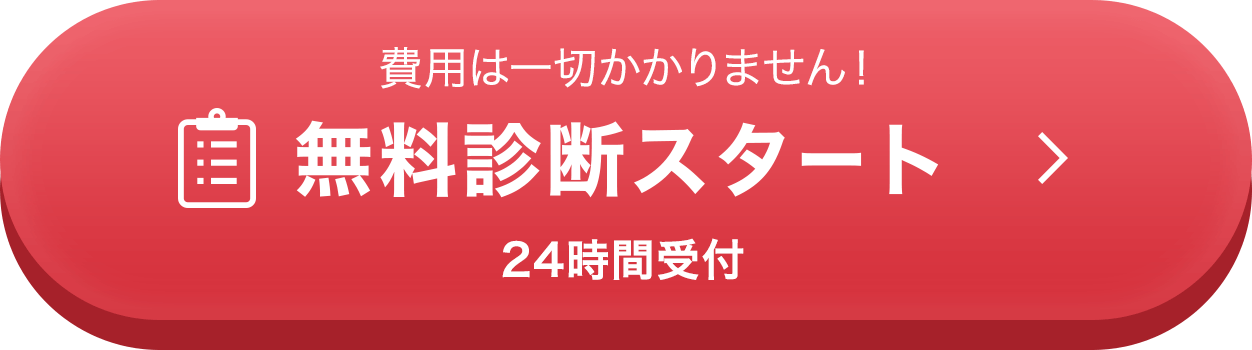金銭を貸し付ける時の利息の額は、利息制限法で決められた限度内でなければなりません。
今回は、「利息制限法の目的と規制内容」と題して、利息制限法の具体的な規制内容を詳しく解説していきます。
目次
1、利息制限法とは
利息制限法とは、消費者金融や銀行の融資商品に代表される「金銭貸借契約」につき、上記のような貸す者(=債権者)を規制する法律です。名称の通り、借りる者(=債務者)に支払ってもらう利息につき、限度を決めて債権者に守らせるためのものです。
(1)金銭貸借契約における利息の種類【基礎知識】
実際に金銭を貸し付ける取引では、返済時に「契約金利に応じた利息」と「遅延損害金」を上乗せして支払います。
上記どちらも利息制限法による規制対象ですが、契約上の扱いが異なれば、定められた限度にも違いがあります。
ここで基礎知識として利息の種類を整理し、お金を貸し付ける契約のどの部分に利息制限法が関わるのか、整理しておきましょう。
①契約金利(利率・年利とも)
ATMで出金操作する等の借入取引を行うと、翌日から利息の計算が始まります。
計算のベースになるのは、当初の契約内容にある「元本につき年●%」とのような取り決めです。
上記の定めは「利率」や「契約金利」と呼び、年単位としている点で「年利」と表現することもあります。
利息制限法では、第1条で年利の上限を定めています。
②遅延損害金(延滞利息とも)
期日を過ぎても返済がないと、利息の代わりに「遅延損害金」が毎日加算されます。
取引上の見かけは利息の呼び方を変えただけですが、法律上の扱いは、債務不履行によって債権者が負った損害額です(民法第419条)。
上記の扱いと結び付けて理解しておきたいのは、遅延損害金には「契約で利率を定めなくても発生する性質」がある点です。
もちろん、利率についてあらかじめ合意するのは自由ですが、その際は利息制限法第4条または第7条の限度を守らなくてはなりません。
(4)出資法と利息制限法との関係
債権者が受領できる利息に限度を設ける法律として、別に「出資法」もあります。
金銭貸借をするなら利息制限法も出資法もどちらも遵守しなければなりません。
2つの法律は、互いに債権者に対する規制を補完し合う関係にあります。
利息制限法は貸借取引そのものにルールを課すのに対し、出資法は金銭貸借取引を含む営業活動全体にやっていいこと・やってはならないことを定めるイメージです。
▼利息制限法の内容
- 利息の制限
- 遅延損害金の制限
- 債務者負担額のうち利息として扱う部分(=みなし利息)の定義
→融資取引の契約時は、出資法の利息制限規定と合わせて必ず確認する
▼出資法の規制内容(一例)
- 利息制限法の最高利率を超える場合の罰則
- 特定金融機関(=銀行等)以外の預り金の禁止
- 不特定多数の者に対する元本保証の上での出資受け入れの禁止等
2、利息制限法の上限を超える金利の扱い
債務者から受け取った利息のうち、利息制限法の上限金利を超える部分は「超過利息」と呼ばれます。
ひとたび超過利息が認められると、当事者の問題では済まされません。少なくとも行政処分は避けられず、刑事訴追されて二度と営業できなくなる場合すらあります。
超過利息の例は以下の通りです。
2022年1月に5万円貸し付け、翌年1月になって迷惑料込みで10万円支払ってもらった場合
→上限利息は1万円(5万円×20%)
→受領して良いのは元本5万円+利息1万円=6万円まで
→実際の受領額は10万円で、うち4万円が超過利息となる
貸金業者が融資額ごとの上限金利を上回る取引をしていたと分かった場合、営業を制限する行政処分が下されます。
(3)法律上の処罰規定【刑事上の責任】
年20%以上の契約金利を課していた債権者は、刑事訴追される可能性があります。
罰則の内容は出資法第5条で明示されており、整理すると表のようになります。
取引上の利率 | 貸金業者である場合 | 貸金業者ではない場合 (1回限りの取引等) |
年20%以上109.5%未満 | 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科 | なし |
年109.5%超 | 10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、または併科 | 5年以下の懲役 もしくは1000万円 |
3、利息制限法で定める金利の上限を表で確認
金銭貸借契約につき1つひとつ適法性を確認していくとなると、利息制限法の内容が一目で分かるものが欲しいところです。ここで一旦、上限金利を表にまとめてみましょう。
(1)契約金利の上限
利息制限法第1条で定められた契約金利の上限を整理すると、下の表の通りとなります。
元本に応じて段階的に上限が引き下げられており、表の「元本の額」には利息とみなされる各種手数料等も含まれる点、ここで改めて注意しましょう。
元本の額 | 金利の上限 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上 100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
(2)遅延損害金の年利
遅延損害金の利率は、当事者間の合意の有無で変わります。
契約上の合意がなければ民法第404条2項・第404条3項の「法定金利」が適用され、合意があれば利息制限法第4条もしくは第7条1項の規定が適用されます(表参照)。
ここまでの解説を整理しつつ、表で遅延損害金の限度を確認してみましょう。
元本の額 | 契約上の合意なし | 契約上の合意あり | |
非営業的取引 | 営業的取引 | ||
10万円以内 | 一律3%※ | 年29.2%以内 | 20%以内 |
10万円以上 100万円未満 | 年26.28%以内 | ||
100万円以上 | 年21.9%以内 | ||
※先の民法大改正により、2020年4月1日以降の取引に適用される利率です。変動制であり、今後3年おきに見直される予定です。
4、利息制限法に基づく返済利息の計算式
法律に基づく利息の最大額は、個別の融資額から計算しなくてはなりません。
個人消費者向けの商品(クレジットカード・住宅ローン等)は残債方式で契約するのが一般的で、返済する度に下記の式を使って利息を割り出します。
残債方式では以下の通りです。
前回返済後の元金(借入残高とも)×年利÷その年の日数×前回返済からの経過日数
なお、契約上は決済手数料として利息を受領する場合は、下記のアドオン方式を使います。融資額・年利共に同一の契約で、かつ1回払いを選択するのであれば、法律上の利息は残債方式と同額です。
アドオン方式では以下の通りです。
借入当初の元金(借入残高とも)×年利×貸出期間
5、利息制限法&出資法の改正を巡る問題│過払金の仕組み
金銭貸借契約に関わる機会があるのなら、なるべく頭に入れておきたい問題があります。
貸金業界で見られるようになった「過払金返還請求」を巡るトラブルです。
トラブルのきっかけは、平成22年(2008年)にあった利息制限規定の見直しです。
法改正で撤廃された「グレーゾーン金利」を巡り、当時の取引当事者の間で、支払済の利息の返還について話し合わざるを得なくなっているのです。
(1)グレーゾーン金利とは【平成22年6月に完全撤廃】
グレーゾーン金利とは、利息制限法の規制を超え、かつ旧出資法の罰則の対象にならない範囲で定められた高金利を意味します。
利息制限法の最高利率(年20%)を超えると刑事罰が科される仕組みは、法改正で整えられたものです。
上記法律の内容は改正以前から据え置かれているところ、刑事罰を定める出資法側の基準がより緩やか(年29.2%超)で、高利貸し規制のシステムは実効性に欠けていました。
実際、一定の要件を満たして旧出資法の適用を受け、年20%超かつ年29.2%未満の契約金利=グレーゾーン金利で営業する業者が多数存在したのです。
元本の額 | ①利息制限法の上限 | ②旧出資法で刑事罰の対象となる金利 | ③改正出資法で刑事罰の対象となる金利 |
10万円以内 | 年20% | 年29.2%超 | 年20%超 |
10万円以上 100万円未満 | 年18% | ||
100万円以上 | 年15% |
グレーゾーン金利は、現在、廃止されているため、利息制限法の上限金利を超えて支払ったお金は「過払い金」として取り戻せる可能性があります。
まとめ
契約金利を定める時は、利息制限法で定められる上限を守らなくてはなりません。
融資担当者として誤案内でトラブルになったり、債務者として損になる取引をしたりすることのないよう、法律の理解をしっかり深めておきましょう。
最後に改めて上限金利を整理しておくと、次のようになります。
▼みなし利息を含む契約金利の上限
10万円未満…年20%
10万円以上100万円未満…年18%
100万円以上…年15%
※融資額に関わらず、契約金利が年20%を超えると刑事罰に処される恐れあり
▼遅延損害金の上限金利
契約時に合意がない場合…年3%
契約時に合意あり+営業的取引の場合…年21.9%~年29.2%※
契約時に合意あり+営業的取引でない場合…20%
※融資額で異なる