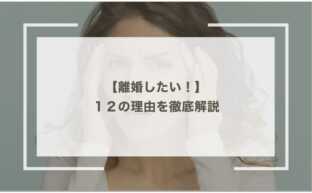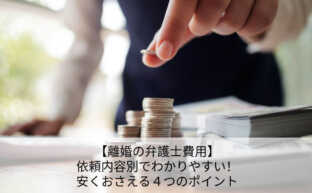夫婦関係が不妊によって険悪になり、離婚を検討する人は珍しくありません。
一つの調査によれば、日本の夫婦の中で、不妊治療や検査を受けているか、または経験したことがあると回答した割合は全体の22.7%に達しています。
(引用元:国立社会保障・人口問題研究所の「2016年社会保障・人口問題基本調査」)
不妊は深刻な悩みに突き当たると、夫婦間での誤解が生まれ、最終的には離婚の危機に直面することがあります。
このため、今回は以下の点に焦点を当てて説明します。
- 不妊を理由にして離婚できるのか?
- 不妊離婚時の慰謝料請求は可能か?
- 不妊だけど離婚せずに子供を望む場合、どう進めるべきか?
この記事が、子供を授かることに悩みを抱える夫婦に、役立つ情報を提供できれば幸いです。
また、離婚したい方が網羅的に把握しておくべき内容についてはこちらをご参照ください。
目次
1、不妊で離婚を考える4つのパターンとは
不妊が原因で離婚を考えるようになるまでにはさまざまな事情があるものですが、よくあるのは以下の4つのパターンです。あなたに当てはまるものはあるでしょうか。
(1)夫が妊活に非協力的
まず第一に挙げられるのは、妻が子どもを望んで妊活に励もうと思っても、夫が協力的でないパターンです。
夫が「子どもはいらない」というわけではないものの、「仕事が忙しくて疲れている」「今日はそんな気分じゃない」などと言って、やんわりと子作りを避けるケースは多いものです。
妻から「一度、検査を受けてみない?」と提案しても、「そんな必要はない」「そのうち授かるだろうから、自然に任せよう」などと言って協力してもらえないこともあるでしょう。
このような状況では、不妊の原因がどちらにあるのかすらあやふやで、妻としては夫に協力を強制することもできず、ジレンマで苦しむことになります。
やがて、「いっそのこと、手遅れになる前に別れた方がいいのかな……」と考えてしまうのが、このパターンです。
(2)妊活が原因で不仲に
第二のパターンは、妊活が原因で夫婦の仲が悪くなってしまうというケースです。
不妊の原因がどちらにもないものの、妻と夫で妊活に対する温度差がある場合に起こりがちなパターンといえます。典型的なケースは、妻が妊活に傾注するあまりに子作りの行為が義務的なものになってしまい、夫が冷めてしまうというものです。
他にも、お互いに仕事などが忙しくて子作りのスケジュールがなかなか合わず、次第に冷めてしまうケースもあります。
また、二人目不妊の場合、一方が「妊活をしてでも二人目が欲しい」と言い、もう一方は「一人いるからいいじゃないか」と言って対立してしまうこともあるでしょう。
(3)どちらかに不妊の原因があった
不妊の原因が判明した場合も、離婚の危機に陥るケースがあります。
どちらに原因があったとしても、それは責めるべきことではありません。それがわかるからこそ、気持ちのぶつけようがなくなり、お互いにとても辛くなってしまいます。
このケースで、原因がない側が、「子どもが作れない相手とは別れて別の人を探そう」などと考えるケースがあるのなら、それはもう抵抗せず別れた方がよいでしょう。悪い人ではないのでしょうが、自己中心的な性格であることは間違いありません。あなたのために、自分の夢を諦める気はないのです。
一方で問題なのは、相手のために別れた方がいいのでは、と考えてしまうケースです。相手を思いやるがゆえに、自分ではない相手となら幸せになれるのでは、と思い詰めてしまいます。苦しいに違いありません。
2、不妊の原因
そもそも不妊とは、日本産婦人科学会では以下のように定義されています。
「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないものをいいます。
日本産科婦人科学会では、この「一定期間」について「1年というのが一般的である」と定義しています。
つまり、健康な夫婦が避妊をせずに性生活をしていても1年間妊娠しない状態を不妊といいます。
では、不妊の原因にはどのようなものがあるのでしょうか。
(1)男性不妊
男性不妊の原因としては、主に以下のようなものが挙げられます。
①造精機能障害
精子が作られていなかったり(無精子症)、あるいは精子の数が少ない(乏精子症)、精神の運動性が悪いといった障害のことです。
②精路通過障害
精子が正常に生産されていても、体外に排出されるまでの道が何らかの原因で詰まっているために、精子を排出できないという障害です。
手術によって精路を再建すれば、正常に精子を排出できるようになることが期待できます。
③性機能障害
勃起障害(ED)や膣内射精障害などによって性行為ができないか、できても射精できないという障害です。
ストレスが原因で起こりやすい障害ですので、精神的なケアが有効とされています。投薬治療も行われます。
④加齢による影響
男性の場合も概ね35歳を過ぎると精子の質が低下し、妊娠率が低下していくとされています。
男性不妊の治療法としては、上記で説明した方法の他、人工授精や体外受精といった方法があります。
(2)女性不妊
女性不妊の原因としては、主に以下のようなものが挙げられます。
①排卵障害
月経がないか、月経のような出血があったとしても排卵が行われない障害のことです。
原因としては、ホルモンバランスの異常や、極度の肥満あるいは体重減少、甲状腺の病気、精神的な要因などが考えられます。
治療法としては、原因となる疾患の治療や、排卵を誘発する療法などが有効とされています。
②卵管障害
卵管が炎症などによって詰まることによって卵子が子宮に至ることができないという障害です。
クラミジア感染症や子宮内膜症の病変によって、卵管が詰まりやすいとされています。
治療法としては、手術によって卵管を開通させることが有効とされています。
③頸管障害
子宮頸管内の粘液の分泌が少なかったり、異常があったりすることで、精子は子宮内に入りにくくなるという障害です。
投薬治療が有効とされています。
④子宮の異常
子宮に異常があるために、受精卵(胚)が着床しにくくなることがあります。
原因としては、子宮筋腫や先天的な子宮の異常などが考えられます。
治療法としては、手術療法が有効とされています。
⑤加齢による影響
女性の場合は男性の場合よりも加齢による影響が大きく、30歳を過ぎると卵子の質が低下して自然妊娠する確率が低下しはじめ、35歳を過ぎるとその傾向が顕著に進むといわれています。
女性不妊の治療法としては、上記で説明した方法の他、子宮が正常な場合は人工授精や体外受精も有効です。
(3)機能性不妊
不妊検査を受けても、夫婦のどちらにも原因が見当たらず、原因不明の不妊症のことを「機能性不妊」といいます。
この場合には、タイミング法(排卵日を予測して性交を行う方法)や排卵誘発法(投薬によって排卵を起こさせる方法)によって自然妊娠できるように試みます。
それでも妊娠しない場合は、人工授精(採取した精子を排卵の時期に合わせて子宮内に注入する方法)や体外受精(体外で精子と卵子を合わせて受精させ、その受精卵を子宮内に戻す方法)を行います。
参考:一般社団法人日本生殖医学会|Q8.不妊症の治療にはどんな方法があり、どのように行うのですか?
3、不妊を理由に離婚はできるのか
不妊によって夫婦が不仲になり、二人の合意のもと離婚することは自由です。
問題は、相手が離婚を拒否した時に、司法の力で離婚を成立させられるかどうかということでしょう。
(1)婚姻を継続し難い重大な事由かどうか
相手が離婚を拒否する場合に裁判をしてでも離婚を成立させるためには、配偶者に「法定離婚事由」があることが必要です。
具体的には、民法770条1項に列挙されている以下の5つのいずれかに該当する事情がなければ離婚は認められません。
不妊が原因で夫婦関係に亀裂が入った場合、問題となるのは5番目の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかです。
結論として、不妊そのものは婚姻を継続しがたい重大な事由には該当しません。しかし、不妊をきっかけとして他の事情も絡んでいる場合には、婚姻を継続しがたい重大な状況に至っているといえるケースもあります。
(2)婚姻を継続し難い重大な事由であるケース
婚姻を継続しがたい重大な事由といえる可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます。
①不妊治療を巡ってケンカが絶えず極端に夫婦仲が悪くなった
単なる夫婦喧嘩では離婚は認められませんが、修復困難なほどに夫婦仲が悪くなった場合や、パートナーからの暴力(DV)や暴言(モラハラ)がある場合には、婚姻を継続できないとして離婚が認められる可能性があります。
②不妊に悩みうつになった
夫婦の一方がうつ病になったとしても、それだけでは婚姻を継続しがたい重大な状況とまではいえません。「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」に該当するともいえないので、離婚するのは難しいといえます。
もっとも、うつ病で苦しんでいるのにパートナーの思いやりが欠けており、それが原因で長い別居に至ってしまったなどということになれば、離婚が認められる可能性があります。
③セックスレスになった
夫婦間において、性交渉というのは重要な部分を占めています。
なので、夫婦の一方が性交渉を拒否する状態が長期間続いている場合には、婚姻を継続しがたい重大な状況に該当し、離婚が認められる可能性があります。
4、不妊離婚と慰謝料の関係
不妊で離婚が認められる場合に、慰謝料を請求できるかどうかも気になるところでしょう。
慰謝料とは、他人の不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
不妊そのものは不法行為ではありませんので、不妊だけを理由として慰謝料請求が認められるのは難しいといえます。
しかし、やはり不妊をきっかけとして他の事情が絡んでいる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。詳しくみていきましょう。
(1)妊活に非協力的だったパートナーへの慰謝料請求は可能?
妊活に非協力的なこと自体は不法行為に当たりません。
しかし、単に協力しないだけでなく、暴力(DV)や暴言(モラハラ)、長期間のセックスレスなどがある場合には、これらの行為が不法行為となり、慰謝料請求が認められる可能性があります。
(2)パートナーに不妊の原因があって離婚したら慰謝料請求は可能?
パートナーに不妊の原因があること自体は責められることではないので、基本的に慰謝料請求は認められません。
ただし、元から不妊の事実がわかっていて、それを偽り結婚していた場合には、その点を不法行為と捉えて慰謝料請求できる可能性があります。
(3)自分に不妊の原因があって離婚をすることになったら慰謝料請求は可能?
自分に不妊の原因がある場合も同様に、パートナーからの暴力(DV)や暴言(モラハラ)、長期間のセックスレスなどといった事情がない限り慰謝料請求は認められません。
ただし、パートナーから離婚を突きつけられた場合、離婚に応じる条件として財産分与に慰謝料的要素を含ませて、多めの財産を取得する(慰謝料的財産分与)ことは考えられます。
簡単にいうと「解決金」を求めるようなものともいえます。
慰謝料的財産分与について詳しくは、こちらのコラムをご参照ください。
(4)二人目不妊で離婚することになったら慰謝料請求は可能?
二人目不妊で離婚する場合も、基本的には上記(1)~(3)と同じです。
ただし、一人目の子どもをあなたが引き取る場合は、「養育費」を多めに請求するという形で、実質的に慰謝料を回収できるかもしれません。
5、不妊離婚はしたくない、でも子供が欲しい・・どうすれば?
不妊に悩んでいても、離婚を考える夫婦ばかりではありません。
そんな理由で離婚したくないという夫婦も数多くいらっしゃいます。
ただ、それでも子どもは欲しい……という気持ちは捨てられず、ジレンマに苦しむこともあるでしょう。
そんなときは、以下の対処法を検討してみましょう。
(1)里親制度
里親制度とは、何らかの事情で子どもを育てられない親に代わって子どもを預かり、養育していく制度です。養子縁組をすれば、あなたたちご夫婦が預かった子どもの親権者となります。
また、「特別養子縁組」を結ぶことも可能で、その場合は子どもと実親との法律上の親子関係は切れ、養親と養子は原則として離縁できなくなります。
戸籍にも実子と同じように「長男」や「長女」などと記載されますので、本当の親子だと思って子どもを育てていくことが可能になります。
子どもの親になってみたい、育てる幸せを感じてみたいというカップルにはいい選択肢になるでしょう。
気になった方は下記記事をご覧ください。
(2)子どものいない夫婦に目を向けてみる
もうひとつの方向性として、子どもがいなくても夫婦で幸せを築くことはできるということも考えてみてはいかがでしょうか。
子どもありきに考えてしまっている場合には一度、子どものいない夫婦にも目を向けてみてください。子どもがいなくてもお互いを信頼し幸せに暮らす夫婦もたくさんいることに気がつけるはず。自分たちに欠けていたものに気がつくことができるかもしれません。
子どもをもうけなかった老齢カップルにも目を向けてみるべきです。その方達はどういう人生を送っているかをみて、そしてそこに自分を重ねることができるかどうか。
子どもがいない夫婦の多くは、夫を子どものようにお世話する関係、対等に男女の親友のようになる関係など、自分たちらしいカップルへ成長しています。
子どもは、いつしか巣立って手を離れていきます。いずれはどのカップルも夫婦2人きり。
子どもに時間とお金をかけることなく、自分のために、そして2人の時間を謳歌するのも大変充実した人生です。
さまざまな情報に触れて、自分たちらしい人生を築いてみてはいかがでしょうか。
6、不妊が絡んだ離婚で悩んだら弁護士に相談を
不妊はデリケートな問題であるだけに、離婚を考え始めると、他の原因による離婚問題の場合よりも深い悩みやジレンマに苦しむことが多いです。
そんなときは、弁護士に相談することをおすすめします。
法律の専門家である弁護士に相談すれば、離婚が可能かどうかや、可能な場合には離婚手続きをどのように進めればよいのか、慰謝料請求はどうすればよいのかについてもアドバイスが得られます。
また、離婚問題の経験が豊富な弁護士はさまざまな問題を抱えた夫婦を見てきていますので、夫婦関係を修復する方向でもアドバイスを得ることが可能です。
法的手段をとるにしても、「離婚調停」を依頼する方向性もあれば、修復するための「夫婦関係調整調停」を依頼する方向性もあります。
費用についても、柔軟に相談に応じてもらえる法律事務所が多くあります。あなたの状況に応じて最善の解決策を提案してもらえるはずですので、ひとりで悩まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
不妊という現実に直面すると、夫婦の価値観の違いが顕著に表れやすくなります。子どもをもうけるかどうか、そのために多大な経済的負担や精神的負担に耐えてまで努力するかどうかについて、双方の価値観の違いから深刻な対立に発展することもあるでしょう。
しかし、不妊の原因がどちらかにあったとしても、一方的に責めることはできませんので、不妊は2人で協力して乗り越えていくべき問題です。
最終的に離婚するとしても、お互いの将来のことを冷静に考えて、最善の道を選択しなければなりません。
どうすればよいのかが分からないときは、弁護士の力を借りましょう。
本記事を参考に、あなたが幸せのために少しでも前向きに考えられたら幸いです。