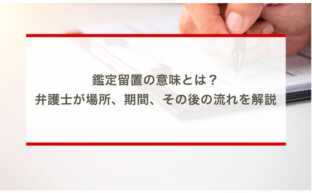鑑定留置は、刑事事件において被疑者や被告人が精神障害などで刑事責任能力に疑念がある場合、病院などの施設に留置する処分のことです。
今回は
- 鑑定留置とは何か?
- 鑑定留置の内容とは?
- 鑑定留置後の流れ
について解説します。
1、鑑定留置とは?
(1)鑑定のために身体拘束する処分
刑事事件を犯すと、罪証隠滅や逃亡を防ぐ目的のために、逮捕され、その後、勾留という最大20日間の身体拘束がなされる可能性があります。
鑑定留置とは、逮捕や勾留と同じく、身体の自由を拘束する処分ではあるものの、刑事事件の被疑者・被告人の責任能力についての鑑定を行うことを目的として、病院などに留置する処分をいいます。
このように、逮捕・勾留と鑑定留置は、その目的を異にします。
一般的には起訴前になされ、検察官の請求を裁判所が認め、令状が発行されることで可能となるものです(刑事訴訟法第224条)。
起訴後は、裁判所の職権によって決定されます((刑事訴訟法第165条))
(2)責任能力がないと刑罰を科せない
鑑定留置をする際に問題となる責任能力とは、行為の是非を弁別し、それに従って行動を制御できる能力をいいます。事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のない者に対しては、行為を非難することが出来ず、刑罰を科す意味に欠けるので、刑罰を科すには責任能力が必要です。
責任能力が欠けている状態としては、心神喪失と心神耗弱があります(刑法第39条)。
①心神喪失(刑法第39条1項)
心神喪失とは、精神の障害により、弁識能力(行為の是非を判断する能力)を欠くまたは行動制御能力(行動をコントロールする能力)を欠く場合をいいます。心神喪失の場合には責任能力が全くないため、刑罰が科されません。
②心神耗弱(刑法第39条2項)
心神耗弱とは、精神の障害により、弁識能力が著しく低いまたは行動制御能力が著しく低い場合をいいます。心神耗弱の場合には責任能力が一部認められるため、刑が減軽され上限は低くなるものの、刑罰を科すこと自体は可能です。
(3)簡易鑑定と起訴前本鑑定との違い
責任能力に問題があって起訴前に鑑定が行われる場合、簡易鑑定と起訴前本鑑定の2種類の鑑定があります。鑑定留置がなされるのは、起訴前本鑑定の場合です。
①簡易鑑定
簡易鑑定では、医師が拘留中の被疑者を検察庁などで診察し、責任能力についての意見を検察官に伝えます。短時間で終了し、窃盗などの軽微な事件で用いられることが多いです。簡易鑑定で判断がつかずに起訴前本鑑定に回されることもあります。精神鑑定の多くがこの簡易鑑定です。
②起訴前本鑑定
起訴前本鑑定では、約2~3ヶ月の長期間にわたって病院などで医師が診察し、結果を鑑定書にまとめます。期間が長期に及ぶため、裁判所の令状を得たうえで鑑定留置をします。起訴前本鑑定が行われるのは殺人などの重大事件であり、件数としては多くありません。
まとめると以下の表の通りです。
鑑定の種類 | 期間 | 場所 | 特徴 |
簡易鑑定 | 1日 | 検察庁など | ・軽微な事件 ・判断できなければ本鑑定 |
起訴前本鑑定 | 2~3ヶ月程度 | 病院・拘置所など | ・重大事件 ・簡易鑑定で不十分な場合 |
2、鑑定留置の内容
(1)鑑定留置で調べられること
鑑定留置では、精神疾患が事件に影響を与えたかを判断するために、医師が面接や検査を行います。
メインとなるのは面接であり、医師は、供述調書などの捜査資料を読んだ上で面接に臨みます。
面接で調べるのは、生い立ち、事件前後の生活状況、事件当時の精神状態などです。面接の補助として心理テストも用いられます。
身体的な問題が精神に影響を与えることもあるため、医学的な検査も必要です。
具体的には、脳の画像検査、血液検査、脳波検査などが行われます。
医師は鑑定が終わると結果をまとめ、精神疾患が事件に与えた影響についての意見を述べます。
起訴・不起訴を判断するのは検察官であるため、医師は責任能力の有無までは言及しないのが一般的です。
(2)鑑定留置の場所
鑑定留置の場所は法律の条文で「病院その他相当な場所」とされています。
病院は医師にとって鑑定がしやすいですが、警備が不十分でなく、被疑者が逃走してしまうという事例も過去にありました。
そのようなことがないように、警備体制の整った拘置所が鑑定留置の場所とされるケースもあります。
(3)鑑定留置の期間
鑑定留置の期間に定めはありませんが、2~3ヶ月とされることが多いです。
期間中は勾留の執行は停止され、勾留の日数としてはカウントされません(刑事訴訟法第167条の2)。鑑定留置は責任能力の有無の判断を目的としているため、原則として鑑定留置中に検察官による取り調べは行われません。
また、接見禁止がついていれば家族などは面会が許されず、弁護士だけが面会できることになります。
3、鑑定留置後の流れ
(1)検察官が起訴するかを判断する
鑑定留置が終了すると、残りの拘留期間で検察官が責任能力の有無を検討し、起訴するか否かを判断します。
検察官は医師の鑑定結果を参考にしますが、起訴の決定権は検察官だけが持っているため、最終的には検察官が判断することになります。
(2)不起訴となった場合
検察官による検討の結果、「責任能力がなく罪に問えない」として不起訴になった場合でも、被疑者が直ちに社会に復帰できるとは限りません。
事件によって、検察官が都道府県知事に通報したり、医療観察法に基づく申立てを行ったりするなどの適切な措置をとり、被疑者が入院することもあります。
(3)起訴された場合
検察官が責任能力ありと判断して起訴した場合は、裁判で責任能力の有無が審理されることになります。
殺人や放火などの重大事件は裁判員裁判となるため、一般市民も参加して、裁判官とともに責任能力の有無を判断しなければなりません。
責任能力がなければ無罪となりますが、審理の結果としては「責任能力あり」とされることが多く、通常と同様の刑罰が科されます。
心神喪失・心神耗弱と判断された場合、重大犯罪については医療観察法に基づいて入院することになります。
4、鑑定留置を争う方法
(1)拘束期間を争う場合
鑑定留置の決定が出ても、弁護士が裁判所に準抗告を申立て、取消しや期間の短縮を求めることが可能です。
鑑定留置は2~3ヶ月という長期にわたって身体を拘束する処分であるため、弁護士が不適切と判断すれば、その是非をめぐって争いになることがあります。
実際に、3ヶ月半の鑑定留置期間の決定をした事件において、「短期間で実施可能な簡易鑑定を行うなどして本格的な精神鑑定の必要性を吟味すべきであって、これを経ることなく、直ちに本格的な精神鑑定を行うことを前提とした3か月以上の期間にわたる身柄拘束を認めることは、被疑者に対して過度の負担を強いるもの」として、14日間に限った鑑定留置期間のみを認める変更決定をしたものがあります(岐阜地決平成27年10月21日)。
鑑定留置がなされるのは、責任能力が問題となる難しい事件であるため、弁護士の力量が問われることになります。
(2)鑑定結果を争う場合
鑑定結果に納得がいかない場合、再度の鑑定の請求は、検察官からなされることもあります。
2017年7月に発生し、世間をにぎわせた無差別殺人事件(神戸市北区5人殺傷事件)では、鑑定留置中の精神鑑定で、被告人の犯行時の精神状態は不安定だった可能性があるものの責任能力に問題はないといったん判断されましたが、責任能力を慎重に見極めるため、検察官が再度の鑑定の請求を行い、裁判所がこれを認めました。
まとめ
ここまで、鑑定留置の内容や鑑定留置後の流れなどについて解説してきました。
鑑定留置についてのイメージはつかめたでしょうか。今後ニュースで耳にする機会があれば、ぜひこの記事の内容を思い出してみてください。