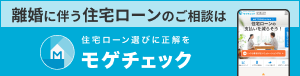「養育費算定表」をご存じでしょうか。
未成年者の子どもがいる夫婦が離婚をする場合、子どもの養育費を取り決めておくことが必要です。
また、養育費の取り決めがなかった場合でも、未成年の子どもを養育している場合には、養育していない側に対して養育費の請求をすることができます。
「養育費算定表」は、裁判所で用いられている養育費計算のためのツールです。「養育費算定表」を参照することで、子ども1人の家庭の場合、子ども2人の家庭の場合等、具体的な事例に即して、話し合いの基準となる養育費の額を知ることができます。
この記事では、「養育費算定表」の見方、「養育費算定表」を使った養育費の計算方法などについて、解説していきます。
養育費については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、「養育費算定表」は養育費の額を定める基準

(1)「養育費算定表」とは?
養育費算定表とは、東京・大阪に所属する裁判官の共同研究の結果、養育費算定のために作成された表です。
養育費算定表は、全国の裁判所で広く用いられており、裁判所は、養育費算定表に基づいて、具体的な養育費の額を決めています。そのため、養育費算定表は、養育費を算定する際の重要な資料ということができます。
(2)現在使われているのは「養育費算定表」(令和元年版)
養育費算定表は、平成15年に発表されたものと、令和元年に発表されたものの2つがあります。
現在使われているのは、令和元年に発表された新しい養育費算定表です。
養育費算定表が新しく発表された背景には、養育費算定表の基礎となっている職業費や学費等の統計データの変化があります。
新しい養育費算定表は、たとえば、令和元年よりも前に離婚した夫婦について養育費を定める場合のように、新しい養育費算定表発表前に離婚した夫婦についても用いられるため、現在では、平成15年に発表された古い養育費算定表が用いられることはありません。
(3)裁判所では「養育費算定表」に基づいて養育費の額が決められる
裁判所において、養育費を定める場合、養育費算定表が参照されます。
裁判所が、養育費を定めるにあたって、養育費算定表を全く用いることなく、独自に、養育費の額を決めることはありません。
また、裁判所が、裁判所が発表した養育費算定表以外の算定表を用いることもありません。
たとえば、日本弁護士連合会(日弁連)は、平成30年に、「養育費・婚姻費用の新算定表」を発表しました。日弁連が発表した「養育費・婚姻費用の新算定表」は、裁判所の養育費算定表に似たものですが、権利者に比較的有利な内容となっています。
養育費を多く支払ってもらいたいと考える側としては、日弁連の養育費算定表を使いたいところです。しかし、現在のところ、裁判所は、日弁連の養育費算定表は参照せず、あくまで裁判所の養育費算定表を用いて、養育費の額を決めています。
(4)話し合いでも「養育費算定表」は使える
養育費算定表は、裁判となった場合に、裁判所が用いる表です。
ただ、裁判となる前の話し合いでも、養育費算定表は使えます。
話し合いがまとまらなければ、裁判になり、いずれ養育費算定表を用いて養育費の額が決まりますから、わざわざ裁判をすることなく、養育費算定表を用いて養育費の額が決められるのであれば、それは合理的といえます。
そのため、裁判となる前の話し合いにおいても、養育費算定表は使えるということができます。
2、「養育費算定表」を見るときのポイント3つ

(1)子どもの人数と年齢を選ぶ
裁判所が公表している養育費算定表は、裁判所ホームページからダウンロードできます。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
表は全部で19個あり、子どもの人数と年齢によって区分されています。
子どもの人数は1人~3人で分かれており、年齢は0歳~14歳までと15歳以上とで分かれています。
たとえば、子どもが2人いて、上の子ども(第1子)が15歳、下の子ども(第2子)が10歳の場合には、「子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)」の表を選ぶことになります。
(2)お互いの年収は幾らかを確認する
①給与所得者の場合の確認方法
次に、お互いの年収を確認します。
給料所得者、いわゆる会社勤めの方の場合、直近の源泉徴収票で確認します。
注意が必要なのは、源泉徴収票のうち、税引き前の年収をみるということです。
税引き前の年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されています。下の図でいうと、赤い〇で囲った部分です。
また、昇給等により直近の源泉徴収票より変動がある場合や、働いて間もないために現在の勤務先の源泉徴収票がない場合などには、直近の給料明細書を確認することもあります。
ここでも注意が必要なのは、各種控除がされた後の「手取り」ではなく、控除前の支払金額を確認するという点です。
源泉徴収票や給料明細書は、基本的には勤務先から再発行してもらえますから、もし手元にない場合には、勤務先から再発行してもらいます。
②自営業者の場合の確認方法
自営業者の場合、直近の確定申告書で確認します。
まず、確定申告書の「課税される所得金額」の欄をみます。下の図でいうと、右上の青で〇をした部分で、図では289万7000円となっています。
次に、次のような項目を、「課税される所得金額」に加算します。
- 「雑控除」
- 「寡婦・寡夫控除」
- 「勤労学生・障害者控除」
- 「配偶者控除」
- 「配偶者特別控除」
- 「扶養控除」
- 「基礎控除」
- 「青色申告特別控除額」
- 現実に支出されていない場合には「専従者給与額の合計額」
- 「医療費控除」
- 「生命保険料控除」
- 「損害保険料控除」
- 「小規模企業共済等掛金控除」
- 「寄付金控除」
これらを加算する理由は、項目ごとによって異なりますが、①税務上控除されているだけで実際には支払っていない(配偶者控除や基礎控除)、②養育費算定表の中で一定額を控除することが予定されている(生命保険料控除や損害保険料控除)、③養育費の支払に優先するとは考えられない(寄付金控除)といったことが挙げられます。
上の図でいうと、加算する項目は、左下の青で〇をした項目になります。
したがって、上の図では、「課税される所得金額」が289万7000円、加算する「医療費控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「扶養控除」、「基礎控除」の合計が122万2000円ですから、合計411万9000円が養育費算定の基礎となる年収ということになります。
(3)お互いの年収が交差する部分を見る
お互いの年収が確認できたら、最後に、お互いの年収が交差する部分をみます。
養育費算定表では、養育費をもらう側を「権利者」、養育費を支払う側を「義務者」といいます。
たとえば、子ども2人、上の子が15歳、下の子が10歳、権利者・義務者共に給与所得者、権利者の年収が100万円、義務者の年収が500万円だとすると、「子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)」の表を使って、下の図のように、「8万~10万」の枠の下の方になります。
この場合には、おおむね、8万~9万円程度が養育費として相当ということになります。
3、具体例でみる「養育費算定表」を使った養育費の計算方法

(1)夫婦共に給与所得者、子ども1人の場合
この場合は、子どもが0歳~14歳であるか、15歳以上であるかによって使う表が異なります。
子どもが0歳~14歳であれば、「子1人表(0歳~14歳)」を使い、15歳以上であれば「子1人表(15歳以上)」を使います。
子どもが10歳であるとして、義務者の年収が500万円、権利者の年収が100万円であるとすると、下の図のように、「4万円~6万円」の枠の上の方になります。
この場合には、おおむね、5万円~6万円程度が養育費として相当ということになります。
(2)夫婦の一方が自営業者、他方が給与所得者、子ども2人の場合
まず、子どもの年齢を確認します。
仮に、上の子(第1子)が15歳、下の子(第2子)が10歳であるとすると、「子2人表(第1子15歳以上、第2子0歳~14歳)」の表を使うことになります。
次に、お互いの年収を確認します。
仮に、義務者が自営業者で、養育費の算定の基礎となる年収が500万円、権利者が給与所得者で年収100万円であるとすると、義務者の年収は養育費算定表の「自営」の欄を、権利者の年収は「給与」の欄を見て、交差する部分を確認します。
義務者の「自営」の欄をみると、500万円に対応する数字がありませんが、「512万円」と「496万円」の間と考えられますから、そこから横に線を伸ばし、交差する部分を見ます。
そうすると、下の図のように、「10万円~12万円」の枠の上の方になります。
この場合には、おおむね、11万円~12万円程度が養育費として相当ということになります。
(3)妻(又は夫)が専業主婦(主夫)、子ども1人の場合
一方が専業主婦(主夫)の場合、年収を0円として計算すべきでしょうか。
ケースバイケースではありますが、0円として計算することは少なく、パート程度の見込み収入(100万円~120万円)があるものとして、計算されることが多いです。
仮に、子どもの年齢が15歳、義務者が給与所得者で年収700万円、権利者が専業主婦(主夫)であるとすると、「子1人表(15歳以上)」を使って、下の図のように、「8万円~10万円」の枠の中くらいになります。
この場合、おおむね、9万円~10万円が養育費として相当ということになります。
(4)養育費計算ツールを使う
養育費算定表は、使い方が分かれば、ある程度、誰でも使うことができます。
ただ、表の選択や、給与の見方(給与所得者か自営業者か)を間違えると、間違った結論に至ってしまうという難点もあります。
また、わざわざ表をダウンロードして、線を引いてみてといった作業自体、面倒ということもあります。
現在では、子どもの人数、年齢、お互いの年収、給与所得者と自営業者の別を入力すると、養育費算定表上の養育費の枠が自動的に計算される便利なツールがあります(養育費計算ツール|弁護士による離婚相談ならベリーベスト法律事務所 (vbest.jp))。
こうしたツールを使って計算すると、簡単に、養育費の額を計算することができます。
4、「養育費算定表」からの修正が必要なケース

(1)住宅ローンを支払い続けるケース
たとえば、住宅ローンで自宅を購入した後、離婚することになり、権利者が子どもと一緒に自宅に住み続けることが予定されているとします。
他方、住宅ローンの名義は義務者であり、義務者が住宅ローンの支払を続けることが予定されているとします。
義務者が住宅ローンの支払を続ける場合、義務者は、権利者の生活費の一部を負担していることになります。
養育費算定表は、お互いが、お互いの生活費を負担することを前提に作られていますから、修正が必要です。
修正の方法は幾つか考えられますが、よく用いられる方法は、権利者の年収に応じた住居費相当額を、養育費の額から差し引くという方法です。
たとえば、3の(1)で挙げた、子どもが10歳、権利者・義務者共に給与所得者、義務者の年収が500万円、権利者の年収が100万円であるとすると、おおむね、5万円~6万円程度が養育費として相当ということになります。
次に、養育費算定表では、年収に応じた住居費を次のように考えています。
年収 | 住居費 |
~199万円 | 2万2247円 |
~249万円 | 2万6630円 |
~299万円 | 3万5586円 |
~349万円 | 3万7455円 |
~399万円 | 4万5284円 |
~449万円 | 4万6562円 |
~549万円 | 5万5167円 |
・・・ | ・・・ |
100万円に対応する住居費相当額は2万2247円ですから、約2万円と考えて、上記の5万~6万円から2万円を差し引き、3万~4万円が養育費として相当ということになります。
(2)生活費の一部を負担しているケース
たとえば、離婚をした後も、義務者が、子どもの携帯代や権利者の自宅の電気水道代を支払続けるという場合があります。
同居中に、子どもの携帯代や、自宅の電気水道代の引き落とし先を義務者の口座にしている場合には、引き落とし先口座を変更する手間などから、こうした取り決めをすることが少なくないようです。
このように、義務者が権利者の生活費の一部を負担している場合には、養育費算定表で計算された養育費の額から、その実額を差し引くという処理をすることが多いです。
たとえば、3の(1)で挙げた、子どもが10歳、権利者・義務者共に給与所得者、義務者の年収が500万円、権利者の年収が100万円であるとすると、おおむね、5万円~6万円程度が養育費として相当ということになります。
そして、義務者が、子どもの携帯代月額5000円を毎月負担しているとすると、上記5万円~6万円から、5000円を差し引いた4万5000円~5万5000円が養育費として相当ということになります。
(3)私立大学の学費や留学費用が問題となるケース
養育費算定表では、標準的な公立高校の学費までは考慮されていますが、私立大学の学費や留学費用は考慮されていません。
そこで、私立大学や留学費用など、算定表を超える学費が必要となる場合、上乗せを検討することになります。
上乗せの計算方法については、様々な考え方がありますが、比較的簡単なものは、標準的な公立高校の学費を超過する分について、双方の基礎収入割合で分担するというものです。
たとえば、義務者の年収が800万円、権利者の年収が100万円、子どもが19歳で私立大学に進学しており、私立大学の学費が年間100万円必要であるとします。
まず、養育費算定表には19歳の表がありませんが、子どもが18歳であるとして計算します。
養育費計算ツール(養育費計算ツール|弁護士による離婚相談ならベリーベスト法律事務所 (vbest.jp))を使って計算すると、10万円~12万円が養育費として相当という結果になります。
次に、双方の基礎収入についてみます。
基礎収入とは、簡単にいえば、年収の中で生活にあてられる金額のことをいいます。
養育費算定表では、基礎収入を、年収に応じた割合(基礎収入割合)で計算する方法を採用しています。
給与所得者の場合の基礎収入割合は次の表のとおりとなっています。
収入(円) | 割合(%) |
0~75 | 54 |
~100 | 50 |
~125 | 46 |
~175 | 44 |
~275 | 43 |
~525 | 42 |
~725 | 41 |
~1325 | 40 |
年収800万円と年収100万円の基礎収入についてみると、年収800万円の基礎収入は800万円×40%で320万円、年収100万円の基礎収入は100万円×50%で50万円と計算できます。
最後に、超過分の分担を計算します。
養育費算定表では、標準的な公立高校の学費として年間約26万円が考慮されています。
そこで、超過分は、私立大学の学費100万円-26万円=74万円です。
そして、これを双方の基礎収入割合で分担します。基礎収入比は、義務者:権利者=3.2:1ですから、おおむね、義務者:権利者=56万3800円(月約4万7000円):17万6200円(月約1万4680円)となります。
したがって、義務者の上記10万~12万円に、私立大学の学費の分担額である4万7000円を加算した、14万7000円~16万7000円が養育費として相当と計算できます。
5、養育費の話し合いがまとまらなかったら?

(1)離婚する前にまとまらない場合
①離婚調停を起こす
離婚する前に、養育費について話し合いが決まらない場合、「離婚」調停を起こします。
離婚全体について調停を起こす必要があるのは、離婚をする前には、養育費だけを定める調停手続が存在しないからです。
離婚調停では、養育費以外の離婚条件(親権、財産分与、慰謝料等)についても話し合うことができますが、養育費だけが決まっていない場合には、事実上、養育費だけが話し合いの対象となるでしょう。
調停手続では、これまで述べた養育費算定表を用いて、養育費の目安額が決められ、それを前提に額の増減について話し合いがされることが一般的です。
②訴訟を起こす
調停でも養育費の額について折り合いがつかない場合、調停を不成立とした上で、離婚全体について訴訟を提起することが必要です。
もっとも、訴訟においても、養育費の額は、養育費算定表を基本として、ある程度機械的に決められます。一方で、訴訟となると、労力的・時間的なコストがかかります。
そのため、よほどの事情がない限り、養育費が決まらないことだけを理由に訴訟に移行することは少ないといえます。
(2)離婚した後にまとまらなかった場合
①養育費分担調停を起こす
たとえば、養育費を定めずに、ひとまず離婚届を提出し、その後、養育費について話し合うということは、珍しくありません。
離婚をする前に対し、離婚をした後では、養育費を定める養育費分担調停が存在しますから、離婚をした後に養育費について話し合いがまとめらなければ、養育費分担調停を起こすことができます。
②話し合いがまとまらなければ自動的に審判手続に移行する
養育費分担調停で話し合いがまとまらず調停不成立となった場合、訴訟ではなく、審判という手続に「自動的に」移行します。
つまり、調停不成立となったとしても、養育費が決められずに終わることはなく、審判という形で、何らかの結論が出ることになります。
審判手続は、基本的に書面のやり取りによる手続です。
一般的には、調停不成立となった後、裁判所が、結論を出す日(審判日)と主張を提出できる期限を定め、それまでの間に、双方が主張書面を提出し、審判日に結論が出る、という手続きの流れで進んでいきます。
審判においては、養育費算定表を基準に養育費の目安額が決められ、これに双方の主張を加味して、最終的な養育費の分担額が決められることが通常です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
養育費算定表が、使いやすいツールであることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
もっとも、養育費算定表は、表の選択や収入の認定を間違えると結論が異なってしまうという難点があります。
また、自営業者の場合や、特別な事情がある場合については、計算の仕方が複雑で、かつ、様々な考え方があるため、養育費算定表だけでは結論が出ないことがあります。
養育費についてお困りの際には、一度、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。