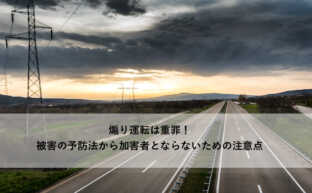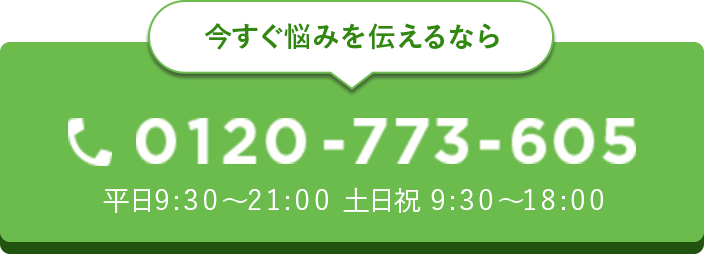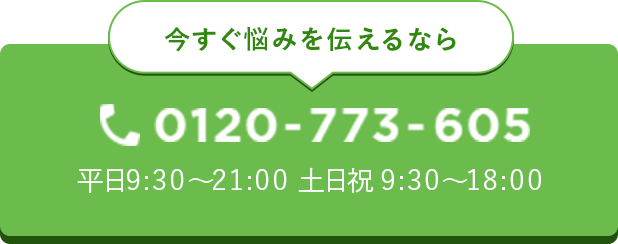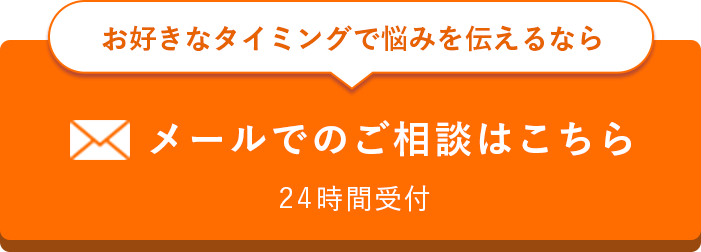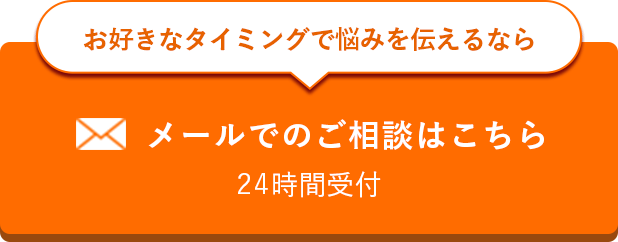クラクションでのトラブルは、車を運転する場合には起こりやすいものです。
普段、車を運転する上でクラクションを適切に使用できているでしょうか?
適切に使用しなければ、思わぬ処分を受けたり、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
そこで、この記事では思わぬ処分を受けたりトラブルに巻き込まれないために、
- クラクションのルール
について確認するとともに
- トラブルに巻き込まれないための方法
- トラブルに巻き込まれた場合の対処法
についてご紹介したいと思います。この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
また、以下の関連記事ではあおり運転被害に関する7つの知識について解説しています。運転中の突然のハプニング(煽り運転等)に対しお困りの方は、以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。
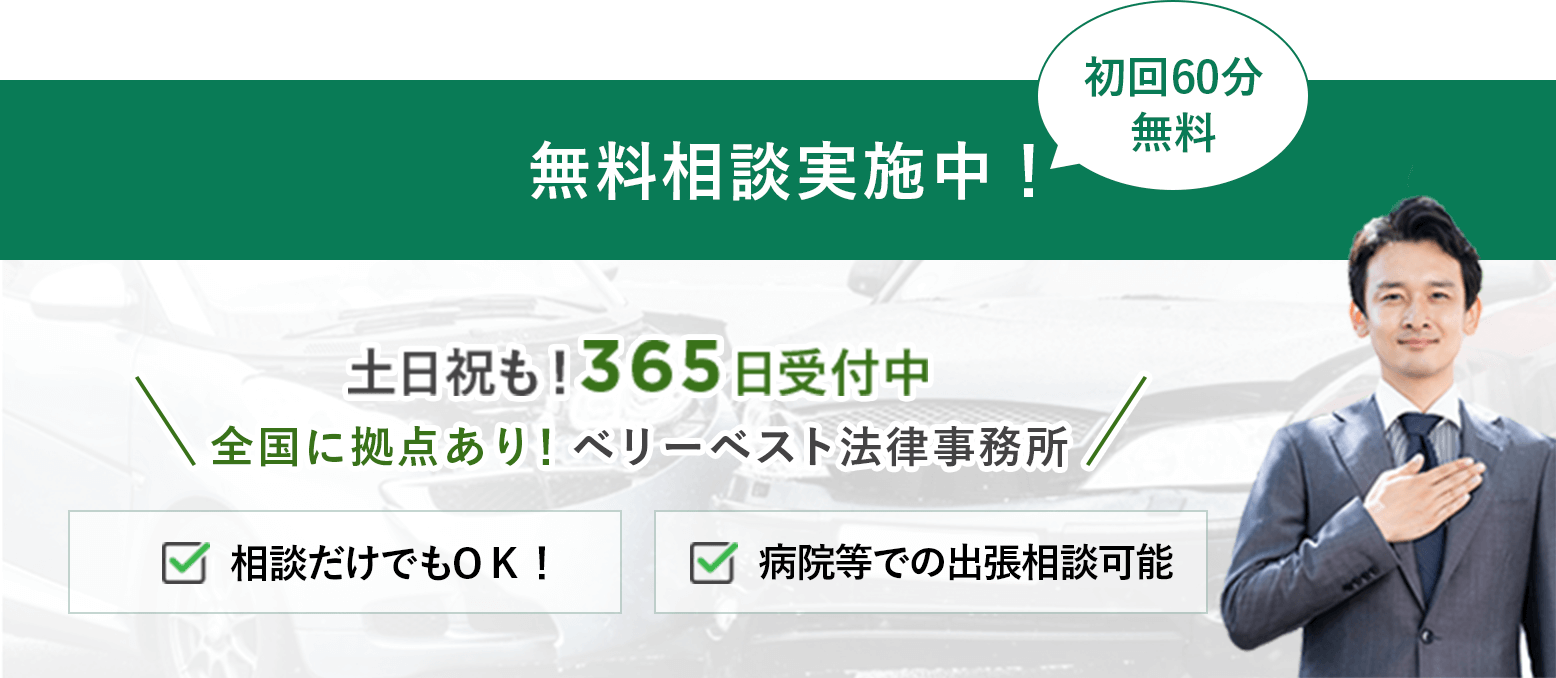

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、クラクショントラブルはできるだけ避けたい…クラクションが多くの人のイライラのもとになっている
車を運転したことがある人ならば、誰しもが運転中のイライラを経験しているのではないでしょうか?
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が発表した「危険運転と怒りに関するアンケート調査」では、約9割以上の人が運転中のイライラを経験している、との結果が出ています。
そのアンケート調査の中の「運転中にイライラした際、どのような行動を起こしたことがありますか?あるいは起こしたくなりますか?」という問いに対しては、7.9%の人が「クラクションを鳴らしてしまう」と回答しています。
また、「どんなことでイライラすることが多いですか?」という問いに対しては、34.8%の方が「クラクションを鳴らされたとき」と回答しており、クラクションがトラブルのもととなっていることを示しています。
2、クラクションを鳴らしたことでこんなトラブルに巻き込まれる可能性も
具体的にクラクションでどんなトラブルが起きているのか。ほんの一例ですがご紹介します。
(1)胸ぐらをつかまれる(暴行)
東京都内で、SUV車のすぐ後ろを走っていた小型車の運転手が、SUV車が赤色信号で停止したことからクラクションを鳴らしたところ、車を降りてきたSUV車の運転手に胸ぐらをつかまれた。
(2)ドアミラーを壊される(器物損壊)
愛知県内で、交差点を右折しようとしていた女性が、男性が運転する車に内側から追い抜かれたためクラクションを鳴らしたところ、その男性に車のドアミラーを壊された。
(3)殺されそうになる(殺人未遂)
大阪府内で、後続の軽乗用車を運転していた男性が前方の軽乗用車の運転手に向かってクラクションを鳴らしたところ、これに立腹した男性から先端のとがったドライバーで左胸を刺された。
3、クラクショントラブル|実は使用等については法令で規定されている
そもそもクラクションに関し法令で規定されていることはご存知でしょうか?
(1)クラクションは鳴らさないのが原則
クラクションは道路交通法上「警音器」と呼ばれています。
そして、道路交通法54条2項は、クラクションの使用に関し次のように規定しています。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
つまり、クラクションは鳴らさないことが原則で、例外的に鳴らすことが許される、ということまず確認しましょう。
(2)クラクションを鳴らしてよいときは
では、どんな場合にクラクションを鳴らすことが許されるのでしょうか?
先の道路交通法54条2項によれば、「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」と「危険を防止するためやむを得ないとき」とされています。
①「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」とは
ここでいう「法令」とは、
- 道路交通法52条1項
- 道路運送法に基づく旅客自動車運送事業運輸規則
のことを指しますが、「道路運送法に基づく旅客自動車運送事業運輸規則」は路線バス等が対象となることから、今回は「道路交通法52条1項」についてご紹介します。
道路交通法52条1項は、次のように規定しています。
車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
1号、2号とも「通行しようとするとき」とされていることから、クラクションは「交差点等を通行するとき」ではなく、それらの場所のやや手前において鳴らさなければなりません。
②「危険を防止するためやむを得ないとき」とは
上記の「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」でなくても、「危険を防止するためやむを得ないとき」はクラクションを鳴らすことができます(52条1項の場合と異なり、クラクションを鳴らさなければならないわけではありません)。
ここで、「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、現実、具体的に危険が認められるような状況下で、その危険を防止するためにやむを得ないとき、という意味であると解されています。
ですから、普段よくみかける
- 道ですれ違った知り合いとの挨拶
- 道を譲ってもらったときのお礼
などでクラクションを鳴らしてはならないのはもちろんですし、
- 発進しない前車へイライラした
- 急に割り込んできた車への抗議
といった理由も「危険を防止するためにやむを得ないとき」とはいえませんので、クラクションを鳴らしてはいけません。
他方、
- 車両等の接近に気がつかずにその前方を横断しようという歩行者を認めた場合
- 追い越しの際に、前車が後車の追い越しに気づかず、前車が急に進路を変更しようとするなどして、前者に接触する危険が生じた場合
などはクラクションを鳴らしても構いません。
(3)違反すると?
道路交通法では、
- クラクション鳴らすべきときに鳴らさなかった場合(54条1項違反=警音器吹聴義務違反)
- クラクションを鳴らしてならないのに鳴らした場合(54条2項違反=警音器使用制限違反)
の2つの場合に、それぞれ罰則(刑事罰)、反則金、違反点数を設けています。
①クラクション鳴らすべきときに鳴らさなかった場合(警音器吹聴義務違反)
ア 罰則
5万円以下の罰金
イ 反則金
大型車:7000円
普通車:6000円
二輪車:6000円
原付車:5000円
ウ 違反点数
1点
②クラクションを鳴らしてならないのに鳴らした場合(警音器使用制限違反)
ア 罰則
2万円以下の罰金又は科料
イ 反則金
3000円
ウ 違反点数
なし
なお、違反が発覚した場合、「交通反則通告制度」により、警察官から通称「青切符」を交付され、反則金を納付するよう促されることが大多数です。
反則金を納付することにより、罰則が適用されることはなくなります。
4、クラクショントラブルに巻き込まれないために
クラクションのトラブルに巻き込まれないようにするためには、どうしたら良いでしょうか?
(1)クラクションのルールを守ろう
まずは、前記「3」でご紹介したクラクションに関するルールを再確認し、ルールを守りましょう。
むやみやたらにクラクションを鳴らすと、あなた自身が切符を切られたり、最悪の場合、罰則が科されて前科が付いてしまうことになりかねません。
(2)運転中のイライラを抑える
次に、むやみにクラクションを鳴らしてしまう原因である「運転中のイライラ」を抑えることも必要です。
冒頭でご紹介した、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が実施した「危険運転と怒りに関するアンケート調査」によると、「運転中のイライラを抑えるために、どのような対処法を取るか」との問いに対する回答は、以下の通りとなっています。
- 飲み物を飲む/食べ物を食べる(33.2%)
- 深呼吸をする(27.7%)
- 外(遠く)を眺める(11.6%)
- 一度停車し、休憩する(10.8%)
- 前の車(ナンバープレートなど)を見て気を紛らわす(6.6%)
ただ、「何もしない」という方も39.1%いたそうで、同協会は「これは危険な状態で、自分なりの回避方法を考えて欲しい」などと呼び掛けています。
(3)クラクショントラブルに巻き込まれた時のために
前記「2」でご紹介したように、不用意にクラクションを鳴らしてしまったことで犯罪被害に遭う可能性もなくはありませんから、被害状況を証拠として保全するために車内にドライブレコーダーを設置したり、車に「ドライブレコーダー設置車」などのステッカーを張ることを検討したりしてもいいでしょう。
5、万が一クラクションによるトラブルに巻き込まれたら
最後に、「4」の対策をとったにもかかわらずトラブルに巻き込まれた場合の対処法をご紹介します。
(1)クラクションが原因で煽り運転を受けた場合
まずは、ハザードランプを点灯させ、後続車及び周囲に注意を促します。
そして、徐々にスピードを落とします。次にゆっくりと車を路肩に寄せ、停車させます。
ここで、急ブレーキを踏んで急停止しないでください。
後続車に追突させてしまった場合、あなたが過失責任を問われる場合があります。
(2)自分が停車したときに相手が走り去らずに、車から降りてきた場合
まず、相手から危害を加えられることを防止するため、車の鍵は全部ロックしましょう。
そして、実際に110番通報するか、電話をするふりをしてみるのも一つの方法です。
相手に「誰かに助けを求めている」と思わせることができれば、それだけで相手を他の場から立ち去らせる効果が期待できるでしょう。
110番通報した場合は、警察が来るまで絶対に車外に出てはいけません。
また、やむを得ずその場から立ち去る場合は、相手に怪我をさせたり、周囲の車にぶつからないように、慎重に車を動かしましょう(急発進は怪我を負わせる原因となります)。
まとめ
以上、クラクションのルール、トラブルに巻き込まれないための対処法、巻き込まれた場合の対処法について紹介いたしました。
クラクショントラブルは、車を頻繁に運転する方にとって、誰しもが起こしやすいあるいは巻き込まれやすいトラブルではないかと思います。
この機会に、本記事で基本事項をご確認いただけたらと思います。