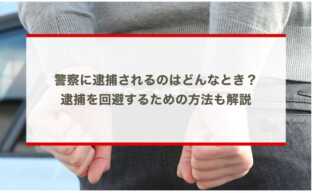実際の法律において、殺人罪には時効の適用はありません。
今回は、
- 殺人罪に時効がない理由
- 殺人を犯した場合は自首すべきか
- 殺人罪の刑罰を軽減する方法
について詳しく解説します。
目次
1、殺人罪に時効はある?時効の種類と成立するまでの期間
殺人罪で問題となり得る「時効」には、3種類のものがあります。
本章では、それぞれについて殺人罪に適用されるか、されるとして時効期間は何年なのかを解説します。
(1)起訴されるかどうかの時効
1つめは「起訴されるかどうかの時効」ですが、殺人罪にはこの意味での時効はありません。
刑事事件には、法律で定められた一定の期間が経過すると検察官が起訴することができなくなり、犯人が処罰されなくなるという制度があります(刑事訴訟法第250条)。
この制度のことを、「公訴時効」といいます。
冒頭から「殺人罪に時効はない」と申し上げているのは、「公訴時効」のことです。
以前は、殺人罪にも25年という公訴時効が定められていましたが、刑事訴訟法の改正によって、2010年4月27日以降は廃止されました。
(2)刑を科せられるかどうかの時効
刑事事件における「時効」にはもう1種類、「刑の時効」という制度があります。
刑の時効では、刑事裁判の判決で刑(死刑を除く)の言い渡しを受けても、法律で定められた一定期間、刑の執行を受けなければ時効が成立します。
結果として、刑の執行が免除されるという制度です(刑法第31条)。
刑の時効が成立するケースは滅多にありませんが、刑を言い渡した判決が確定した後に犯人が逃亡したようなケースでの適用があり得ます。
殺人罪については、刑の時効も刑法改正によって、2010年4月27日以降は廃止されています。
(3)民事上の損害賠償請求権の時効
殺人罪では、民事上の損害賠償請求権の時効も問題となります。
被害者(遺族)は、犯人に対し民法上の不法行為を原因として、慰謝料等の損害賠償請求権を有しています。
損害賠償請求権には民法上の「消滅時効」の制度が適用されるのです。
時効期間は、
- 被害者(遺族)が損害および加害者を知った時から5年(2020年3月31日以前に発生した事件については3年)
です(民法第724条の2)。
消滅時効が成立すると、被害者や遺族から損害賠償請求を受けることはなくなります。
ただし、犯人が誰であるかが発覚せず、被害者や遺族が「加害者」を知るまでは前者の「5年」(2020年3月31日以前に発生した事件については3年)の時効期間は進行しないということに注意が必要です。
2、殺人罪には種類がある
殺人罪には時効がないと冒頭で説明しましたが、例外もあります。
殺人罪にはいくつかの種類があります。単純な「殺人罪」に時効はないのですが、種類によっては時効があるということです。
まずは、殺人罪とはどういうものかについて簡単に確認した上で、殺人罪の種類と刑罰をご紹介します。
(1)殺人罪の構成要件
殺人罪とは、
- 故意(殺意)を持って、
- 人を死亡させる行為をし、
- 人の死亡という結果が発生する
ことによって成立する犯罪です。
「故意(殺意)」には、明確に「人を殺そう」という意思がある場合だけではありません。
「人が死んでしまうかもしれないけれど、それでも構わない」という意思(未必の故意)も含まれます。
人が死亡することを予見していなかった場合(故意がない場合)は、殺人罪ではなく傷害致死罪や過失致死罪等の対象となります。
「人を死亡させる行為」とは、人の死亡という結果が生じうる現実的危険性のある行為のことです。
このような行為をし、人が死亡する現実的危険性が発生すると、結果的に相手が死亡しなかったとしても「殺人未遂罪」が成立します。
相手が死亡した場合には、「殺人既遂罪」となります。
(2)殺人罪の種類と刑罰
人を死亡させる犯罪は殺人罪だけでなく、さまざまなものがあります。
ここでまとめて、刑罰とともにご紹介します。
①故意に人を死亡させる犯罪
罪名 | 刑罰 | 条文 |
殺人既遂罪 | 死刑または無期もしくは5年以上の懲役 | 刑法第199条 |
殺人未遂罪 | 死刑または無期もしくは5年以上の懲役 | 刑法第203条 |
同意殺人既遂罪 | 6月以上7年以下の懲役または禁錮 | 刑法第202条 |
同意殺人未遂罪 | 6月以上7年以下の懲役または禁錮 | 刑法第203条 |
既遂罪も未遂罪も刑罰の上限は同じですが、未遂罪の場合は刑を減軽することができるとされている(刑法第43条)ため、実際には量刑が軽くなることが一般的です。
②過失で人を死亡させる犯罪
参考までに、殺人ではなく過失で人を死亡させる犯罪についての刑罰もご紹介しておきます。
罪名 | 刑罰 | 条文 |
過失致死罪 | 50万円以下の罰金 | 刑法第210条 |
業務上過失致死罪 | 5年以下の懲役もしくは禁固 または100万円以下の罰金 | 刑法第211条 |
傷害致死罪 | 3年以上の有期懲役 | 刑法第205条 |
過失運転致死罪 | 7年以下の懲役もしくは禁固 または100万円以下の罰金 | 自動車運転処罰法第5条 |
危険運転致死罪 | 1年以上の有期懲役 | 自動車運転処罰法第2条 |
「有期懲役」の上限は原則として20年ですが、他にも犯罪が成立している場合は併合罪となり、最大30年となる可能性があります。
3、殺人罪の公訴時効はなぜ廃止された?
公訴時効制度が定められている趣旨は、
- 事件後の時間の経過によって被害者側や社会の犯人に対する処罰感情が消滅すると考えられること
- 証拠の散逸により真実の発見が困難となること
などです。
しかし、凶悪な殺人犯等が、25年だけ逃げ切って処罰を免れるケースが実際に複数件発生しています。
結果として、遺族の方々から「納得できない」「殺人罪等の重大事件については公訴時効が撤廃されるべきである」といった声が、相次いで起こりました。
人の生命を奪うような重大事件については、時間の経過によって処罰感情が消滅するという公訴時効制度の趣旨は、必ずしも当てはまらないといえます。
以上のような動きを背景として、刑法および刑事訴訟法が改正され、2010年4月27日以降は殺人罪の公訴時効が廃止されました。
参考までに、この改正による公訴時効の変更点をまとめておきます。
公訴時効の有無や刑罰は、法定刑(罪名ごとに法律で定められた刑罰)に応じて定められており、改正前と改正後を比較すると以下の表のとおりになっています。
法定刑
| 改正前の公訴時効期間 | 改正後の公訴時効期間 |
人を死亡させた罪のうち、法定刑の上限が死刑であるもの(殺人罪等) | 25年 | 公訴時効廃止 |
人を死亡させた罪のうち、法定刑の上限が無期の懲役・禁固であるもの(強制性交等致死罪等) | 15年 | 30年 |
人を死亡させた罪のうち、法定刑の上限が20年の懲役・禁固であるもの(危険運転致死罪等) | 10年 | 20年 |
人を死亡させた罪のうち、法定刑の上限が懲役・禁固で、上記のいずれにも該当しないもの(過失運転致死罪等) | 5年または3年 | 10年 |
4、時効の廃止後も殺人罪で公訴時効が成立するケース
現行法のもとでも、以下の2つのケースでは殺人罪でも公訴時効が成立します。
(1)時効廃止前に公訴時効が成立していた場合
時効廃止前、つまり2010年4月26日以前に公訴時効が成立していた場合は、もはや犯人が罪に問われることはありません。
なお、公訴時効が進行し始めるのは、犯罪行為が終わったときからです(刑事訴訟法第253条)。
例えば、1985年4月1日に殺害行為が行われ、その後25年の間に犯人が起訴されなかった場合は、時効廃止前に公訴時効が成立していることになります。
この場合には、犯人は起訴されることも処罰されることもありません。
ただし、犯人が国外にいる場合、または逃げ隠れしているために起訴状の送達等が行えなかった場合には、その間、時効の進行は停止します(刑事訴訟法第255条1項)。
公訴時効廃止より25年以上前に殺害行為が行われた場合でも、犯人が国外にいたり、起訴を免れるために逃げ隠れていたりした場合には、2010年4月27日時点で公訴時効が成立していない可能性もあります。
殺害行為が行われたのが時効廃止前でも、2010年4月27日の時点で公訴時効が成立していない場合は、現行法が適用されますので、公訴時効にかかりません。
この場合は、殺害行為から何十年が経過しても、犯人は逮捕され、処罰される可能性があります。
(2)同意殺人罪の場合
2つめのケースは、単純な「殺人罪」ではなく、「同意殺人罪」の場合です。
同意殺人罪とは、被害者の承諾を得て、または被害者から頼まれて殺害する犯罪です。
同意殺人罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役または禁錮ですので、現行法のもとでは10年の公訴時効が適用されます。
そのため、同意殺人の実行行為から10年間起訴されなければ、犯人は起訴されることも処罰されることもなくなるのです。
5、もし、殺人を犯してしまったら…。
殺人罪が成立する場合、ここまででご紹介した2つの例外を除いて公訴時効はないことを説明しました。
それでは、殺人を犯してしまったとしたら、どうすればよいのでしょうか。
(1)時効で刑罰を免れることはできない
公訴時効がないということは、当然ながら時効によって起訴や刑罰を免れる可能性はないということです。
逃げ隠れして罪の発覚や逮捕を免れたとしても、一生涯、
「いつか逮捕されるのではないか」
「死刑などの重罰に処せられるのではないか」
といった、恐怖心や不安感を抱えて生きていかなければなりません。
(2)逃亡していると刑罰が重くなることがある
逃亡後に逮捕された場合は、犯行後すぐに逮捕された場合よりも刑罰が重くなる可能性があります。
犯行を隠ぺいするような行為をしていると、さらにその傾向が強まります。
これらの行為をすることは「反省」とは正反対の態度であり、刑事裁判において悪い情状として評価されるからです。
逃亡期間が長くなればなるほど、悪質な態度と評価され、刑罰が重くなる可能性が高まってしまいます。
(3)自首すれば減刑される可能性が高い
一方、自首すれば刑罰が軽くなる可能性が高くなります。
自首した場合には、刑を減軽することができると法律で定められているからです(刑法第42条1項)。
犯人が誰であるかが既に捜査機関に判明している場合には、犯人が警察に出頭しても法律上の「自首」は成立しません。
しかし、この場合でも自ら出頭し、罪を自白することはプラスの情状として評価されますので、刑罰が軽くなる可能性が高まるのです。
6、殺人罪で逮捕された場合の対処法
自首した場合も、捜査機関に見つかった場合でも、殺人罪で逮捕された場合にはできる限り刑罰を軽くしたいと考えることでしょう。
そのためには、以下のような対処が重要となります。
(1)真摯に反省する
罪を犯したことが事実であれば、まずは素直に犯行を認め、真摯に反省することです。
取調官に対し、犯行の動機から犯行に至る経緯、犯行の具体的な内容、犯行後はどのように過ごしていたのかなどを、正直に話しましょう。
そのうえで、
- 自分のどこか悪かったのか
- どうしていればよかったのか
- 罪を犯してどう思っているか
- 被害者や遺族に対してどのように思っているか
などを、心を込めて話していくことです。
(2)取り調べで不利な調書にサインしない
取り調べで反省の態度を示すことと、取調官の言いなりになることは全く異なります。
取り調べでは、不利な供述調書には決してサインしないようにしましょう。
いったんサインすると、基本的にはその供述調書の内容のとおりに自分が話したものとして扱われ、後に刑事裁判で供述調書で話したとされる内容を覆すことは非常に困難となるからです。
犯行を自白していても、取調官は犯行の動機や犯行に至る経緯、犯行の態様などについて、実際よりも悪質な内容の供述調書を作成しようとするケースが少なくありません。
反省の態度を示しつつも、事実は事実としてありのままに供述することが大切です。
取調官が作成した供述調書は、必ず手に取って内容を十分に確認しましょう。
内容に納得できない点があれば、納得できるまで訂正を申し出ることです。
もし、取調官が言い分を聞き入れてくれないときは、弁護士に相談のうえ、対応についてアドバイスを受けるべきでしょう。
(3)弁護士を通じて被害者側と示談交渉をする
刑罰を軽くするためには、被害者側(遺族)と示談することが有効です。
しかし、逮捕・勾留されていると自分で示談交渉をすることは事実上不可能です。
遺族は犯人に対して強い処罰感情を持っているのが通常ですので、手紙を送ったとしても交渉に応じてもらえないことも少なくありません。
以上のような場合には、弁護士を通じて示談交渉をすることをおすすめします。
刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、遺族の感情にも十分に配慮して示談交渉を進めてくれますので、示談成立も期待できます。
ただし、殺人事件で示談を成立させるためには、多額の示談金を要する可能性が高いうえ、いくら示談金を用意しても示談には応じてもらえない可能性も十分にあります。
そのため、殺人罪のケースでは、示談成立に至らないことも多いでしょう。
その場合でも、弁護士を通じて遺族へ真摯な謝罪の意思を伝え、できる限りの示談金を提示することはプラスの情状として評価されます。
(4)身元引受人を立てる
身元引受人を立てることも大切です。身元引受人とは、一般的に犯人が釈放された後の生活を指導・監督し、二度と間違いを起こさないように導く人のことを指します。
殺人事件で実刑判決を受ける見込みが強い場合でも、被疑者・被告人に寄り添ってくれる人を立てれば、その人の存在がプラスの情状として評価され、刑罰を軽くできる可能性があります。
殺人事件でも事案の内容や、上記(1)~(3)の状況次第では、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予が見込める事案では、身元引受人の存在がとりわけ重要となるのです。
家族や親戚、上司、お世話になっている知人等の中から、できる限り本人に対する指導力が強い人を身元引受人に選びましょう。
まとめ
この記事では、殺人罪と時効の関係について解説してきました。
しかし、ご自身や近しい方が殺人事件に関わってしまった場合、実際にどうするのかを決断しきれないことも多いのではないでしょうか。
自首した方がよいと分かってはいても、勇気が出ないということもあるでしょう。
そんなときは、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
数十年前の事件であれば、公訴時効が成立しているかもしれません。
その場合には、弁護士からその旨の指摘があります。
公訴時効が成立していない場合にも、弁護士が最善の対処法をアドバイスしてくれます。
自首する際には、弁護士に同行してもらうことも可能です。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密が漏れる心配はありません。
1人で悩まず、弁護士にご相談の上、最善の対処をとることをおすすめします。