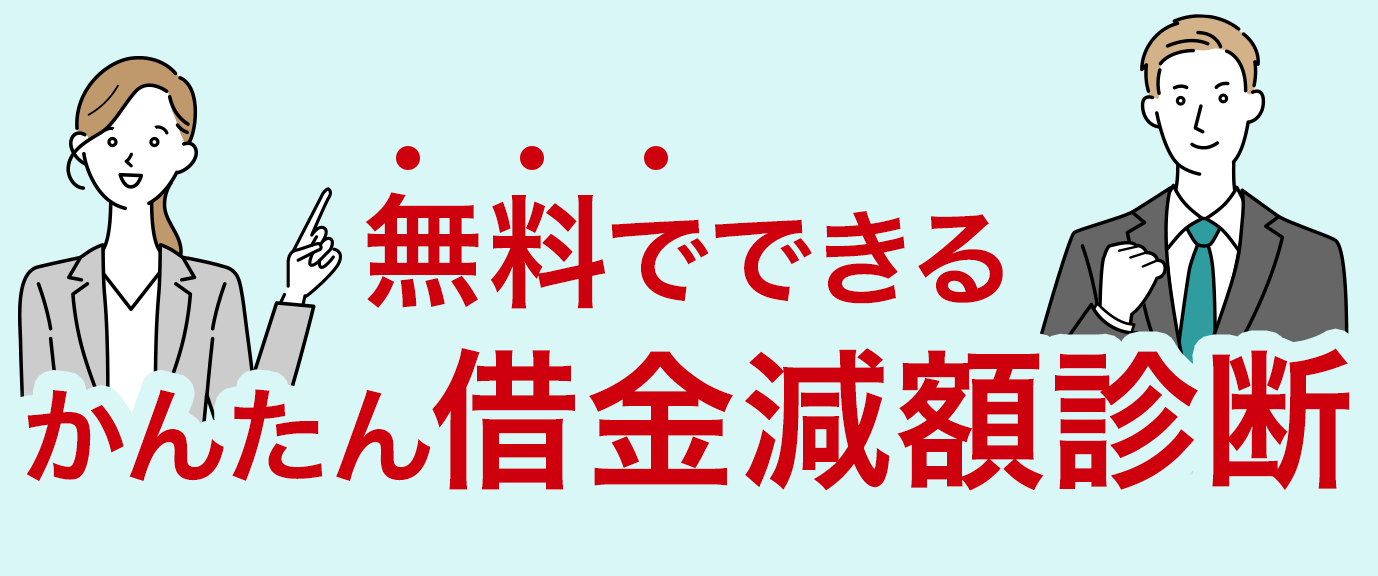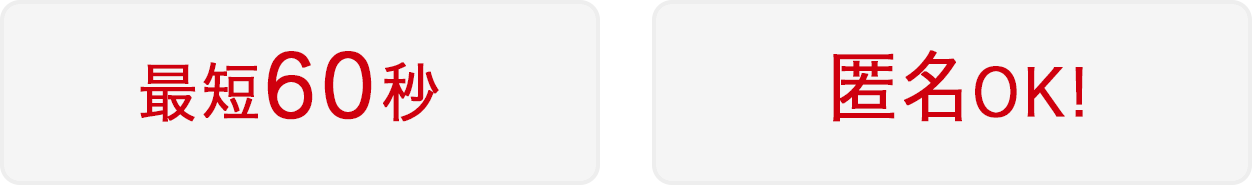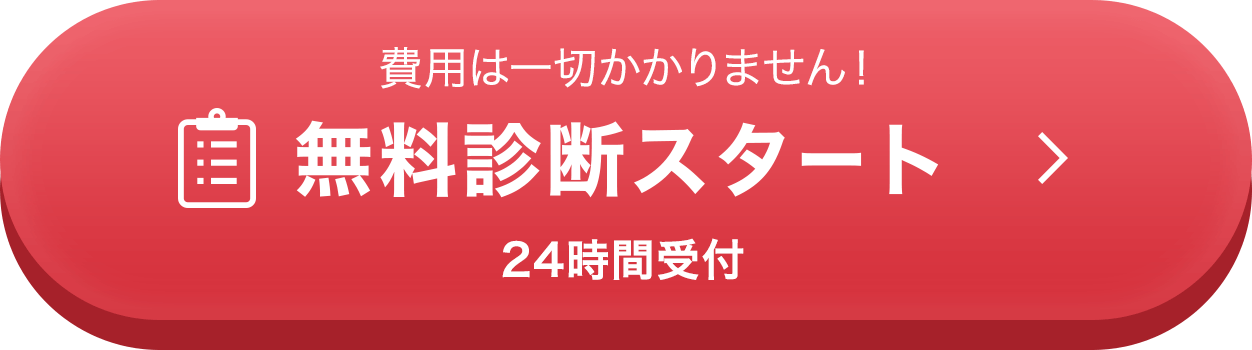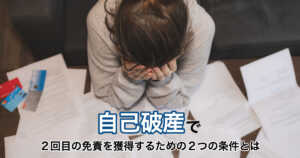
「1度自己破産をしたことがあるけれど、2回目もできるのかな?」
自己破産で免責が認められると、すべての借金がなくなりますが、さまざまな事情で再び借金を抱えてしまうこともあるでしょう。そんなとき、「自己破産は2回目もできるのか」が気になる方が多いことと思います。
結論からいうと、自己破産には法律上の回数制限はないので、何度でも申し立てることは可能です。しかし、2回目以降の自己破産では免責を受けるための条件が1回目よりも厳しくなるため、注意しなければならないことがいくつかあります。
ベリーベスト法律事務所の弁護士がお伝えする、2回目の自己破産で免責を獲得できる条件や申し立てる際の注意点、さらに免責が得られない場合の対処法について詳しく解説していきます。
自己破産手続きに精通した専門家の知見に基づいた貴重な情報をまとめましたので、2回目の自己破産をお考えの方々の手助けとなることを願っております。自己破産に関する疑問や悩みの解決に向け、的確な情報を身につけて新たな一歩を踏み出しましょう。
目次
1、自己破産は2回目もできる?

まずは、「自己破産は2回目もできるのか」という疑問に対して、明確にお答えいたします。
(1)自己破産そのものは何度でもできる
自己破産を申し立てるための条件は、「支払不能又は債務超過にある」ことだけです(破産法第1条)。
破産法には「○回目まで」という制限は定められていませんので、自己破産そのものは2日目はもちろん、3回目・4回目……と無制限に申し立てることも可能です。
したがって、到底返済できないほどの借金を抱えてしまった以上、2回目の自己破産は「できる」ということになります。
(2)ただし2回目以降は免責が得られないことがある
もっとも、自己破産をする目的は「免責」を得ることにあります。
免責とは、破産者の債務の返済義務をすべて免除するという裁判所の決定のことです。この決定を得て初めて借金がゼロになるのですから、免責が得られなければ2回目の自己破産をする意味がありません。
しかし、2回目以降の自己破産では、裁判所による免責の判断が1回目よりも厳しくなってしまうという問題があります。
2、2回目の自己破産で免責を獲得するための条件

2回目の自己破産で免責を獲得するための条件は、以下の2点です。これらの条件を両方満たす場合は、2回目以降の自己破産でも問題なく免責が許可されます。
(1)免責不許可事由がないこと
まず1つめの条件は、免責不許可事由がないことです。この点は、1回目の自己破産の場合とまったく同じ条件となります。
免責不許可事由とは、1度自己破産を経験した方はご存じかもしれませんが、借金の返済義務を免除するのが相当でない事情として破産法第252条1項に規定されている事由のことです。
主な免責不許可事由として、以下のようなものが挙げられます。
- パチンコや競馬などのギャンブルのために借金をしたこと
- 株式やFX、仮想通貨などの射幸行為のために借金をしたこと
- 収入に見合わない高価な買い物や飲食、遊興費などの浪費のために借金をしたこと
- クレジットカードで購入したものを転売して現金化したこと
- 返済できる見込みがないのにあるように装って借金をしたこと
- 一部の債権者にのみ優先的に返済したこと
- 破産手続きにおいて虚偽の説明や財産隠しをしたこと
これらの免責不許可事由がある場合は、原則として免責が許可されません。
(2)1回目の免責から7年以上が経過していること
2回目の自己破産における特有の免責条件として、「1回目の免責から7年以上が経過していること」が必要です(破産法第252条1項10号)。
免責が許可されると、債務者はすべての借金から解放されるという大きな利益を受けますが、その反面で債権者は多大な損失をこうむってしまいます。
このように重大な影響を及ぼす免責を無制限に認めると、債務者と債権者の利益のバランスが取れなくなってしまいます。そのため、破産法では前回の免責から7年間は次の免責を認めないこととしているのです。
したがって、1回目の自己破産における免責許可決定が確定した日から7年以内に2回目の自己破産を申し立てた場合は、免責を獲得することはできません。
3、2回目の自己破産をするときに注意すべきこと

上記の解説を読まれて、2回目の自己破産で免責を獲得するのもそれほど難しいことではないと思われたかもいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には2回目の免責を獲得するのは容易でないケースも少なくありません。なぜなら、2回目の自己破産では、法律上の条件意外にも以下の点が1回目の自己破産とは異なるからです。
(1)免責の判断が厳しくなる
免責不許可事由がなければ免責が許可されるのが原則ですが、現実には一切の免責不許可事由がないという人は意外に少ないものです。
ただ、免責不許可事由があっても軽微なものであれば免責が許可されます。見過ごせない程度の免責不許可事由がある場合でも、事情によっては裁判所の裁量によって免責を許可してもらうことも可能です(「裁量免責」といいます。破産法第252条2項)。
2回目の自己破産では、このような免責の判断が厳しくなります。
一切の免責不許可事由がないという場合でも、裁判所は本当に免責不許可事由がないかどうかを厳しくチェックしてきます。
そのため、2回目の自己破産を申し立てるときには、借金を抱えた経緯を1回目のときよりも詳しく裁判所に説明しなければなりません。
また、1度免責を受けても経済生活を立て直せなかったことを真摯に反省することも求められます。場合によっては、免責許可の条件として反省文の提出を指示されることもあります。
(2)管財事件になる可能性が高い
高価な所有財産がない人の自己破産手続きは、「同時廃止事件」として早期に終了するのが通常ですが、2回目の自己破産の場合は「管財事件」となる可能性が高くなります。
なぜなら、免責不許可事由の存否を調査する必要性が高いからです。破産者本人から裁判所への自己申告だけでは調査に限界があるため、裁判所は破産管財人を選任し、免責不許可事由の存否を詳しく調査するように命じるのです。
この場合の管財手続きは「少額管財」という、やや簡易的な手続きに付されるのが一般的ですが、その場合でも管財費用として20万円を予納することが必要となります。
管財人による調査の結果、免責不許可事由がないと判断されると免責が許可されます。多少の免責不許可事由がある場合にも、裁量免責が許可される可能性があります。
(3)債権者によっては免責後もトラブルが続く可能性がある
2回目の自己破産を申し立てるケースでは、銀行や消費者金融といった一般的な金融機関・貸金業者以外のところから借金をしている人が少なくありません。その場合は、2回目の免責が得られたとしても、トラブルが続く可能性があります。
そもそも、1回目の免責から10年は銀行や消費者金融などから借金をすることはできませんし、クレジットカードも利用できません。
このような人がお金を借りするとなると、どうしても闇金や友人・知人など正規の金融機関ではないところに頼ることになってしまいます。
しかし、闇金業者は借り手が自己破産をしたからといって厳しい取り立てをやめることはありません。友人や知人なども、感情的になって返済を要求してきたり、そうではなくても人間関係が壊れてしまう可能性が高いといえます。
これらの問題は、別途、警察や弁護士に相談するなどして解決する必要があります。
4、2回目の自己破産で免責が得られないときの対処法

2回目の自己破産では、裁判所から厳しくチェックされる結果、免責が許可されない可能性もあります。その場合は、以下の対処法によって借金問題の解決を図りましょう。
(1)任意整理をする
任意整理とは、債権者と直接交渉することによって借金の返済額や返済方法を変更する手続きのことです。
裁判所の手続きを利用しないため、利用条件は特に定められていません。そのため、2回目の自己破産で免責が認められない人でも、任意整理によって借金を減額することが可能です。
ただし、任意整理によってカットできるのは原則として将来利息のみであり、大幅な借金の減額は期待できません。
そのため、多額の借金を抱えてしまった場合は他の方法を検討する必要があるでしょう。
(2)個人再生を申し立てる
個人再生とは、裁判所の手続きを利用することによって借金を大幅に減額し、減額後の借金を3年~5年で分割返済していく手続きのことです。
裁判所の手続きが必要なので利用条件は細かく定められていますが、自己破産のように免責不許可事由はなく、借金の使い途は問われません。そのため、ギャンブルや浪費などで多額の借金を抱えた人でも個人再生なら解決できる可能性が高いといえます。
ただし、自己破産による免責許可決定が確定してから7年以内は「給与所得者等再生」はできないことに注意が必要です(民事再生法第239条5項2号、第241条2項6号)。
(3)あえて自己破産を申し立てる
実務上は、免責が得られないようなケースでも、あえて自己破産を申し立てることもあります。なぜなら、免責が得られなくても自己破産が認められれば、貸し手である金融機関が返済の請求を諦めることがあるからです。
自己破産手続きは、「破産手続」と「免責手続」の2段階に分かれています。多額の借金を抱えていれば、免責が得られなくても破産手続きによって「破産者」と認められることは無制限に可能です。
金融機関は、債務者に貸したお金を回収するにもコストがかかります。破産者となった債務者に対して返済を請求しても回収できる見込みは乏しいため、諦めて請求してこなくなるのはよくあることです。
請求されないまま最終取引から5年が経過すると、消滅時効を援用することによって借金から逃れることが可能になります。
ただし、免責が得られない以上は、請求されないという保証はありませんので、あえて自己破産を申し立てるという方法は最終手段として考えておくべきです。
(4)免責不許可決定に対して即時抗告をする
裁判所が免責不許可決定を出した事例を見てみると、判断が厳しすぎると思えるケースもないではありません。
そんなときは、免責不許可決定に対して「即時抗告」をすることによって異議を述べることも可能です(破産法第252条5項)。即時抗告をすると、高等裁判所で再度、免責許可について判断してもらえます。
ただし、即時抗告によって免責不許可決定が覆る可能性は極めて低いのが現状です。したがって、2回目の自己破産をお考えの方は、申立前に免責の見通しをしっかりと判断しておくべきといえます。
(5)闇金等から借りている場合は警察や弁護士に相談する
闇金等から厳しい取り立てを受けている場合は、警察や弁護士に相談することをおすすめします。
そもそも闇金業者からの借入の契約は、法外な利息の約定を伴っているため法律上無効であり、返済義務はありません。そのため、自己破産で解決すべき問題ではないのです。
ただ、自分で対応しようとすると、闇金業者からの嫌がらせ等によって重大な被害を受ける可能性が高いので、警察や弁護士に相談して対応してもらうようにしましょう。
また、友人・知人から借りている場合も、感情的なトラブルから事件に発展するおそれがありますので、弁護士に間に入ってもらって解決を図った方がよいでしょう。
5、2回目の自己破産をお考えなら弁護士に相談を

2回目の自己破産を成功させるためには、専門的な知識とノウハウが要求されます。そのため、2回目の自己破産をお考えの方は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士を味方につければ、以下のメリットが得られます。
(1)免責が得られやすくなる
2回目の自己破産では、1回目よりも裁判所から借金を抱えた経緯について詳しく尋ねられます。
そのとき、同じ事情でも説明の方法次第で裁判官の心証が異なり、免責の許可・不許可の判断が分かれることがあります。
弁護士は豊富な経験から裁判官の心証が良くなる説明方法を心得ていますので、弁護士に説明を任せた方が免責を獲得できる可能性が高まります。
(2)同時廃止決定が得られやすくなる
また、弁護士に自己破産手続きを任せることによって、管財事件を回避して同時廃止決定で手続きを終了できる可能性も高まります。
2回目の自己破産で管財事件に付されるのは、主に免責不許可決定の存否を調査するためです。
その点、弁護士が申立代理人として詳しい事情を裁判所に報告し、免責が相当であることを裏づける資料も提出することが可能です。
裁判所も代理人弁護士からの詳しい報告と資料を見て、「これ以上の調査は必要なし」と判断する可能性が高まりますので、同時廃止決定が得られやすくなるのです。
(3)金融機関以外の債権者にも対応してもらえる
弁護士が付いていれば、闇金業者や友人・知人といった金融機関以外の貸し手に対しても代理人として対応してもらえます。
これらの貸し手には法律が通用せず、対応が難しいことが多いのですが、さまざまなケースに対応してきた弁護士の経験に基づいた対処によって、平和な生活を取り戻すことが可能となるでしょう。
(4)自己破産以外の解決方法も提案してもらえる
2回目の免責を得られる見込みが乏しい場合には、前記「4」でご紹介したように、他の対処法を検討する必要があります。
また、ご自身では2回目の自己破産をするしかないと考えていても、弁護士から見ればより良い解決方法があるというケースも少なくありません。
弁護士の豊富な知識と経験に基づいたアドバイスを受けることで、最短で借金問題を解決できる方法が見つかるはずです。
まとめ
2回目の自己破産をすることは可能ですが、1回目よりも免責を獲得するのが難しくなるということがお分かりいただけたでしょうか。
2回目の免責を獲得するには専門的な知識やノウハウが必要となりますが、その一方で、自己破産以外に良い解決方法が存在する可能性もあります。
ベストな解決方法を見つけるためには、弁護士への相談が有効です。まずはお気軽に無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。