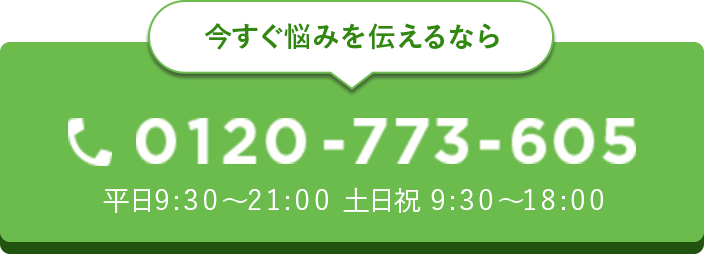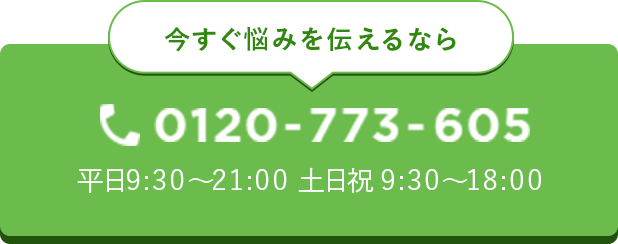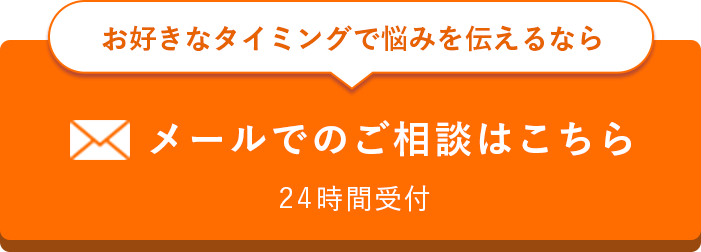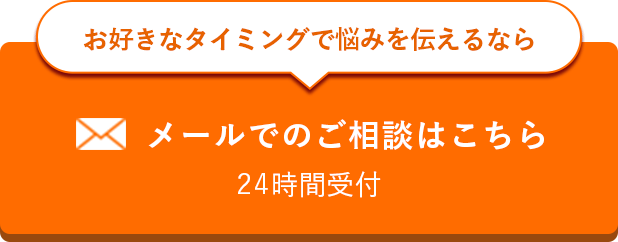交通事故証明書をご存知ですか?
交通事故に遭ってしまい、怪我をしてしまったり、ご家族が亡くなってしまったりしたとき、交通事故で負った損害を賠償して欲しいと思い立っても、何をすればよいのか分からない方や届出に必要な物が分からない方が多いのではないでしょうか。
まず、どのような事故があったのかについての資料や申請書を手に入れる必要があります。それが、「交通事故証明書」です。
この記事の本文では、「交通事故証明書」とはそもそも何なのか、「交通事故証明書」の入手・申し込み方法などについて解説しています。あわせて、保険金等の請求方法についても触れたいと思います。
また、以下の関連記事では交通事故にあった後の対応で知っておきたい知識について解説しています。突然の交通事故に遭われた方は以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。
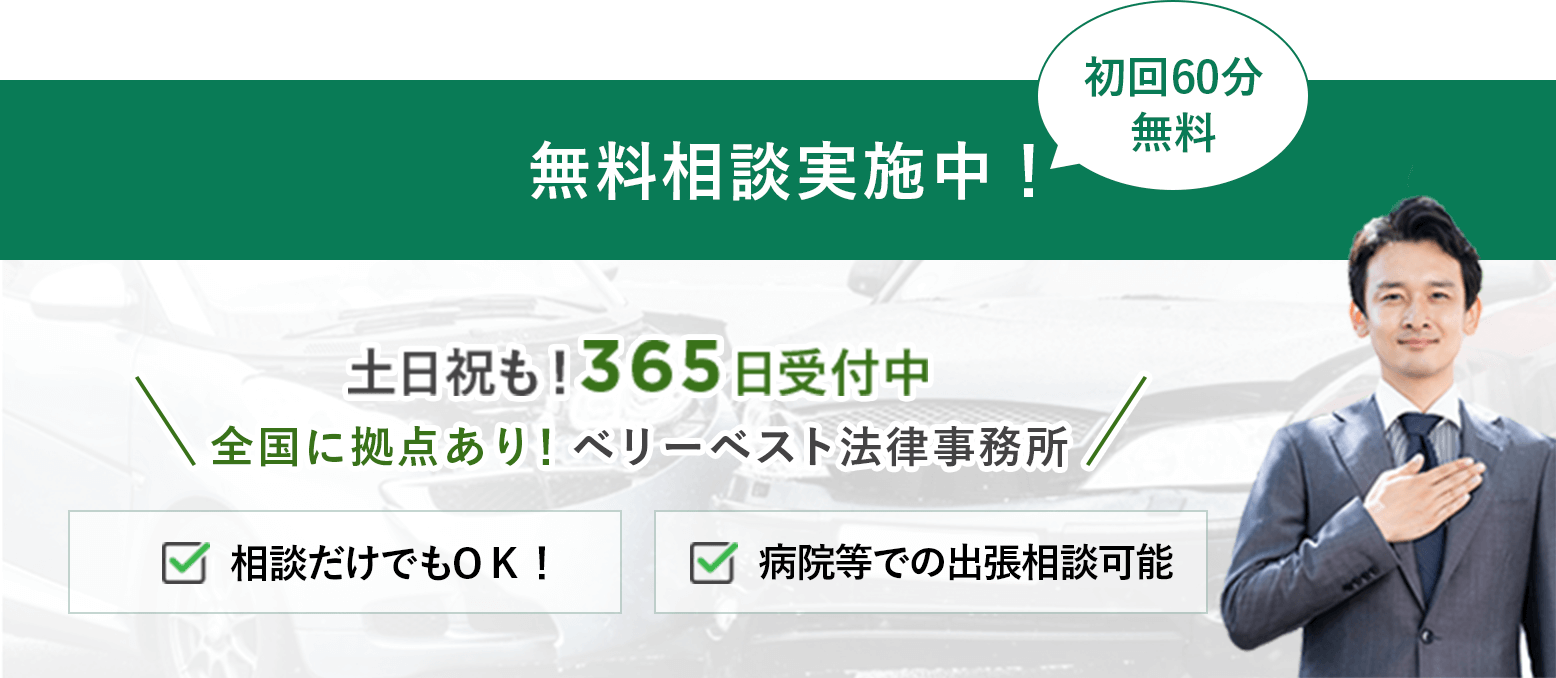

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、交通事故証明書とは一体?
(1)交通事故証明書とは?
まずはじめに、「交通事故証明書」とはどのような証明書なのでしょうか。
「交通事故証明書」とは、交通事故が発生した事実を公に証明してくれる書面です。
交通事故が発生し警察に連絡すると、警察による現場確認が行われます。そして、その結果が自動車安全運転センターという機関に情報提供され、「交通事故証明書」が作られます。
(2)交通事故証明書には何が書かれている?
「交通事故証明書」には、①事故の発生日時・場所、②事故当事者の氏名・住所等、③運転車両の車両番号(登録番号又は車両番号)、④加入自賠責保険会社と証明書番号、⑤事故の類型、⑥人身事故か物件事故の区別などが書かれています。
事故原因、過失割合、損害の程度などは書かれていません。あくまでも、「このような事故があった」という事実を証明するものです。
2、交通事故証明書はなぜ必要?
では、「交通事故証明書」はなぜ必要になるのでしょうか。
事故の被害者は、加害者に損害賠償をしたり、保険会社に損害賠償額の支払いを求めたりします。その時に、事故の発生日時・場所、事故当事者の住所、氏名などが分からなければ、加害者に対して損害賠償請求のしようがありません。交渉がうまくいかない場合には裁判を起こす必要がありますが、その際の請求手続や、警察の作成した実況見分調書などの資料の取り寄せなどにも必要です。
このように、交通事故による損害回復のためには、「交通事故証明書」が必要なのです。
3、交通事故証明書の発行を申請できるのは誰?
「交通事故証明書」の発行を申請できるのは誰なのでしょうか。
(1)交通事故の当事者
交通事故の当事者、すなわち事故の被害者や加害者のことです。
(2)証明書を受け取ることにつき正当な利益がある者
具体的には、損害賠償請求権を持っている親族や険金の受取人などのことです。
ただし、詳しくは後ほど説明しますが、「自動車安全運転センター」サイトの申請フォームから申請する場合は、交通事故の当事者でない方は申請できません。
4、交通事故証明書の発行にかかる費用は?
交付手数料は540円です。
なお、郵便振替や「自動車安全運転センター」サイトの申請フォームから申請する場合は、払込手数料も負担する必要があります。
5、交通事故証明書の申請方法は?
(1)窓口申請
「自動車安全運転センター」という機関に直接赴き、窓口で直接申請する方法です。
所定の申請用紙に必要事項を記入し、交付手数料を支払って申請します。交通事故の資料が既に警察から届いていれば、原則その日のうちに交付してもらえます。
まだ資料が警察から届いていなければ、申請者の住所又は申請者の希望する住所に郵送してもらえます。他の都道府県での事故の場合も後日郵送となります。
(2)郵便振替申請
自動車安全運転センターがお近くにない場合、直接窓口で申請することが困難となります。
その場合には、交通事故証明書取得用の用紙が警察署、交番、損害保険会社、農業協同組合などに置いてありますので、最寄りの警察署などに行って用紙をもらってきて必要事項を記入し、最寄りの郵便局で払込手数料と交付手数料を支払って申し込む方法もあります。
(3)サイト申請
さらに、自宅に居ながら申請する方法もあります。「自動車安全運転センター」のサイトの申請フォームから申請する方法です。この場合も、払込手数料と交付手数料がかかります。支払方法は、コンビニ、金融機関のペイジー、ネットバンクです。
ただし、申請できるのは、交通事故の当事者で、かつ、事故当時の住所と同じ住所に住んでいる方に限られますので注意してください。
6、交通事故証明書の読み方
既に少し説明しましたが、「交通事故証明書」には以下のことが書かれています。
(1)事件照会番号
警察署名と照会番号が書かれています。
(2)発生日時
交通事故の発生日時が書かれています。
(3)発生場所
交通事故の発生場所が書かれています。
(4)甲欄
加害者の住所・氏名、車種(事業用か自家用か)、車両番号(いわゆるナンバー)、自賠責保険会社名・証明書番号、事故時の状態(運転,同乗,歩行等)が書かれています。
なお、甲欄には、加害者の情報が載っていたりするのですが、交通事故証明書はあくまでも過失の有無や程度を証明するものではないので、過失の有無や程度についてはその他の資料等で証明する必要があります。
(5)乙欄
被害者の情報が書かれています。
ただし、これも甲欄と同様、過失の有無や程度を証明するものではありません。
(6)事故類型
人対車両、車両相互、車両単独(自損)、踏切、不明・調査中のいずれかに○印が付けられています。
(7)照会記録簿の種別
人身事故か物件事故かが書かれています。
7、交通事故証明書|自賠責保険の場合の保険金等を請求する手順
(1)請求方法は2つ!
①加害者請求
まず加害者が被害者に対して損害を賠償して、それから改めて保険会社に対して加害者が保険金の請求する場合です。
②被害者請求
保険会社に対して、被害者が直接、損害賠償額の支払を請求する場合です。
(2)請求の手順
事故発生から保険金等が支払われるまではおおよそ以下のように進みます。
①加害者請求のケース
・事故発生
↓
・当事者で話し合い
↓
・被害者に対して支払い
↓
・加害者が必要書類を提出
↓
・保険会社の審査
↓
・入金
②被害者請求のケース
・事故発生
↓
・保険会社に仮渡金請求(入通院費用等の捻出が困難な場合)
↓
・仮渡金の支払
↓
・損害額の確定
↓
・保険会社に必要書類を提出
↓
・保険会社の審査
↓
・入金
(3)請求するのに必要な書類
では、保険金等を請求するために、一体何を準備すればよいのでしょうか。以下に挙げてみました。
なお、保険会社から保険金請求のための書類一式を取り寄せて、様式や必要な資料を確認することが大切です。
- 保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 「交通事故証明書」
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書又は死亡診断書
- レセプト
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書又は看護料領収書
- 休業損害証明書(自営業者は納税証明書等)
- 示談書(加害者請求の場合)
- 加害者の示談金支払を証明する証明書(領収書等)
- 請求者の印鑑証明書
- 委任状及び委任者の印鑑証明
- 戸籍謄本
- 後遺障害診断書
- レントゲン写真等
8、交通事故証明書|任意保険の場合の保険金等を請求する手順
(1)請求方法
任意保険は被保険者が交通事故による損害賠償責任を負った場合に、それを填補するための保険ですので、基本的には、加害者が、任意保険会社に保険金を請求することができます。
もっとも、任意保険の約款には、交通事故の被害者による直接請求権を認める規定があることが多く、その場合には、被害者からも任意保険会社に対して損害賠償額を請求することができます。
①加害者からの請求
交通事故が発生した後、任意保険会社に保険金の請求手続をとれば、任意保険会社が被害者との示談交渉を行ってくれ、示談成立後に保険金を被害者に支払ってくれます。
なお、任意保険会社が自賠責保険の請求手続も一括で行ってくれますので、加害者は別途自賠責保険の請求手続をする必要はありません。
②被害者からの請求
交通事故が発生した後、任意保険会社に損害賠償額の請求手続をとり、交渉を経て示談が成立すれば、損害賠償金が支払われます。
なお、こちらについても、任意保険会社が自賠責保険の請求手続も一括で行ってくれますので、被害者は別途自賠責保険の請求手続をする必要はありません。
(2)請求の手順
事故発生から保険金等が支払われるまでの流れをみていきましょう。
①加害者からの請求
・事故発生
↓
・加害者と被害者との交渉
↓
・加害者による被害者への損害賠償金の支払
↓
・加害者が任意保険会社に必要書類を提出
↓
・任意保険会社による審査
↓
・保険金の支払
②被害者からの請求
・事故発生
↓
・被害者が任意保険会社に必要書類を提出
↓
・任意保険会社による審査
↓
・損害賠償額の支払
なお、任意保険は、加害者(加害者側任意保険会社)と被害者との間で示談が成立しないと支払われないのが原則ですが、実際には、一括対応といって治療費については病院に直接支払ってくれることが多く、休業損害や通院交通費などについても示談成立前に内払金として受け取ることができる場合が多いです。
(3)請求に必要な書類
保険金等の請求のために必要な書類を以下に挙げてみました。
- 保険金又は損害賠償額請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 示談書,示談金領収書(加害者からの請求の場合)
- 診断書・死亡検案書等
- 交通費,看護料等の明細書
- 休業損害証明書
- 請求者の印鑑証明書
- 委任状及び委任者の印鑑証明
- 戸籍謄本
- 後遺障害診断書
- レントゲン写真等
- 保険証券(加害者からの請求の場合)
交通事故証明書まとめ
今回は交通事故証明書について説明してきましたが、いかがでしたか。
今回の話が交通事故証明書の内容や請求方法についてご理解頂ければ幸いです。