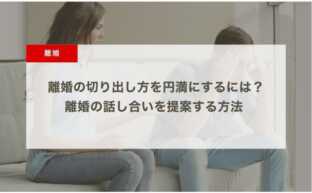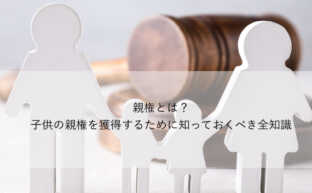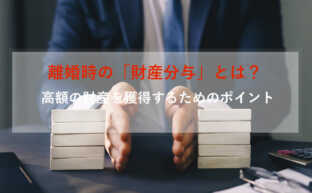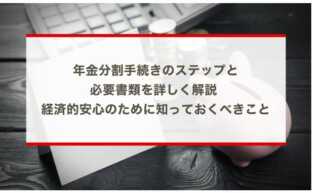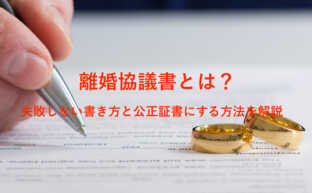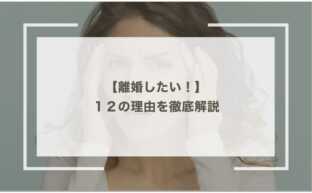「協議離婚」は、夫婦が話し合いによって離婚を決める方法です。
この記事では、個々の状況に合わせた離婚の話し合いの進め方について詳しく解説し、スムーズな離婚プロセスへの理解を深めるためのガイドとしています。
目次
1、相手を離婚の話し合いのテーブルにつかせるには
離婚の話し合いにおいて、第一の難関は、相手を話し合いのテーブルにつかせることです。
多くのケースにおいて、夫婦双方が同時に同じレベルで離婚を考えている、ということはありません。片方のみが強く離婚を考えており、そうでない相手に対し離婚を切り出す、という形でしょう。
このようなケースでは、まず、相手が話し合いのテーブルにつきません。もしくは、穏便に進みません。不機嫌な態度を取られたり怒鳴られたり、いいことは何一つないのです。
(1)相手を話し合いのテーブルにつかせるたった1つの方法
相手を話し合いのテーブルにつかせるために行うことはただ1つ。
本気を見せることです。
離婚をすることに対する本気もそうですし、相手の反応によっては離婚をするかどうかはわからない場合でも「話し合い」に対する本気を見せるということです。
(2)本気を見せる具体的な方法
ここで、本気を見せる具体的な方法は人間の数ほどあるということをご理解ください。
本気とは、自然ににじみ出るものなのです。にじみ方に決まった方法などありません。
- 大きな声を出す、泣く
- 家事等を放棄する(できなくなる)
- 粘り強く話続ける
- 家を出る
等々、相手が「この人本気だな」と思う瞬間は様々でしょう。
ただ、
- 相手の反応を恐れ行動に出られない
- 何度も本気をぶつけたつもりだが相手は微動だにしない
というときは、どうか「味方」をつけてください。たとえば、相手のDVやモラハラがひどいケースなどです。
このようなケースでは一人で行動するのは危険ですし、本気を出したところで握りつぶされてしまう可能性もあります。
そのため一人では戦わず、親族や友人をはじめ、場合によっては自治体や警察など、適切なところへ相談しましょう。
どこへ相談したらよいか迷う場合は、まずは弁護士の無料相談がおすすめです。
2、離婚を相手と話し合う前に整理しておくべき内容
話し合いを本気で望むときは、話し合う前に自分の中で整理をしておかなければなりません。
あなたは、何を話し合いたいのでしょうか。
離婚に合意してほしい、という一択であれば、整理しておくべき内容は以下の項目の通りです。
一方で、相手の行動を辛く思い、直してほしいなどの気持ちがある場合は、まずは気持ちを整理しなければなりません。
気持ちの整理は、紙に書いたり人に話したり、今ではネットの掲示板で相談したりAIに語りかけたりすることもよいかもしれません。とにかく、心の中にしまわず、外に出して客観視できる状態にしておきましょう。
(1)離婚したい理由
離婚を切り出される側としてもっとも気になるのは、あなたが離婚をしたい理由です。
離婚の決意が固い場合は、離婚の理由を相手のせいにしないことが重要です。
- あなたが浮気したから
- あなたと性格が合わないから
- 家族のことを気にかけてくれないから
等々、相手のせいにするような言葉を使ってしまうと、「そんなつもりはない」「自分も嫌な思いをした」などと始まり、話が前に進まなくなります。
離婚を決意したもともとの理由が相手のせいであったとしても、
- (あなたの●●が原因になったけれど)家庭を出て自分らしくいろんなことに挑戦してみたい
と、自分の思い描く人生を生きるために離婚が必要だということを主張することをお勧めします。
(2)その他条件
離婚では、夫婦で築き上げてきたものを清算しなければなりません。
子どもがいれば、どちらが引き取るかを決めなければなりませんし(親権、養育費)、その他財産の清算(財産分与、年金分割)、そして離婚原因に相手に有責行為(不倫など)があった場合はその損害を賠償してもらうのかどうか(慰謝料)などです。
各項目について、詳しくは以下の関連記事をご確認ください。
3、離婚を相手と話し合う前に準備すべき「自立」とは
離婚の話し合いをスムーズに進めるために欠かせないのは、なんといっても「自立」です。
相手に大きな欠点があり、これ以上共に生活をしていかれないという心労がいかに大きかったとしても、あなた自身の自立が足りなければ話し合いが進むことはないのです。
(1)経済的な自立
離婚をした後にあなたは自分で稼いだお金で生活していくことになります。
もしもシングルマザーになった場合には、それ相応の稼ぎが必要です。
先に、経済的な自立をしっかりしておきましょう。
仕事も決まっていない段階では、離婚話を進めたところで、現実味がないと配偶者に笑われてしまうかもしれません。
経済的な自立とは、生活していく上で必要になるお金の確保や仕事の確保のことです。
離婚後に職探しをしたところですぐに見つかるとは限りません。
離婚後すぐに路頭に迷う危険性があるでしょう。
そのような状態では配偶者も心配で離婚には合意してくれない可能性があり、また自身も離婚への強い気持ちとはうらはらに相手の経済力に結局絆されてしまうのです。
(2)離婚後の住まいの確保
離婚後の住まいの確保も同様です。
子どもがいるならそれなりの住まいを見つけておく必要があります。
例えば、一時的に実家に身を置くなどでもいいでしょう。離婚後の住まいの確保は確実に必要になる項目です。先に考えておければ、配偶者も納得してくれる確率が高まります。
子どもがいる場合には、学校や幼稚園に目星をつけておくことも大切です。
引越し先にあわせて子どもがしっかり生活できる環境を事前に整えておけるかも配偶者は気になることでしょう。
(3)精神的な自立
何よりも重要なのは、精神的な自立です。
当然離婚した暁にはもう配偶者はいません。何かあってもあてにはできないワケです。
これまで配偶者に精神的に依存していた場合には、自我を持って行動できるように自分を律する必要があります。
4、離婚の話し合いの切り出し方
ここまで整ったら、いよいよ離婚の話し合いを本気で切り出しましょう。
以下の関連記事で詳しく解説しています。ぜひお目通しください。
5、離婚を切り出してから成立までの期間は1年未満
では、実際に離婚を切り出してから離婚が成立するまではどの程度の期間が必要なのでしょうか。
離婚を決意したなら一刻も早く離婚を成立させて配偶者とは無関係になりたいと感じるはず。
しかし、そううまくいくのか誰もが気になることでしょう。
令和4年度の厚生労働省の「離婚に関する統計」の概況によると、ほとんどのカップルは別居をしてから離婚成立するまでの期間は1年未満です。
婚姻期間が短いほどに1年未満で離婚できる割合は高い結果に。婚姻期間が長くなるにつれ、離婚までの期間が長くなる結果がわかります。
しかし婚姻生活が35年以上に及んでいる夫婦に関してのみ、離婚の話し合いがスムーズに進む傾向がみられています。
とはいえ、中には、離婚を切り出してから成立するまでに10年以上の月日を費やしている夫婦がいることも事実です。
後悔しないためにも離婚の話し合いはスムーズに進めていきましょう。
6、離婚の話し合いが進まない場合の対処法
協議離婚で配偶者と折り合いが合わずに話し合いが進まない場合の対処はどうしたらいいのでしょうか。いくつか案をご紹介します。
(1)親など第三者を交えて話し合いをする
親などの第三者を交えて話し合いを進める方法も一つの手段です。
2人きりでは話が平行線をたどる可能性があるでしょう。
親を交えれば冷静に判断できる可能性があります。
どちらかがいつもキレてしまい話し合いが進まない場合にはおすすめです。
また、弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。
お互いの収入から、養育費や財産分与の適切な数値などを割り出してくれます。
離婚の金銭的な条件で配偶者が合意しない場合にはおすすめになるでしょう。
(2)調停離婚
第三者を通しても協議離婚では話し合いが進まない場合には、家庭裁判所で行われる調停離婚を行うことになります。
調停離婚とは、調停委員を介して話し合いが進められる方法です。
調停委員が介入することで、お互いの意思が尊重され公平な話し合いができることでしょう。
あなたの離婚したい意思が固いことが調停委員に伝わることで、有利に話し合いをすすめてくれるかもしれません。
しかしそれでも配偶者側が離婚に合意してくれない場合には、裁判離婚へと発展してしまいます。
裁判離婚では、話し合いは行いませんから、どうしても離婚したいという場合には、調停離婚までに決着をつけておく方がいいでしょう。
そのためには配偶者の条件を尊重して、少し譲歩してでも離婚に同意してもらう方が賢いやり方です。
(3)裁判離婚
最終的に離婚の合意が得られない場合には、裁判離婚の形になるでしょう。
裁判離婚とは、裁判官が法的に離婚できるのかどうかを判決する方法です。
ここでは、法律に基づいて、結論を下すわけですからあなたの離婚したい理由が「性格の不一致」だけの場合には離婚できない可能性の方が高いといえます。
そして、裁判離婚に発展したケースでは時間もお金もかかってしまいます。心的負担も多くなるでしょう。
裁判離婚まで行って本当に離婚をした方が良い状態なのか、夫婦関係の修復は本当に不可能なのかを今一度よく考えてから裁判離婚には踏み切ってください。
そして、あなたの離婚したい理由が民法第770条で定められた離婚事由(・配偶者に不貞な行為があったとき ・配偶者から悪意で遺棄されたとき ・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき)に相当するのかも今一度よくチェックしてみましょう。
認められない理由では裁判離婚では離婚はできない判決になってしまいます。
よくわからない場合には、信頼できる弁護士に相談をして離婚ができる状態なのかを確認してみるといいでしょう。
7、離婚の合意が得られたら公正証書を作成しよう
最後に離婚の合意が得られた場合には、公正証書を作成しておく必要があります。
後から取り決めが違うなどの意思の齟齬などがないようにしっかり作成することが大切です。
もしも、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、公正証書があれば、裁判を起こすことなく、配偶者の財産を差し押さえることが可能です。
協議離婚の話し合いで条件を決めたなら後々困らないためにも必ず作成しておきましょう。
公正証書は公証役場で作成してもらいます。
あなたが住んでいる地域の公証役場で作成が可能なので、チェックしてみてください。
公正証書は公証人と呼ばれる公務員が作成します。
自分では作成ができませんから注意してください。
公正証書の作成には、離婚協議内容のまとめ、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などが必要です。
詳しくは公証役場確認してみましょう。
作成依頼には30分から1時間程度が必要です。
依頼してからでき上がるまでには約1週間。
作成手数料は、慰謝料の額によって変動しますが、慰謝料が200万円から500万円の場合には、11,000円です。
公正証書は離婚の合意が取れた場合にすぐに作成しておきましょう。
離婚が成立してからでは、お互いに意思の齟齬が発生してしまい、うやむやになってしまう可能性があります。
公正証書でしっかり意識合わせをした後に離婚届を提出しておきましょう。
これらの面倒な手続きは弁護士に依頼することで代理で行ってくれます。
自分では自信がない場合には、信頼できる弁護士に頼ってみてもいいでしょう。
最後に離婚の合意が得られた場合には、公正証書を作成しておく必要があります。
後から取り決めが違うなどの意思の齟齬などがないようにしっかり作成することが大切です。
もしも、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、公正証書があれば、裁判を起こすことなく、配偶者の財産を差し押さえることが可能です。
協議離婚の話し合いで条件を決めたなら後々困らないためにも必ず作成しておきましょう。
公正証書は公証役場で作成してもらいます。
あなたが住んでいる地域の公証役場で作成が可能なので、チェックしてみてください。
公正証書は公証人と呼ばれる公務員が作成します。
自分では作成ができませんから注意してください。
公正証書の作成には、離婚協議内容のまとめ、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などが必要です。
詳しくは公証役場確認してみましょう。
作成依頼には30分から1時間程度が必要です。
依頼してからでき上がるまでには約1週間。
作成手数料は、慰謝料の額によって変動しますが、慰謝料が200万円から500万円の場合には、11,000円です。
公正証書は離婚の合意が取れた場合にすぐに作成しておきましょう。
離婚が成立してからでは、お互いに意思の齟齬が発生してしまい、うやむやになってしまう可能性があります。
公正証書でしっかり意識合わせをした後に離婚届を提出しておきましょう。
これらの面倒な手続きは弁護士に依頼することで代理で行ってくれます。
自分では自信がない場合には、信頼できる弁護士に頼ってみてもいいでしょう。
離婚の話し合いに関するQ&A
Q1.離婚の話し合いで取り決めが必要な内容は?
- 離婚するのか関係の修復を目指すのか
- 親権・子供の面会交流など
- 財産分与・養育費・慰謝料・年金など
- その他個別に取り決めが必要だと思うこと
Q2.離婚を切り出してから成立までの期間は?
平成21年度の厚生労働省の「離婚に関する統計」の概況によると、ほとんどのカップルは離婚を切り出してから成立するまでの期間は1年未満です。
婚姻期間が短いほどに1年未満で離婚できる割合は高い結果に。
Q3.離婚の話し合いをする前に準備すべきことは?
- 経済的な自立
- 離婚後の住まいの確保
- 精神的な自立
まとめ
離婚の話し合いの進め方・流れはご理解いただけましたか?
離婚すると決めたなら、配偶者と冷静に真摯に話し合うことが大切です。話し合いで離婚できるように事前準備をしっかりしておきましょう。
話し合いがスムーズに進まない限りは心身共に疲れ切ってしまいます。
その前に一度立ち止まり、本当に家族のためには離婚した方が良いのかを今一度考えてください。
離婚が成立してから後悔しても遅いのです。
少しでも不安があるなら、実は離婚はしない方がいいのかもしれません。
子どもがいる場合は子どもの幸せという観点も含め、あなたにより良い選択ができますように。