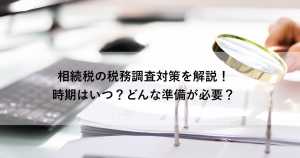
相続税で税務調査が入った場合、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
- 過去に行った相続税申告のまちがいに気づいた…。税務調査が来る可能性はある?
- 税務調査に入られた場合にはどんなペナルティが課せられる?
- 実際の税務調査はどんなふうに行われる?やっておくべき対策・対応は?
相続税の申告を行った後、およそ5年以内の間は税務署による税務調査が行われる可能性があります。
特に調査が来る可能性が高いのは、申告を行った年の翌年または翌々年の秋にかけての時期です。
税務調査によって申告内容の誤りが指摘された場合には、延滞税や加算税という形でペナルティが課せられてしまうこともありますので、注意が必要です。
今回は、相続税の税務調査とはどのようなものなのかについて、実際に指摘されることの多い項目をもとに解説いたします。
過去に行った相続税の申告につて不安を感じている方の参考になれば幸いです。
相続税に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、相続税の税務調査とはどんなもの?

相続税の税務調査とは、過去に発生した相続について、納税者が正しく相続税の納税を行ったかどうかを、税務署の職員がチェックしに来ることをいいます。
以下、相続税の税務調査の具体的な内容について見ていきましょう。
(1)強制調査と任意調査の違いは?
税務調査には大きく分けて「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。
強制調査とは、税務署が強制力を行使して行う税務調査のことをいいます。
強制調査を行うのは、国税局査察部という部署で、いわゆる「マルサ」と呼ばれる組織です。
一般的に浸透している税務調査のイメージはこの強制調査に関するものだと思われますが、実際には、強制調査が行われるのはよほど悪質な脱税のケースに限られます。
任意調査は、その名の通り納税者側の同意を得て行われる税務調査です。
世でいう「税務調査」のほとんどが、この任意調査に該当します。
任意調査は納税者側の意思で拒否することができますが、税務署が調査を行うことそのものはやめてもらうことはできません。
そのため、任意調査を拒否してしまうと、多くのケースで最終的に不利な条件で納税義務や追徴課税が確定してしまう可能性があります。
税務署側には、最終的に納税者の税額を確定する処分を行う権限が認められていますので、任意調査の拒否をすることがメリットになることは非常に少ないと言えます。
後で見るように、税務調査が来ること自体は珍しいことでもありませんので、調査には協力的な態度を示すことが望ましいでしょう。
(2)相続税の税務調査は実際にどのぐらい行われている?
税務調査が行われた件数は、毎年国税庁がホームページで詳細に発表しています。
その情報によると、相続税の課税対象となった相続のうち、およそ12%に対して税務調査が実施されています。
税務調査が実施された場合、83.7%の確率で何らかの非違(申告内容の誤り)が指摘されています。
税務調査が来ることは比較的少ないですが、来た場合にはほとんどのケースで何か間違いを指摘されると考えておく必要があるでしょう。
この記事を作成している時点での最新の情報は平成29年度のものですが、まとめるとおおむね以下のようになっています。
- 平成29年度中に実施された相続税税務調査は、平成27年中に生じた相続に関するものが中心です。
- 平成27年中に発生した相続で、相続税の課税対象となった人の数はおよそ10万3000人です。
- 実際に行われた税務調査の件数は1万2576件でした。
- 相続税の課税対象となった相続のうちおよそ12%に対して税務調査が実施されています。
- 実施された税務調査のうち、何らかの形で申告内容の誤りが指摘されたのは1万521件です。
- 税務調査全体のおよそ83.7%において、何らかの申告内容の誤りが指摘されています。
(3)税務署の調査が行われること自体は問題ではない
上記の通り、相続税の税務調査が行われるのは全体の12%程度ではありますが、税務調査が行われること自体は大きな問題ではありません。
過去の申告内容が事実に基づく正しいものであれば、税務調査は何も恐ろしいことはありませんし、税額の大幅な変更はよほどの事実誤認がない限りは生じる可能性は低いからです。
ただし、税務調査への対応の仕方によっては、本来は負担する必要のない追徴課税を課せられてしまうことも考えられますから注意しなくてはなりません。
税務署職員は税額計算の基礎となるさまざまな事実について質問をしてきますが、その質問への回答内容を証拠として、新たに税額を徴収する根拠としてくることも考えられます。
税務調査の対応は、相続税申告に関する実務にくわしい税理士に立会いを依頼することをおすすめします。
(4)相続税の税務調査が行われる時期は?
相続税の税務調査が行われるのは、「申告を行なった翌年か、翌々年の秋ごろ」であることが多いです。
例えば、相続の発生したのが2019年の1月であった場合には、おおむね以下のようなスケジュールになると考えておきましょう。
- 2019年1月:相続の発生(親族の死亡)
- 2019年11月:相続税の申告期限
- 2020年8月〜2021年11月:税務調査が行われる可能性が高い時期
- 2021年12月〜2024年10月:税務調査が行われる可能性がある時期
- 2024年11月〜:相続税の時効が成立するため税務調査が行われる可能性はありません。ただし、例外的に時効が7年間に延長されるケースもあります
また、相続税の時効は原則として申告期限から起算して5年間、例外的なケースで7年間とされています。(例外的なケースとは、納税者が申告義務を認識していたにもかかわらず、故意に無申告とした場合などが該当します)
そのため、通常は税務調査が入るのは申告を行った年の2年後までですが、5年〜7年が経過するまでは何らかの理由で税務調査が行われる可能性がありますので、安心はできないということになります。
秋に税務調査が行われることが多いのは、税務署内の業務スケジュールによるところが大きいです。
税務署は毎年7月に人事異動を行い、その直後のタイミングの8月〜11月に税務調査を行うのが通例となっています。
12月〜翌年3月にかけては年末調整や確定申告の対応業務がありますので、その間に税務調査が行われることは比較的少ないでしょう(ただし、絶対にないわけではありません)
その後、さらに4月〜6月に年度はじめにやり残した税務調査を終結させていくと言ったように動いていると思われます。
2、税務調査によるペナルティにはどんなものがある?

税務調査が行われた結果、過去の申告内容に誤りがあったことが発覚した場合には、本来納める税金に加えてペナルティとしての税金が課せられてしまう可能性があります。
具体的には、以下のようなペナルティが課せられる可能性があります。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
それぞれのペナルティの内容について、順番に見ていきましょう。
(1)延滞税
延滞税とは、本来納めなくてはならない税金につく利息のようなものです。
延滞税の利率は毎年変更されますが、令和元年時点では以下のとおりです。
- 納期限の翌日〜2ヶ月以内:2.6%
- それ以降:8.9%
延滞税は、申告納税の期限〜税務調査によって指定される納税期限の間の期間で計算されます。
(2)無申告加算税
無申告加算税は、本来は相続税の申告を行わなければならなかったのに、期限までに行わなかったことに対して課せられるペナルティです。
無申告加算税の税率は、本税50万円までの部分については15%、50万円を超える部分については20%となります。
(3)過少申告加算税
過少申告加算税は、相続税の申告は行っていたものの、計算方法の誤りや相続財産に含める範囲の誤りなどによって、本来納めないといけない税額よりも少ない金額を納税していた場合に課せられるペナルティです。
過少申告加算税の税率は、本税50万円までは10%、50万円を超える部分は15%となります。
(4)重加算税
重加算税は、財産の隠匿などの悪質な状況が認められる場合に課せられる、税務調査におけるもっとも重いペナルティです。
重加算税は、上で見た無申告加算税や過少申告加算税に「代わって」課せられるものですので、重加算税が課せられる場合には無申告加算税や過少申告加算税が課せられることはありません。
重加算税は、無申告加算税に代わって課せられる場合には40%、過少申告加算税に代わって課せられる場合には35%の税率で計算して追徴課税されます。
(5)脱税が理由で逮捕されることはある?
ニュースなどでは有名人が脱税を理由に検察に逮捕される場面が報道されますが、脱税を理由に逮捕されるケースというのは極めてまれなケースといえます。
具体的には、手法として脱税を認めることが社会に与える影響が大きい場合とか、脱税した金額が非常に大きい場合(億単位など)、さらには過去の再三の指摘にもかかわらず態度を改めなかったなどの場合に逮捕されるケースが考えられます。
3、税務署はどの程度の情報を把握している?

税務署の職員は、さまざまな情報をもとに納税義務の有無を判断し、税務調査を行う案件の絞り込みを行っています。
典型的には、相続税の申告書の内容に不備が見つかったような場合が該当しますが、他にも以下のようなことがらをきっかけとして税務調査が行われる可能性があります。
- 市区町村に提出される戸籍変更の届出や死亡届
- 法務局で行われる不動産登記情報の変更(相続登記)
- 市区町村が把握している固定資産税に関する情報
- 預貯金口座や証券会社の口座情報の変更
- 故人が運営していた会社の法人税申告情報など
実際に、全体の83.7%(平成29年度)の税務調査で過去の申告の修正を要する指摘がされています。
こうしたことからも、税務署側は入念な準備のもとに税務調査に踏み切っていることがうかがえます。
税務調査が行われる時点で、税務署側は非違の存在におおまか目星を受けている可能性が高いと言えるでしょう。
4、税務調査は実際にどのように行われる?

実際に行われている税務調査のほとんどは任意調査ですので、いきなり職員が自宅にやってくるというようなことはありません。
事前に電話で税務署から連絡が入り、調査日程を決定します。
調査日程当日には、税務署の職員が2名で自宅にやってきて、1日かけて口頭でのヒアリングや、財産の保管場所などの実地調査が行われることになります。
調査結果は、数日〜数週間で納税者に対して通知されます。
過去の申告や納税の内容に問題が見つかった場合には、修正申告という形で申告書を作成し直した上で、追徴課税(延滞税や加算税)を納めなくてはなりません。
税務署側の決定にどうしても納得がいかない場合には、国税不服審判所(税務署や国税局からは独立している国税庁の組織)に不服申立てを行うことができます。
ただし、国税不服審判所への不服申立てを行った結果として、税務署側の判断がくつがえるケースは全体の10%程度といわれています。
(1)税務署から電話がきたらまずやるべきこと
税務調査が行われることが決定したら、税務署の職員から日程調整のための電話連絡が入ります。
通常は、税務署側が仮で決めている日程の10日間ほど前に連絡が来ますが、指定された日にどうしても外せない用事がある場合には日程の変更も認めてもらえますので、遠慮なく伝えるようにしましょう。
また、過去に相続税申告を依頼した税理士がいる場合には、その税理士と速やかに連絡をとってください。
過去の申告を自力でされた方は、相続税申告を専門とする税理士に税務調査対応の相談をされることをおすすめします。
(2)質問応答記録書への対応
税務調査においては、税務署職員からの質問に回答した内容を証拠とする目的で、「質問応答記録書」という書類が作成されることがあります。
例えば、名義預金の有無などを確認する際には、口座の管理が過去にどのような形で行われていたかを納税者自身がコメントすること自体が、事実認定のための証拠に使われる可能性があります。
質問応答記録書の内容は、調査終了時に職員から書面で内容を提示され、間違いがなければ署名押印をするように求められます。
そのため、税務署職員の質問に対する回答は慎重に行わなくてはなりません。
もし、納得がいかない場合には署名押印を拒否することもできますが、その場合には「納税者は署名押印を拒否した」という事実が記録されることとなります。
質問応答記録書については、回答した内容が最終的な税額にどのような影響を与えるのかを理解した上で、慎重な対応をすることが必要です。
5、相続税の税務調査でチェックされるのはどんなこと?
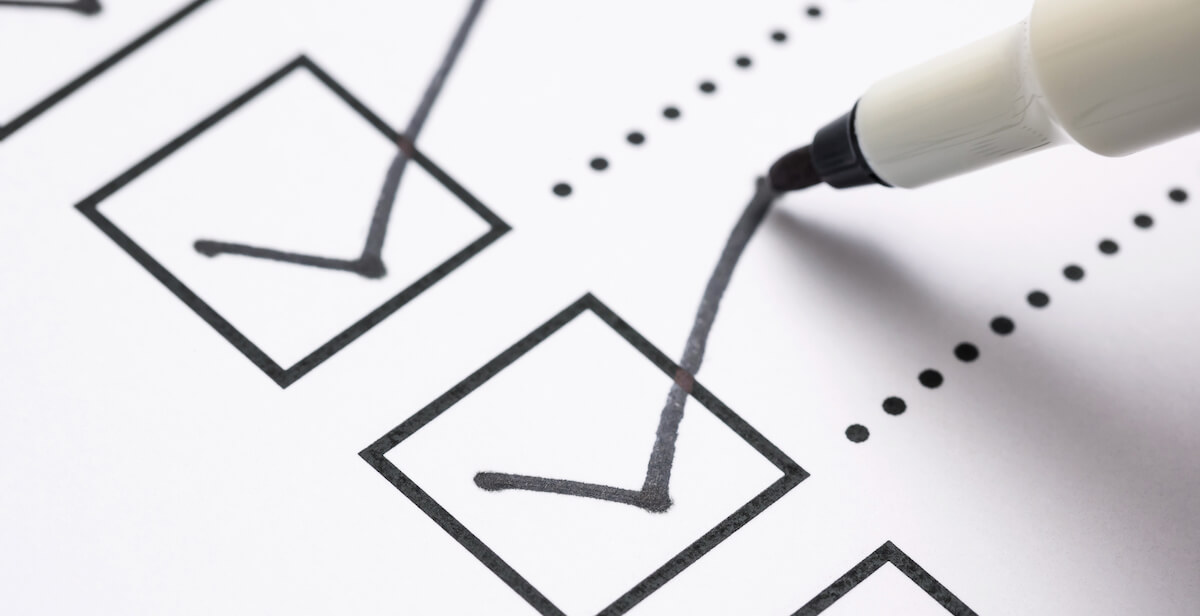
税務調査は、当然のことながら「相続税の申告書に記載されていないこと」を調査するために行われます。
申告書の内容は税務署側でも把握していますから、申告書の記載から知ることができる内容についてはわざわざ納税者の自宅まで出向いてチェックする必要がないからです。
そのため、税務調査ではごくおおまかにいうと以下の2点がチェックされることになります。
- 過去に提出した相続税の申告書に記載漏れとなっている相続財産がないか
- 相続税計算の根拠となる財産の評価方法が正しいか
相続税の金額は、相続した財産の価値に基づいて計算されますので、その相続財産の価値評価が正しく行われていない場合には、相続税の税額も正しくないことになるためです。
以下では、実際の税務調査でチェックされることの多い具体的な項目について、いくつか代表的なものを見ておきましょう。
(1)名義預金の有無
名義預金とは、「名義上は故人以外の人になっているが、実際には故人が自分の財産として管理していたものとみなされる銀行口座」のことをいいます。
例えば、亡くなった人の配偶者や、孫の名義で多額の預金があるようなケースでは名義預金とみなされてしまう可能性があります。
名義預金の存在が指摘された場合、その預金額は相続財産に含めて相続税の計算をしなくてはならないため、税務調査での指摘事項としてよく見られるものとなっています。
税務署側は、相続人となった人が故人の生前からその名義の存在について知っており、実際に自分の財産として使用していた事実があったかなどをヒアリングし、名義預金となるかどうかを事実認定していきます。
(2)生前贈与加算が正しく相続税に反映されているか
生前贈与加算とは、相続が発生する3年前以内のタイミングで生前贈与が行われていた場合に、その贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算することを言います。
税務調査では、故人の銀行預金通帳などの情報をもとに生前贈与加算適用の有無を判断します。
具体的には、相続発生の直前に多額の引き出しがされていないか、通帳から引き出したお金が不自然に消費されていないかといった事柄が指摘される可能性があります。
(3)実質的な生前贈与がなかったか(借金の肩代わりなど)
亡くなった人が、生前において相続人となった人の借金の肩代わりをするなど、実質的な形で経済的な供与をした事実がなかったかどうか?も、よく確認される項目です。
そうした経済的な利益の供与が相続発生の3年以内に行われていた場合には、これも生前贈与加算の対象となりますから、相続財産に含めて相続税を計算しなくてはなりません。
6、税務調査の連絡が来たらどう対応する?

税務署から税務調査の連絡が来たときには、どのように対応すべきでしょうか。
まず、過去に相続税の納税を行った際に、申告書の作成等を依頼した税理士がいる場合には、税務調査が来た旨の連絡をしましょう。
相続税の申告は自力で行ったという場合には、相続税に関する相談を専門で受け付けている税理士に相談することをおすすめします。
税理士に調査の立ち会いを依頼するには料金が発生しますが、税務調査は対応の仕方を誤ると本来納める必要のない追徴課税を納める羽目にもなりかねません。
税務調査の対応は、専門知識を持った税理士に任せるのが賢明といえます。
まとめ
今回は、相続税の税務調査がどのように行われるのかについて解説いたしました。
税務調査が行われるのは全体の12%程度ですが、実際に調査が行われる場合には何らかの形でペナルティが課せられる可能性が高いです。
その際、税務署職員の質問に対してどのような返答をするかによって、最終的に負担することとなる税額に大きな影響が出ることもありますから、注意が必要です。
税務署から税務調査の連絡が来たら、まずは相続対策を専門とする税理士に相談し、対応策を入念に検討することが大切です。
多くの税理士事務所では初回の相談を無料で受け付けていますので、気軽に相談してみてください。






