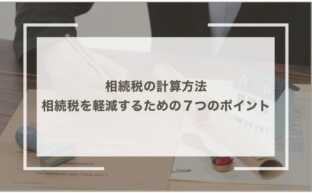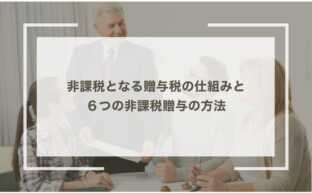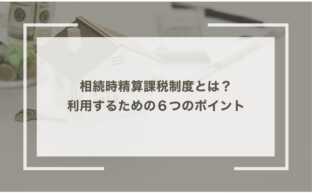「子どもたちに相続税の負担をかけたくないので、節税対策をしなければ……」
「親が亡くなり相続税を払うことになったが、あまりに高い!今からでも節税対策ができないか?」
相続税に関して、このような悩みをお持ちの方も多いことでしょう。
相続税には大きな基礎控除があるため、相続税がかかる割合は低いとはいえ、かかる場合には税額が意外に高額となることが少なくありません。
節税対策を適切に行えば、相続税額を数百万円~数千万円減らせることもありますので、できることはやっておいた方がよいでしょう。
被相続人の生前から計画的に節税対策を行うことによって大きな節税効果が得られるケースが多いですが、本人の没後にも実行可能な節税対策はあります。
そこで今回は、被相続人の生前と没後に分けて、有効な相続税の節税対策を詳しくご紹介します。
なお、相続税がかかる日本人の割合はおおよそ8%程度のみです。
まずは、そもそも相続税がかかるのかどうかを計算してみることが必要です。
相続税がかかるのは、課税対象となる相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に限られます。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。
例えば、父親が亡くなり母親と子ども2人が相続人となる場合は、課税対象となる相続財産の総額が4,800万円を超える場合にのみ節税対策を考えれば足りることになります。
1、相続税の節税のために生前に行うべきこと

相続税を効果的に節税するなら、被相続人の生前に対策をとるのがおすすめです。
生前に行える節税対策として、主に以下のようなものがあります。
(1)相続財産を減らす
まずは、相続財産を減らしておくことで、相続税が非課税となるか、課税されたとしても税額を減らすことができます。
① 生前贈与を活用する
相続財産を減らすための代表的な方法が「生前贈与」です。
ただし、生前贈与には基本的に贈与税がかかるため、贈与税が非課税となる贈与方法を選択することが重要となります。
贈与税のかからない贈与方法として、以下の6つの方法があります。
家族構成や家庭のライフスタイルに応じて、利用可能な方法を組み合わせて活用されるとよいでしょう。
- 暦年贈与(毎年110万円まで)
- 相続時精算課税制度(最大2,500万円まで)
- 配偶者に対する居住用不動産または資金贈与(最大2,000万円まで)
- 教育資金贈与(最大1,500万円まで)
- 結婚・子育て資金贈与(最大1,000万円まで)
- 直系尊属から直系卑属に対する居住用不動産の資金贈与(最大1,500万円まで)
各贈与方法の詳細については、こちらの記事をご参照ください。
② 国や地方公共団体等に寄付する
国や地方公共団体、公益目的の事業を行っている団体に相続財産を寄付した場合には、相続税が課税されないという特例があります。
空き家や空き地、別荘など活用しきれない財産がある場合は、いっそのこと寄付を検討するのもよいでしょう。
寄付による非課税の特例は、被相続人の没後でも利用することができます。
ただし、非課税の特例を受けるには、相続発生の翌日から10か月以内に相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。
③ 保有不動産の価値を下げる
相続財産を被相続人が手放す以外にも、保有不動産の価値を下げることによって相続財産の価額を下げることができます。
- アパート経営など不動産投資をする
相続税の計算における土地の評価額は、自用地(自分たちが住む家が建っている土地)よりも、アパートなどの賃貸不動産が経っている「貸家建付地」の方が20%程度低くなります。
そのため、土地を所有している場合はアパートなどの賃貸不動産を立てることで、土地の評価額を下げることができます。
不動産投資を行うことで継続的に家賃収入も得られますので、空いている土地がある場合にはメリットが大きいといえます。
- 土地を分筆する
土地を分筆すると、路線価が下がることがあります。
そこでで、一筆の土地を分筆して別々の相続人に相続させることで、全体的な土地の評価を下げることも可能になります。
ただし、相続税を回避するためだけに分筆したと認められる場合は「不合理分割」に該当し、相続税の計算においては分割前の評価額を適用することとされているので、注意が必要です。
節税対策として土地の分筆を適切に行うためには高度な専門知識が要求されますので、弁護士や税理士といった専門家に相談することをおすすめします。
(2)非課税財産を購入する
相続財産の中には、相続税が課税されない「非課税財産」もいくつかあります。
生前の節税対策として活用できる非課税財産は、主に次の2つです。
- 墓所等を購入しておく
墓石や墓地、仏壇といった宗教的な意味合いのある財産に対しては、相続税が課税されません。
そのため、現金や預貯金などの形で保有している財産で、これらの非課税財産を購入しておけば、相続税の負担額を抑えることができます。
- 生命保険を活用する
生命保険の死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」までが非課税とされています。
法定相続人を受取人とする生命保険を掛けて、保険金を納めることによって相続財産を減らせる他、相続人にとっては上記の範囲内なら非課税で保険金を受け取れるため、二重に節税効果が期待できます。
(3)基礎控除額を上げる
基礎控除額は先ほどご説明したとおり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますので、法定相続人の数が多ければ多いほど非課税枠が大きくなります。
養子も実子と同様に法定相続人となりますので、養子縁組をすることで基礎控除額を上げることができます。
孫や弟・妹などを養子とすることもできますので、養子縁組は相続税の節税対策として活用できます。
ただし、相続税の控除対象となるのは、実子がいる人の場合は養子1人まで、実子がいない人の場合は養子2人までとされていますので、無制限に基礎控除額を上げられるわけではありません。
(4)事業を営んでいる場合は事業承継税制を活用する
会社のオーナー経営者として活動してきた人は、「事業承継税制」という相続税対策を利用することができます。
事業承継税制とは、簡単に言えば、親族などの後継者となる人が事業を継続することを条件として、前経営者の保有していた株式を非課税で譲ることができるというものです。
事業承継税制は、2019年の税制改正によって適用の条件が大幅に緩和されたため、自営業者として活動されてきた人には非常に利用しやすい方法となっています。
なお、上で見た不動産投資の事業については、事業承継税制の対象としてもらえない可能性がありますから注意しておきましょう。
2、相続税の節税のために没後に行うべきこと

被相続人が亡くなった後でも、以下のように相続税の節税対策としてできることがあります。
(1)控除制度の利用
相続税の申告をする際に、各種の「控除制度」を利用すれば税額を下げることができますし、それによって基礎控除額以下となれば非課税となります。
ただし、各種控除制度は相続人が相続税の申告を行って適用しなければ控除されませんので、ご注意ください。
以下の控除制度のうち、ご自身に該当するものがあれば漏れなく適用しましょう。
①配偶者の税額軽減
亡くなった人の配偶者だった人は、配偶者の税額軽減(配偶者控除とも言います)という税額軽減制度を利用することができます。
配偶者の税額軽減を使うと、多くのケースで相続人である配偶者が負担する相続税は0円となります。
具体的には、配偶者が相続する遺産額が以下の金額までである場合には、その配偶者に対して相続税は課せられないことになっています。
- 法定相続分で相続する場合は、その全額
- 法定相続分と異なる遺産分割を行う場合は、1億6000万円まで
配偶者の法定相続分は以下のとおりです。
- 相続人が配偶者のみである場合:全額
- 相続人が配偶者と子供である場合:2分の1
- 相続人が配偶者と父母である場合:3分の2
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合:4分の3
配偶者控除を利用すれば配偶者の相続税額を0円とすることができますが、利用にあたっては以下のような条件があることにも注意しておきましょう。
- 役所に婚姻届を出している「法律上の配偶者」に限られる
- 相続税の申告を行わなければ控除されない
- 相続税の申告を行うときまでに、遺産分割協議が完了していなければならない
②未成年者控除
相続人となる人が未成年者(20歳未満の人)である場合には、未成年者控除という税額軽減制度を利用することができます。
未成年者控除によって軽減される相続税の金額は、以下の計算式で計算できます。
- 未成年者控除=(20歳-相続時の相続人の年齢)×10万円
なお、年齢のうち1年未満の年月は切り捨てて考えます。
例えば、相続が発生した時の相続人の年齢が8歳3ヶ月だったとしたら、未成年者控除の金額は以下のように計算できます。
未成年者控除=(20歳-8歳)×10万円=120万円
この人が成年者であったと仮定して計算される相続税の金額が1000万円だったとしたら、ここから未成年者控除の120万円を差し引きし、880万円を税務署に納めれば良いということになります。
③障害者控除
相続人となる人が85歳未満の障害者である場合には、障害者控除という税額軽減制度を利用できます。
ここでいう障害者は「一般障害者」と「特別障害者(重度と診断される人)」とに分けられます。
相続税の障害者控除の金額は、以下のように計算します。
- 一般障害者の障害者控除=(85歳-相続時の年齢)×10万円
- 特別障害者の障害者控除=(85歳-相続時の年齢)×20万円
例えば、一般障害者である30歳の人が相続人となる場合には、障害者控除の金額は以下のように計算できます。
- 一般障害者の障害者控除=(85歳-30歳)×10万円=550万円
なお、障害者控除の適用を受けられる相続人は、法定相続人に限ることに注意しておきましょう。
全くの他人に遺言によって遺産を分け与えるような場合には、その人が障害者であったとしても障害者控除の適用を受けることはできません。
④相次相続控除
10年以内に相次いで相続が発生した場合には、「相次相続控除」という税額軽減制度を利用できます。
例えば、ある人が亡くなってその子供が相続をした後に、その子どももすぐに亡くなって孫が遺産を相続するという時に、孫が負担する相続税を軽減してもらえるのが相次相続控除の仕組みです。
相次相続控除によって控除される金額の計算方法は複雑ですが、ごく大まかに説明すると以下のようになります。
- 「今回亡くなった人が、相続をした時に支払った相続税」から、「前回の相続から今回の相続までの経過年数×10%」を減額した金額
例えば、上の例で遺産が1億円あり、「父→子」の相続が発生した際に、子が1000万円の相続税を負担していたとしましょう(遺産は子1人ですべて相続したとします)
その後、3年が経過した時に「子→孫」の相続が発生したとします(遺産額は9000万円とします)
このときに適用される相次相続控除の金額は、以下のように計算できます。
相次相続控除=今回亡くなった人が前の相続の際に支払った相続税額×今回の相続の相続財産の合計額÷(今回亡くなった人が前の相続の時に取得した財産額―今回亡くなった人が前の相続の際に支払った相続税額)×(今回の相続人が取得する相続財産額÷今回の相続の相続財産の合計額)×(10年―前の相続から今回の相続までの期間)=1000万円×9000万円÷(1億円-1000万円)×(9000万円÷9000万円)×(10年-3年)×10%=700万円
1回目の相続から、2回目の相続までの期間が短ければ短いほど、相次相続控除による税額軽減額は大きくなります。
⑤贈与税額控除
相続開始前3年以内に行われた生前贈与は、相続財産に含めて相続税を計算しなくてはなりません。
一方で、この生前贈与を行なった際にすでに負担した贈与税額がある場合には、相続税の金額から控除することが可能です。
例えば、相続発生から3年以内に行なった生前贈与も含めて計算した相続税の金額が1000万円だったとします。
その上で、生前贈与を行なった時点で200万円の贈与税を負担していたとすると、相続税として負担しなくてはならない金額は800万円(本来の相続税額1000万円-贈与税額控除200万円)ということになります。
⑥外国税額控除
亡くなった人が海外に財産を所有していた場合には、その国において相続税が課せられる可能性があります。
海外の相続税が課税された後に、日本の相続税が課税されると二重課税となってしまいます。
そのため、このようなケースでは、海外の相続税を支払った分については、外国税額控除として相続税の負担額から控除してもらうことが可能です。
外国税額控除は、以下の金額のうち「少ない方の金額」で計算されます。
- 外国の法律に基づいて納めた相続税の金額
- 日本の相続税の金額×海外資産の評価額÷相続人が相続する総額
⑦相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税額控除
生前に贈与を行う場合、贈与額が一定額を超える場合には贈与税を負担しなくてはなりません。
一方で、贈与を行う際に「相続時精算課税制度を利用する」という意思表示を税務署に対して行なった場合には、負担すべき贈与税を相続の発生後に繰り越すことが可能です。
相続時精算課税制度を使うと、合計で2500万円までの贈与税を相続発生後まで繰り越すことが可能です。
ただし、贈与額が2500万円を超える場合には贈与税が課税されますから、そのときに納めた贈与税額は相続税の計算時に控除してもらうことができます。
このような仕組みのことを、相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税額控除と呼んでいます。
(2)特例の利用
被相続人の生前に保有不動産の価値を下げる方法は前記「1」(1)③でご紹介しましたが、没後にも土地の評価を下げることができる方法があります。
それは、「小規模宅地等の特例」を利用することです。
住宅を建てるために使っている土地は相続人の生活に欠かせない場合も多いので、一定の要件のもとに相続税の計算における評価額が最大80%と、大幅に軽減されるのです。
対象となる土地には、被相続人の自宅を建てている土地の他にも、賃貸アパートなどを建てていた土地や、事業用の建物を建てている土地も含まれます。
特例を適用できる土地の面積や相続税評価額の減額割合は、土地の用途などに応じて異なります。
自宅用の土地の場合は330㎡まで、減額割合は80%です。
したがって、本来の評価額1億円の土地があったとしても、要件を満たせば2,000万円の土地として相続税の計算ができることになります。
賃貸アパートや事業用建物のための土地については、条件がより厳しくなっています。
「被相続人に持ち家があると相続税の負担は免れないのでは?」と思われる方も多いのですが、小規模宅地等の特例を利用することによって非課税となるケースが多くあります。
ただ、この特例の適用要件はかなり複雑ですので、利用したい場合は弁護士や税理士などの専門家に相談して進めた方がよいでしょう。
(3)相続不動産の価値を税理士に相談
相続税の計算において、土地の評価は基本的に路線価に基づいて行われます。
ただ、土地の形状や立地条件によっては、路線価では適切に評価できない場合もあります。
例えば、面積1,000㎡を超えるような広大な土地などの場合です。
このような場合は、相続税評価額を下げることができる可能性が高いので、専門の税理士に相談することをおすすめします。
なお、この相談は被相続人の没後でも間に合いますが、生前に行っておくのもおすすめです。
(4)盛大な葬儀を行う
葬儀費用は、相続税を計算する際に相続財産が差し引くことができます。
そのため、盛大な葬儀を行うことで相続財産を減らし、相続税の負担を抑えることも可能になります。
ただし、差し引くことが可能な葬儀費用は、「被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの」に限られることに注意が必要です。
一般的に、葬儀費用の相場は150万円~200万円程度と言われています。
被相続人の職業や財産などにもよりますが、相場を大きく超えるような盛大すぎる葬儀は避けた方が無難でしょう。
また、香典返しや法事(初七日、四十九日等)に関する費用は差し引けないことにも注意しましょう。
(5)国や地方公共団体等に寄付する
前記「1」(1)②でもご説明したように、相続財産を国や地方公共団体等に寄付することで相続財産を減らして相続税の負担を抑える方法は、被相続人の没後でも間に合います。
ここで、被相続人の生前にできる相続税の節税対策と、没後にできる節税対策を一覧表にまとめておきますので、参考になさってください。
節税対策の種類 | 生前の節税対策 | 没後の節税対策 |
生前贈与の活用 | ○ |
|
国や地方公共団体等への寄付 | ○ | ○ |
不動産投資 | ○ |
|
土地の分筆 | ○ | ○ |
現地調査 | ○ | ○ |
墓所等の非課税財産の購入 | ○ |
|
生命保険の活用 | ○ |
|
養子縁組 | ○ |
|
事業承継税制の利用 | 〇 |
|
各種控除制度の利用 |
| ○ |
小規模宅地等の特例の利用 |
| ○ |
盛大な葬儀を行う |
| ○ |
3、相続税の節税対策における注意点

相続税を節税するためには、実行可能な対策を手当たり次第にやればよいというものではありません。
以下の3つのポイントに注意した上で、計画的に節税対策を実践することが大切です。
(1)贈与税の方が高くつくこともある
相続税の節税対策として生前贈与を活用する人は非常に多いですが、贈与税にはくれぐれも注意が必要です。
贈与税率は相続税率よりも高いので、贈与税がかかる場合には、かえって相続税よりも高くついてしまう可能性が高いといえます。
前記「1」(1)①でご説明したように、贈与税がかからない贈与方法を選びましょう。
ただ、「暦年贈与」についてはさらに注意が必要で、被相続人が毎年110万円以内の範囲で配偶者や子ども、孫などの名義の口座に預金を積み立てていた場合、税務署から「名義預金」とみなされることがあります。
名義預金とは、口座名義は他人であっても、実際には入金者が管理していた場合に、入金者の財産として取り扱われる銀行口座のことです。
被相続人の生前に名義預金が税務署に発覚すると贈与税が課され、没後に発覚すると相続税が課せられます。
どちらにしても節税効果はゼロとなってしまいます。
(2)二次相続も考慮してシミュレーションをすべき
相続税対策は、今回の相続だけでなく、いわゆる「二次相続」まで考慮してシミュレーションしておくことが大切です。
二次相続とは、例えば夫が亡くなった後に妻が財産を相続し、その後短期間のうちに妻も亡くなってしまったような場合のことをいいます。
この場合、夫が亡くなったときの「一次相続」において妻がすべての遺産を相続すると、配偶者の税額軽減を適用することによって相続税を非課税とすることが可能です。
しかし、ほどなくして妻も亡くなってしまうと、夫から妻へ相続された遺産が、そっくりそのまま妻から子どもで相続されることになります。
そうなると、二次相続においては子どもにかかる相続税の負担がかえって増える可能性が高くなります。
こうした事態を避けるためには、一次相続の段階で、子どもにもある程度の遺産を相続させる方が得策となります。
つまり、将来的に発生する相続まで考慮したうえで、トータルで最も相続税の負担が小さくなるように対策を行うことが大切なのです。
(3)不動産投資などに失敗するリスクも考慮する
相続対策の方法として、アパート経営などの不動産投資を選択される人は少なくありません。
本記事でも、前記「1」(1)③でおすすめしたところです。
ただ、不動産投資はビジネスの一つであり、失敗するリスクもあることに注意が必要です。
つまり、不動産投資そのものが黒字にできないと、結局は親族に残す財産が少なくなってしまう可能性があるということです。
相続税対策のために不動産投資を行い、結果として相続税も減ったけれど残す財産そのものが減ってしまった…というのでは本末転倒です。
相続税対策のために不動産投資を選択するのであれば、不動産投資そのものも成功に導けるようしっかりと研究を行う必要があります。
4、相続税の節税対策は専門家に相談しよう

ここまで、相続税の節税対策として有効な方法をひととおりご紹介してきましたが、どの方法が適しているかは事案ごとに異なります。
そのため、実際に節税対策を行う際には、専門家に相談することをおすすめします。
税金についての専門家とは大抵「税理士」を指しますが、特に相続税については「税理士と提携している法律事務所」がおすすめです。
というのも、相続税は当然、相続において発生する税金ですが、相続の手続き自体は法律のプロである弁護士の専門分野です。
相続では相続税のみならず、遺産分割の取り分に関するトラブルから相続人廃除などの相続人問題、遺言書があった場合の手続きなどが発生します。
これらについては弁護士の専門分野です。
つまり、相続は、その軸となる手続きの部分で弁護士をつけることによってスマート&スムースに手続きを進めることができるのです。
相続税は、相続手続きを進める中での1つの問題にすぎません。
相続については基本的に弁護士マターですので、問題点を法律事務所で精査し、そこから提携する税理士へ処理を預けると大変スマートでしょう。
税理士といってもいろんな専門分野を持った人たちがいますが、法律事務所を通すことにより遺産相続専門の税理士に容易にたどり着くことができるというメリットもあります。
なお、相続税の申告は相続発生から10ヶ月以内に行わなくてはなりません。
もしこの間に申告と納税ができなかった場合には、加算税や延滞税といった形でペナルティが課せられてしまう可能性があるので注意が必要です。
配偶者控除や小規模宅地等の特例といった「税額軽減制度」を利用するためには、相続税の申告前に遺産分割手続きが完了していることが条件となります。
相続割合をめぐってトラブルになってしまう可能性があるときには、少しでも早いタイミングで専門家に相談しましょう。
まとめ
相続税の節税対策においては、まずは法律上認められている節税方法を正確に知り、利用可能な方法をできるだけ早いタイミングで行うことが大切です。
どのような節税方法を選択するのが適切か?は現状の財産の状況や、誰が相続人となるのかによって異なりますから、慎重に判断する必要があります。
少しでも不安がある場合は、早めに税理士と提携する法律事務所へ相談してみるとよいでしょう。