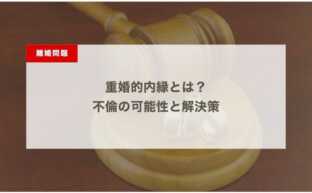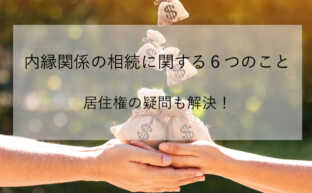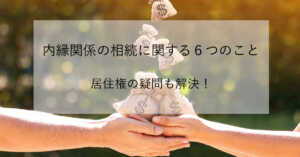
内縁の配偶者の財産を相続できるのでしょうか。
内縁関係は婚姻している夫婦とは権利や義務が違います。
ここでは、
- 内縁の夫(妻)が残した財産を相続する方法
について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご紹介します。
気になる相続権や居住権についての疑問を解決していきましょう。
法定相続人に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、内縁関係の相続について知る前に|法律からみる内縁関係とは

そもそも内縁関係とは、法律上どんな関係のことを指しているのでしょうか。
(1)事実上夫婦のように生活している男女
内縁関係とは、婚姻をしていない男女が生活を共にし、事実上夫婦のように生活していることを指しています。
実態は夫婦同然であるけれど、何らかの事情をもって法律婚をしないカップルのことです。
(2)愛人との違い-社会生活上夫婦同然の生活をしているかどうか
内縁関係にあると言えるのは、法律上の婚姻関係にはないけれど社会生活上夫婦同然の生活をしている場合のみです。
法律用語ではありませんが、一般的に「愛人」という言葉が使われることがあります。この「愛人」という言葉を使う場合には夫婦同然の生活をしているということまで意味せず、単に不貞関係(不倫関係)にある場合を指すものと言えます。
したがって、愛人関係と内縁関係は異なるものと言えるでしょう。
(3)重婚的内縁
内縁関係であることは双方が独身であることを必ずしも意味しません。
つまり一方もしくは双方が他の人と法律上の婚姻関係にあったとしても、別の男性(または女性)と内縁関係にあるということはあり得ます。
これを「重婚的内縁」と言います。
一方又は双方が法律上の配偶者がいますので、双方が独身の場合と比較して内縁関係と認められるハードルが高いと言えます。
2、内縁関係における権利義務

内縁関係は法律上の婚姻関係ではありませんが、準婚関係として一定の保護を受けることができます。
(1)婚姻関係にある夫婦と同じように与えられている権利義務
内縁関係であっても法律婚の夫婦同様に認められる権利と義務が存在します。見ていきましょう。
①貞操義務
法律婚の場合と同様に、互いに貞操義務を負うと考えられています。したがって、一方が不貞行為をした場合には、他方による損害賠償請求が認められます。
②同居・協力扶助の義務(民法752条)
内縁関係であっても、同居し、互いに協力し、助け合わなければいけません。
③婚姻費用分担の義務(民法760条)
内縁関係でも生活に必要なお金は分担する義務があります。
④日常家事の連帯責任の義務(民法761条)
日常家事債務、すなわち夫婦が共同生活を送るうえで負った債務は、連帯して支払う義務があります。
どこまでが日常家事債務と言えるかは、夫婦の社会的地位・職業・資産・収入、その夫婦が生活する地域の慣習によって異なります。
⑤帰属不明財産の共有推定(民法762条)
婚姻前の財産や婚姻中でも相続などで得た財産はどちらか一方の財産です。
しかし、内縁関係にある最中に得た財産でどちらのものかわからない財産は、共有財産と推定されます。
⑥財産分与(民法768条)
内縁関係を解消する際には、財産分与を請求する権利があります。
⑦遺族年金の受給権
遺族年金は内縁の配偶者でも受け取ることができます。
⑧労働災害の遺族補償の受給権
労働災害の遺族補償は内縁の配偶者でも受け取ることができます。
⑨退職手当の受給権
退職手当や死亡退職金については、会社の規程の内容によりますが、内縁の配偶者でも受け取れるとしている規程が増えています。
(2)内縁関係では認められていない権利義務
一方で婚姻関係では認められている義務や権利でも内縁関係には認められていない権利や義務もありますので、確認しておきましょう。
①夫婦の同姓(民法750条)
内縁関係の夫婦は別姓となり、同姓にはなりません。
②成年擬制(民法753条)
婚姻によって未成年者は成人の権利を得られますが、内縁関係ではその権利は得られません。
③嫡出の推定
内縁関係にある男女の間に生まれた子どもは嫡出の推定を受けません。そのため、その間に生まれた子どもは非嫡出子となり、父親の認知を受けない限り、父子関係は発生しません。
④準正(民法789条)
準正とは、非嫡出子が父母の婚姻と認知によって嫡出子の身分を取得するという制度です。
内縁の場合、内縁関係になる前に非嫡出子がいたとしても内縁関係になったからといって嫡出子にはなりません。
⑤配偶者の相続権(民法890条)
法律上の婚姻関係にある夫婦では、一方が亡くなった時に配偶者は必ず相続人となりますが、内縁関係の配偶者に相続権はありません。
正式な婚姻関係と内縁関係において、これが決定的な違いといっても過言ではないでしょう。
3、内縁の妻(夫)には相続権がない

相続において、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
しかしながら、この「配偶者」とは、法律婚の配偶者のことを意味しており、内縁関係にある配偶者は含まれません。したがって、日本の法律では内縁関係の夫婦には、相手の財産についての相続権がありません。
例え何十年連れ添っていたとしても同様です。挙式をしていたとしても相続権は認められないのです。
法的な婚姻関係でない限りは配偶者として法定相続人となることはありません。
4、内縁関係でも遺産を取得する方法はある
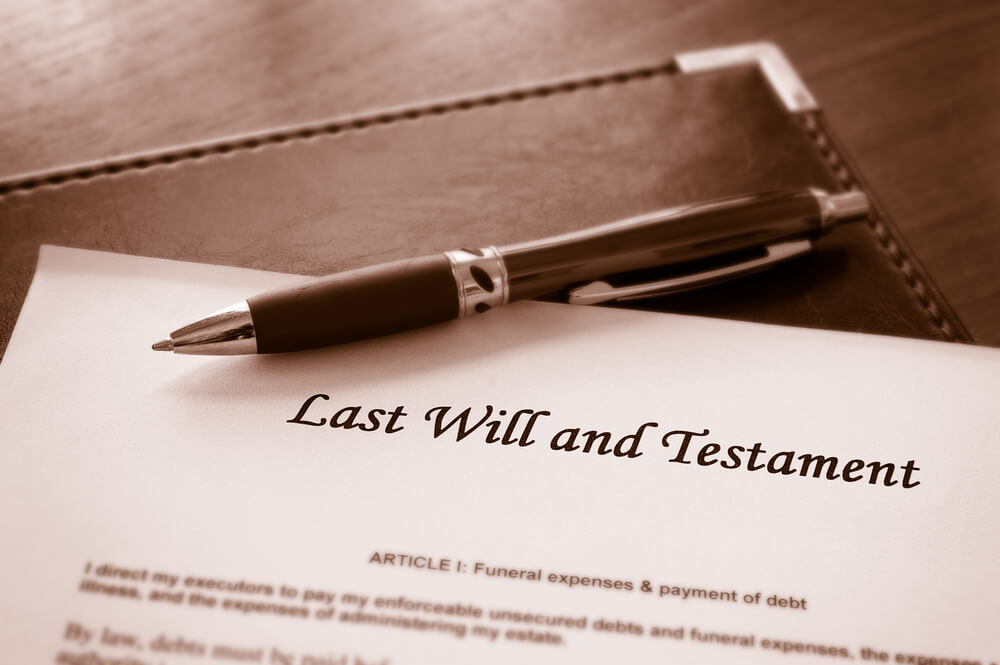
では、内縁関係の夫婦には遺産などを相続する権利がないため、遺産を取得することは不可能なのかというとそうではありません。
被相続人の遺産を取得する方法はあります。
(1)生前贈与しておく
生前に内縁の配偶者に生前贈与しておけば、確実に財産を取得させることができます。
ただし、相続税よりも高額な贈与税が課されますので、生前贈与をする前に税理士に相談することをおすすめします。
また、法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける場合がありますので、その点にも注意が必要です。遺留分侵害額請求については後述します。
(2)遺言書に遺贈する旨を記載してもらう
亡くなった際に、確実に取得させる方法としては、遺言書を作成して、そこで遺産を内縁の妻に遺贈する旨記載するという方法があります。
遺産の全部や一部といった割合で遺贈することもできますし、特定の財産のみを遺贈することもできます。
遺贈をする場合にも、法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける場合があります。
遺留分とは、相続の際に、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限取得することができる割合のことです。被相続人の子どものみが相続人である場合には、法定相続分の半分が遺留分です。
仮に、「内縁の妻に全財産を遺贈する」という遺言がのこされていた場合、法定相続人は自らの遺留分を侵害されていますので、内縁の妻に対して遺留分侵害額請求を行う可能性があります。
これを避けるためには、遺言書を作成される際に、細かく計算し、遺留分に配慮した内容で遺言書を作成する必要があります。その際は、弁護士にご相談されるとよいでしょう。
(3)特別縁故者として財産の分与を受ける
遺言書がない場合には、内縁の配偶者は遺産を得ることはできません。被相続人に法律婚の配偶者や子どもなど法定相続人がいる場合には、遺産を取得することはできません。
法定相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として遺産を受け取れる可能性があります。
すなわち、民法958条の3は、被相続人と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者、その他被相続人と特別な縁故のあった者を相続人と認めてその財産の全部または一部を相続できると定めています。内縁の配偶者は、「被相続人と生計を同じくしていた者」に該当するでしょうから、この「特別縁故者」として財産を得られる可能性があるのです。
ただし、法定相続人が1人もいない場合にだけ認められるものであって、使える可能性が低いと言えます。
また、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行う前提として相続財産管理人の選任申立てを行う必要があるなど、時間や費用がかかります。
さらに、内縁関係にあれば必ず特別縁故者と認められるものではなく、さらに、特別縁故者と認められても財産をどの程度取得できるかの判断は家庭裁判所に委ねられています。
遺産を取得できるかどうかが非常に不明確になり、内縁の配偶者は不安定な地位に置かれることになってしまいますので、この手段は最終手段であるとお考えになるのがよいでしょう。
財産を取得させたい、したいとお考えの場合は、生前贈与や遺言書の作成を進められることをおすすめします。
(3)賃借権を取得できる可能性
一方が亡くなった時に今住んでいる家がどうなるのか、自分が住み続けることができるのか不安だという方もいらっしゃるでしょう。
まず、住んでいる家が2人の共有だった場合には、原則として、他方は亡くなるまでその家に無償で住むことができると考えられています。
しかしながら、亡くなった方の持分は相続人が相続しますので、共有物分割請求をされた場合にはどうなるのかなど不確定な部分は多々あります。
次に、住んでいる家が亡くなった方の単独所有だった場合にはどうなるでしょうか。
この場合、所有権は相続人が相続しますので、原則として内縁の配偶者はその家を出ていかなければなりません。
しかしながら、これまで内縁関係で長く住んでいた住まいをすぐさま明け渡すのは難しいことでしょうし、それは亡くなった方の意思に反することでもあるでしょう。
そのため、相続人からの明渡請求が権利の濫用にあたるとして、内縁の配偶者に対する明渡請求を認めないという判断がなされたこともあります。
最後に、不動産が賃貸の場合で、亡くなった方が賃借人であった(契約当事者であった)という場合にはどうなるでしょうか。
亡くなった方に相続人がいる場合には、相続人が賃借権を相続しますので、それ以上住むことはできず、出ていかなければならなくなります。
亡くなった方に相続人がいない場合には、借地借家法36条1項により、同居していた内縁の配偶者が賃借権を承継します。そのため、賃料を支払う必要はありますが、一緒に暮らしていた家に住み続けることはできます。
いずれにしても、相続人や賃貸人から明渡しを求められるとどうしたらよいのか非常に悩まれることと思いますし、対応もとても難しいと言えます。亡くなった方と一緒に暮らした家から出ていきたくないとお考えの場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
(4)法律婚をする
内縁の配偶者に相続させたいと考える時、相続だけを考えれば、法律婚をして法律上の婚姻関係になることが最善の方法です。
配偶者が離婚経験者だった場合などには、婚姻関係にためらいを感じて内縁関係を長らく続けていたケースもあるでしょう。しかし、遺産相続を考えた場合には法律上の婚姻関係を発生させることが何よりの対策になります。
5、遺言書の作成以外で生前にできる内縁妻(夫)の相続対策

生前に遺産相続についてできるだけ内縁関係の配偶者と相談しておくとよいでしょう。
生前にできる相続対策について見ていきましょう。
(1)生前贈与
生前贈与であらかじめ生きている間に内縁の妻に自身の財産を渡しておくという方法があります。
原則として贈与税がかかりますが、年間に110万円以内であれば非課税となりますので、制度を上手に利用して生前贈与を行うのもよいでしょう。
なお、亡くなる前3年間に贈られた贈与は相続税の課税対象になってしまいますので注意しましょう。
(2)生命保険の受取人指定
生命保険の受取人を内縁関係の配偶者に指定しておく手段もあります。
保険は遺産分割の対象にはなりません。そのため、あらかじめ保険の受取人に指定してもらえば法定相続人との揉めごとにも発展しにくくなるでしょう。
ただし、死亡保険金は相続税の課税対象です。これを踏まえたうえで金額などをご検討ください。
6、内縁者の相続について悩んだときは

このように内縁関係の夫婦の相続は難しいことが多くあります。また、婚姻関係の夫婦とは違い認められない権利や義務もたくさんあります。
遺産相続に困ったことがあるなら、弁護士を頼ってみてください。法的な根拠を元に適切な解決方法を提案してもらえるでしょう。面倒な手続きも代行してくれるため、精神的な負担も少なくて済みます。
まとめ
内縁関係の配偶者が財産を相続するためには、遺言書を残してもらう方法が確実です。もしくは生前贈与などであらかじめ対策を講じておきましょう。
内縁関係といえども長らく生計を共にしてきたはず。財産を相続したいと感じたとしても不思議はありません。
一緒に暮らした住まいを手放したくないのは当然です。できるだけ生前にカップル間で相談し、後々困らないようにしてください。
困った場合には迷わずに知識豊富な弁護士に相談するといいでしょう。