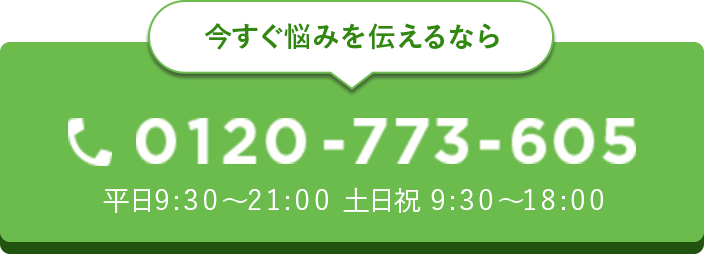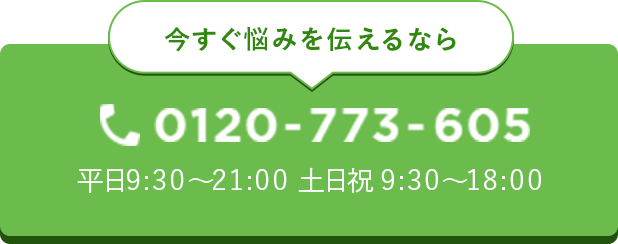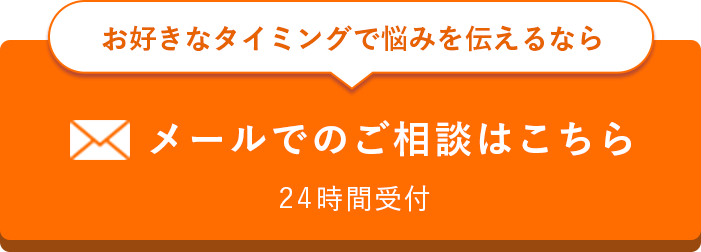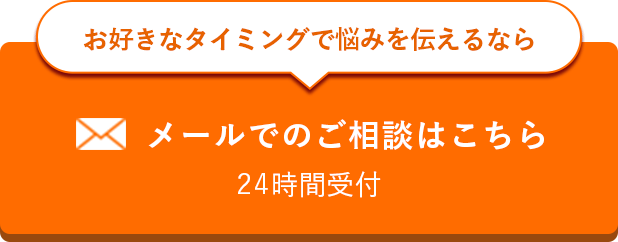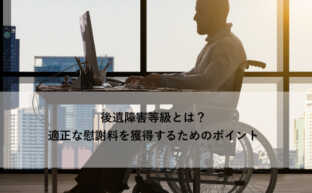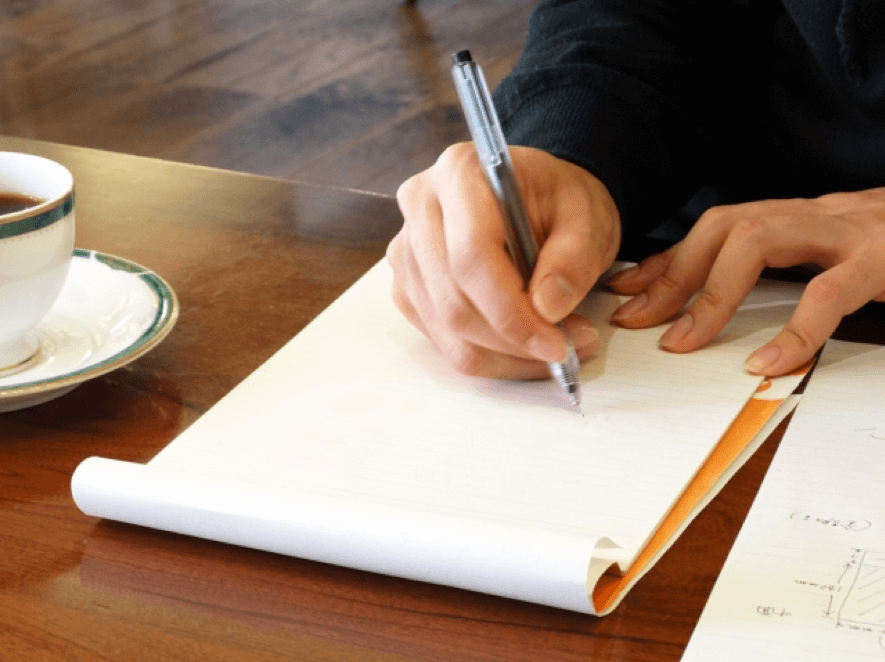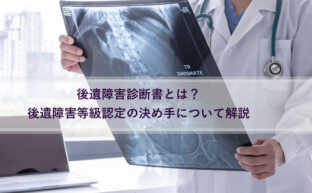後遺障害等級の申請にはどのようなポイントがあるのでしょうか。
交通事故に遭われた方の中には、後遺障害が残ってしまったという方もいるでしょう。
そのような方が後遺障害の程度に応じた賠償金の支払いを受けるためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
そして、この認定を受けるためには後遺障害等級の申請手続をする必要があります。
この申請には、加害者の保険会社が代行して行う「事前認定」手続と、被害者自身で行う「被害者請求」手続とがあります。
今回は、
- 後遺障害等級申請手続における事前認定と被害者請求の違い
- オススメの被害者請求による必要書類と申請手続きの流れ
- 適切な後遺障害等級認定を受ける上で大切なこと
などについて解説していきます。
ご参考になれば幸いです。
交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。
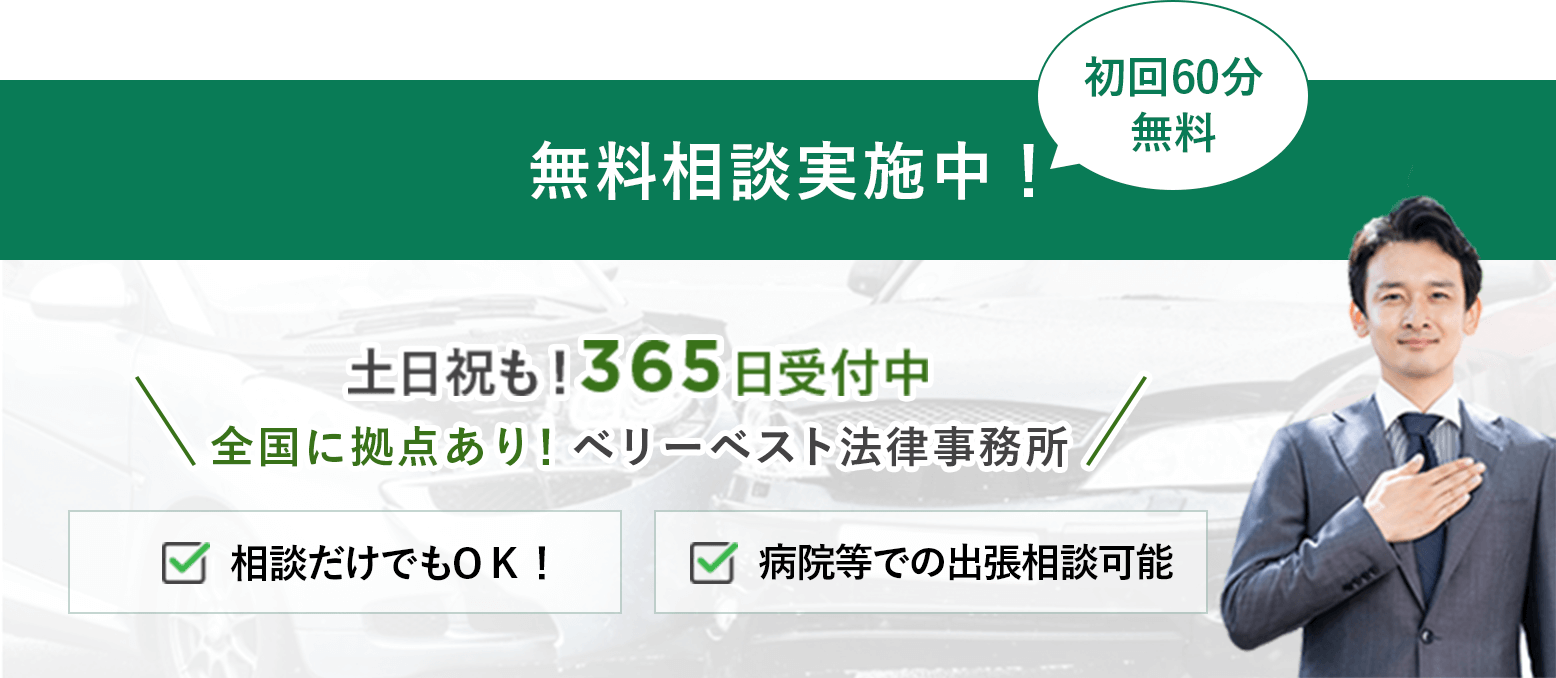

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、後遺障害等級認定の申請方法は2つ
後遺障害等級認定の手続には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
どちらの手続も、残存する症状が固定していること(それ以上治療しても症状が改善しないこと)が前提となります。
(1)事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社に等級認定の申請をほぼ一任する方法です。
事前認定の場合、主治医に作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出し、その他の資料は基本的に加害者側の任意保険会社に収集してもらうことになります。
被害者は後遺障害診断書を提出するだけでよいので手続としては簡単ですが、弁護士に依頼する場合(被害者請求)に比べると、下記の理由から、適切な等級認定が受けられなくなってしまう可能性があります。適切な等級認定が受けられないと、受け取れる損害賠償の額が下がってしまいます。
また、事前認定の場合は、等級認定がされただけで保険金が支払われるわけではなく、示談が成立した後に保険会社から賠償金(示談金)が支払われるので、示談にかかる時間の分だけ現実に自分の手元に賠償金が入ってくる時期が遅くなってしまいます。
【事前認定の流れ】
- 症状固定
- 後遺障害診断書を主治医に作成してもらう
- 主治医作成の後遺障害診断書を任意保険会社へ送付
- 任意保険会社が損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に資料を提出
- 損害保険料率算出機構から任意保険会社に認定結果の通知
- 任意保険会社から被害者に認定結果の通知
(2)被害者請求
被害者請求とは、被害者自らが後遺障害等級認定を行う申請方法です。
被害者請求の場合は、被害者が自分で必要書類を準備し、自賠責保険会社に書類を送付します。
被害者請求は、被害者自身がすべての書類を集めて手続を行うため、提出資料等の詳細について被害者が把握することができます。
これらの資料収集については、傷病の程度によってはかなりの手間がかかることがあります。
しかし、資料作成についても弁護士に依頼をすれば、ご自身の手間はあまりかからずに有利な資料を揃えることができます。そのため、後遺障害認定の申請前の段階でも、弁護士に相談するメリットは十分あるといえます。
また、事前認定より手間はかかってしまいますが、等級認定に向けて積極的に必要資料を揃えることができますし、不利な資料については必要に応じて修正を求めることもできるため、加害者側保険会社に任せる事前認定に比べて適切な等級認定を受けられる可能性が高くなります。
また、被害者請求の場合は、等級が認定されれば自賠責からすぐに保険金を受け取ることができますので、この点でも被害者請求にはメリットがあるといえます。
2、後遺障害等級の認定で大切なこととは
後遺障害等級認定において大切なことは何でしょうか。ここで確認しておきましょう。
(1)適切な等級の認定を受けること
後遺障害等級認定で何よりも大切なのは、適切な等級の認定を受けることです。
手足の欠損など、客観的に見て明らかな後遺障害の場合は、適切な等級認定を受けることは比較的難しくありませんが、むちうち症や高次脳機能障害などの客観的に見えにくい障害の場合は、適切な等級認定を受けられないこともしばしばあります。
自賠責損害調査事務所は書面審査のみで等級を判断するため、客観的に見えにくい障害の場合には、後遺障害診断書等の書面に後遺障害の実態が表れにくく、そのため、本当に後遺障害が残っているにもかかわらず、客観的に見て後遺障害がはっきりしないがために適切な等級認定がなされない場合があるからです。
レントゲンやMRI検査で異常所見がない場合は、目には見えない症状を証明するための検査方法が他にないかを医師に確認するなどして、適切な等級認定を受けられるようにしましょう。
(2)等級が重要なワケ
認定される等級がとても重要なのは、等級によってある程度画一的に賠償額が決まってしまい、その差がかなり大きいものになるからです。
重い後遺障害が残ったにもかかわらず、適切な等級認定が受けられず、賠償額が著しく低くなってしまうケースもあるため注意が必要です。
(3)適切な等級認定を受けるために必要なこととは
適切な等級認定を受けるためには、きちんと書類を揃えて提出することが必要です。
不足書類や記載漏れがあると、適切な等級認定が受けられなくなってしまいかねません。
また、書類に不適切な記載があった場合にも等級認定がされなかったり、実際よりも等級が低くなったりしてしまうため、後遺障害等級に関する正確な知識が必要になります。
3、事前認定では認定される等級が適切でないケースも
事前認定は、後遺障害診断書を保険会社へ提出するだけでよいので、手続としては手間がかからないのですが、適切な等級認定を受けられないケースもあるので、ご注意ください。
事前認定は、任意保険会社に手続を一任するため、被害者が提出書類を把握できないことから、提出書類の不備・不足により適切な認定を受けられないおそれがあります。
認定された等級に納得がいかない場合は、異議申し立てをすることもできますが、いったん等級認定されると覆すのは簡単ではなく、審査には最低でも2~3ヶ月、長い場合は6ヶ月以上かかってしまうこともあります。
そのため、なるべく最初から適切な認定を受けた方が良いといえるでしょう。
4、被害者請求で必要となる書類
ケースによりますが、被害者請求に必要な書類は、主に以下のとおりです。
①交通事故証明書
自動車安全運転センター事務所、警察署・交番及び駐在所に備え付けてある「交通事故証明書申込用紙(払込取扱票及び振替払込請求書兼受領証)」を用いてゆうちょ銀行、郵便局での払込みをするか、または自動車安全運転センター窓口にて申し込みをすることができます。
また、自動車安全運転センターのサイトからも申込みができます。
②支払請求書兼支払指図書
実印を押印してください。支払請求書には請求額の記載欄がありますが、空欄のままで大丈夫です。
③事故発生状況説明図
事故現場における事故当時の状況をできる限り正確に記入してください。
事故状況は、現場周辺の防犯カメラや目撃者・同乗者へのヒアリング、ドライブレコーダーの映像などで確認することでより正確に確認することができますが、それらがなければ記憶の限りで記載するので問題ありません。
④印鑑証明書
住民票のある市区町村役場またはコンビニエンスストア(コンビニエンスストアで発行を行っている市区町村の場合)で発行できます(印鑑登録が必要)。
⑤診断書
医師が作成した受傷から症状固定までの診断書を入手する必要があります。
診断書に「治癒」と記載されていると、後遺障害には該当しないという認定結果になってしまう可能性が高くなるので、「治癒」ではなく「中止」などと記載してもらう必要があります。
また、診断書に「症状軽快しほぼなくなった」などと書かれていると、それをもって後遺障害が残っていないと判断されかねませんので、それが事実と異なるのであれば、その記載を削ってもらうように主治医にお願いする必要があるかもしれません。
⑥診療報酬明細書
医療機関が、被害者や加害者側の自動車保険に請求する医療費の明細書です。
治療日数などが事実と相違ないかしっかり確認しましょう。
⑦後遺障害診断書
上記⑤の診断書とは別の書類で、症状固定時に残っている症状を記載する書面です。等級認定において最も重要な書類といえます。
後遺障害診断書の記載内容に不備があると、等級が認められないなど適切な賠償金を得られないケースもありますので、正確に記載してもらう必要があります。
認定に大きな影響を与える資料ですので、必要な内容が正しく記載されているかをきちんと確認してください。
記載内容に不備がある場合、医師に追記・修正をお願いしなければならない場合もありますが、診断書には医師の診断(医学的見解)が書かれているわけですから、その追記・修正を求めるには相応の根拠が必要になります。
⑧病院の画像データ
MRI画像やレントゲンなどの画像データも提出の必要があります。
MRI画像やレントゲンなどにはうつらない症状である場合は、他に何か症状を証明できるような検査がないか医師に確認してみましょう。
5、被害者請求における申請の流れ
被害者請求における等級認定の申請の流れは、以下の通りです。
- 症状固定
- 後遺障害診断書等の必要書類を自賠責保険会社へ送付し、自賠責保険金の請求を行う
- 自賠責保険会社は書類を確認し、それらの書類を損害保険料率算出機構へ送付
- 損害保険料率算出機構は審査を行い、審査結果を自賠責保険会社へ報告
- 自賠責保険会社がその結果を踏まえて等級認定
- 被害者へ認定結果の通知
個々のケースにもよりますが、申請してから認定結果が出るまでには、2~3ヶ月程度かかる場合が多いです。
1ヶ月ほどで終わる場合もあれば、複雑な事案である場合、半年ほどかかる場合もあります。
なお、後遺障害認定の申請をする権利の消滅時効(その期間を経過すると権利が消滅してしまうという時効)は、5年間です(※民法の改正により、2020年4月1日時点で時効を迎えていないものについては、5年間に延長されました)。
ただし、注意が必要なのが、異議申立てに時効を中断する効力(時効期間をリセットする効力)がないという点です。
そのため、症状固定したのであれば、なるべく早く申請することを心掛けたほうがよいでしょう。
なお、自賠責保険金の請求権に関しては、時効中断の申請をすることができますので、症状固定から長時間が経過してしまっている場合には、申請を検討した方がよいでしょう。
もっとも、上記のとおりに、自賠責保険に対する異議申立は加害者に対する損害賠償請求権の時効を中断する効力を持ちませんので、「症状固定から長期間が経過してしまっているが、未だに後遺障害の認定結果が出ていない」というケースについては、弁護士相談してみた方がいいでしょう。
6、適切な等級を受けたい場合は弁護士に相談を
これまで見てきたように、適切な等級認定を受けるためには、細かい注意点が複数あるため、ご自身で行うには難しく感じるでしょう。
そういった場合には、交通事故に詳しい弁護士へ相談することにより、余計なストレスなく後遺障害等級認定の申請をすることができます。
(1)適切な等級認定を目指します
適切な等級認定を受けるには、意識すべきポイントがあります。
上述のとおり、自賠責保険における後遺障害等級認定は書面のみによってなされます。
そのため、ちょっとした書類の記載漏れや記載違いによって認定要件を満たすことができず、適切な認定が受けられない場合もあります。
弁護士に依頼すれば、知識豊富な弁護士がポイントを踏まえて書類の作成等をお手伝いいたしますので、ご自身で対応するよりも適切な等級認定を受けられる可能性が高くなります。
特に、視覚的な確認が難しい後遺障害(むちうち症、高次脳機能障害など)の場合は証明が難しくなりますし、重大な後遺障害の場合は些細なことで賠償金の額が大きく変わってきますので、ぜひご相談ください。
(2)得られる損害賠償金の増額を目指します
事前認定で保険会社に手続を一任すると、賠償金は自賠責ないしは保険会社の基準で算定されます。自賠責や保険会社の基準は、裁判によって算定される賠償金の基準(裁判所基準)より少ないことが多いです。
弁護士へ交渉を依頼すれば、裁判所基準で賠償金を算定して交渉をするため、もらえる賠償金額が多くなる可能性が高くなります。
(3)複雑な手続は全てお任せください
事前認定と比べて、被害者請求の手続は難しく、手間もかかります。
思わぬ事故に遭った後では、ご自身の体調や精神状態がすぐれないことも多いでしょう。
そんな中で必要な書類を記載内容に注意しながらすべて集めて、手続を進めていくのは大きな負担になるでしょう。
弁護士に依頼すれば、複雑な手続は弁護士に任せて治療に専念することが可能です。
まとめ
交通事故によって後遺症が残ってしまった場合に、適切な後遺障害等級認定を受け、適切な損害賠償金を受け取るには、一定の専門的知識が必要となります。
手続は難しくなりますが、被害者請求をした方が実態にあった等級認定を受けることができる場合が多いです。
とはいえ、ご自身の体調がすぐれない中で、すべての手続をご自分だけで行うのは大変です。
交通事故の後遺障害認定に詳しい弁護士に相談・依頼をすれば、安心して手続をすすめることができますので、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。