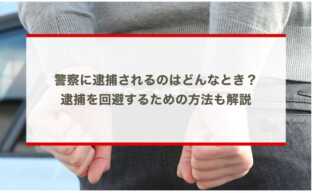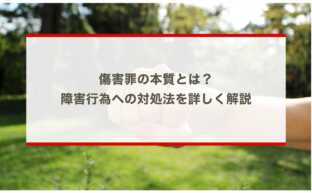近年、傷害罪に関する注目すべき事件が報道されました。元プロボクサーで、大学院生の男性が、弁護士の男性に対し局部を切断するという驚愕の事件や、大相撲の部屋親方が運転手に暴行を加え、2週間の怪我を負わせるという事件などが話題となりました。
これらは極めて異例の事件であると言えますが、日常生活での些細な口論から生じる「お酒に酔っての殴り合い」のようなことであれば、身近にも起こりうる事態ではないでしょうか。
もしもあなたがそうした状況に巻き込まれた場合、どのように対処したらよいのでしょう。今回は、傷害行為をしてしまった場合の対処法について解説していきます。ご参考になれば幸いです。
警察に逮捕について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、傷害罪とは?傷害行為の内容と不起訴を獲得する方法

傷害罪(刑法204条)とは「人の身体を傷害」した者に対して成立する罪です。
罪を犯した者は15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
傷害罪は上記のとおり法定刑の重い犯罪ですから、警察が捜査を始めた場合、基本的には示談をせずに不起訴となることは考えにくいため、被害者との示談をすることが最も重要となります。
詳しい傷害罪における不起訴の獲得方法は、以下の記事をご覧ください。
2、「傷害」に当たるのはどのような行為?
(1)傷害罪(刑法204条)と暴行罪(刑法208条)の違いとは
傷害罪と暴行罪というのは一般的には違いがわかりにくいと思いますが、端的にいうと暴行に及んだが被害者に怪我が生じていない場合には暴行罪(刑法208条)が成立し、暴行により被害者に怪我が生じると傷害罪(刑法204条)が成立することになります。
他に傷害罪の成否が問題となるケースとして、暴行の認識はあったが被害者に怪我をさせる認識はなかったという場合に、結果的に被害者に怪我を負わせてしまった場合がありますが、判例上はこれらの行為についても結果的過重犯として傷害罪が成立します。
(2)過失傷害罪(刑法209条)と傷害罪(刑法204条)の違いとは
過失傷害とは、過失により相手方に怪我をさせてしまった場合の罪をいいます。
例えば、自転車を押して歩いていたところ、側を通る女性がこれに気付かずに自転車に接触して転倒した事案で、自転車を押していた人に動静注視の義務が認められるような場合にはこの罪が成立します。
傷害罪との大きな違いは、暴行等について故意があったか、過失だったか、という点になります。
(3)被害者からも暴行等があった場合
傷害罪については、単に加害者が被害者を殴っただけというわけではなく、先に被害者から殴られたので殴った、周りの人を助けるために殴った等様々な状況があり得ます。
もちろん刑法上正当防衛となる場合もありますが、正当防衛に該当するには「急迫不正の侵害に対して」「やむを得ずにした行為」等の法律上の要件を満たすことが必要となり、暴行を予期していたため急迫不正の侵害ではないと判断される、または結果的にはこちらの傷害行為のほうが重く、正当防衛ではなく過剰防衛として違法と判断される、ということも十分にありえます。
また、その場の捜査だけで正当防衛状況がはっきりとわかることはあまりなく加害者及び被害者に加えその場にいた人などを十分に取調べなくては正当防衛状況にあったことを立証できないことから、加害者が逮捕される可能性もありますし、逮捕されなくとも数回にわたって取調べを受けることになるでしょう(逮捕されずとも、在宅捜査において取調べが半年近くに及ぶことは十分にあり得ますし、刑事裁判において争うことになるとさらに時間がかかります)。
このような場合には、長期間にわたり不安定な地位におかれるより、上記の状況を踏まえた条件で相手方と示談をすることで、心理的負担を減らすことも考えられます。
3、傷害行為をしてしまった場合に被害者と示談することで逮捕を回避する具体的な方法は?
(1)示談について
示談とは、通常は金銭を支払ったうえで、被害者とこれ以上債権債務関係がないということ、及び「処罰を望まない」又は「宥恕する(許すという意味です)」等処罰についての被害者感情を記載した書面を作成することをいいます。
示談をする際には、特に裁判所における刑事裁判が始まる前に、加害者が被害者に対してお金を支払う代わりに被害者が加害者に対する被害届等(被害届及び告訴状)の提出をしないことや既に提出した被害届等を取り下げることを約束することが重要となります。起訴前に示談をすることにより、不起訴の可能性が高まるため、起訴前の示談は、被害者との関係を民事上で解決し、前科を付けないために重要な弁護方法となります。
また、示談というとなにか悪いことのように聞こえるかもしれませんが、日本の法制度上基本的には国が犯罪被害者の被害を賠償するというシステムは採用されていません。
したがって、被害者が犯罪被害について賠償を得るためには、加害者に弁護士がついて示談を進めるのでなければ、自ら費用を支払って弁護士を雇い、長い時間をかけて民事訴訟をする必要があるという現実があります。
検察庁も裁判所もこのような現実をよく理解していることから、被害者に示談して賠償を得るという選択肢を与えるということについて、悪く考えてはいません。
(2)弁護士に対する依頼のメリット
示談をするためには必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、加害者と被害者との間で話を進めることができる場合もありますが、以下のようなメリットを考慮して弁護士に依頼することを前向きに考慮されてもよいでしょう。
①当事者同士の話し合いでは、一度話合いがついて金銭を支払ってからも追加で慰謝料や治療費を請求されたりする、金銭の支払いが少しでも遅れるなど相手の意向に沿わない事実があると追加で倍額の請求をされたりするなど後から再び紛争となる可能性があること
②弁護士が守秘義務等多種の義務を負っていることや、示談交渉のプロであり経験が豊富であることから相手方からも一定の信頼を得られる場合が多いこと
③加害者本人でないことから、相手方も忌憚なく踏み込んだ話をしやすく、感情的にならずにすむこと
また、既に事件化しているものの、加害者からは被害者の氏名や住所が不明である場合には、被害者を特定するため弁護士から警察や検察官等に問い合わせをする必要があります。
したがって、この場合には、弁護士をつけなければ示談をすることができないことになります。
(3)示談のメリット
次に刑事事件の各段階において示談するメリットについて書いていきます。主なものは以下のとおりです。
①被害届、告訴状の提出を回避できること
被害届とは、被害者等が捜査機関に犯罪事実を伝えた上で、犯人を刑事処罰してもらうよう求めることをいいます。
被害届は、通常は犯罪の直後に、被害者が犯罪にあったことを報告するものなので、犯人を特定できている場合もあれば、誰かはわからないが店のガラスが割られている、というように犯人はわかっていない場合もあります。
示談が成立すれば、このように被害届を提出され、警察が事件を把握して捜査を開始することを回避できます。
また、告訴とは犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示を言います。
器物損壊等の犯罪は親告罪といって、告訴がないと刑事裁判ができない犯罪にあたります。
そのため、告訴を回避することで起訴を回避できることになり、ひいては前科を付けることを回避することに繋がります。
実務上は、親告罪か非親告罪かに関わらず、警察が被害者から告訴状を取得することが多いようです。
告訴状において被害者の処罰感情は基本的には「厳しい処罰を望みます」と記載されており、示談が出来ない限りはそこに記載されている処罰感情や被害者の供述調書の処罰感情を前提として刑事処分が下されることになります。
示談が成立すると、被害届や告訴状が提出されていなければ、提出を回避できますし、仮に提出されていた場合には、取り下げてもらうことを示談に盛り込むことができます。
②既に逮捕されていたとしてもその後釈放される可能性が高まること
示談が成立したということは、被害者としては犯人を処罰して欲しい気持ちが弱まっていることが推測されます。
警察も検察も、犯人の処分を決めるにあたっては被害者の感情を無視することはできません。
そのため、逮捕されていたとしても、検察庁や裁判所に示談書を提出することで、勾留が却下される、勾留が延長されない等の事情により釈放される可能性が高まります。
③逮捕勾留されてしまったとしても、その後不起訴になる可能性が高まること
釈放の場合と同様に、示談が成立しているということであれば、示談が成立していない場合と比較して不起訴になる可能性が高まります。
日本の刑事訴訟法は起訴便宜主義を採用しており、検察官が犯罪後の情況も加味して考えたうえで、処罰する必要がない場合には起訴猶予処分として公訴を提起しないことができるからです。
④起訴されても実刑判決を回避し執行猶予判決を得られる可能性が高まること
裁判所も、警察や検察官と同様に、判決をするにあたっては被害者の感情を考慮します。
そのため、示談が成立し、特に示談書に「宥恕(加害者を許すという意味)」の文言が記載されているということであれば、実刑を回避できる可能性が高まります。
⑤実刑判決になった場合でも、刑が軽くなる可能性が高まること
また、仮に実刑になってしまったとしても、示談が成立しているということであれば、示談が成立していない場合と比較して刑が軽くなる可能性が高まります。
実刑の場合には判決後刑務所に服役することになりますので、執行猶予の場合と比較しても、懲役1年、半年、3カ月の差が非常に大きなものになりますので、少しでも刑期を短くすることは大変重要なことです。
⑥民事裁判で損害賠償請求されるおそれがなくなること
示談をすることで、示談金を支払うことになりますが、示談書において加害者と被害者の間にはその他に債権債務がないという清算条項を入れることになりますので、後遺症が生じた場合等を除けば、原則として被害者からそれ以上の損害賠償を請求されるおそれがなくなります。
(4)示談額の相場とは
示談は加害者と被害者との合意(額や処罰感情の記載、その他の約束等)が形成されて成立し、通常はその合意内容を書面にして明確化することになります。
示談額は加害者の資力や相手方の資力、処罰感情や関係性(見ず知らずの人か知人か)等の事情も影響することになりますので、どうしても示談しないという被害者もいれば、金銭の支払いなく示談をする被害者もおり、相手次第になる面は否定できません。
しかし、一般的には相手を殴って怪我をさせたという態様の傷害事件であれば、怪我の状況に応じて10万円から100万円くらいが相場と言えるでしょう。
4、傷害行為により逮捕されてしまった場合の手続の流れと不起訴を獲得する方法とは
(1)逮捕されてからの手続の流れ
加害者が傷害で逮捕される場合としては、現行犯逮捕(逮捕状によらずその場で逮捕される場合)か、通常逮捕(多くは数日後以降に警察官が逮捕状を持ってきて逮捕される場合)が考えられます。
加害者が逮捕されると、警察官は、加害者の家族に、逮捕されたことを連絡します。
加害者の家族は逮捕中の加害者と面会を求めることが多いです。しかし、加害者が逮捕されてから48時間は、加害者の家族であっても面会をすることは出来ません。逮捕の間に加害者と面会を出来るのは弁護士だけとされています。
現行犯逮捕され警察署に連行された後、または、通常逮捕された後、警察署では、警察官から取り調べを受けることになります。
警察官が聞き取りした内容は、記録され書面(「調書」と言います)となりますが、これに署名と指印を押すことを要求されます。
ここで、調書に自分に不利な内容が記載されているのに、訂正せずそのまま認めてしまうと、後でその内容を覆すことは実務上極めて困難です。
「調書」に対する署名・指印は義務であるかのように警察からは言われますが、あくまで任意で行うものです。事実と異なる箇所があれば署名・指印を拒否するか、訂正を申し出る必要があります。
逮捕直後に加害者から事情を聞きたいのであれば、家族が弁護士を選任するか、差し当たって一度の面会(「接見」と言います)を依頼することで、弁護士が加害者と面会することができます。
逮捕直後には、加害者から事情を聴く他の手段が少ないうえ、家族はなにが起きて逮捕されているのかまったくわからないというのが通常ですから、弁護士への依頼を検討すべき場合と言えるでしょう。
警察官は逮捕してから48時間以内に、事件記録と加害者の身柄を検察庁に送ります(これを「送検」と言います)。
通常は逮捕された次の日に送検され、加害者は検察官と会うことになります。検察官が加害者と会って話を聞き(これを「弁解録取」と言います)、勾留請求をするかしないかをここで判断します。
検察官が釈放すべきと判断すれば、検察庁から警察署に戻った後に、身柄を解放されて、自宅に戻ることができます。検察官が裁判所に対して勾留請求をする場合には、警察署に戻った後、引き続き留置場等に留め置かれることになります。
なお、弁護人を選任して、検察官に対し意見書等を提出して、勾留請求しないことを請求することはできます。ただし、一度勾留請求することを決定した検察官を翻意させることは難しいでしょう。
勾留請求をされた場合、次の日に加害者は裁判所に連れて行かれ、裁判官と会います(これを「勾留質問」と言います)。そして、裁判官が、加害者を10日間勾留するか否かを決めます。
ここで弁護人としては、裁判所に対して意見書等を提出して、釈放するよう(勾留請求却下)求めることが出来ます。傷害事件について言えば、弁護人が加害者の生活状況(仕事の状況、家族の状況等)や被害者との関係、被害者の意向などを書面にして裁判所に伝えることで、勾留を免れることができる場合があります。
ただし、釈放される前提条件として、家族等の身近な人が加害者の身元を引き受けてくれることを確約してくれること、加害者が被害者と連絡を取らないことを誓約すること等が必要となります。
勾留の期間は10日間までであるのが原則ですが、この10日間のうちに、不起訴や身柄解放への成果(例えば、示談成立等)がない場合には、勾留が延長されることがあります。4日や5日の延長ということもありますが、最大で10日間勾留が延長される(合計20日)こととなります。
勾留期間が終わるまでに、検察官が裁判所に起訴をするか、不起訴にするかを決めることになります。
起訴には、略式命令と公判請求があります。略式命令の場合には、検察庁で罰金を納付するのと引き換えに釈放されます。罰金については、加害者自身が現金で用意するか、家族に立て替えてもらうことなどにより用意する必要があります。
公判請求された場合、裁判所で裁判手続が始まることになりますが、「保釈」をされなければ裁判が終わるまでは、警察の留置場や拘置所にいることになります。この場合裁判が1回で終わる事件でも、少なくとも約1カ月は身体拘束が続くことになります。裁判が4~5回続く場合ですと、半年以上身体拘束が続く場合もあります。
保釈の請求をする場合も、勾留請求等に対応する場合と同様に、保釈申請書などの書面を作成し、裁判官と面接等をし、保釈を認めるべき事件であることについて、説明をすることになります。
保釈が認められた場合には、担保として「保釈保証金」を裁判所に預ける必要があります。 保釈保証金は加害者が逃げずに裁判に出席すれば返還されますが、金額としては200万円以上となる場合も多いです。保釈保証金を準備できない場合でも、比較的簡単な手続きで保釈保証金を貸してくれる団体もありますので、保釈金についても併せて弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
まとめ
傷害事件の弁護活動を弁護士に依頼した場合、逮捕されていない状況で直ちに弁護士が活動を行い、すぐに警察を通じて被害者と連絡をとったことから、逮捕されずに1月以内に示談を成立させ、不起訴処分を得たような事案があります。また、逮捕後の弁護士接見から5日後には示談が成立し、結果的に不起訴処分を得られたような事案もあります。
前科は、普通に生活していて周囲の人等が知り得るものではありませんが、一度ついてしまうと公的な記録においては生涯消えることはありません。10年後、20年後あるいは30年後に後悔しないように、過ちを犯してしまった場合には、その挽回のため迅速な対応を採ることが重要と言えるでしょう。