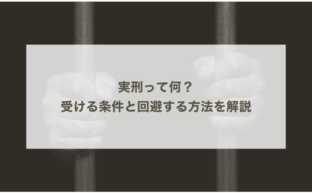刑事司法においてよく聞かれる言葉、「情状酌量の余地あり」や「情状酌量の余地なし」。しかし、その「情状酌量」の正確な意味を理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 「情状」
- 「情状酌量」
について解説します。さらに、
- 「酌量減軽」
の意味も紐解いてみましょう。そして最後に、
- 裁判で情状酌量される際に注意すべきポイント
をお伝えします。この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
実刑について知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。
1、情状酌量とは?
情状酌量とは、「情状」によって、刑事処分や量刑(懲役刑か罰金刑か、懲役刑として何年か、実刑か執行猶予か)を決める際に被告人に有利な事情を汲み取る(「酌量」)、ということです。
以下、詳しくみていきましょう。
(1)情状酌量の「情状」とは?
「情状」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
実は、「情状」には、犯罪そのものに関する情状(犯情)と、犯情以外の一般情状があります。
①犯情
犯罪そのものに関する情状である犯情は、次のようなものが該当します。
- 犯行態様(武器使用の有無、回数、単独か共犯か、故意か過失かなど)
- 犯行の計画性(計画的か偶発的か)
- 犯行の動機(私利私欲のためか、被害者にも落ち度があるかなど)
- 犯行の結果(死亡か怪我か、怪我・被害額の程度、後遺症の有無など)
②一般情状
犯情以外の一般情状は、次のようなものが該当します。
- 被告人の年齢、性格
- 被告人の反省の有無
- 被害弁償、示談の有無
- 被害者の処罰(被害)感情の程度
- 更生可能性の有無(被告人に更生意欲があるか、適切な身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整備されているかなど)
- 再犯可能性の有無(前科・前歴をどの程度有しているか、常習性が認められるか、犯行の原因は消滅しているか・縁は切れているかなど)
(2)酌量軽減
裁判官は、これらの「情状」を加味し、法定刑を減軽することができます。これが情状酌量(酌量軽減 刑法66条)です。
刑法66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
①減刑方法
減刑方法は、刑法68条1号から6号に規定されています。
たとえば3号では、
| 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる |
と定められています。
これを傷害罪についてみてみると、懲役刑は「15年以下」ですので、「7年以下」と減刑されることになります。
②任意的軽減
もっとも、ここで刑法66条では、「減軽する」ではなく「減軽することができる」と規定されていることに注意が必要です。
つまり、情状に酌量すべきものがあったとしても、必ずしも減軽されるわけではなく、その判断は裁判官の心証に委ねられています。これを任意的減軽といいます。
(3)裁判官による量刑の決定
酌量軽減だけでは、まだ量刑は確定されてはいません。
酌量軽減で法定刑を減刑したあと、最終的に「懲役●年」などの判決を決定する際、あらためて裁判官がその心証から情状を酌量(斟酌)することがあります。
一般的にこちらを「情状酌量」とイメージされる方が多いかもしれません。
2、情状酌量を受けるには弁護人の力が必要
刑事裁判では、各裁判上のプレイヤーはその役割が決まっています。
「検察官」は、被告人の公訴事実について証拠をもって主張し、相当な刑を求めます。
これに対し、「弁護人」は、被告人の行為について認める場合も、その理由、事情、背景に加え、情状等を主張します。
そして、「裁判官」は、裁判での審理を踏まえて、自らの心証で有罪か無罪、有罪の場合には量刑を決定する、という役割です。
以上からわかるように、基本的に、検察官、裁判官は積極的に情状を調査することはありません。
被告人の情状を細やかに調べ上げ、精査した上で主張するのは「弁護人」の役割なのです。
このため、情状酌量を得るためには、弁護人の力が必要不可欠です。
3、情状酌量を目指すなら、刑事裁判に精通した弁護人をつけるべき?
(1)刑事事件では弁護人は必須
刑事事件では、弁護人は不可欠な存在です。
刑事事件では、手続きのあらゆる場面で人権侵害のおそれが多々あります。
無罪推定がある中でも、身柄は拘束され、拘束中は最低限の自由があるのみで精神的にも肉体的にも多大な負担を強いられます。自由の中で生活をしてきた人々にとって、このような状況はどれだけ辛いことでしょうか。
このような状況下で、あなたの味方として面会に行くことができる者は、面会者と弁護人だけです。中でも、逮捕から72時間は面会ができるのは弁護人だけです。
そして、弁護人は、精神的な支えとなるだけなく、刑事弁護の戦略も考えます。
裁判においては、検察官の主張のうち、どこを、どのように主張して争い、それをどのような証拠により立証するか等の検事弁護の戦略が非常に重要です。
こういった戦略を立て、その戦略の基づいて訴訟追行することは法律に精通している弁護士でなければ困難です。
そのため、刑事事件では、弁護人の存在は必須なのです。
とはいえ、法律上は全ての刑事事件で弁護人をつける必要はなく、弁護人をつけなくても良い「任意的弁護事件」もあります。
法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年(上限側が3年、の意味)を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件など、比較的重い犯罪を「必要的弁護事件」と言いますが、それ以外の事件が「任意的弁護事件」です。
必要的弁護事件は、法律上、弁護人がなければ裁判をすることができません。
任意的弁護事件においてはこのような法律上の定めはありませんが、やはり上記の事情から弁護人をつけるのが一般的です。
(2)弁護士には「専門」がある
といっても、弁護人ならば誰でも同じ結果を得られるわけではありません。
弁護士も、分野によって得意、不得意があります。刑事事件、ことに裁判を控えているのであれば、刑事裁判に関する知識、経験が豊富な弁護人を選任した方が、よりよい結果を得られるでしょう。
なお、刑事事件では国選弁護人という選択肢もあります。
しかし、選任された国選弁護人が必ずしも刑事事件、刑事裁判の知識、経験が豊富かどうかは保障されません。一度、国選弁護人を選任した後でも、少しでも「この弁護士、刑事事件に詳しいのかな?」と不安に感じるのであれば、私選弁護人への切り替えることも可能です。
刑事事件で弁護人をつける際は、刑事事件を専門とした弁護人を自ら選んで依頼することをお勧めいたします。
まとめ
以上のように、情状に酌量すべき点がある場合は酌量減軽を受ける可能性はあります。そこで、まずは被告人にとって有利な情状とは何かを確定し、その情状を裁判で効果的に主張・立証していくことが酌量減軽を受けるためのポイントとなります。
また、裁判でそういった酌量減軽を主張するためには刑事裁判に慣れた弁護士の力が必要不可欠です。