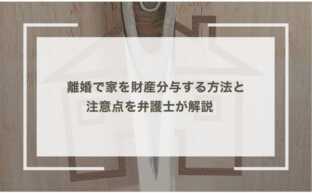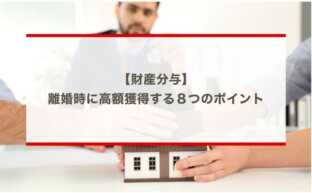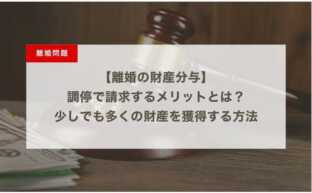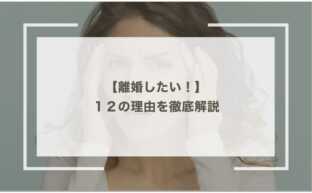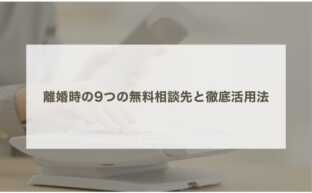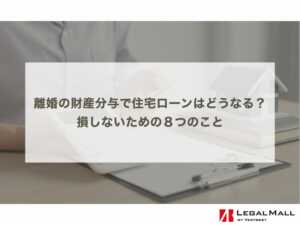
離婚の財産分与のタイミングで住宅ローンを負担しなければならないだろうか。できれば負担したくない……。
弊所では数多くの離婚相談者からのご依頼があり、こういった種類のお悩みをたくさんお受けしています。
結婚後、夫婦で一緒に暮らしていた夫名義、または、妻名義の不動産を持っている場合や、不動産そのもののみならず、住宅のローンの返済がまだ終わっていないのであれば、それも財産分与の際にローンを考慮する必要があります。場合によっては不動産の名義変更の必要性も出てきます。
ですので、損をしないために財産分与時の住宅ローンについての扱いを正確に理解することが大切です。
そこで今回は、これまで多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の元、
- そもそも住宅ローンも財産分与の対象になるのか?
- 住宅ローンがある場合の財産分与の手順
についてご紹介していきます。離婚時に財産分与の問題をお抱えの方のご参考になれば幸いです。
目次
1、離婚の財産分与の対象に住宅ローンも含まれる?

結婚期間中にお互いの協力によって得られた財産を、離婚時に清算することを財産分与と言います。
財産分与の対象となるものには、お金や預金、不動産、保険、株式、退職金などの様々な富が含まれます。ただし、財産分与はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も考慮する必要があります。住宅ローンもその一つです。
財産分与について詳しくは、以下の記事も参考にしてみてください。
2、財産分与の手順|住宅ローン付き居住用不動産の場合

住宅ローン付きの居住用不動産の財産分与ですが、基本は下記の手順で進めます。
- 住宅ローンの残額を確認する
- 現在の不動産の値段を調べる
- 不動産の価格が住宅ローンの残りの金額より大きいか(アンダーローンか)、住宅ローンの残りの金額が不動産の値段より大きいか(オーバーローンか)を調べる
- 「3」を考慮に入れて不動産が必要かどうか考える
- 財産分与に関する話し合い、調停、裁判
- 必要であれば、不動産登記移転の手続き
- 必要に応じて、住宅ローンの負担者移転の手続き
住宅ローンに関する財産分与は、大きな論点となっている裁判例も多数存在します。
下記で、それぞれの手続きの内容を詳しくご説明いたします。
3、住宅ローンがあるときの財産分与の手続き①|まずは住宅ローンの残額を確認

では、いよいよ財産分与の手続きを開始します。
まずは住宅ローンの残額を確認しましょう。
残高は、住宅金融公庫などの借入先金融機関に問い合わせることで確認できるでしょう。
なお、家を購入した際に、夫婦の一方あるいは両方が頭金を出していたという場合、頭金を支払った方へ優先的に返還してもらいたいですよね。
婚姻前からの財産から頭金を支払った場合には、優先的に頭金を返してもらうことができます。
しかし、頭金で支払った金額を減額されずに、そのまま返してもらえるわけではありません。
4、住宅ローンがあるときの財産分与の手続き②|不動産査定で物件の価格を確認

【1】不動産の価値を知るためには、不動産鑑定士に鑑定を依頼するのが良いです。資金的に余裕がある場合は、不動産鑑定士に依頼しましょう。
【2】手軽に不動産の価値を知りたい場合は、インターネット上にある売却査定サイトを利用するのがおすすめです。例えば「不動産 売却」などと検索すると、たくさんのサイトが出てきます。必要事項を入力することで、不動産がおおよそいくらで売却できるのかを知ることができます。
【3】正確な不動産価格を知るためには、大手の不動産業者に訪問査定してもらうのが良いでしょう。無料で不動産の査定書を作成してもらうことができます。より正確な不動産価格を知るためには、複数社から査定書を取り、その平均値を算出することがおすすめです。
5、住宅ローンがあるときの財産分与の手続き③|不動産の査定価格と住宅ローンの残額のどちらが大きいかを確認

不動産査定を踏まえて以下のいずれの状態か判断します。
- アンダーローン・・・不動産の価格が住宅ローンの残額より大きい状態
- オーバーローン・・・住宅ローンの残額が不動産の価格より大きい状態
上記は財産分与の内容を決定する上で非常に大切です。
詳しくは次の項目をご参照下さい。
6、住宅ローンがあるときの財産分与の手続き④|今後の不動産利用の方針を決める

アンダーローンかオーバーローンかを確認したら、次は
- (1)妻が住み続けるか
- (2)夫が住み続けるか
- (3)それとも不動産を売却するのか
のいずれの方針にするのかを、
- 夫婦での話し合い
- 調停
などで決定します。各選択肢ごとの住宅ローンの扱いはそれぞれ以下の通りになります。
あなたが引き続きその不動産に住み続けたいのか否かの希望を相手に主張していくことが重要です。なお、基本的に夫名義の場合がほとんどですので、下記は夫名義が前提で進めます。
(1)妻が不動産に住み続ける場合
①妻の名義に不動産を変更し、住宅ローンの返済は夫のままの場合、不動産がアンダーローンである場合、不動産の価格から住宅ローンの残高を差し引いた金額の約半分を妻が夫に支払う必要があります。抵当権が付いている場合、夫が返済を滞らせた場合にリスクがあります。
②不動産の名義と住宅ローンの債務者を夫のままにする場合、住宅の所有権は夫に、離婚後のローンの支払いも夫が行います。妻にとってはメリットがありますが、夫がローンの支払いを滞らせる可能性があるため、差し押さえを行えるように公正証書を作成しておくことが望ましいです。
③不動産の名義と住宅ローンの債務者を夫のままにしたまま、妻が夫に家賃を支払う場合、妻が月ごとに家賃を夫に支払います。通常、支払う家賃の金額は住宅ローンの支払額よりも少なくなります。この方法は、子供が転校を希望しないなどの事情がある場合に有用です。
④不動産の名義と金融機関の債務者を妻にする場合、妻が住宅ローンを返済しますが、妻の収入や資産状況などが金融機関によって審査されます。当事者の合意だけでなく、金融機関の許可が必要です。妻と夫の両方がローンを負担することもできます。アンダーローンの場合、不動産がプラスの財産となるため、妻から夫に金銭の支払いが必要になる可能性があります。また、夫の持分とローン残高の両方を取得した場合、住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除について、詳しくは国税庁の「No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について」をご確認ください。
(2)名義は夫のままで夫が住み続ける場合
アンダーローンの場合、実質的な価値は「不動産の価格からローン残高を差し引いた金額」です。
その「実質的な価値」について、財産分与の割合に応じて金銭を請求します。
つまり、財産分与時の不動産の価格が3,000万円で住宅ローンが2,000万円残っていて財産分与の割合が半分という場合、妻は夫に500万円請求する権利があります。
(3)不動産を売却する場合
この場合、オーバーローンの場合かアンダーローンの場合で扱いが異なるので、以下それぞれみていきましょう。
①オーバーローンの場合
財産分与はマイナス財産も考慮するので、不動産を売却して、住宅ローンが残った場合、他にもプラスの財産があればそこからローンの価格を差し引きます。
②アンダーローンの場合
不動産を売って得たお金を住宅ローンの支払いに回しても金銭が余る場合、余った金銭が財産分与の対象です。
財産分与の割合が2分の1の場合、残りの金銭の半分を夫に請求できます。
なお、不動産を売って利益が出た場合、譲渡所得税という税金を支払わなければならない場合があります。
7、住宅ローンがあるときの財産分与の手続き⑤|協議、調停、裁判を行う

不動産をどうするかの方針が決まったら、次はいよいよ具体的に財産分与の手続きを進めていきましょう。
下記の流れです。
(1)まずは協議をしましょう!
まずは、財産分与の対象(不動産、ローン)の扱いについて協議しましょう。
前述の通り、まずはオーバーローンなのかアンダーローンなのかを確認した上で、その不動産に住み続けたいか否かを判断しましょう。
妻が住み続ける場合は、「6ー(1)妻が不動産に住む場合」をご参照の上で、できるだけ有利な条件でまとめられるよう交渉しましょう。
逆に妻が家を出る場合には「6ー(2)夫が住み続ける場合」をご参照の上でできるだけ有利な条件でまとめられるよう交渉しましょう。
前提として、同居しているかどうかで進行が変わります。
①同居中
同居中の場合、不動産と住宅ローンの財産分与に関して直接協議することになります。
②別居中
別居中の場合、直接財産分与に関して協議をすることが難しいと思います。
ですので、連絡が取りやすい「電子メール」や「LINE」(会話の内容を撮影する)を使用するなどして、証拠が残るように不動産と住宅ローンの財産分与について協議をしましょう。
協議に応じない時には、内容証明郵便を送りましょう。
(2)調停で決める
調停で協議する方法は、離婚調停で離婚について協議するか、財産分与請求調停で協議する方法です。
①申立てに必要な書類
下記の書類を集めることが必要です。
- 調停の申立書およびその写し1通ずつ
- 離婚時の夫婦の戸籍謄本
- 財産目録
- 夫婦双方の財産に関する書類→退職金の明細、給与明細、預金通帳写し、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
②申立てにかかる費用
申立てに必要な費用は以下の通りとなります。
- 収入印紙 1,200円分
収入印紙は郵便局で買うことが可能です。
- 連絡用の郵便切手 800円分
申し立てをする家庭裁判所に確認する。
③申立て先の裁判所
原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所です。
詳細は以下の記事をご参照下さい。
(3)離婚調停でもまとまらなければ、離婚裁判!
調停で財産分与に関しての協議が解決しない場合は、離婚裁判を提起します。
①裁判離婚をするには離婚原因が必要!
裁判によって離婚をするには、以下の通り法律が定める離婚の原因(民法770条1項各号)が必要とされています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(暴行、浪費、犯罪、性格の不一致など)
②離婚裁判の流れ
下記で進みます。
- 訴状の作成
- 訴状の提出
- 相手方へ訴状の送達
- 第一回口頭弁論期日の決定
- 数回の口頭弁論を繰り返す
- 判決
時には裁判途中で和解が成立する時もあります。
③裁判では、証拠の重要性が高い!
離婚相手の退職金額の明細や財産目録等、しっかりと証拠を手に入れてから裁判するようにしましょう。
8、住宅ローンがあるときの財産分与の手続き⑥|その他の手続き

最後に、その他不動産の財産分与で必要な手続きについて説明していきます。
(1)不動産の名義変更が必要となる場合
不動産を夫名義から妻名義に変更する場合、登記移転手続きが必要となります。
なお、不動産に抵当権が付いているときは銀行も比較的柔軟に対応してくれることが多いですが、そうでない場合は、住宅ローンを完済するまでは,銀行側が名義変更を了承してくれないことが多いでしょう。
ですので、離婚をする際は「ローンを完済した後は妻の名義に変更する」等、しっかりと同意をしておくことが大切です。
ただ、登記請求権の時効の問題もありますので、弁護士や司法書士などの専門家に事前にきちんと相談したほうがよいでしょう。
(2)住宅ローンの債務者変更が必要となる場合
住宅ローンの債務者は夫婦間で自由に変更できません。借入先金融機関の審査に通ることが必要となります。
妻の収入や資産状況が銀行により審査されます。銀行の審査に通過した場合は名義変更が可能です。
(3)夫が主債務者で妻が連帯保証人となっていたが、財産分与の話し合いで妻が連帯保証人を外れることになった場合
夫の方が主債務者、妻側が連帯保証人のケースもあります。
財産分与に関する話し合いで、今後妻が責任を負わない事となった場合、銀行と妻との連帯保証契約を解除する必要があります。
この場合にも、連帯保証契約を解除するかは夫婦間の話し合いで決められるものではなく、銀行の決定が必要となります。
なお、連帯保証契約を解除する方法として具体的には、
- 住宅ローンの借り換えをする
- 別の方に連帯債務者・連帯保証人になってもらう
等の方法があります。
銀行と話をして上記の方法を採ることができるか確認してみましょう。
まとめ
財産分与における住宅ローンの取り扱いについて紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?
今回の内容が財産分与のタイミングで損しないための参考になれば幸いです。